
2018.2.20訪問。東京ドームで世界らん展→本郷弓町のクス→湯島聖堂のカイノキ(今ここ)。
東京メトロ丸ノ内線御茶ノ水駅下車。神田川に架けられた聖橋の下をくぐって湯島聖堂へ。

坂道です。かつての昌平坂かも?今は相生坂と呼ばれているらしい。ってか、湯島聖堂がかつての昌平坂学問所な訳で。元は江戸時代、林羅山が儒学の私塾を開いたのが起源です。ここに孔子廟を設けて維持運営したのが橙の林家。その後1690年(元禄3)、将軍徳川綱吉が神田湯島に孔子廟を移築。この際講堂・学寮を整備。
で、トップ画像が現在の湯島聖堂の入り口です。門の奥にぼんやり写ってるのが訪問の目的のカイノキです。

巨樹・巨木の本には湯島聖堂のカイノキ
樹高:14メートル
幹回り:2、2メートル
樹種:カイノキ
推定樹齢:80年とあります。
カイノキの下に説明板が設置してあります。
「楷(かい)樹の由来
学名:とねりばはぜのき(うるし科)
楷は曲阜にある孔子の墓所に植えられている名水で初め子貢が植えたと伝えられ、今日まで植えつがれてきている。枝や葉が整然としているので、書道でいう楷書の語源ともなったといわれている。
わが国に渡来したのは大正4年。林学博士の白澤保美氏が曲阜から種子を持ち帰り、東京目黒の農高務省林業試験場で苗に仕立てたのが最初である。これらの苗は当聖廟をはじめ儒学に関係深い所に領ち植えられた。その後も数氏が持ち帰って苗を作ったが性来雌雄異株であるうえ、花が咲くまでに30年くらいもかかるため、わが国で種子を得ることはできなかったが、幸いにして数年前から2・3箇所で結実を見るに至ったので、今後は次第に孫苗が増えていくと思われる。
中国ではほとんど全土に生育し、黄連木黄連茶そのほかの別名も多く、秋の紅葉が美しいという台湾では爛心木と呼ばれている。牧野富太郎博士はこれに孔子木と命名された。
孔子と楷の木とは離すことができないものとなっているが、特に当廟にあるものは曲阜の樹の正子に当る聖木であることをここに記して世に伝える。 昭和44年 矢野一郎」

カイノキの傍には、孔子像がありました。

訪問したのは2月20日、カイノキは落葉樹。去年の12月3日に皇居乾通り通り抜けに参加した後、岩崎邸庭園のイチョウの大木を見物し、最寄りの千代田線湯島駅から新御茶ノ水へ移動。丸ノ内線御茶ノ水駅へ乗り換える時に神田川の聖橋の上から、湯島聖堂のカイノキの紅葉を遠望してました。

上の画像中央奥に赤く色づいているのがカイノキです。
巨木探訪は落葉樹の場合、葉がある時に見に行くか?落葉した後冬の枝を見に行くか?悩みどころです。真っ赤に紅葉してるところも素敵ですよね〜。

せっかくなので、湯島聖堂の聖堂を見に行くことに。

元の建物は大正11年(1922)に国の史跡に指定されましたが、翌12年(1923)の関東大震災で焼失。1935年に伊東忠太設計で大林組が施工。寛政時代の建物を模し、鉄筋コンクリート造りで再建されました。現在の建物です。
建物は坂上にあり、石段でつないでいます。
坂下に見頃の白梅がありました。

ちなみに、巨樹・巨木の本には「カイノキを湯島聖堂に5本植えた」とあります。なら他の4本はどれかしら?と見回したら、石段の上にそれらしき木を見つけました。

どうだろか?ちょっと見、樹齢80年の古木に見えないんだよね〜?しかも冬だから葉っぱで判断もできない。まあ、これなんじゃないかな?と。
ちなみに、聖堂手前の門の外に水甕が設置してありまして。

甕には徳川の三つ葉葵が燦然とありました。
時刻は13時45分。次の目的地は湯島天神の梅です。疲れずに移動するには、東京メトロ千代田線新御茶ノ水から湯島駅を利用すべきなんですが、湯島聖堂の近くには神田明神があるんだよね。神田明神の建物と梅の画像が欲しい。行ってみないと、梅があるかどうかはわからんのだけども。ってな事で徒歩移動です。
湯島聖堂へ(2012.1.5)の記事 こちらの記事に聖堂の大成殿の扉が開いてる画像があります。合わせて湯島聖堂の絵馬の画像も掲載。
東京メトロ丸ノ内線御茶ノ水駅下車。神田川に架けられた聖橋の下をくぐって湯島聖堂へ。

坂道です。かつての昌平坂かも?今は相生坂と呼ばれているらしい。ってか、湯島聖堂がかつての昌平坂学問所な訳で。元は江戸時代、林羅山が儒学の私塾を開いたのが起源です。ここに孔子廟を設けて維持運営したのが橙の林家。その後1690年(元禄3)、将軍徳川綱吉が神田湯島に孔子廟を移築。この際講堂・学寮を整備。
で、トップ画像が現在の湯島聖堂の入り口です。門の奥にぼんやり写ってるのが訪問の目的のカイノキです。

巨樹・巨木の本には湯島聖堂のカイノキ
樹高:14メートル
幹回り:2、2メートル
樹種:カイノキ
推定樹齢:80年とあります。
カイノキの下に説明板が設置してあります。
「楷(かい)樹の由来
学名:とねりばはぜのき(うるし科)
楷は曲阜にある孔子の墓所に植えられている名水で初め子貢が植えたと伝えられ、今日まで植えつがれてきている。枝や葉が整然としているので、書道でいう楷書の語源ともなったといわれている。
わが国に渡来したのは大正4年。林学博士の白澤保美氏が曲阜から種子を持ち帰り、東京目黒の農高務省林業試験場で苗に仕立てたのが最初である。これらの苗は当聖廟をはじめ儒学に関係深い所に領ち植えられた。その後も数氏が持ち帰って苗を作ったが性来雌雄異株であるうえ、花が咲くまでに30年くらいもかかるため、わが国で種子を得ることはできなかったが、幸いにして数年前から2・3箇所で結実を見るに至ったので、今後は次第に孫苗が増えていくと思われる。
中国ではほとんど全土に生育し、黄連木黄連茶そのほかの別名も多く、秋の紅葉が美しいという台湾では爛心木と呼ばれている。牧野富太郎博士はこれに孔子木と命名された。
孔子と楷の木とは離すことができないものとなっているが、特に当廟にあるものは曲阜の樹の正子に当る聖木であることをここに記して世に伝える。 昭和44年 矢野一郎」

カイノキの傍には、孔子像がありました。

訪問したのは2月20日、カイノキは落葉樹。去年の12月3日に皇居乾通り通り抜けに参加した後、岩崎邸庭園のイチョウの大木を見物し、最寄りの千代田線湯島駅から新御茶ノ水へ移動。丸ノ内線御茶ノ水駅へ乗り換える時に神田川の聖橋の上から、湯島聖堂のカイノキの紅葉を遠望してました。

上の画像中央奥に赤く色づいているのがカイノキです。
巨木探訪は落葉樹の場合、葉がある時に見に行くか?落葉した後冬の枝を見に行くか?悩みどころです。真っ赤に紅葉してるところも素敵ですよね〜。

せっかくなので、湯島聖堂の聖堂を見に行くことに。

元の建物は大正11年(1922)に国の史跡に指定されましたが、翌12年(1923)の関東大震災で焼失。1935年に伊東忠太設計で大林組が施工。寛政時代の建物を模し、鉄筋コンクリート造りで再建されました。現在の建物です。
建物は坂上にあり、石段でつないでいます。
坂下に見頃の白梅がありました。

ちなみに、巨樹・巨木の本には「カイノキを湯島聖堂に5本植えた」とあります。なら他の4本はどれかしら?と見回したら、石段の上にそれらしき木を見つけました。

どうだろか?ちょっと見、樹齢80年の古木に見えないんだよね〜?しかも冬だから葉っぱで判断もできない。まあ、これなんじゃないかな?と。
ちなみに、聖堂手前の門の外に水甕が設置してありまして。

甕には徳川の三つ葉葵が燦然とありました。
時刻は13時45分。次の目的地は湯島天神の梅です。疲れずに移動するには、東京メトロ千代田線新御茶ノ水から湯島駅を利用すべきなんですが、湯島聖堂の近くには神田明神があるんだよね。神田明神の建物と梅の画像が欲しい。行ってみないと、梅があるかどうかはわからんのだけども。ってな事で徒歩移動です。
湯島聖堂へ(2012.1.5)の記事 こちらの記事に聖堂の大成殿の扉が開いてる画像があります。合わせて湯島聖堂の絵馬の画像も掲載。










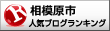

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます