高校の部活で美術部と写真部を兼部してた私。使ってたカメラは父のもの。大学に入って使ってたカメラもレンズも父のものを借りて撮影してました。
結婚して、キャノンの一眼レフを少しだけ使いましたが、ペンタックスのMZ-3が気に入って、レンズもペンタックス。
それが変わったのは約10年前。突然の脳梗塞で、左側に麻痺が出たのね。幸い、リハビリをして日常生活は脳梗塞発症前とほぼ変わらないまでに戻った。私は運が良かった。けどリハビリでウォーキングしまくった為か、皮肉にも脳梗塞発症前に比べて撮影機会は増えた。けど一眼レフとレンズを組み合わせると重い。特にマクロレンズは最悪。重さを麻痺が残る左手が支え切れない。そんなこんなで一眼レフをコンパクトカメラに変えてのウォーキングが増えました。コンパクトカメラは軽いし、機動力が出ていいね。
けど、脳梗塞を発症して使う機会が激減した一眼レフを手放せなかった。
そして10年が過ぎました。
世の中はフィルムカメラを既に必要としてない。
ワープロやポケベルと同じく、過去の異物になってしまったよ。
実は引越しに備え、家の中のあれこれを断捨離と称し少しづつ処分してまして。遂にカメラとレンズに手を出しました。
かつて5万円以上で手に入れた魚眼レンズって今も使えるの?
かつてお出かけで背負ってたカメラリュックに入れっぱなしの大事なMZ-3はどうかしら?と久々に対面した。
並べて撮影してみた。
今回手放す私のかつての宝物。レンズと一眼レフとコンパクトカメラ。実は手前に各種フィルターも並べてありますが、中古品買取店で調べたら、フィルターは買取品に入ってなかったのでトリミング。
で。まずはWebで検索。
おすすめはカメラのキタムラでした。
え〜と??私のカメラとレンズはいくらくらいなのかな?
予想はしていたけども。フィルムカメラの一眼レフのMZ-3とコンパクトカメラ2台は買取対象でなかったよ。
幸い持ってたレンズ3本のうち2本は買取対象でした。
PENTAX FA100mmF2.8 買取価格10630円 下取り11820円
PENTAX F17mm-28mm 買取価格3600ー4870円 下取り5420円
安っす!
けど、私はもう使えないので、どこかの誰かが使ってくれたら嬉しいや。
ポ(チッ)ーーー。
ポチる寸前に電話がかかってきた。
出たら、最近多い「不用品を買取ます。対象はアクセサリー・ブランド品各種・陶器・古銭・カメラなどありましたらば」と。
う〜ん。まさにタイミングがいいねえ。
「カメラならありますが」ってなことで、一度買取査定してもらうことに。しかもタイミングのいいことに「明日の2時ー2時半にそちらの近所を回ってるので都合が良いのですが」と。
乗ってみた。慎重な私はこういうの大概お断りしてたのですが。中にはさぎまがいの業者も混じってるし。実は訪問予約したのに来なかったおばさん2人組に当たったことがありまして。来なかったので、実質被害はなかったけどね。待ってた時間が無駄になったのと。用意したあれこれを探してた時間も無駄になったのと。不愉快になっただけ。
翌日は、まさに熱海で土石流が発生した当日で、「約束の時間に遅れます〜。渋滞で動かないんです〜」と査定の人から電話があったので。どうも横浜から車を運転してきて近所で買取希望者宅を回ってるらしい。
長くなるので割愛しますが、横浜の買取業者の査定は「買取対象はマクロレンズと魚眼レンズのみ。全部で1万円です」なんだって。
実はこの業者さんは頑張ってた。「うちはこれが精一杯です」と。
更にろくなアクセサリーを持ってない私。「実は今、医療用に金メッキに使ったタングステン製のネックレスも探してます。お値段つきます」だってさ。レアメタルの発掘ということか?
ろくな陶器も持ってない私。けど海外旅行の自分土産で何か一つと買い求めた品があれこれありまして。イギリスのウェッジウッドの製造工場で買った奴があったよね?と探したのですが。「あ〜、これ、みた事あります!」とおっしゃるので、買取に出しても良いかな?と思ったのですが。
「実は今、カップ&ソーサーなどは売れるのですが、大皿などパーティー需要が全くなくて、在庫がですねえ」と。
需要がコロナで変わってしまった模様。
「大きなカバンとかキャリーケースも(在庫が)全く動かないんです」と。
買取業者も予想外の事態な模様。けど、お家時間が増えて、人々が私のように断捨離したり整理をしてる現在は買取業者はお家訪問が増えてるようですよ?使いようによっては不要品やゴミが僅かでもお金に変割ります。まあ、今時は個人で気軽にネット販売できますので、時間があればそっちを選んでいたかもね。私の場合は引越しまでにあれこれ処分したいので、ネット販売は考えなかったけども。
で。昨日、久々に晴れたのでカメラ一式を担いて町田に出かけました。カメラのキタムラ 町田モディ8階中古買取センターに持ち込んでみた。
ちなみに、事前に電話して「持ち込み予約必要ですか?東京都に緊急事態宣言が出ましたが、営業してますか?」と問い合わせしてから行きました。
で。受付はすぐ。「1個1個査定しますので、20分ほどかかります」と。
うん。知ってた。けど事前に聞いてたのはもっと時間がかかるハズだったので、お店の向かいが本屋さんだったので、そこで時間を潰すことに。
時間を見計らい戻ると見積書が出来上がっていた。
差し出された買取見積書には。
コンパクトカメラ 50円
コンパクトカメラ 50円
タムロン製28-200mmレンズ 50円
一眼レフペンタックス MZ-3 100円
ペンタックスFA100/2.8マクロレンズ 250円
ペンタックスF17-28/3.5-4.5魚眼レンズ 4000円 合計4500円でした。
安い〜。私の宝物だったのに〜。
買取業者はレンズ2本のみで10000円買取だったんだ。
表情の曇る私に査定をしたおじさんが「マクロレンズはね、レンズがもう曇ってるんだ。こうなると撮影画像がね」と。
光に照らす先には、曇りガラスのようにレンズの周囲がぼやけてる。
完全に私のせい。
「10年前に脳梗塞になって。一眼レフで手持ち撮影するのが難しくなって」と私。
「カメラは使わないとこうなるよね」とおじさん。
高いレンズだったんだ。けどこのマクロレンズを使って撮影した花はとても綺麗にボケが出てた。花をドレスアップ出来た。なのに、レンズの手入れを怠った私。
おじさんが「どうしますか?」と。査定額はゴミみたい。金額だけならば、横浜の買取業者のけども。
大きな違いはカメラのキタムラでは既に需要のなさそうなフィルム仕様のコンパクトカメラや一眼レフもわずか50円や100円であっても買い取ってもらえること。
もしここでお断りしたら?相模原のゴミ区分においては、カメラと50センチ以下のレンズは一般ゴミです。(ちなみに50センチ超えのレンズは粗大ゴミ)
「もう使えないカメラでも部品だけでもどこかの誰かのカメラで使ってもらえるなら買取をお願いします」
私の優先順位は買取額の安い高いではなかったの。
宝物だったカメラなので、どこかの誰かに使って欲しかった。
「もう少し早く諦めがついてたら良かったのにね」と私。ダメにしてしまったレンズが悔やまれる。マクロレンズはもう復活出来ないだろう。幸い、魚眼レンズの状態は良かった。どこかの誰かの思い出の1枚を写すのに役立て!
おじさんが「カメラはね。それぞれの思い出だから。捨てるのはね」と。
それがわかるのがカメラ屋さん。私のカメラとレンズ、良い出会いがあるといいな。
まさに不用品の買取業者との差がここでした。
あ〜。記事を書きながら泣けてきた。
ちなみに、最後のおじさんが「MZ-3にフィルムがセットしたままなので返します」と。「1枚だけ撮影してありますね」と。
その1枚に何をいつ撮影したかもう忘れてしまったけど。記念にこのフィルムはとっておこう。それこそ記念品だし。
オリンピック観戦中。お台場のユニコーンガンダムを見た世界の人が話題にしてる。
そういや記事投稿したな?と検索。
あった!しかも公開初日に見物に行ってました。
せっかくなのでオリンピックで赤く光ってるところも写ればいいのにな。等身大のガンダムを見上げるとワクワクするんだよ。

 2021/7/16 17:29泉の森公園の山野草園にて撮影。
2021/7/16 17:29泉の森公園の山野草園にて撮影。

































 2020/9/29麻溝公園にて撮影。
2020/9/29麻溝公園にて撮影。

























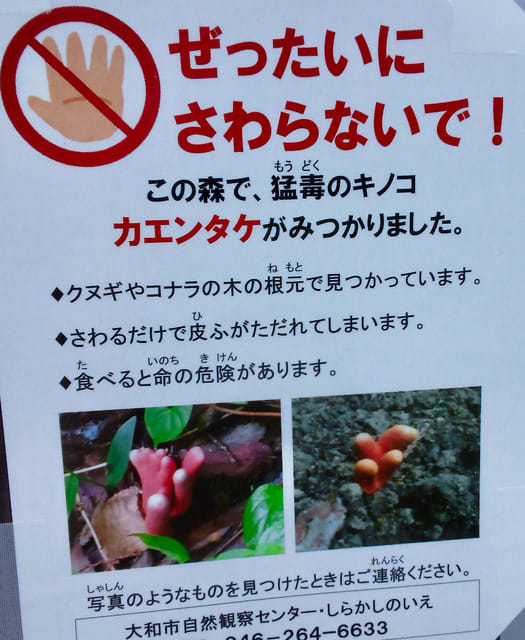













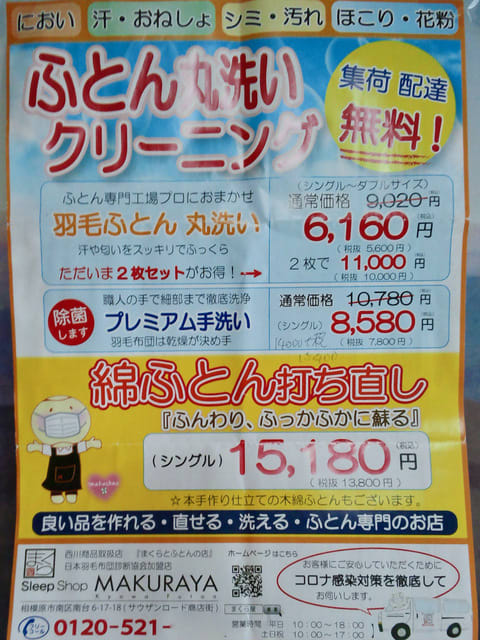

































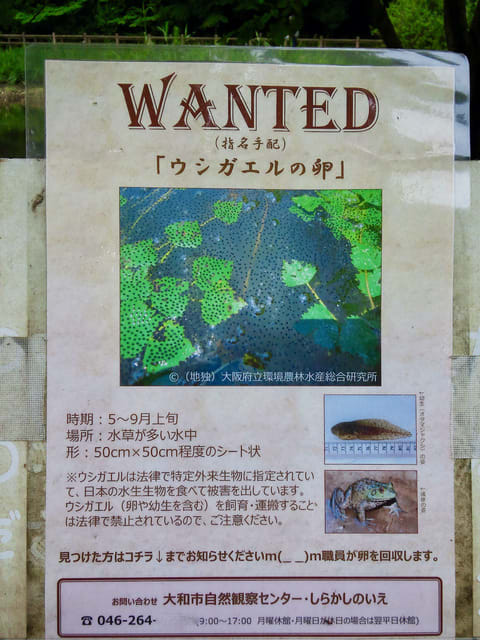












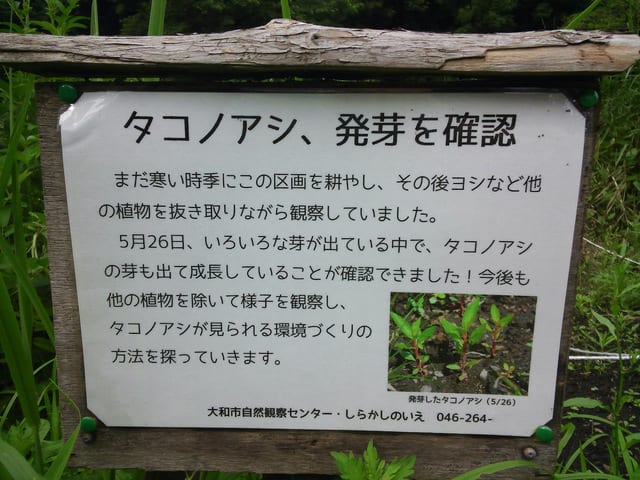













 反対側の木に花芽を見つけました。ちょっと高い場所で咲いてます。もう少し近くから観察したかったなあ。
反対側の木に花芽を見つけました。ちょっと高い場所で咲いてます。もう少し近くから観察したかったなあ。











