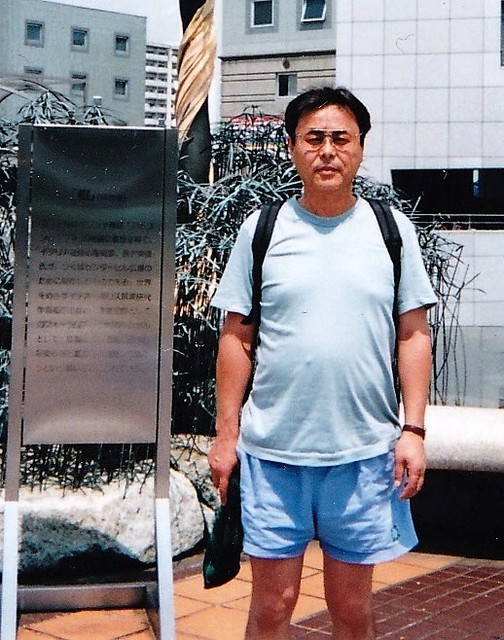昨日の続きです。
歯の間に挟まったニラを気にしつつ表に出ると、西武バスが見事なコーナーワークでカーブを曲がり駅前に入って行きます、通行人とバスの間隔は数十㎝の狭い路です。
郊外の私鉄沿線に良くある風景です。西武池袋線石神井公園駅は西武新宿線上井草駅より賑やかです。
池袋線沿線より、新宿線沿線の方が都会的と云うイメージだったのですが、今回歩いてみて、この認識は訂正しなければ・・・と、そんな気がしてきました。
今回、調べてみたら池袋線(池袋~飯能間)は1915年(大正4年)(44.2kmの)開業でした。
新宿線(高田馬場駅~東村山駅間)の方は、1927年(昭和2年)(23.7km)開業です。池袋線の方が12年だけ歴史が古いのです。
それにしても、この高層マンションの「偉容」は、周囲の景観とはかけ離れ「異様」です。
この辺りでもこの様な高層建築が可能になったのです、これも「規制緩和」の影響でしようか?
このマンションも10年も経てば、周囲の変化にとけ込んで行くのでしょう。しかし、少子高齢化で住宅需要は低下傾向にあると思うし、都心回帰傾向もあるようですし、この辺りは、マンションの立地としては中途半端ではと・・・・・・。
まぁ。私が「マンション業者」の事など心配するのは、余計なお世話でした。
この駅舎、装飾的なものを一切排除し実用性のみを追及した、低コスト無味乾燥建築です。「もの悲し感」が漂っています。
直線のホームより、カーブしたホームが好きです。ホームの全てを屋根が覆っていません。
田舎の駅はホームに屋根は全く有りません。都心と田舎の中間的スタイルです。それにしても、人の居ないホームには哀愁があります。演歌です。
踏切を渡り、少し行った処で「この工場」を見つけました。「へぇー。こんなところにあったんだぁ!」と、しばし見つめて、昔のことを思い出してしまいました。
普通の人は、この会社の社名は聞いたことも、見たこともないと思います。この会社の名前を知ったのは・・・・・・、エート、三番目に務めた会社ですから、今から30年近く前のことです。
その会社は、プラスチックの成形加工、音響、映像部品の組み立て等をしていたのです。
その時に、この会社の「Eリング」とか、「波形スプリングピン」と呼ばれる、固定したり、連結したりする、数㍉から十数㍉の小さな部品を使用していました。
この会社の小さな部品は、家庭電化製品の中にほぼ間違いなく、一つや二つ入っています。その業界ではそれなりに知られている会社です。
部品の入った箱に書かれていた、社名と住所を今でもうっすら覚えていたのです。「へぇー。こんな感じの会社だったんだ・・・・・・」と、思いながら、時間が逆戻りするような不思議な感覚でした。
駅前から数分でこの景色です。広い畑越しに望む高層マンション。
さぁてと、これから池袋線の「豊島園駅」を目指そうと思います。
それではまた明日。