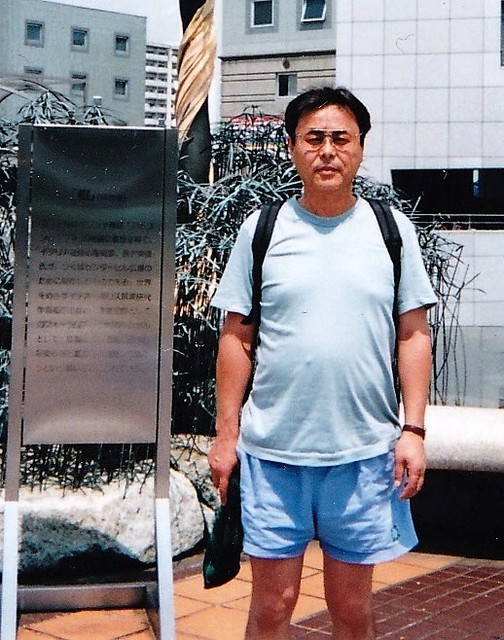映画『剣鬼』を観ました。
三隅研次監督、市川雷蔵主演 原作柴田錬三郎で1965年10月の公開です。
面白かったです、飽きることなく、最後まで観てしまいました。あっと云う間の1時間23分でした。
見終わって感じたのは、何か、紙芝居でチャンバラを見ていた感覚でした。
1965年ですから、私が15歳でたぶん中学3年の頃です。あの頃は、もう、映画も全盛期から斜陽期への過渡期的な頃だったと思います。
全盛期のチャンバラ映画は、ハラハラとドキドキで、笑いあり涙ありで、最後は正義が勝って、ハッピーエンドで、観客はヨカッタ!ヨカッタ!で、映画館を後にしたのでした。
勧善懲悪でもなく、誰が勝った負けだでもなく、笑いもなく、ハーピーエンドでもなく、ど真ん中の大衆娯楽作品でもなく、時代劇としては、微妙な作品だと思います。
微妙な時期ですから、市川雷蔵の化粧も白塗りで、アイラインはバッチリキメキメで、二枚目で、大衆娯楽ど真ん中の色を引き摺っているのでした。
大衆娯楽的作品として、ストーリーの展開の速さ、ストーリーの分かり易さ、これは、観ていて、とても、とても、ここち良かったです。
主人公の設定とかは、それなりに考えると、それなりに疑問とか、謎とか、隠しテーマとか、深読みも?楽しめる作品だったりして、ここいら辺が過渡期の時代劇なのです。
それで、ストーリーなのですが、藩主の奥方に使える女中が、奥方の臨終の床で賜ったのが、何故か『斑の大きな犬』で、賜った女中も子を産み落として直ぐに謎の死を遂げるのです。
奥方も、女中も、死を遂げるシーンの背景に、うめき声とも、喘ぎ声ともとれる、犬の声と、犬のアップが映し出されるのです。
女中の死に際では、犬の声と重なるように、喘ぎ声をあげ、身もだえるシーンが映し出されるのです。奥方も、女中も、犬と交わり狂い死にしたと、城中では、家来一同みんな、そう囁くのでした。
そして、女中の産み落とした子は、下級武士の家に引き取られ育てられるのでした。犬と人間の間にできた「犬子」と云われつつ、蔑まれながら、虐められ、それでも、挫けず真面目に育って行くのでした。
それにしても、犬と人間の交合により子供が産まれた、と、匂わせる、暗示させる設定、生物学的にはありえないのですが、文学的にはありえるのです。
獣婬は、古今東西の歴史上、よくある事でもなく、それほど珍しい事でもないのです。
製作意図として、人間の業とか、欲望とか、罪深さとかを、隠し味とし、作品としての、厚みとか、奥行きとか、重みとか、単なる薄っぺらなチャンバラ映画ではないと、そう主張したかったのでしょう。
それで、犬の子と囁かれている子供に、犬が斑模様だったので、班平と命名するのは、かなり変です。そうあからさまに「犬子」を背負わせてどうするの?
成長して、何故か花造りの名人となったり、また、何故か、馬と同等の早足で、殿様の遠乗りのお供をに引き上げられたり、何故か、居合いの達人にその技を伝授されたり。
そうでした。殿様は狂い死にした奥方の息子で、かなり狂気的な行状で、母の血を受け継いでいると囁かれ、藩の存続を危ぶまれる存在なのです。演じた“戸浦六宏”は、とても、とても、犬顔でした。
犬との関わりを暗示させる二人り、狂気の殿様と、驚異の走り、驚異の剣の使い手、互いにもに、その宿命に、それとなく気づきつつ、繋がっていくのです。
斑平は、花作りを愛しつつ、殿様を守る為に、十数人を容赦なく斬り殺す。一時、そんな己に疑問を抱くが、人を斬り殺す魔力からは逃れることはできないのです。
取り憑かれている、呪われている、宿命として、狂気として、鬼として、斬り殺し続けるのです。
まあ、そんな、屁理屈はこれぐらいにして、兎に角、展開の速さ、殺陣の見事さ、美しさ、市川雷蔵は、とても、とても、素晴らしい時代劇役者です。
まあ、気楽に、あまり余計なことを考えずに、チャンバラ映画として、とても、とても、楽しめる作品です。
それでは、また。
三隅研次監督、市川雷蔵主演 原作柴田錬三郎で1965年10月の公開です。
面白かったです、飽きることなく、最後まで観てしまいました。あっと云う間の1時間23分でした。
見終わって感じたのは、何か、紙芝居でチャンバラを見ていた感覚でした。
1965年ですから、私が15歳でたぶん中学3年の頃です。あの頃は、もう、映画も全盛期から斜陽期への過渡期的な頃だったと思います。
全盛期のチャンバラ映画は、ハラハラとドキドキで、笑いあり涙ありで、最後は正義が勝って、ハッピーエンドで、観客はヨカッタ!ヨカッタ!で、映画館を後にしたのでした。
勧善懲悪でもなく、誰が勝った負けだでもなく、笑いもなく、ハーピーエンドでもなく、ど真ん中の大衆娯楽作品でもなく、時代劇としては、微妙な作品だと思います。
微妙な時期ですから、市川雷蔵の化粧も白塗りで、アイラインはバッチリキメキメで、二枚目で、大衆娯楽ど真ん中の色を引き摺っているのでした。
大衆娯楽的作品として、ストーリーの展開の速さ、ストーリーの分かり易さ、これは、観ていて、とても、とても、ここち良かったです。
主人公の設定とかは、それなりに考えると、それなりに疑問とか、謎とか、隠しテーマとか、深読みも?楽しめる作品だったりして、ここいら辺が過渡期の時代劇なのです。
それで、ストーリーなのですが、藩主の奥方に使える女中が、奥方の臨終の床で賜ったのが、何故か『斑の大きな犬』で、賜った女中も子を産み落として直ぐに謎の死を遂げるのです。
奥方も、女中も、死を遂げるシーンの背景に、うめき声とも、喘ぎ声ともとれる、犬の声と、犬のアップが映し出されるのです。
女中の死に際では、犬の声と重なるように、喘ぎ声をあげ、身もだえるシーンが映し出されるのです。奥方も、女中も、犬と交わり狂い死にしたと、城中では、家来一同みんな、そう囁くのでした。
そして、女中の産み落とした子は、下級武士の家に引き取られ育てられるのでした。犬と人間の間にできた「犬子」と云われつつ、蔑まれながら、虐められ、それでも、挫けず真面目に育って行くのでした。
それにしても、犬と人間の交合により子供が産まれた、と、匂わせる、暗示させる設定、生物学的にはありえないのですが、文学的にはありえるのです。
獣婬は、古今東西の歴史上、よくある事でもなく、それほど珍しい事でもないのです。
製作意図として、人間の業とか、欲望とか、罪深さとかを、隠し味とし、作品としての、厚みとか、奥行きとか、重みとか、単なる薄っぺらなチャンバラ映画ではないと、そう主張したかったのでしょう。
それで、犬の子と囁かれている子供に、犬が斑模様だったので、班平と命名するのは、かなり変です。そうあからさまに「犬子」を背負わせてどうするの?
成長して、何故か花造りの名人となったり、また、何故か、馬と同等の早足で、殿様の遠乗りのお供をに引き上げられたり、何故か、居合いの達人にその技を伝授されたり。
そうでした。殿様は狂い死にした奥方の息子で、かなり狂気的な行状で、母の血を受け継いでいると囁かれ、藩の存続を危ぶまれる存在なのです。演じた“戸浦六宏”は、とても、とても、犬顔でした。
犬との関わりを暗示させる二人り、狂気の殿様と、驚異の走り、驚異の剣の使い手、互いにもに、その宿命に、それとなく気づきつつ、繋がっていくのです。
斑平は、花作りを愛しつつ、殿様を守る為に、十数人を容赦なく斬り殺す。一時、そんな己に疑問を抱くが、人を斬り殺す魔力からは逃れることはできないのです。
取り憑かれている、呪われている、宿命として、狂気として、鬼として、斬り殺し続けるのです。
まあ、そんな、屁理屈はこれぐらいにして、兎に角、展開の速さ、殺陣の見事さ、美しさ、市川雷蔵は、とても、とても、素晴らしい時代劇役者です。
まあ、気楽に、あまり余計なことを考えずに、チャンバラ映画として、とても、とても、楽しめる作品です。
それでは、また。