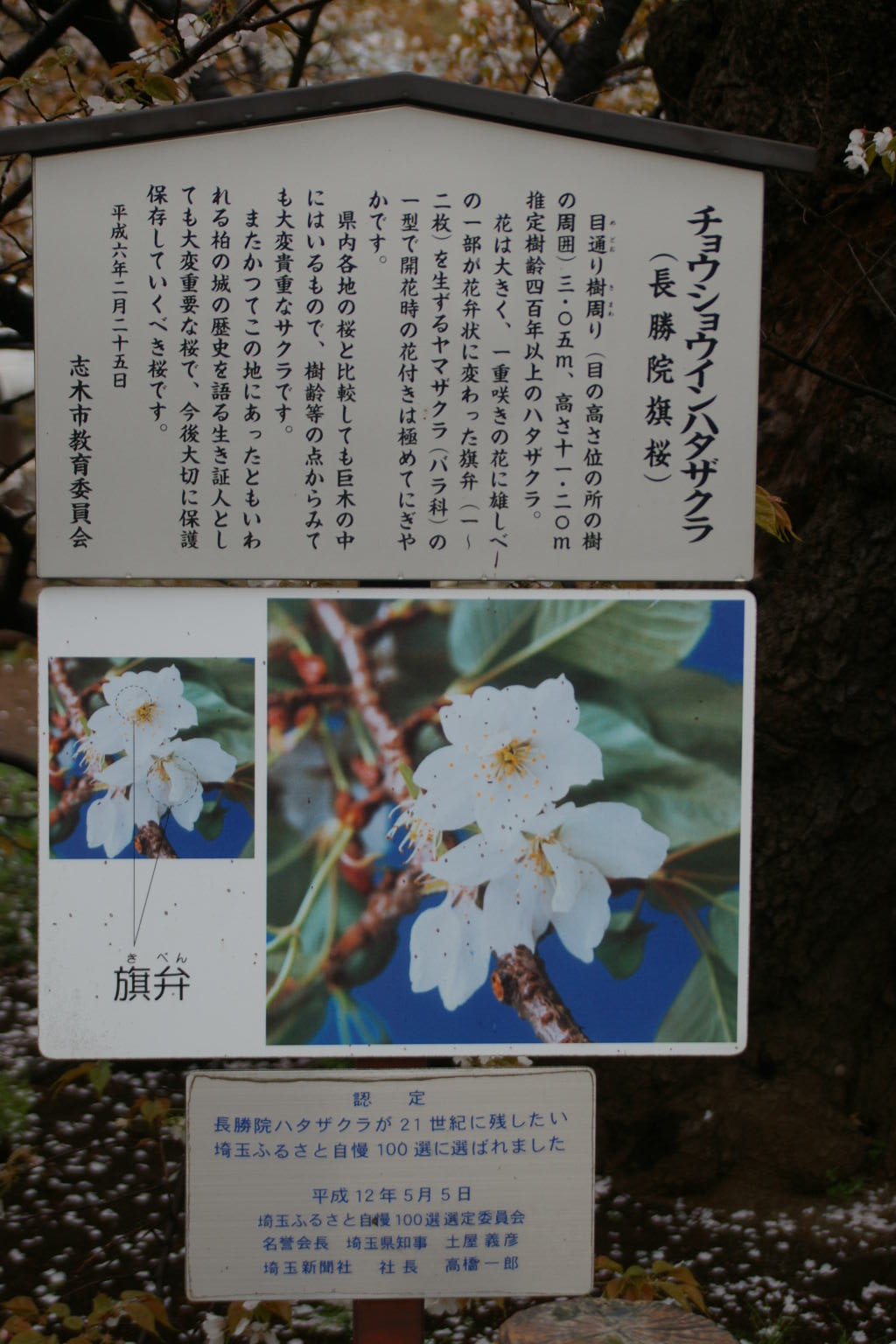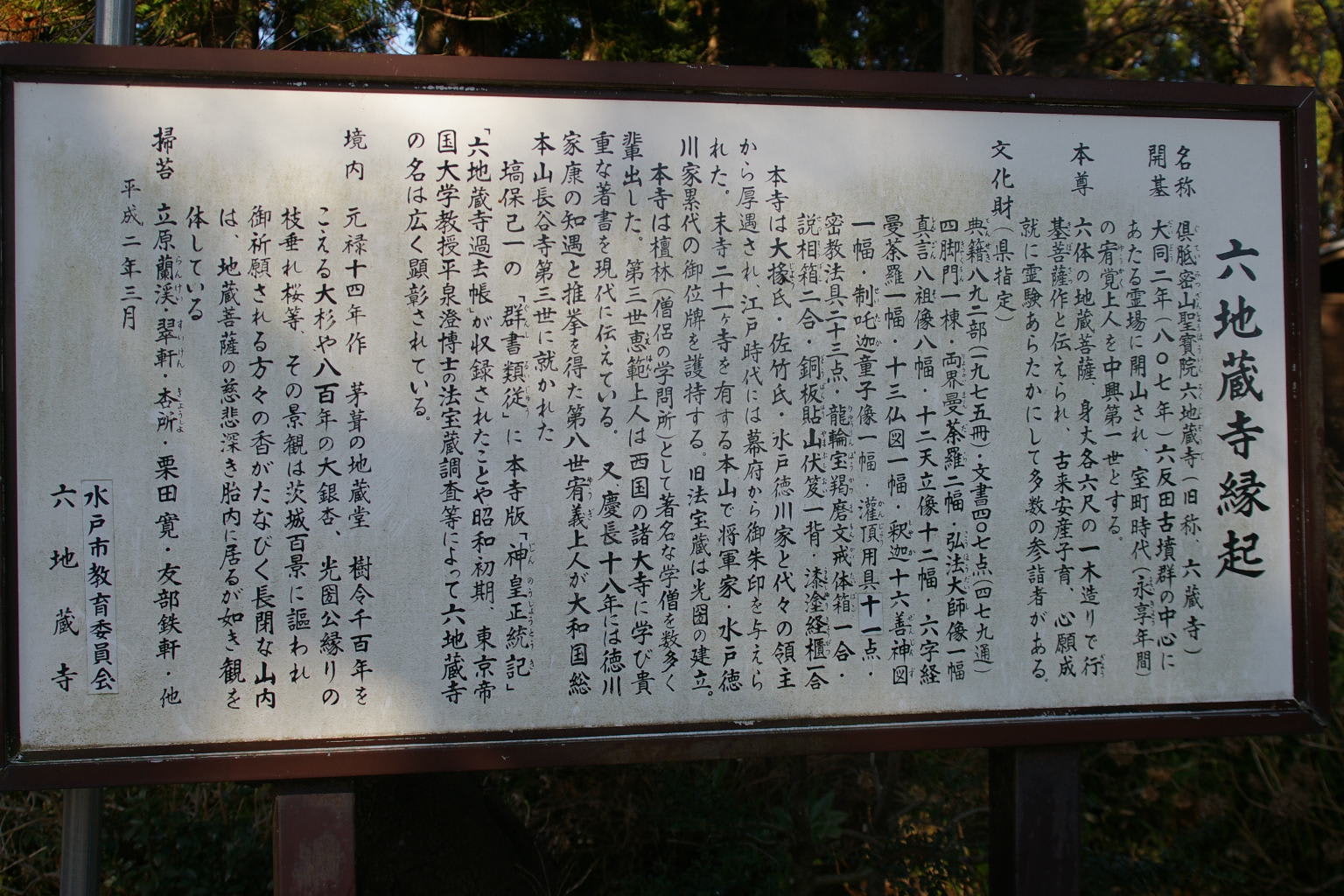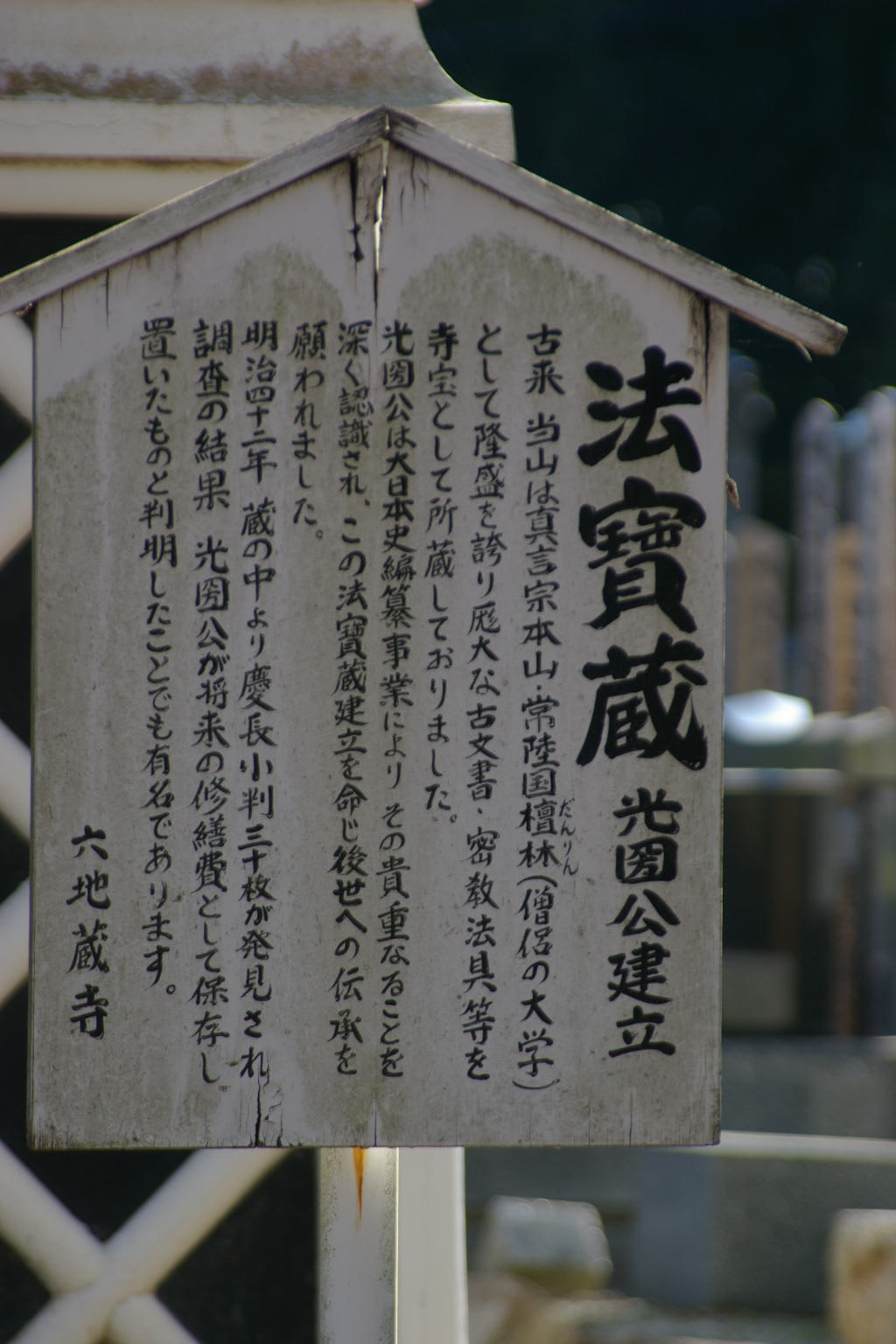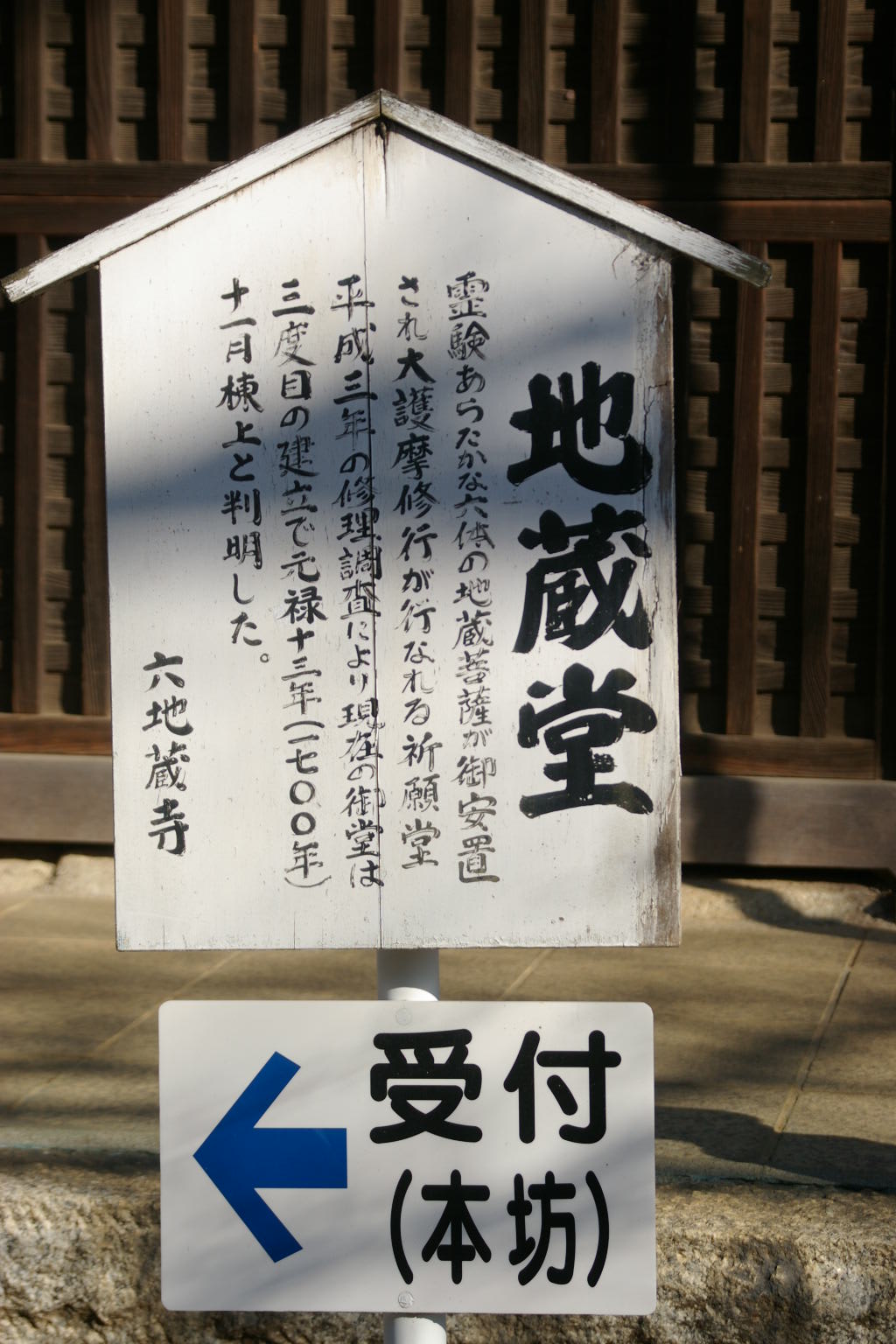宮ヶ崎館跡は、宮崎城跡の直ぐ南側にあります
県道16号線バイパスを挟んで南側に鹿嶋神社が有り
その南側の畑地の中に遺構が残っています
宮崎城跡から500m程南です
宮崎城が詰の城で、宮ヶ崎館が居館部分と言うこともできそうです


東西に延びる道路の南側に堀跡があります、堀の中は薮に成っています

堀の切れ目は虎口の趾でしょうか

堀の内側には大きな土塁が残っています、北側道路からは薮が濃くてわかりませんでした

虎口状の部分を入った内側です、北側から東側に大きな土塁が廻っています

南側へ延びる堀と土塁の北西隅の部分です、ここから南の一部が農地に成ってしまって消えています


土塁と堀跡が、消えてしまった部分から繋がって南に延びています

南側は農地化されてしまって、土塁も低く成ってしまっています
東西110m南北150mほどの方形の居館跡でした
では、次へ行きましょう

県道16号線バイパスを挟んで南側に鹿嶋神社が有り
その南側の畑地の中に遺構が残っています
宮崎城跡から500m程南です
宮崎城が詰の城で、宮ヶ崎館が居館部分と言うこともできそうです



東西に延びる道路の南側に堀跡があります、堀の中は薮に成っています


堀の切れ目は虎口の趾でしょうか


堀の内側には大きな土塁が残っています、北側道路からは薮が濃くてわかりませんでした


虎口状の部分を入った内側です、北側から東側に大きな土塁が廻っています


南側へ延びる堀と土塁の北西隅の部分です、ここから南の一部が農地に成ってしまって消えています



土塁と堀跡が、消えてしまった部分から繋がって南に延びています


南側は農地化されてしまって、土塁も低く成ってしまっています

東西110m南北150mほどの方形の居館跡でした
では、次へ行きましょう



































































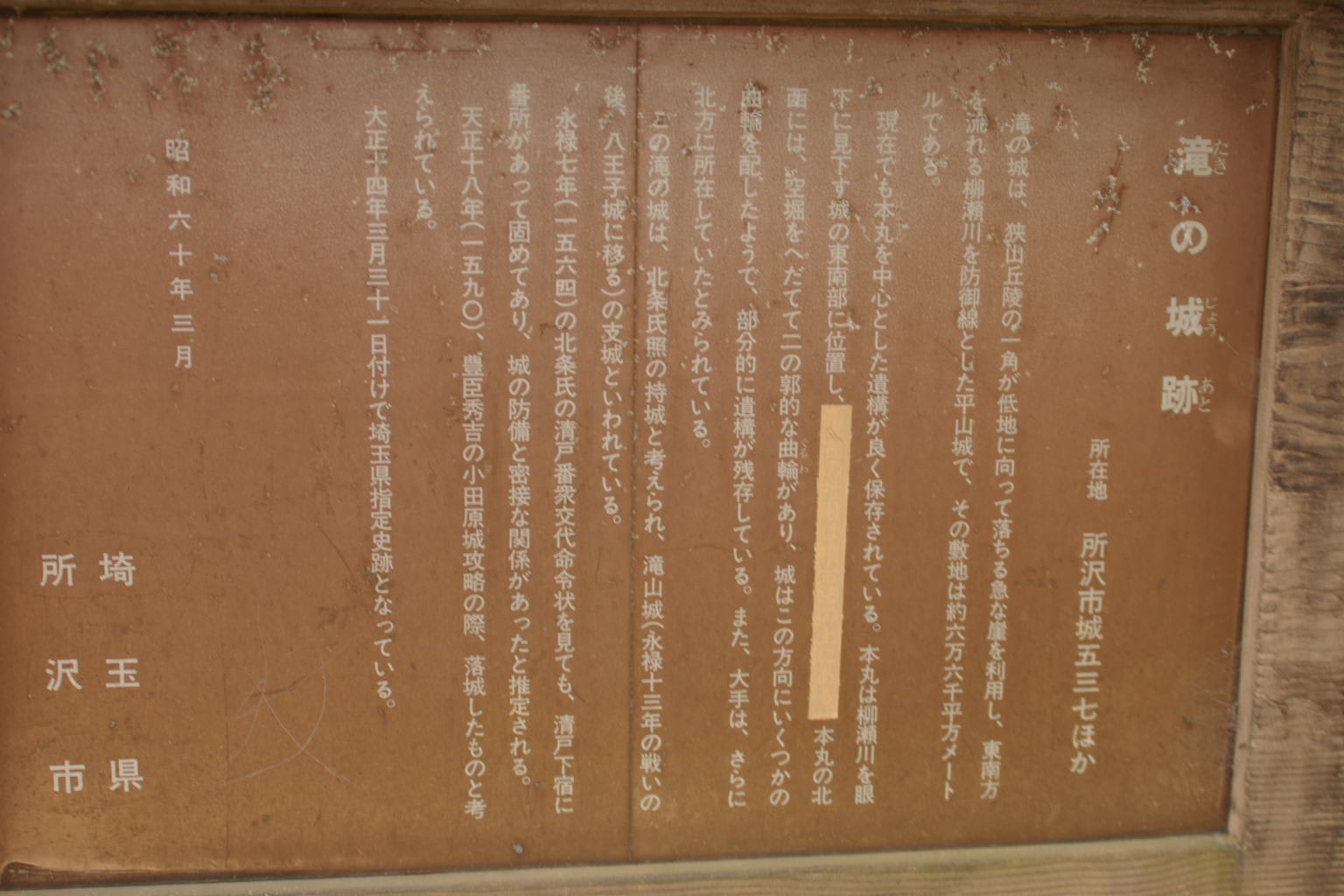
























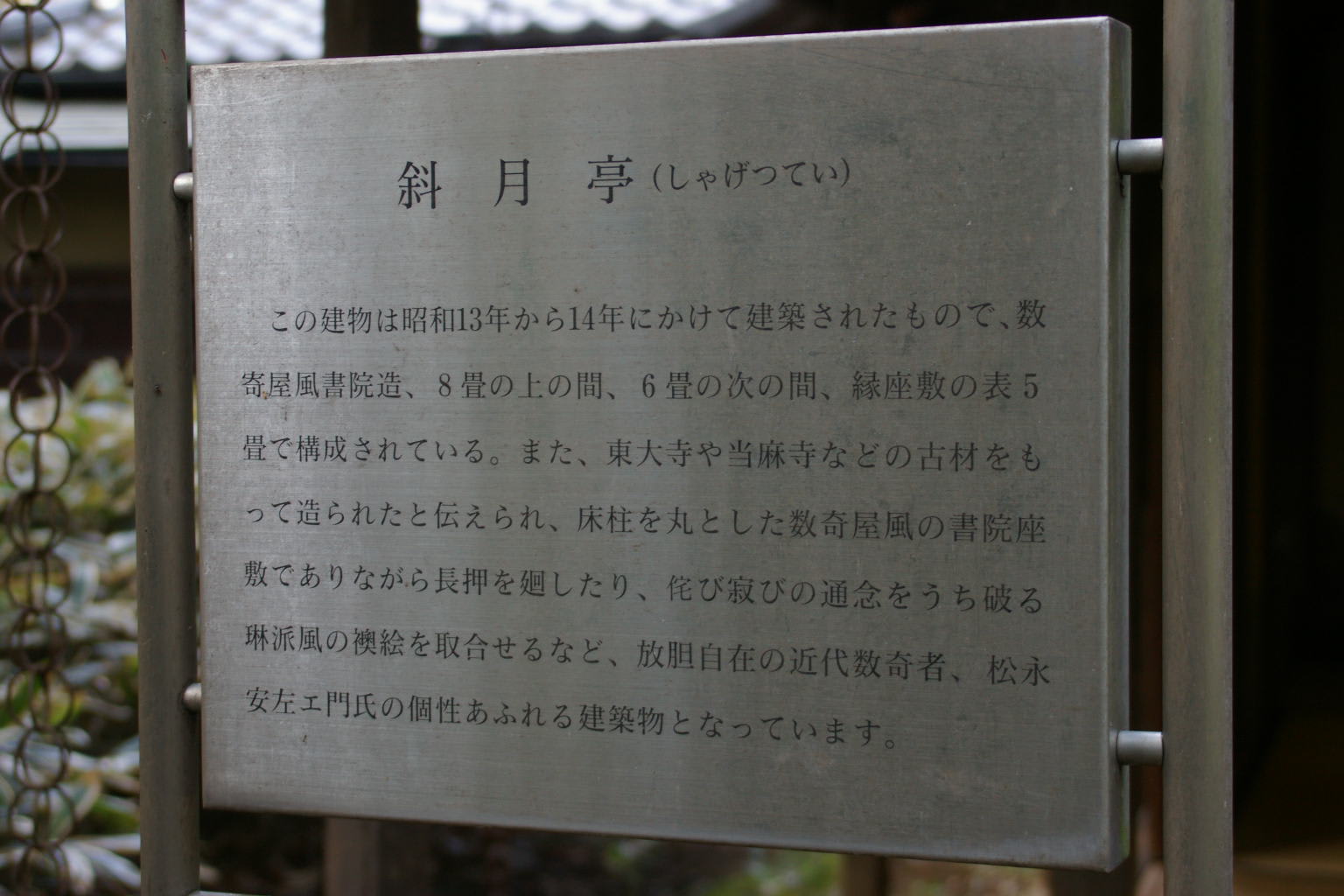


































 花びらが地面を覆います
花びらが地面を覆います