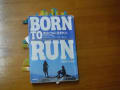2020.7.9(木)曇り
般若心経について続きが書けていないのは多忙であったためもあるが、一体何のために書かれたものだろう、一体何を伝えたいのだろうと素人なりに考えていたためである。勿論そんなことが解明できるのは何年も禅の修行を行ってはじめて出来ることなんだろうが、凡人の戯言として聞いて頂きたい。
この間、連日唱えてなんとか憶えることが出来たが、水上さん同様悟りの境地に近づくこともできない。世の熱心な仏教徒の方も、偉いお坊さんも果たして悟りを開いておられるのだろうかといぶかしく思えてきた。空になるなんてことが生身の人間にはとても無理なことじゃないかと思っていたら、松原泰道氏の「色即是空」の教えとは何かという節の中に「空」には消極的な「空」と積極的な「空」があって、前者はあくまでゼロと考えるが後者はすべてのものは単独では存在しえない、ありえないというもので、「無我」という言葉が近いと言われる。一体どういうことか解らないと思うが、続いて「「無我」とは孤立自尊の事ではなく「他と相互に関わり合い依存し合って初めて存在できる事実を深く認識することなのです」とある。平たく言うと「空」とはゼロではなく人と人、物と物が相互に関わり合って成り立っているということらしい。自分の周囲の人や物に感謝して、相互に依存し合って生きていくというなら生きていく人々を応援する仏の教えとして充分に納得いくのだが、あくまで松原氏の解釈であって、般若心経を直訳して果たしてそのような事が書かれているとは思えないのである。
偉いお坊さんが解釈して諭してくれるのだから、凡人のわたくしどもは黙って従っていればよいのかもしれないが、般若心経が一体何のために誰によって書かれたものなのかなどと考えると、迷宮に入り込んでしまうのだ。つづく
【今日の”のびちゃん”】NO. 33

おりこうさんでお座りしてるように見えるでしょ。ところがこれ押しても引いても動かない困った行動なのだ。散歩の途中で頑として動かなくなる妙な行動である。自己主張するようになってきたのかな?
”うかれめのストライキ、さりとはつらいね ”
”