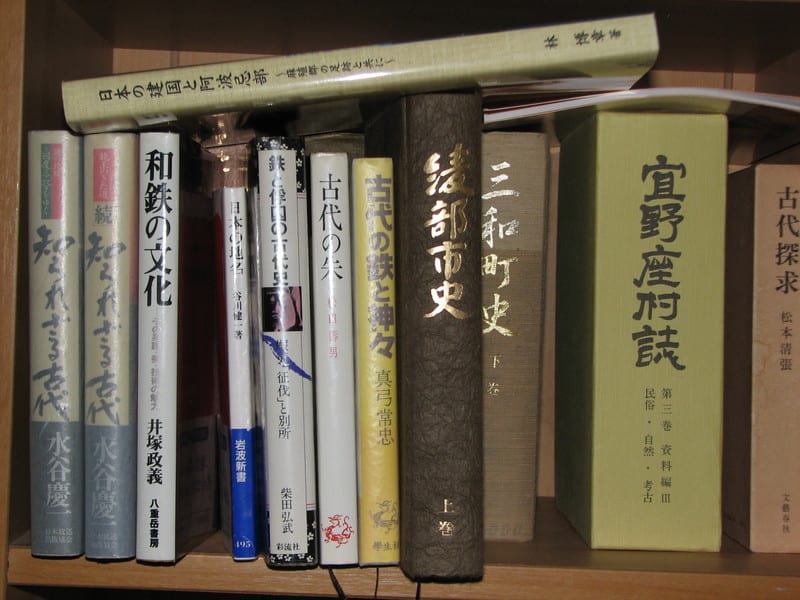2009.11.19(木)曇
引地のことの続きが長い間書けなかった。この間なんとか引地地名の解読手がかりが無いものかと各種の書籍を読んだり、インターネットのサイトを探ったりしてきたが、どうもそれらしいものには行き当たらず、やむなく豊田市の引地を続けて紹介することとした。
j 豊田市中立町引地、足助白山町引地
足助の北北西3Kmあたり、矢作川の支流の支流の源頭近くに存在する。京和カントリークラブの北西に接し、県道344線沿いあたりだ。地形的に特徴的なものは見あたらない。矢作川の支流沿いに下切、中切、上切という地名がある。足助川の上流域にも同様三つの地名があり気になるところである。他に気になる地名は下引地、湯ノ木など。他に~洞地名が嫌というほどある。洞地名は洞地形から来る地名ということを書いたが、ここまで数があるとちょっと疑問を感じる。韓国にあるように、~村というような意味があるのだろうか。もう一つカタカナ地名の小字が多いことである。ビワクビ、ビンダライ、ホドイシ、ナメラ、ハシカガタ等々日本の国内かという地名が続く。洞地名とカタカナ地名は研究の余地がありそうだ。県道344号を南西に行くと中金町があり、東に行くと大蔵町、大蔵町から県道33号線を南に行くと足助白山町があり、そこにも引地がある。実はこの足助白山町はヤフーの地図では出てこなくてグーグルの地図で見つかったものである。縮尺を大きくしてみるとこちらの地図は小字が詳しく掲載されている。地図としてはヤフーの方が見やすいので、そちらを使ってきたが、地名を研究する場合は小字までしっかり載っている方が意味がありそうだ。ただ、航空写真はヤフーが見やすいし、地形図はグーグルだったりして、一長一短がありそうだ。
足助白山町引地は中立町引地から直線距離で1Kmあまりのところである。これだけ近距離に同じ字名があるのは不思議な感がする。引地の周りの気になる地名は、上金田、西佐切田、中佐切田、東佐切田、佐切田前などである。
k 山ノ中立町引地
足助川の支流神越川の流域に存在する。今までの引地は川の源流近くの谷沿いにあったが、この地は少し違うようだ。国道420号線と県道364号線に挟まれた丘陵状に在るように見える。ただ航空写真で見ると西からの谷の源頭のようにも見える。神社とその周りに数軒の家、段々になった耕地が見える。丘陵地であり、低地で水害が起きやすいという地形ではない。気になる地名は西洞、中洞、東洞、西ノソンデ、日向。
l 豊田市日面町引地
矢作川上流笹戸温泉の西に蚕霊山(434.9m)という山があり、蚕霊山神社が祀られている。サンレイサンかと思えばコダマサンと読むそうだ、読めないねえ。その山の西南尾根上に引地はある。ここも山ノ中立町引地と同じく山稜上にある。近隣の気になる地名はガンバガソラ。
m 豊田市永太郎町引地
蚕霊山の北4Kmのところに永太郎町引地がある。この地も丘陵状のところにあり、近隣には地蔵洞、法師洞、月ヶ洞などがある。
以上豊田市の東部に16ヶ所の引地がある。共通点といえば山の奥まったところにあるくらいだろうか。ほとんどが谷の源頭近くにあり、無理にこじつけようとしたら飲み水や農業用水の引き込み場所とでも考えられそうだ。そう言う意味で過去に調べた引地を比較検討すると、確かに水源となりそうなところが多い。しかしこれだけ普遍的な地名となれば、独特の地形、独特の役目を持つところであっても良さそうだ。というわけで、もう少し調査を続けたい。
【作業日誌 11/19】
木小屋造り14日目(背面筋交い塗装)
今日のじょん:食事やうんPのリズムが狂ってきている。かみさんが必要以上に心配するので、悪循環しているようだ。じょんは神経質な犬なので人間の心模様を察しているようだ。どちらももう少しおおらかにすることが解決のポイントだと思うのだが、、、、。困ったちゃんですね~。