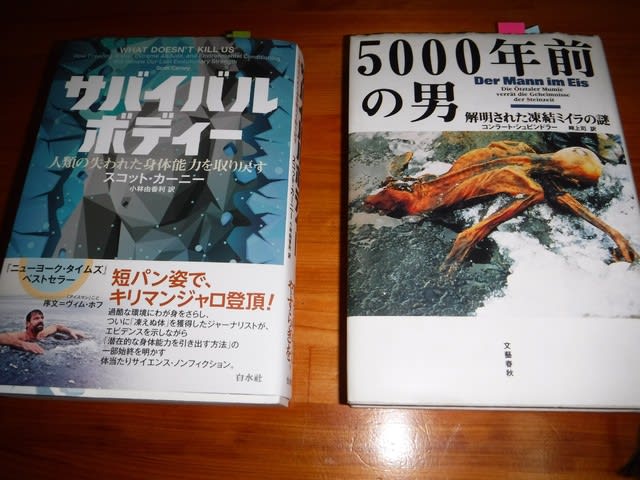2019.9.23(月・祝)
ベアフットランニング(Barefoot Running・裸足走行)が注目を浴びている。ランニングのありかたが根本的に変わるもので、双方から様々な意見が飛び交っている。裸足歩行を推奨実践しているわたしとしては他人事ではない。ランニングもウォーキングも同じ足を持った同じ人間が行う行為だからだ。実はこのことに関してわたしは明確な見解を持っている。いずれ発表することとなるが、その前に足に関する書物を順次紹介したい。一般的にはあまり読まれない分野だと思うが、足というのは奥深いものであり、我々の関心事である健康や長寿、病気や免疫、人類の進化や未来について実に密接に関係するものである。まずは古典から始めたい。
「足の話」近藤四郎著 岩波新書 1979年10月発行

足について書かれた書物では今のところ最も古いだろう本である。足の古典といって良いだろう。もう数年前に読んだもので、その時点で雨読に投稿しておけばいいものを今日になって書いているので、記憶が怪しい。
足や歩行について研究を進めるならまずこの本を読んでいただきたい。足、脚の違いや素足、裸足の違いなど今日混同されがちな用語がはっきりと区別されている。
また、歩行の基本である「あおり」についても初めての記述ではないかと思う。「ヒトは足を外から内へあおって歩く」ということを関取の歩みを見て発見されたそうだ。このことは足裏の荷重という意味で大変重要な原因となる。
ロコモーションや姿勢、ヒトと足の進化、履き物の起源などについて興味有る記事が掲載されているが、裸足歩行が足のためによいと提唱されたのはわたしが読んだ本の中では最も古い。そのなかで近年よく言われるメカノレセプター(受容器)についても言及されているのはすばらしい。
【今日の”のび”】NO.4
じょんの時はコンパネでフェンスを作ったが今はそんな馬力もなく、出来合いのフェンスを買った。
これがなかなか優れもので、この出入り口はかみさんのお気に入りである。