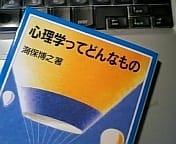6 集中してリラックスする
瞬発カを発揮するまでのリラックスの話をしてきたが、それ以上に大事なのは、瞬発力を発揮する瞬間のリラックスである。最高に集中した状態でリラックスすることができたら、すばらしいカが発揮できる。
テニスでは、サーブ、レシーブの際に相手のサーブがコートを外れてしまった時にも、思わず球を打ち返すことが多いのだが、そういう時に限って、実にすばらしい球が相手のコートに返る。カを抜いて無心に球を打ち返すのがいい結果につながるらしい。これが「集中してリラックス」の例である。
テニスの講習を受けたりすると「ハイ、そこでカを抜いて」というアドバイスをもらう。わかってはいてもまずできない。カを抜くことを意識すると、かえって力が入ってしまう。これができるかどうかがアマとプロの違いかと、絶望的になる。
坐禅のエキスパートの坐禅中の脳波をとると、普通の人がボンヤリしている時に出てくるアルファ波が見られる。しかし、坐禅を組んでいる人が、まさかボンヤリしているとも思えない。一種の集中状態にあるはずである。普通の人が、何かに集中すればベータ波が出てくるのに、坐禅では集中してもアルファ波が出てくるらしい。
図 典型的な脳波と精神状態
多分、坐禅中の心の状態が、ここで言う「集中してリラックス」にあたるように思われる。こんな状態になりたいものであるが、そのためには、膨大な訓練が必要のようだ。ただ、こういう状態のあることを知っておくと、何かの時に自分でも体験できるかもしれないと思い、紹介してみた。
図 集中と緊張を組み合わせると p219の図


















 脳への還元のほかに、最近では、遺伝子への還元も注目されている。性格を遺伝子配列によって説明しようとする話さえある。かつては、体液への還元説もあった(ヒッポクラテス;460-377B.C.)。すべて、物質的な基盤に心を還元しようとするものである。
脳への還元のほかに、最近では、遺伝子への還元も注目されている。性格を遺伝子配列によって説明しようとする話さえある。かつては、体液への還元説もあった(ヒッポクラテス;460-377B.C.)。すべて、物質的な基盤に心を還元しようとするものである。