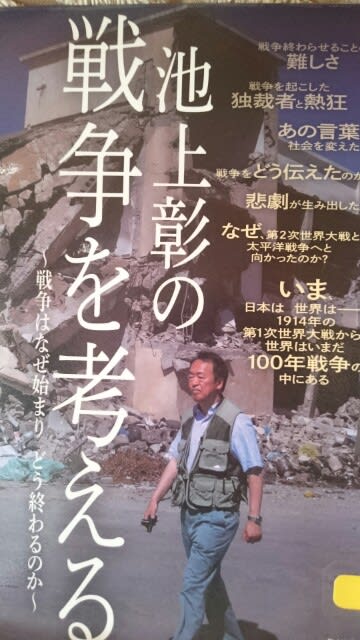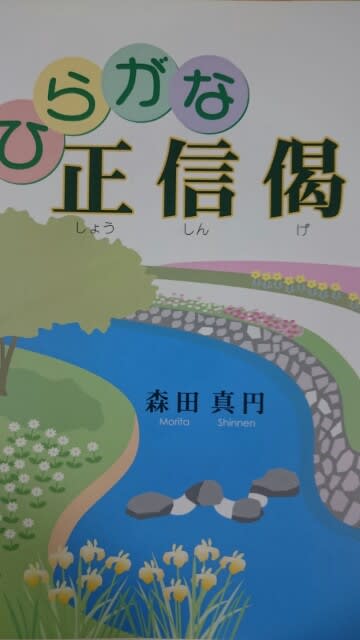
昨日はお隣、神埼市のJ寺様の巡番報恩講にお参りさせていただきました。
美しく見事な本堂、お荘厳。美味しいおとき、別室ホールでは、美味しいコーヒー、ご講師の森田真円師の書籍や念珠、門徒式章などお参りグッズの販売まで。
法要前には、バイオリンとピアノの演奏
 もあり、美人のお二人が奏でる美しい音楽にうっとり、夢心地。
もあり、美人のお二人が奏でる美しい音楽にうっとり、夢心地。
さて、法座、
森田先生のご著書は拝読していましたが、直接、ご法話を聞かせていただいたのは初めて。
浄土真宗で平素お勤めする「正信偈」(浄土真宗の教えをギュギュッと凝縮し、偈(げ:詩)として、あらわしてくださった親鸞聖人が書かれた聖教)の後半部分で、
七高僧(お釈迦様の後、インドの龍樹菩薩に始まり、日本の法然上人まで、阿弥陀如来の真宗の教えを伝えてくださった7人の高僧)のうち、3番目の中国の曇鸞大師の箇所について、中国の歴史を交え、大変わかりやすくお話くださいました。
先生の著書「ひらがな正信偈」のエピソードなど引用しながら、お話くださいましたが、本を読んだだけではスルーしてしまうところ、やはり、肉声で聞かせていただくと、スーと頭に入り、しみじみ味わせていただきました。
全てに感動した、最高に仕合わせな1日でしたので、きょうも、午後からお聴聞させていただきました。


お参り前、J寺さん駐車場係のご門徒さんが、
「ごゆっくり、お聴聞ください。どうぞ、ごゆっくり
 」
」と、声をかけてくださいました。
お言葉通り、心身ゆっくり、仏前に座らせていただきました。ご縁に恵まれ、本当に有り難いことでした。至福のひとときでした。

「巡番報恩講」って、本当に素敵

 (当番会所は大変ですが、お参りに行かせていただく側は、ホント楽しい
(当番会所は大変ですが、お参りに行かせていただく側は、ホント楽しい )
)J寺さん報恩講は、明日日曜日が、ご満座(最終日)です。










 と仰ぎ、自分の姿に気づかされる
と仰ぎ、自分の姿に気づかされる 全国のお寺の数はコンビニに数より、ずっと多い。
全国のお寺の数はコンビニに数より、ずっと多い。