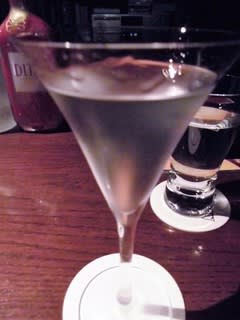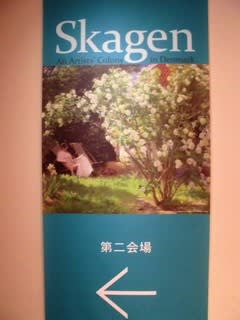今日は悩んだ結果、国立西洋美術館から見ていくことにした。開館の15分前に着くが、予想を上回る行列(50人くらい?)。外国人の団体客もいるな。しかし、この展覧会って、人気あるんだっけ?
■国立西洋美術館「シャセリオー展」。
シャセリオー「16世紀スペイン女性の肖像の模写」:古典的な技法を完全再現。素晴らしいテクニックだ。
シャセリオー「プロスペール・マリヤの肖像」:黒地に黒服を着た男、完成された肖像画と言えるだろう。
シャセリオー「黒人男性像の習作」:宙に浮かぶかのような黒人男性、そして周りに手のスケッチ。完成していないところが面白い。
ギュスターヴ・モロー「アポロンとダフネ」:シャセリオーと関係があったのは、アングル、モロー、ルドンなど。私の好みでもある。
シャセリオー「サッフォー」:今まさに崖から身を投げんとする女性。目力が強い。
ギュスターヴ・モロー「牢獄のサロメ」:細かい所が上手いんだよな。
シャセリオー「泉のほとりで眠るニンフ」:森の中で眠るニンフという幻想性と、モデルがアリス・オジーという女優だったという生々しさが両立。
シャセリオー「カバリュス嬢の肖像」:古典的な肖像画というよりは、幻想性を感じさせる。白い服と白い手に目が行くね。

シャセリオー「授乳するムーア人女性と老女」:東洋的なものにも興味を持ったらしく、目力のあるオリエンタル美女が得意。
ほぼ先頭で入ったので、全くストレスなく見ることができたが、私が見終わるころには作品の展示している前は完全に人がつながった状態になっていた。しかし、あんなに沢山いた行列の人たちはどこに行ったのだろう。
と、思い常設展示場に行くと、世界遺産登録のせいか、建物をしきりに撮影している人が多かったな。
常設展示は昔紹介したものもあるはずだが、いくつかの作品をお見せしたい。
エル・グレコ「十字架のキリスト」。これが常設してあるというのは流石だ。
↓

スケッジャ「スザンナ伝」。2015年の新収蔵品。
↓

14世紀シエナ派「聖ミカエルと竜」。小動物をいじめているようにも見える。
↓

ロダン「オルフェウス」。
↓

レオナルド・ビストルフィ「死の花嫁たち」。
↓

シャヴァンヌ「貧しき漁夫」。
↓

ハンマースホイ「ピアノを弾く妻イーダのいる室内」。ピアノを弾くと言いつつ、何とも言えない静寂感。
↓

また、常設展示場内では「スケーエン:デンマークの芸術家村」と題した、展覧会が開催されていた。
ミカエル・アンカー「ボートを漕ぎ出す漁師たち」:報道写真のような、プロレタリア風絵画。
ぺーダー・セヴェリン・クロヤー「スケーエンの南海岸の画家たち」:逆光で海が輝き、ヨットが走っている。
ぺーダー・セヴェリン・クロヤー「クリストファー邸の前で、スケーエンの真夏の夕べ」:北欧の夏は日が長く、どこか北海道に近いものがある。
ミカエル・アンカー「海辺の散歩」:女性5人の優雅な散歩。
ミカエル・アンカー「草原を歩くアンカー夫妻と娘ヘルガ」:これは印象派の明るさだ。
ぺーダー・セヴェリン・クロヤー「室内で漁網を直すクリストファー」:パイプをくわえたいい男。
ぺーダー・セヴェリン・クロヤー「ばら」:薔薇の向こうでデッキチェアに座り新聞らしきものを読む女性。
ミカエル・アンカー「奴は岬を回れるだろうか?」:むんむんと男くさい、漁師たちの集団。
ぺーダー・セヴェリン・クロヤー「刺繍をするマリー・クロヤー」:美人の奥さん自慢という感じか。
どの作品も、素晴らしい天候の元、のびやかに描かれている。また、地元の漁師の肖像も多く、いい関係を結べていたのではあるまいか。
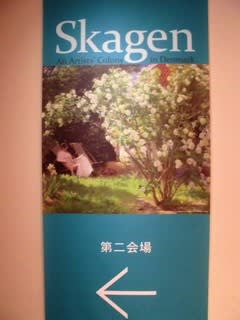
こういうのを見る機会というのは、羨ましいものだ。