― 一昨日のことだが、郵便局のATMで、「ずる」をしたおばあさんがいた。 ―(猫猫センセ)

http://yanagisawalab.org/message/post-2.html#Q.6 より。 本愚記事とは何の関係もありません。
ネットで話題になっている研究不正のこと。東京大学の分子細胞生物研究所(web site)のある教授の研究室(ラボ)から刊行されている学術論文において、実験結果の画像などが使いまわしにされていると「告発」されているらしい。
告発サイト; 東京大学 分子細胞生物学研究所の類似画像掲載論文
⇒ わかりやすい解説サイト
興味深いのは、この東京大学の分子細胞生物研究所のうわさの教授のラボでかつてこの教授と一緒に研究をしていたらしい研究者が彼らが独立した後も同様に「実験結果試料=画像の使いまわし」をしている可能性があること。
「実験結果試料=画像の使いまわし」とは端的に言って、画像処理を伴うコピペ(コピー&ペースト)らしい。
おいらが、知りたいのは、もしこれらが不正行為だとしたら、彼らは自覚的に悪いことだと思って遂行したのか?それとも、画像処理を伴うコピペは普通の研究行為であると認識していたかである。
つまらないたとえ話でいうと、信号無視と信号見落としがどちらが重大事故に結びつくかと言えば、これは信号見落としなのである。信号無視は「悪いこと」をしているという自覚と事故が起こりうるというリスクを抱え、一生懸命、注意を払い、遂行するのだ。
その視点から、今回の「一連」の画像処理を伴うコピペによる試料・画像の使いまわしはどうなんだろう?
まさか、公開されても、使いまわしの画像は、誰も照合なんかしないだろうと、高をくくっていたのだろうか?
それとも、画像処理を伴うコピペによる試料・画像の使いまわしは東大仕込の当たり前の研究行為だと信じ、なんら悪いこととは思わず遂行してきたのだろうか?
どうも、自覚的悪党であったとは思えない。
だからこそ、問題は深刻なのだ。「愚か者は邪悪な人間よりも始末が悪い、といったのだ。つまり、邪悪な人間はときどき邪悪でなくなるが、愚か者は死ぬまで治らないからだ。」という観点から見て。
もっとも、分子生物学会では「画像処理を伴うコピペによる試料・画像の使いまわし」は標準なので、なんら問題はないのかもしれない。
秀才バカ=ストーリーにあわせて「証拠」を揃える。
最近のぬっぽんのエリートさまの愚行で記憶に新しいのが検察官によるデッチあげ調書。
まさに、ストーリーにあわせて「証拠」を揃える、という愚行だ。
でも、犯罪捜査にしろ、科学研究にしろ、疑いや仮説なしに、捜査や研究は始まらないし、進まないのだ。これは原理的にそうなのだ。
犯罪捜査だって「容疑者」を列挙し、捜査する。あたりまえだろう。戸籍の「あいうえお」順で人々に話を聞いたりアリバイをとったりするわけではない。科学もそうだ。仮説があって、それを実験で検証する。
でも、犯罪捜査は知らないが、科学研究ってのは仮説がそのまま科学的結論になることなんざ、まぁない。実験すると、そうならない(事実)。もっとも、それはおまいがバカだからだという指摘はあるだろう。そして、いるのだ、仮説が百発百中の研究者さまが。そうい研究者さまは自分の脳内で考えついたことが「真実」なのである。だから、そういう真実である彼の仮説に反する実験結果(事実)が出ると、「<事実>は<真実>の敵である!」と叫び、槍を持ってロシナンテにまたがり、<真実>にあった<事実>をコピペしちゃうのだ。あるいは、仮説を支持する<事実>をコピペで作製するのだ。
こあたりの実感はKOデーガクの教授さまが書いている;
しかしデータの取り扱いは難しい。昔どなたかが”よい論文は良質の推理小説のようなものだ”と言われたことがあるが、どうしても論文にはstoryが欲し くなる。そこでデータを捏造するのは論外で、そんなのは研究者をやる資格はない。本当のフィクションになってしまう。しかしstroyにあうかあわないか わからない微妙なデータも出てくる。そこで話にあうチャンピンデータを選ぶことになる。 このプロセスは必ずしも間違っているとは言えない。その場合は必ず他の方法論や次のステップ(そのデータから派生する次の仮説)のデータで当初の仮説は補 強されなければいけない。あやふやなデータのみでできた論文はどんなにstoryが魅力的でもやがて淘汰され忘れられる。某先生にいわせると”商業誌に出 る論文の半分は嘘”だそうだが、そこまで極端なことはないとは思うが確かにTwo-hybrid全盛時代に出て来た分子の多くが忘れられている。手前味噌 で恐縮だが正しいものはSOCSやSpredのように何年も続いていくし他の研究者も参入してくる。なのでstoryが怪しいことをいちいち咎めるのは時 間の無駄かもしれない。科学の仮説がすべて正しいわけではないことは皆よく知っているし、間違った仮説や定説を否定しながら科学は進歩してきたことは歴史 が証明している。酒井先生の本には”間違いを恐れては独創的な仕事はできない”と書かれている。 (先週の講演/仮説とデータの関係 )
それにしても、今回多量に指摘されている画像処理を伴うコピペによる試料・画像の使いまわしは、彼らが、そういう真実である彼の仮説に反する実験結果が出ると、「<事実>は<真実>の敵である!」と叫び、槍を持ってロシナンテにまたがり、<真実>にあった<事実>をコピペしちゃうのだ。あるいは、仮説を支持する<事実>をコピペで作製するということをルーチンでやっていたのだ。
不思議なのが、そんなことしてもいずればれるだろうと思わなかったのだろうか?
他人を欺かん欲するものはまずは自らを欺け、ってことで、画像処理を伴うコピペによる試料・画像が<真実>と信じ込んじゃったのかな?
もちろん、他人を欺かん欲するものはまずは自らを欺け、は愚者の選択。
悪党の選択する信条は、ばれる嘘はつくな!である。
これからの彼らの弁明に注目したいが、彼らは、問題は<真実>なのであるから、支持証拠は二の次だ、とでもいうのだろうか?
これではもちろん吉村センセの言うように、しかしそれと意図的なデータの改ざんは全く別物でこれは罪が大きい。たとえ論文の内容は間違っていないと言ってもそんな行為を許していると今のような科学の社会システムが成り立たない。データのひとつにでも改ざんがあるとすべてが疑惑の眼で見られ認められなくなる。
▼まとめ; やはり、プライドは大切だ。
 って謎かけ。[1]
って謎かけ。[1]












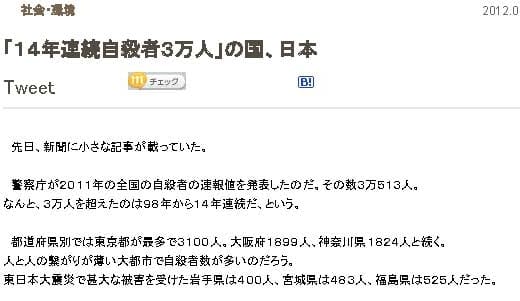
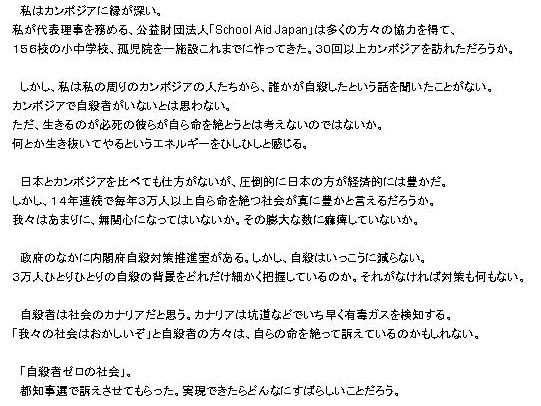





























 「
「






