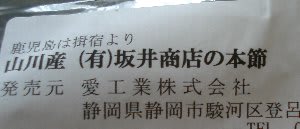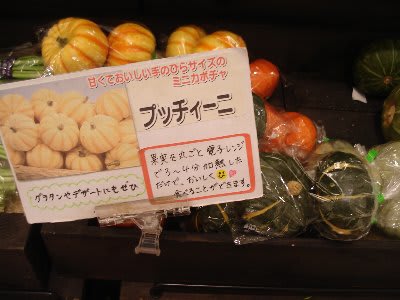― 昨日から夏になった。昨日の筑波山麓 ―
懸案だった、闘いうどん氏の『福田恒存 VS 武智鉄二 ―西洋か伝統か、それが問題だ!』を読むことにす
― 昨日から夏になった。昨日の筑波山麓 ―
懸案だった、闘いうどん氏の『福田恒存 VS 武智鉄二 ―西洋か伝統か、それが問題だ!』を読むことにするということを先週木曜日に書いた。読むこととオマージュをささげることは大違いなので、苦労する。今回闘いうどん氏作品を読んで、福田恒存全集をひっぱりだそうとしたことが収穫。『近代の宿命』、『芸術とは何か』などをbrowseする。それで、思いついたことを書くことで、闘いうどん氏作品オマージュとしてささげるかわりとする。各段落に論理的流れはない。あくまでも、思い付き。
■
ゲルマン人の"武智鉄二"っているのかな? that is my question
『福田恒存 VS 武智鉄二 ―西洋か伝統か、それが問題だ!』の要点は、現行演劇における主要素を「西洋」に求めるのと「伝統」に求めるのとどちらに価値があるかとういうことをめぐる論争についての議論。ところで、演劇という芸術は言語的要素(せりふ)と非言語的要素(音楽、舞台装飾)から構成される総合芸術である。福田恒存 と 武智鉄二は「西洋」対「伝統」という対立軸とあわせて「言語」か「非言語」という対立軸もある。
なぜ、福田恒存が「西洋」・「言語(せりふ)」を重視するのかという闘いうどん氏の説明が福田が近代の確立を図りたかったからだというものだ。つまり、この論文はもう演劇論などに収まるものではなく19世紀以降の日本の芸術を含む文明状況における「西洋」対「伝統」について語ることを意図しているものととれる。もうおいらの手に負えない。さらには、
物部氏蘇我氏の争いにもつうじているというのだから、何も近代日本の運命ということばかりでもなく、列島における外来と土着の抗争史に一般化される仁義なき試みと知るや、ただ恐れ入るばかりである。
そこで、福田恒存の『近代の宿命』をbrowseすることと闘いうどん氏論文への思いつきを書くこととする。
・ここで驚くことは『近代の宿命』における福田恒存と『福田恒存 VS 武智鉄二 ―西洋か伝統か、それが問題だ!』における闘いうどん氏の相同性である。すなわち、イエス・キリスト、キリスト教、中世、トマス・アクイナスなど前近代から掘り起こして西洋近代を語る福田の動機の説明が"小説を、読みあさる一介の常識人にすぎぬ。ただ明治以来の近代日本文学にとって古典となった十九世紀末葉のヨーロッパ文学に源泉をたづねようとするこころみが、おのづとルネサンス以後の近代ヨーロッパ精神史へとぼくの関心をそそったまでである"と自称している。この積極的な超事大主義。いや、実は違うのだ。小説は福田にとっては入口の口実にすぎないことは明らかだ。一方、現行日本演劇を入口とする闘いうどん氏はどうなのだろうか?
・突然だが最近読んだ本に「ヨーロッパは哲学文明」だと書いてあった(『天使はなぜ堕落するのか―中世哲学の興亡』)。そうかもしれない。伝統的なヨーロッパ文明の基盤はキリスト教とギリシア哲学と言われる。別にヨーロッパを構成する主民族であるゲルマン民族の民族性は考慮されていない。つまり、ソクラテスの時代にも、イエス・キリストの時代にも、アウグスティヌスの時代にも、ニーチェやハイデガーやヒトラーの御先祖さまたちはどこかにいたんだろう。けれども、ヨーロッパ文明には寄与していないし、そもそも関係ない。"蛮族"だった彼らはローマ帝国に押し入って、キリスト教に調教、馴化されたのだ。この時、ゲルマンの土俗性の大部分が失われたのだろう。つまり、ゲルマン民族だって、キリスト教、ギリシア文化は外来文化のはずだ。
・でも調教、馴化された"蛮族"はキリスト教を信じ、ギリシア哲学を読み継いできたとされる。もっとも、ギリシア哲学の読み継ぎは連綿したものではないことは
以前、書いた。このキリスト教・ギリシア哲学も2つ相携えてというわけではなく、むしろ、キリスト教が論理的なこと、現実(自然)を無視していることの哲学からの挑戦だった。そしてこの哲学からの挑戦に応戦したのが中世神学者たちで、トマス・アクイナスたちらは"蛮族"の出であった。中世に至って、"蛮族"はすっかりキリスト教プレーヤーになったのだ。福田恒存が、演劇はなかったが、神という絶対者の元で生活者であることをほめそやす時代、演劇など不要な幸せな世界、中世である。ここに至ってゲルマン人の西洋(ヘブライズム・ヘレニズム)同化の伝統が根付きはじめる。闘いうどん氏は"福田の手足となり血肉となったのは、「伝統」ではなく「西洋」だったのだ"と書くが、正確には「伝統」ある「西洋」である。闘いうどん氏の指摘する五節問題は日本の伝統。そもそも、西洋か伝統か、それが問題だという軸が問題だ。問題は、西洋か伝統かという軸と、土着かトランス民族文明(あえて普遍とは言わない)という軸と、2つ以上の分解軸が必要。
・
「伝統」ある「西洋」を実践する恒存;"蛮族"が古典ギリシア語文献を必死にラテン語に翻訳した(愚記事;
12世紀ルネッサンス、アリストテレス翻訳事情 )。普遍的文明の継承である。伝統の遂行!一方、福田恒存はシェークスピアを翻訳することに注力した。100年後の日本語文明において(もしまだ存続していたらの話だが)注目される福田の業績はシェークスピアの翻訳集に違いない。そのころは、「進歩的文化人」とか「正統かなずづかい」とか何の事だかわからなかくなっているだろう。さらには、福田はギリシア劇の翻訳もしている。まさに、ギリシアから連綿とした西欧文明という「捏造された」伝統を信じている(演技をしてる?)。福田は日本人もがんばれば伝統ある西洋文明に連なれると考えていたのだろうか?
・闘いうどん氏は書く;
しかるに日本はどうか。福田の下す結論はつぎもようなものだ。<<いまや、ぼくたちはぼくたちの立っている位置をはっきりと見きわめている。神と理想人間像なくして、個人の確立もその超克もありえぬことを。また肯定すべき、あるいは否定すべきなにものもありえぬことを。そして獲得すべき、あるいは擲棄すべき、いかなる夢もありえぬことを。(中略)>>
この言葉を正確に理解するのは六ヶ敷い。いや不可能といったほうがいいかもしれない。日本は西洋ではないから、個人の確立なぞ絶対永久にありえないというのか。それとも西洋が通過した道を忠実になぞって、もっと西洋化を推し進めて、なんとしても個人を確立せよというのか。いますこし福田の思想の跡をたどってみよう。
たどられた福田の思想とは、「演戯とはありのままの自分からあるべき自分になること」だそうだ。そしてギリシア人というのはありのままの自分を自覚しながら、本来の自分はこんなはずではないという考えから、よごされた人間を演戯した、とのこと。一方、キリスト教の時代では神を司る教会に身をゆだね、演戯をやめ自らすすんで演出権を放棄する、とのこと。
この福田によるポンチ絵的解説はヨタではないだろうか。なぜなら、ゲルマン人は古典ギリシア時代にどんな踊りや芝居していたかはわからない。ゲルマン人はキリスト教に洗脳されて演戯はしなかったとしても、「自らすすんで演出権を放棄」という事実は証明されていない。福田によるポンチ絵的解説の原因は簡単に推測がつく。近代ゲルマン人の図書館の棚にギリシア文化・キリスト教の本が並んでいるからだ。後世捏造した系譜を本物と思い込んでいるのだ。
・
芝居と生活術
福田のポンチ絵も結果的にはそうずれていないかもしれない。なぜなら、時代が経るにつれ、あるいは戦乱などの非常時には、人間社会は伝統的な行動、ステレオタイプ的、紋切型行動様式の必然性が薄れ、恣意的な行動、他人の意表をつく行動の必要性が高まったと推定される。例えば、戦国武将、あるいは江戸初期の徳川将軍は能に耽溺した。それは唯美的動機からではなく、自らが芝居としての政治をしていたからだ。自分の演戯の稽古をしていたのだ。能のやり過ぎで(出費が激しい)周囲が困ったのが伊達政宗、徳川綱吉。彼らは演技派の武将だった。みぶり、せりふという狭い意味だけではなく、戦争、和議、交渉などに筋書きを作り、自己演出していった。なぜここで、こんな例を持ち出したかというと、福田恒存の言う、演戯は絶対者としての神と人間の関係におけるなんちゃらかんちゃらってヨタなんじゃないのかと感じたからである。
・
おしゃれなカラス
おしゃれなカラスという題の寓話がイソップ童話にあったと思う。話は、鳥の世界で誰が一番美しいかというコンテストをやることになった。白鳥か?孔雀か?当日会場には見たこともない鮮やかで麗しい鳥が現れた。優勝だ。でも、ある鳥が「この羽のひとつは私の羽根だわ」と気付く。みんなが私の羽根、私の羽根と麗しい羽根の一本、一本を抜いていくと、そこには真っ黒なカラスが残ったという話だ。黒いカラスが美しくないのか?というPC(political corerctness)問題は置いといて、ヨーロッパからさかんに文化・文物をぱくってきた近代日本こそこのおしゃれなカラスに他ならない(おいらはかつて、
「文明」乞食使節団なんて言ってるね、まぁ、お上品なこと)。
そして何より、実はゲルマン民族こそ、おしゃれなカラスにほかならない。なぜなら、ギリシア文化だって、キリスト教だって本来関係ない。ゲルマン民族から自生したものではないからだ。このことに気づき、わめいたのがニーチェだと思う。キリスト教批判。ハイデガーもその系譜だ。西洋哲学の系譜を暴露する。そして、残った真っ黒なカラスというのが、ヒトラー・ナチズムだ。おいらの妄想は膨らむ。ニーチェとナチズムは理論上は結びつかないとされているが、この麗しい羽根の一本、一本を抜いていくという実践の点で結びついているとおいらは睨んでいる。ここで重要なのは、ニーチェは自分で自らの取って付けた麗しい羽根を抜いていったのである。これは、イソップ童話のおしゃれなカラスとは違う。自生した自己否定!ニーチェが「この羽のひとつは私の羽根だわ」と気付いたのは、ニーチェが古典文献学者だったからだ。やはり、学問は必要だ。破壊のために。なお、ナチズムというのはイギリス、アメリカにも生じたグローバル現象である。ただし、このイギリス、アメリカでのナチズムの参加者がゲルマン人中心(
元来好戦的)であった(のだろう、たぶん)ことは、おいらは未確認。ゲルマン人の悪魔(耶蘇)払い!
・
そして、武智鉄二
自らは何を自生しているのか?と尋ねるのが伝統派ということであろうか?武智鉄二ってよく知らないんだけど、がきんちょの頃の思い出がひとつあった。それは彼の作品で、被曝者の女性が異常な性能力(性欲)を持ち、いろいろくりひげるという話だったらしい。それが、被曝者団体から抗議されたという事件。抗議にも屈せず上演され、たぶん、被曝者団体を圧政弾圧者よばわりしたよな記憶がある。結構いっちゃってる御仁らしい、なにしろ、太田龍とも交流があるらしいから。つまりは伝統派というより、土着派か。それも、闘いうどん氏が解説するように、必死に勉強して、探索して土着を発掘、採集していたと。つまりは、闘いうどん氏のいう「西洋」派も「伝統」派も元来自らに自生していない文化・文物を必死に勉強・探索して摂取するという点で同一である。余裕がないんだ。
それにしてもゲルマン人の土着芝居は復古しないのだろうか?
ゲルマン人の"武智鉄二"っていないのかな? that is my question
いささか走り書きにもほどがあるだろうというできになってしまったが、もう能力が尽きる。人マネ子ザル・偽毛唐国家にのこされた部分は今後の課題として、本記事を閉じよう。
"思いつきとは竟に己の夢を自己翼賛的に語る事ではないか!"ということになってしまったことをお詫びする。