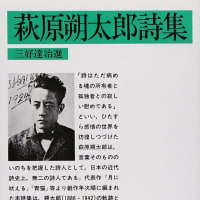アメリカも内心は気付いているはずだ。日本を駄目にしたのは自分たちであったことを。同盟国であるアメリカに今さら謝罪せよとはいわない。しかし、占領軍としてやったことを反省すベきだろう。佐伯啓思の『国家についての考察』では大橋渉の日記が紹介されている。大宅壮一の息子であった彼は、東京裁判を厳しく糾弾した。16歳だったにもかかわらず、ことの本質を見抜いていたのである。「我々人類の国家は、まだ、他の国家を裁くほど成長していないのである。我々の国家はまだゴロツキの集まりなのである。喧嘩は、鼻クソ半分である。ゴロツキの喧嘩において、誰が『おまえとこれから喧嘩するぞ、用心しておけ』といってなぐりつける奴があるだろう。‥‥一番不愉快なことは、ゴロツキのくせに、上品ぶって自己を正当化しようとすることである。ゴロツキの喧嘩は勝ちさえすればよいのである」(『詩と反逆と死』)。佐伯は「戦後の民主主義を立ち上げるためには、大宅少年のような認識は、いわば日記の中にそっとしまわれねばならなかったのである」とコメントしている。A級戦犯7人が絞首刑になったが、ようやく最近になってその裁判を疑問視する意見が大勢を占めつつある。戦後の日本においてはそれを論じることがタブーとされてきた。「大東亜戦争」が「太平洋戦争」と呼ばれるようになったのも、GHQの民間情報教育局によってであり、アメリカの歴史観が日本人に刷り込まれたのである。日本は腑抜けにされてしまい、国家は否定されてしまった。そこから抜け出すためには、日本が自信を取り戻すためには、東京裁判の見直しが必要になってくる。あくまでも「大東亜戦争」は追い詰められた戦争であった。そこで散華した者たちは無駄死にではなかったのである。
←応援のクリックをお願いいたします。