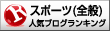音羽界隈を散策しました。
護国寺の観音堂(本堂)は、元禄10年(1697)正月、観音堂新営の幕命があり、約半年余りの工事日数でこの大造営を完成し、同年8月落慶供養の式典が挙げられた。
また元禄時代の建築工芸の粋を結集した大建造物で、その雄大さは都内随一のものと賞され、しかも震災・戦災と二度の大災害にも襲われながら姿も変えず、江戸の面影を今に伝えており安らぎの場として親しまれているところです。境内の松の木の枝がきれいに裁断されています。鐘楼もあります。大仏もあります。富士塚もあり登ってきました。
桂昌殿は、葬儀等で使用されることが多いです。躰道仲間のロック歌手の尾崎豊さんが亡くなった時もこの桂昌殿で通夜、葬儀告別式が行われ参列しました。その日は雨が降っており護国寺の周りには多くの若者たちが集まり尾崎豊との別れを悲しんでいる姿を思い出します。
音羽通りには、出版社の講談社があります。その前には豆大福で有名な和菓子の群林堂があります。江戸川橋の方へ向かうと鳩山会館が高台にあり、門のところからスロープに登っていく道があります。別称として鳩山御殿の呼ばれております。
山手線の池袋駅と大塚駅の間には大きく線路がカーブしているところがあります。 池袋跨線橋から川越街道と明治通りの下を通過する場所の線路です。
なぜ大きくカーブしているのか。
目白駅と巣鴨駅を直線で結んで山手線を設置する計画がありました。しかしその計画線上には、巣鴨プリズン(旧東京拘置所・現サンシャインシティビル)があったために線路敷設計画の変更をしなくてはならなくなり、池袋駅と大塚駅を新しく建設をして山手線を延伸して円を描いて一周する山手線が完成しました。
池袋駅と大塚駅を結ぶためには線路を大きく曲げて敷設する必要がありました。その名残がこのカーブとして存在しております。健康プラザとしまビルのところからカーブを走行する電車を見ていると壮観な気分になります。
池袋跨線橋からは、埼京線や東武東上線、そして山手線、湘南新宿ライナー線を見ることができます。鉄道のパノラマ景観として映画やテレビドラマの撮影などにも採り上げられているところです。
中央の広場には「赤い靴を履いた女の子のきみちゃんの像」があります。
神楽坂・毘沙門天
神楽坂は、大久保通りの神楽坂上から外堀通りの神楽坂下までの早稲田通りの坂道を表しております。
神楽坂は、全国的にも稀な逆転式一方通行となっており、自動車などの進行方向が午前と午後で逆転する。午前中は「坂上→坂下」(早稲田側から飯田橋側へ)であるが、午後は「坂下→坂上」となります。
飯田橋駅から神楽坂の坂を登っていくと、ユニークなお店に出会います。
日本でただ一ヵ所のペコちゃん焼き、鳥すきの鳥茶屋、肉まんの五十番、毘沙せんべいなど老舗のお店が多い。
明治期に尾崎紅葉・泉鏡花などが住み、尾崎紅葉旧居跡は新宿区指定史跡、泉鏡花の旧居跡は新宿区登録史跡になっています。また、坂の周辺には毘沙門天をはじめ、若宮八幡や赤城神社など多くの寺社が散在しています。
池袋駅からの徒歩圏で霊園内を通行する方も多く、園内に入ると緑が多く静かに感じられますが、目線を上に向け見渡すと池袋サンシャイン60ビルや豊島区役所新庁舎などの高層ビルが視界に入り、都心にある希少墓地であることを再確認できます。
夏目漱石の墓は、安楽椅子を模している。とても立派な大きな墓でいつも花が絶えないです。
墓地の中央にある案内図には著名人の墓の位置が明記されております。
また、坂の周辺には毘沙門天善国寺をはじめ、若宮八幡や赤城神社など多くの寺社が散在する。
家を出る時はまだ暗い時ですが、だんだんと空が明るくなり朝明けの中の景色が素晴らしいです。跨線橋を渡ると山手線の先方には東京スカイツリーが見えます。オレンジ色の中に浮かび上がる姿を見ていると希望が湧いてきます。
都電沿線を歩いていると朝の早い電車が通過していきます。大塚駅前にある天祖神社でお参りをしてから、大塚駅南口のトランパル広場で午前6時30分から始まるラジオ体操に参加します。50名ほどの元気な人たちが集まり朝の挨拶でコミュニケーションを図ります。都電の走る風景はとても憧れでロマンチックです。
ラジオ体操が終わると都電沿いのバラの花を見ながら歩いてイケサンパークへと向かいます。朝陽に写された自分の影を見ると足長おじさんです。サッカーの練習をしている親子がいます。東京国際大学池袋キャンパスを通過する時はいつも7時前です。風のある日は万国旗がたなびいて壮観です。
散歩の歩数は約10000歩です。家に着くと、散歩で疲れた足のメンテナンスをして一日の活動の準備をします。
毎日の歩数計算はスマホが自動的に記録してくれます。
11月中の記録は、歩数545,162歩、370㎞、 21,911キロカロリー、84時間でした。距離にすると東京から名古屋までに歩いたことに相当します。
これからも健康の為に、毎日歩いていこう。




朝陽に写された足長おじさん 東京国際大学池袋キャンパスの時計
染井霊園は、明治7年東京府が開設しております。幕末から明治に活躍した大名や活動家、学者らが多く眠るところです。染井霊園の事務所で霊園の案内図を貰います。60名の著名人の墓の場所が明示されています。
高村光太郎は、妻・智恵子の死後、詩集「智恵子抄」で国民的人気を博しました。父・光雲は木彫の第一人者で上野公園の西郷隆盛像の作者。
小説「浮雲」で言文一致の先導者・二葉亭四迷(筆名は父親から「くたばってしまえ」と怒鳴られたことに由来。
東京美術学校(現東京藝術大学)設立の起動者で日本美術の先駆者・岡倉天心。俳句雑誌「馬酔木(あしび)」を主宰した・水原秋桜子。政治家の幣原喜重郎、若槻礼次郎などの墓所があります。
隣接する慈眼寺には、芥川龍之介、谷崎潤一郎の墓があります。さらに隣の本妙寺には、江戸町奉行を務めた遠山金四郎(桜吹雪の金さん)、剣豪・千葉周作、囲碁の名人位である本因坊歴代の墓や明暦の大火(振袖火事)の供養塔などもあります。
井の頭公園の七井橋
井の頭公園の井の頭池はY字型になっていて中央部分を「七井橋」が通っています。
三鷹市牟礼に住んでいる人たちが歩いて吉祥寺に来るときに利用する人も多くおります。
この七井橋はなかなか池との調和があって風情があります。
子供の頃は木橋であり、その頃は名称は付いていなかった。コンクリート橋にリニューアルした時に「橋の名称」を公募していました。小学時代の時ではがきに書いてで応募したことを思い出します。今の橋はさらにリニューアルした最新の橋であります。
七井橋の由来は、井の頭池は湧水で池の水が満たされています。池に湧き出す場所が七つあるところから七井橋と命名されました。
池の水面すれすれのところに渡してあるので、水鳥や池の中の鯉や魚が近くで見ることが出来ます。
七井橋から見る公園の景色は昔とあまり変わっていないところがとても良いです。そして懐かしく昔の思い出を蘇らせてくれます。
5時ごろに家を出発。池袋六つ又交差点から明治通りを北へ進むと北コース(飛鳥山・すがも地蔵・大塚方面)、南へ進むと南コース(池袋駅・千登世橋・目白台・護国寺・大塚方面)を一日おきに交互に歩いていきます。
6時15分に天祖神社で朝のお参りをしてから、6時30分から大塚駅前のトランパル広場で行われているラジオ体操に参加します。60名ほどの人が集まって朝の運動をしています。
ラジオ体操が終わると都電沿いのバラロードを歩きイケサンパークを通ってサンシャインシティを廻って家に到着が7時過ぎとなります。大体朝の散歩の歩数は1万歩です。
日中も動いていますので、スマホが歩数カウントを記録してくれます。
一日平均15,000歩ほどです。
散歩の目的は、①体力維持 ②老化防止 ③体重減量 としています。
継続することにより効果も出ているようです。


大塚駅前のトランパル広場は毎朝ラジオ体操を行っています。


大塚の空蝉橋から見る東京スカイツリー 帰路はイケサンパークを通ります