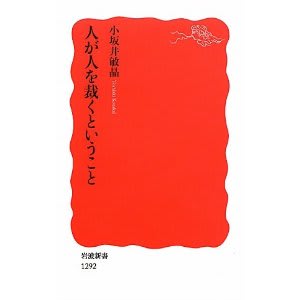2013年8月3日(土)
かつて坂口安吾が推理小説を書いたのだ。
モノグサなので、詳細は Wiki をコピペしてすます。
初出は、1947年(昭和22年)8月1日に大地書房から発売された雑誌『日本小説』で連載された[1]。同誌は「初めての中間小説雑誌」と呼ばれる。推理小説ファンの坂口が「絶対犯人を当てられない探偵小説を書く」と意気込み、犯人当て懸賞小説として連載中に懸賞金を出すことを読者に告知し、大井廣介、平野謙、荒正人、江戸川乱歩らの文人らを指名して挑戦したことでも話題になった。なお、4人の読者が犯人推理について完全答案を提出している。
この小説は江戸川乱歩が絶賛し[1]、1949年(昭和24年)、第2回「探偵作家クラブ賞」(現在の日本推理作家協会賞)長編賞を受賞した[1]。文芸評論家の七北数人は、本作は文学性を排除し、ゲーム性を重視した文体に貫かれていることを指摘している[1]。
異議あり!
なるほどゲーム性を重視してはいるだろうが、安吾一流の歯切れの良さと描写の鮮やかさは、「文学性を排除」といっては言い過ぎだ。
僕は『二流の人』の大ファンなんだよ。
安吾を教えてくれたのは、直前のメールに出てきた旧友Mだった。
この小説をめぐっては、逸話がある。
「4人の読者が犯人推理について完全答案を提出している」とあることに関連するのだが。
法学部の時代に、これまたMと並んで受講した「ローマ法」は思い出深い講義だった。
講じてくださったK先生には卒業後もよくしていただき、30年を超える御厚誼にあずかった。
このK先生の御嬢さんがまた大変なインテリであるが、話のポイントはそこではない。
1980年代前半のある日、用事で御嬢さんとお目にかかる機会があったところ、通りすがりの本屋の前でふと何か思いつかれた様子。
「面白いものを御覧にいれます」
とおっしゃって文庫本のコーナーに入って行かれる。
「この本ですが、」
と取り出されたのが『不連続殺人事件』。
「御覧になって『あっ!』とおっしゃらなかったら、今日は私のオゴリです。」
「ラッキー!」と内心ほくそ笑む。
「えっ!」とか「ギャッ!」とか言えばいいんじゃん、タダ飯ゲットね。
そして開かれた287ページ、
「あっ!」
「ほほほ、」と御嬢さん。
「犯人さがし懸賞」正解者発表
一等 完全正解(95点)賞金一万円
東京都○○区○○ △番地
KT氏
まぎれもない、K先生のお名前がそこにあった。
「あっ」と言ったら僕のオゴリ、としなかったのは、せめてもの救い。
*****
しばらくしてこの一冊を購入したのは、懐かしさと共に対抗心の為せるわざであったこと、いうまでもない。しかし時間というのはどういうカラクリのものか、「そのうち」と先延べするうちすぐに四半世紀経ってしまった。
なぜかふとやる気を起こしたのが一昨日の夜、A4の紙2~3枚に克明にメモを取り、推理小説をこんなに真剣に読んだのは間違いなく初めてだ。
暗中模索の末、昨夜ふと思いつくところがあって。
犯人の正体にほぼ想到し、そういえばクリスティの「スタイルズ荘の怪事件」でも似たことがあったなと考えた。
全ての疑問が解消したわけではないが、骨子を説明できればまずは良かろう。
あらためて先を読み進め、おおむね正解、ああよかったと安堵した。
応募総数が明記されていないようだが、書きぶりからは3ケタの来信があったものか。
正しく犯人を推定した者は8通、7件の殺人のすべてについてその動機を説明できたものは4通とあり、僕も8人のうちには入れた理屈だが、しかし、K先生のような模範答案は書けそうにない。
「特にK氏はその他のあらゆる細部にわたってメンミツ適確をきわめ、一分の狂いもなく、他の三氏にややまさっているので、氏を最上席とした。(他の)三氏は甲乙つけがたい」と安吾自身の講評。
あらゆる細部にわたってメンミツ適確をきわめ、一分の狂いもなく・・・K先生のお姿が彷彿される。
御存命中に「私も当てましたよ」と言ってみたかった。
昭和22年の一万円は大金だ、先生、何に使われたのかな・・・

かつて坂口安吾が推理小説を書いたのだ。
モノグサなので、詳細は Wiki をコピペしてすます。
初出は、1947年(昭和22年)8月1日に大地書房から発売された雑誌『日本小説』で連載された[1]。同誌は「初めての中間小説雑誌」と呼ばれる。推理小説ファンの坂口が「絶対犯人を当てられない探偵小説を書く」と意気込み、犯人当て懸賞小説として連載中に懸賞金を出すことを読者に告知し、大井廣介、平野謙、荒正人、江戸川乱歩らの文人らを指名して挑戦したことでも話題になった。なお、4人の読者が犯人推理について完全答案を提出している。
この小説は江戸川乱歩が絶賛し[1]、1949年(昭和24年)、第2回「探偵作家クラブ賞」(現在の日本推理作家協会賞)長編賞を受賞した[1]。文芸評論家の七北数人は、本作は文学性を排除し、ゲーム性を重視した文体に貫かれていることを指摘している[1]。
異議あり!
なるほどゲーム性を重視してはいるだろうが、安吾一流の歯切れの良さと描写の鮮やかさは、「文学性を排除」といっては言い過ぎだ。
僕は『二流の人』の大ファンなんだよ。
安吾を教えてくれたのは、直前のメールに出てきた旧友Mだった。
この小説をめぐっては、逸話がある。
「4人の読者が犯人推理について完全答案を提出している」とあることに関連するのだが。
法学部の時代に、これまたMと並んで受講した「ローマ法」は思い出深い講義だった。
講じてくださったK先生には卒業後もよくしていただき、30年を超える御厚誼にあずかった。
このK先生の御嬢さんがまた大変なインテリであるが、話のポイントはそこではない。
1980年代前半のある日、用事で御嬢さんとお目にかかる機会があったところ、通りすがりの本屋の前でふと何か思いつかれた様子。
「面白いものを御覧にいれます」
とおっしゃって文庫本のコーナーに入って行かれる。
「この本ですが、」
と取り出されたのが『不連続殺人事件』。
「御覧になって『あっ!』とおっしゃらなかったら、今日は私のオゴリです。」
「ラッキー!」と内心ほくそ笑む。
「えっ!」とか「ギャッ!」とか言えばいいんじゃん、タダ飯ゲットね。
そして開かれた287ページ、
「あっ!」
「ほほほ、」と御嬢さん。
「犯人さがし懸賞」正解者発表
一等 完全正解(95点)賞金一万円
東京都○○区○○ △番地
KT氏
まぎれもない、K先生のお名前がそこにあった。
「あっ」と言ったら僕のオゴリ、としなかったのは、せめてもの救い。
*****
しばらくしてこの一冊を購入したのは、懐かしさと共に対抗心の為せるわざであったこと、いうまでもない。しかし時間というのはどういうカラクリのものか、「そのうち」と先延べするうちすぐに四半世紀経ってしまった。
なぜかふとやる気を起こしたのが一昨日の夜、A4の紙2~3枚に克明にメモを取り、推理小説をこんなに真剣に読んだのは間違いなく初めてだ。
暗中模索の末、昨夜ふと思いつくところがあって。
犯人の正体にほぼ想到し、そういえばクリスティの「スタイルズ荘の怪事件」でも似たことがあったなと考えた。
全ての疑問が解消したわけではないが、骨子を説明できればまずは良かろう。
あらためて先を読み進め、おおむね正解、ああよかったと安堵した。
応募総数が明記されていないようだが、書きぶりからは3ケタの来信があったものか。
正しく犯人を推定した者は8通、7件の殺人のすべてについてその動機を説明できたものは4通とあり、僕も8人のうちには入れた理屈だが、しかし、K先生のような模範答案は書けそうにない。
「特にK氏はその他のあらゆる細部にわたってメンミツ適確をきわめ、一分の狂いもなく、他の三氏にややまさっているので、氏を最上席とした。(他の)三氏は甲乙つけがたい」と安吾自身の講評。
あらゆる細部にわたってメンミツ適確をきわめ、一分の狂いもなく・・・K先生のお姿が彷彿される。
御存命中に「私も当てましたよ」と言ってみたかった。
昭和22年の一万円は大金だ、先生、何に使われたのかな・・・