2024年1月23日(火)
E君より来信:
『クアトロ・ラガッツィ』を読了しました。
少年使節のことだけ書いてあるかと思いきや、信長から家康に至る日本史をキリスト教伝道の盛衰というエピソードから描いた傑作ですね。著者が美術史専門家というのがいい。
いろいろ勉強になりましたが、とりわけヴァリヤーノは文化交流の先達として尊敬すべき人物だと感心しました。現代の国際交流の仕事でも、こちらから出かけた日本人職員が現地スタッフと一緒に働いている場合、現地人に対して上から目線で接する職員と、親しく友達になる職員と、二つのタイプにはっきり分かれるんです。
いろいろ勉強になりましたが、とりわけヴァリヤーノは文化交流の先達として尊敬すべき人物だと感心しました。現代の国際交流の仕事でも、こちらから出かけた日本人職員が現地スタッフと一緒に働いている場合、現地人に対して上から目線で接する職員と、親しく友達になる職員と、二つのタイプにはっきり分かれるんです。
昔も今もスペイン・ポルトガルも日本も変わりませんね。
少年たちのローマでの日本からの書簡の献上の場面は、以前に見た大使の信任状捧呈式とそっくりです。彼らは当時の日本大使の役割を果たしたんだなあと頼もしく読みました。
少年たちのローマでの日本からの書簡の献上の場面は、以前に見た大使の信任状捧呈式とそっくりです。彼らは当時の日本大使の役割を果たしたんだなあと頼もしく読みました。
ところで下の写真は数年前のポルトガル旅行で、コインブラ大学を訪れた時のものです。偶然図書館で日本展を開催しており、日本地図などが展示されてました。この本を先に読んでいたらもっと感動したでしょう。
帰国後の四人が、ローマの思い出にどう向き合って生きたのかと想像してしまいます。ほんとにあの時代だから、ローマに行くなんて夢みたいなことですよね。
帰国後の四人が、ローマの思い出にどう向き合って生きたのかと想像してしまいます。ほんとにあの時代だから、ローマに行くなんて夢みたいなことですよね。


E君へ返信:
示唆に富んだ読後感をありがとうございます。帰国後の四人、そうですね、どんなふうにローマを思い起こしたのでしょうか。
キリスト教信仰をもち続けた三人(伊東マンショ 1612年病没、原マルチノ 1614年のキリシタン追放令でマカオに移り 1629年病没、中浦ジュリアン 1633年殉教)と棄教した千々石ミゲルでは、思い出し方も違ったことでしょう。
キリスト教信仰をもち続けた三人(伊東マンショ 1612年病没、原マルチノ 1614年のキリシタン追放令でマカオに移り 1629年病没、中浦ジュリアン 1633年殉教)と棄教した千々石ミゲルでは、思い出し方も違ったことでしょう。
もっとも千々石ミゲルの棄教は見せかけのものであり、実際には潜伏キリシタンだったとの可能性が指摘されているそうで、個人的には十分あり得ることと思います。2017年に遺骸が発見されたようですね。
海外経験の長かった貴兄は、それぞれの土地についてどんなふうに思い起こされるのでしょう。僕?僕はなかなか変わらない日本の社会を見て「もっと違ったやり方もあるし、変わろうと思えば変われるのだ」と考える時のエネルギーの源を、三年ばかりのアメリカ体験に汲んでいるようです。
若桑みどりさん、おっしゃるとおりタダモノではない美術史家で、別の調べものをしていて、「こんなのも書いてたの?!」とびっくりしたこと一度ならず。かなりの多作でもあります。まぁ見てください。
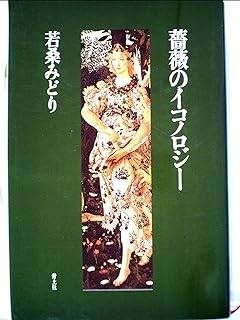

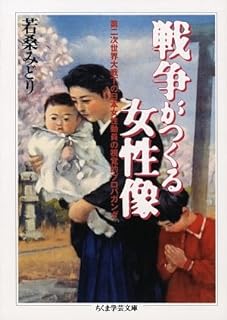
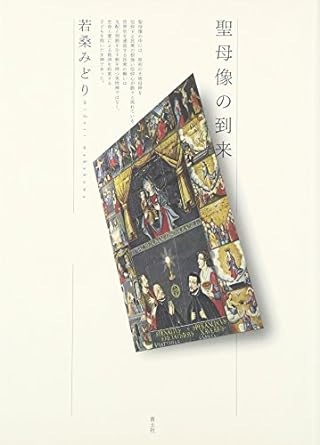

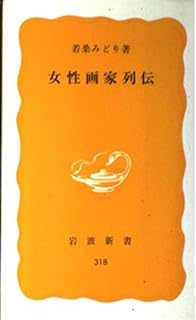

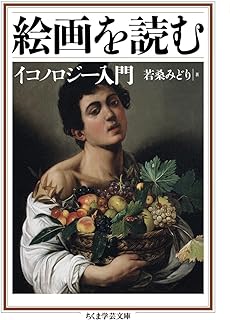

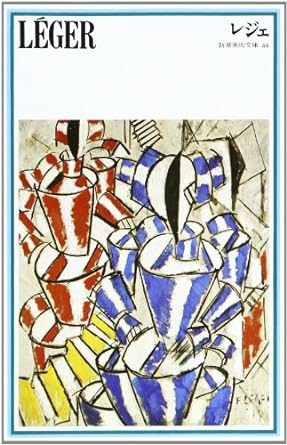
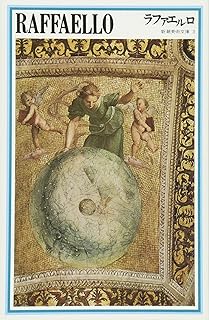

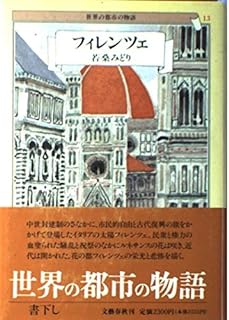

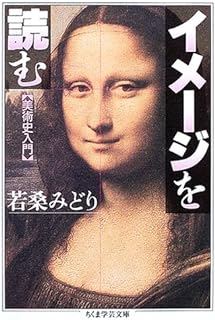



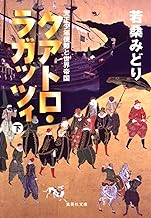
2007年に71歳の若さで他界なさったのは誠に残念、その後の世界史の流れについて是非この方の発言を聞いてみたかった気がします。『クアトロ・ラガッツィ』の書きぶりから御自身はクリスチャンではいらっしゃらないものかと思っていましたが、御葬儀はカトリック教会で行われたようです。
つい先日、フランスの風刺画家ドーミエの作品集を探していたら、ここにも若桑さんが出てきました。ドーミエは面白いですよ、この次もっていきますね。

Ω











