数年前の遠野学会を聴講した際に発表があったひとつでありましたが、その中で、どうしても疑問に思い、少し調べたりした経緯があるも、どうにもならず盛岡南部氏の近世文書を取り扱うサイトへその疑問をぶつけたことがありました。
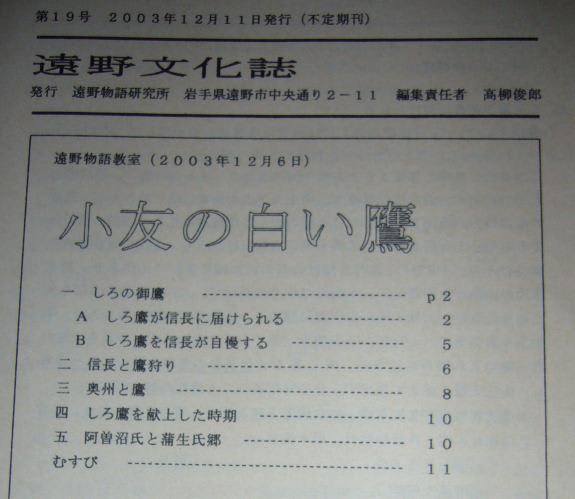
発表された内容に、いちゃもんをつけるものではございませんし、その見解を否定するものではなかったのですが、どうしても自分でも知りたい内容が存在し、識者の意見を仰いだという形になってしまいました。
その後、サイト内でも何度か取り上げられたり、盛岡タイムズにも関連記事が掲載され、ご見解を仰いだ先生もその後も気にされていたようでもあり、それらの記事を拝見することにより、結構勉強になった思いでもありました。
さて、その内容とは・・・上の画像にあるように、「小友の白い鷹」に関連し、遠野孫次郎が時の権力者、織田信長に白鷹を献上したとされること、「信長公記」に記され、史実と思われる内容、これにて登場する「南部宮内少輔」とは何者であったのか、誰であったのか、そのことへの大きな疑問でのことでもありました。
信長公記での関連記事(現代語訳)
「※7月25日、今度は奥州の遠野孫次郎という者から白鷹が進上されてきた。鷹居の石田主計が北国の船路を風雨を凌いではるばる進上してきたもので、雪のような白毛に包まれた鷹であった。その容姿はすぐれて見事で、見る者はみな耳目を驚かせ、信長公の秘蔵もひとかたならぬものがあった。
またこれと同じくして出羽千福の前田薩摩という者も鷹を据えて上国し、信長公へ参礼したのち鷹を進上していった。
7月26日、信長公は石田主計・前田薩摩の両名を召し寄せ、堀秀政邸で饗応を行った。相伴者には津軽の南部宮内少輔もいた。饗応後、信長公は客達に安土の天主を見物させたが、かれらは一様に「かように素晴らしきさま、古今に承ったこともない。まことに生前の思い出、かたじけなし」と嘆息したものであった。
さらに信長公は、遠野孫次郎方へ当座の返礼として
一、御服十着 織田家の紋入り上等品で色は十色、裏着もまた十色。
一、白熊二付
一、虎革二枚
以上三種の品を贈り、使者の石田主計にも御服五着と路銀の黄金を与えた。また前田薩摩にも同様に御服五着に黄金を添えて与えられた。両人はかたじけない恩恵にあずかりつつ奥州へと下っていった。」
・・・天正7年
これに先立ち、津軽の南部氏とみられる者から鷹が進上されている。
「※8月5日には奥州津軽の南部氏より南部宮内少輔が鷹五匹を進上してきた。これに対し、信長公は8月10日南部の使者を万見仙千代邸に迎え、かれらを饗応して返礼をおこなった。」
・・・天正6年
上記によれば、南部宮内少輔は天正6年8月に織田信長に鷹を進上、一年後に遠野からの来た石田主計や出羽の前田薩摩をもてなす宴席に出席し、一年にわたり織田家中の客人若しくは、客分として仕えていたことになります。
信長公記
豊臣時代、豊臣秀吉の命により、かつて織田信長に仕えた太田牛一の日記を元に作られ、一部を除き非常に正確な内容であるため、信長の足跡を辿るには無くてはならない史料とされている。太田牛一が織田信長に仕えた1568年(永禄11年)から信長が死去する1582年(天正10年)について綴られている。十六巻十六冊
遠野孫次郎とは、遠野領主、阿曾沼広郷といわれており、遠野の南隣で境を接する葛西領、葛西晴信の文書にも遠野孫次郎は登場することから、遠野孫次郎とは遠野阿曾沼氏、阿曾沼広郷であるのは、ほぼ間違いないものと思われます。
奥州の片田舎にあっても、中央の動向に着目し、天下人へ近づきつつあった織田信長に接触を図るといった行為にて、遠野孫次郎は中央の権力者との結びつきを持った人物として引用されます。
しかし、後の豊臣時代においては、その中央の動向に疎かった為に、小田原参陣が叶わず所領没収は免れるも三戸南部氏の扶庸とされた史実があります。
別な理由も考えられますが、ここでは割愛いたします。
南部宮内少輔とは・・・・
随分と南部氏関連の資料やら主に書籍にて調べたりもしましたが、ついにその名を見出すことはできませんでした。
遠野学会で講演されたT先生の見解は、南部信直であろうと結んでおりましたが、近世文書から南部氏について解説されるK先生の調べによりますと、南部晴政説と信直説が考えられるとのご見解、また南部宮内少輔政直と記述されておりますが、信長公記には南部宮内少輔とあるも政直とは記述されていない点が指摘されております。
また、別説では秋田安東家の南部氏との見解も示されておりますが、これだっという資料やらが皆無でこれもまた難解な内容でもあります。
近世になってから編纂された南部家資料には信長との接触なども記載はされているものもあるようですが、これもまた信憑性を欠くものとの見解も多分に含まれ、難しいものとなっております。
尻切れトンボとなりますが、かなり長くなる内容、いずれ本サイト「遠野松崎じぇんご2」で、特集として取り上げたいと考えております。
本来は、遠野孫次郎が白鷹を献上したとの内容にて、鷹鳥屋の地名やらで古の時代に鷹を飼育していたことなどを主として取り上げればよかったかもしれませんが、この方面はまたの機会ということで・・・・・。


遠野市小友町鷹鳥屋館跡
白鷹を進上して安土まで出向いた石田主計(宗順)の居舘とされる鷹鳥屋館。
石田氏は、修験の者ともいわれ、諸国の事情に精通していたのではと考えられますが、鷹鳥屋館の館主は沖館氏とも語られ、未だに私的には混迷している状況です。
小友地域(鷹坪・高坪)で捕獲された白鷹は鷹鳥屋で飼育され、安土へ・・・・遠野から進上された鷹は信長を満足させるものであったのは確かなことだと思います。
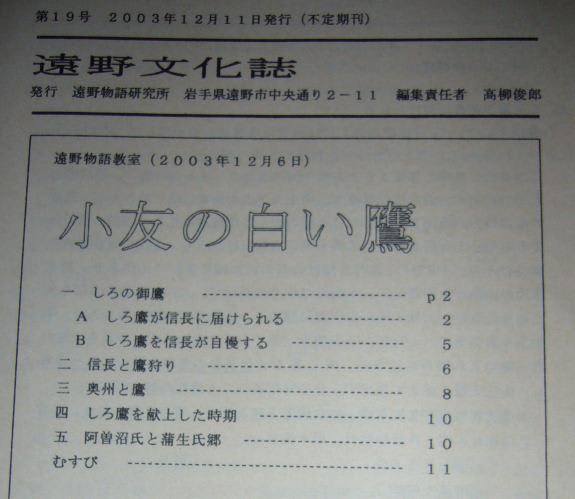
発表された内容に、いちゃもんをつけるものではございませんし、その見解を否定するものではなかったのですが、どうしても自分でも知りたい内容が存在し、識者の意見を仰いだという形になってしまいました。
その後、サイト内でも何度か取り上げられたり、盛岡タイムズにも関連記事が掲載され、ご見解を仰いだ先生もその後も気にされていたようでもあり、それらの記事を拝見することにより、結構勉強になった思いでもありました。
さて、その内容とは・・・上の画像にあるように、「小友の白い鷹」に関連し、遠野孫次郎が時の権力者、織田信長に白鷹を献上したとされること、「信長公記」に記され、史実と思われる内容、これにて登場する「南部宮内少輔」とは何者であったのか、誰であったのか、そのことへの大きな疑問でのことでもありました。
信長公記での関連記事(現代語訳)
「※7月25日、今度は奥州の遠野孫次郎という者から白鷹が進上されてきた。鷹居の石田主計が北国の船路を風雨を凌いではるばる進上してきたもので、雪のような白毛に包まれた鷹であった。その容姿はすぐれて見事で、見る者はみな耳目を驚かせ、信長公の秘蔵もひとかたならぬものがあった。
またこれと同じくして出羽千福の前田薩摩という者も鷹を据えて上国し、信長公へ参礼したのち鷹を進上していった。
7月26日、信長公は石田主計・前田薩摩の両名を召し寄せ、堀秀政邸で饗応を行った。相伴者には津軽の南部宮内少輔もいた。饗応後、信長公は客達に安土の天主を見物させたが、かれらは一様に「かように素晴らしきさま、古今に承ったこともない。まことに生前の思い出、かたじけなし」と嘆息したものであった。
さらに信長公は、遠野孫次郎方へ当座の返礼として
一、御服十着 織田家の紋入り上等品で色は十色、裏着もまた十色。
一、白熊二付
一、虎革二枚
以上三種の品を贈り、使者の石田主計にも御服五着と路銀の黄金を与えた。また前田薩摩にも同様に御服五着に黄金を添えて与えられた。両人はかたじけない恩恵にあずかりつつ奥州へと下っていった。」
・・・天正7年
これに先立ち、津軽の南部氏とみられる者から鷹が進上されている。
「※8月5日には奥州津軽の南部氏より南部宮内少輔が鷹五匹を進上してきた。これに対し、信長公は8月10日南部の使者を万見仙千代邸に迎え、かれらを饗応して返礼をおこなった。」
・・・天正6年
上記によれば、南部宮内少輔は天正6年8月に織田信長に鷹を進上、一年後に遠野からの来た石田主計や出羽の前田薩摩をもてなす宴席に出席し、一年にわたり織田家中の客人若しくは、客分として仕えていたことになります。
信長公記
豊臣時代、豊臣秀吉の命により、かつて織田信長に仕えた太田牛一の日記を元に作られ、一部を除き非常に正確な内容であるため、信長の足跡を辿るには無くてはならない史料とされている。太田牛一が織田信長に仕えた1568年(永禄11年)から信長が死去する1582年(天正10年)について綴られている。十六巻十六冊
遠野孫次郎とは、遠野領主、阿曾沼広郷といわれており、遠野の南隣で境を接する葛西領、葛西晴信の文書にも遠野孫次郎は登場することから、遠野孫次郎とは遠野阿曾沼氏、阿曾沼広郷であるのは、ほぼ間違いないものと思われます。
奥州の片田舎にあっても、中央の動向に着目し、天下人へ近づきつつあった織田信長に接触を図るといった行為にて、遠野孫次郎は中央の権力者との結びつきを持った人物として引用されます。
しかし、後の豊臣時代においては、その中央の動向に疎かった為に、小田原参陣が叶わず所領没収は免れるも三戸南部氏の扶庸とされた史実があります。
別な理由も考えられますが、ここでは割愛いたします。
南部宮内少輔とは・・・・
随分と南部氏関連の資料やら主に書籍にて調べたりもしましたが、ついにその名を見出すことはできませんでした。
遠野学会で講演されたT先生の見解は、南部信直であろうと結んでおりましたが、近世文書から南部氏について解説されるK先生の調べによりますと、南部晴政説と信直説が考えられるとのご見解、また南部宮内少輔政直と記述されておりますが、信長公記には南部宮内少輔とあるも政直とは記述されていない点が指摘されております。
また、別説では秋田安東家の南部氏との見解も示されておりますが、これだっという資料やらが皆無でこれもまた難解な内容でもあります。
近世になってから編纂された南部家資料には信長との接触なども記載はされているものもあるようですが、これもまた信憑性を欠くものとの見解も多分に含まれ、難しいものとなっております。
尻切れトンボとなりますが、かなり長くなる内容、いずれ本サイト「遠野松崎じぇんご2」で、特集として取り上げたいと考えております。
本来は、遠野孫次郎が白鷹を献上したとの内容にて、鷹鳥屋の地名やらで古の時代に鷹を飼育していたことなどを主として取り上げればよかったかもしれませんが、この方面はまたの機会ということで・・・・・。


遠野市小友町鷹鳥屋館跡
白鷹を進上して安土まで出向いた石田主計(宗順)の居舘とされる鷹鳥屋館。
石田氏は、修験の者ともいわれ、諸国の事情に精通していたのではと考えられますが、鷹鳥屋館の館主は沖館氏とも語られ、未だに私的には混迷している状況です。
小友地域(鷹坪・高坪)で捕獲された白鷹は鷹鳥屋で飼育され、安土へ・・・・遠野から進上された鷹は信長を満足させるものであったのは確かなことだと思います。


























石田と白鷹の話、私も興味津々。土淵常堅寺は、大原から、遠野へ移るに際し、似田貝の石田家に当初わらじを脱ぎ、そこから、現在の常堅寺へ入ったと言われており、現在の和尚様が、本吉から来る際も、同様にしたそうです。また、石田の屋号が番田であることが、伊能のくさぐさに書かれてあり、それも気になっており、知りたいことばかりです。笑
石田主計とは、土淵石田の修験石田宗順のこととの見解、おそらくその通りかと思われますが、大原から移った常堅寺は遠野孫次郎代以前に移されたような記述でもありますが、石田家はかなり古い家ということになりますかね。
それと番田の屋号、土淵町内には同名の姓もございますが、こちらとの関連は・・・・ちょっとハマルと深みに陥ってしまいますね・・・・笑
この史実を知ったのがのめり込むきっかけでしたから殊更です。
中央の歴史と解離したイメージから一気にメジャーに成った気分でした。
誇れる歴史の入口の話としても最高ですね。
ロマンで終わる人、検証をする人・・・・宜しくお願い致します。
さて、期日が迫りましたのでヨロシクです!
遠野という名がまたしても中央に出てくる信長公記、おそらくは鷹を進上したことは史実に間違いないものと思います。
遠野の人達の中には、この内容を知っていても、どんな文面で書かれているのか、どんな内容だったかは、ほとんどわかる人はそれほど多いとは思っておりません。
日本の歴史のほんの小さな出来事ながらも、こういったことがあったということ、少しでもわかっていただけたらと考えております。
さて、例の件、八戸の御仁から我家宛に送付されたそうですから、私のものと合わせて25日にお届けいたします。
よろしくお願いします。
と、ここまでは以前とらねこさんにお伝えしたところなのですが、その後、別の文献を見つけました。
吉井功兒氏の「中世南部氏の世界」という論文に、「この人物が桧山安東愛季家臣であることは、夙に大島正隆氏が説かれている」とあり、大島氏の文献とは、1942年(随分昔!)に書かれた「北奥大名領成立過程の一断面~比内浅利氏を中心とする考察~」という論文だそうです。
今度お会いするときにでもコピーをお渡ししますよ。
もしかすると大島氏の説って最近では否定されているんですか?私は知りません・・・。
特集、楽しみにしてま~す!
それで、そんなに不明な人物なのかとヤフッたりググッたりしてみました。
あるサイトで
8月 5日 南部季賢(「奥州津軽之南部宮内少輔」)、近江国安土城の織田信長へ鷹5足を進上。〔『信長公記』〕
8月 5日 蠣崎正広、南部季賢と共に近江国安土に立ち寄る。〔『新羅之記録』上巻〕
8月10日 蠣崎正広、南部季賢と共に近江国安土にて織田信長の饗応を受ける。〔『新羅之記録』上巻
というのを見つけました。まだ他にもあり、やはり安東愛季家臣であることが書かれていました。
今後のとらねこさんの追跡を期待しています。
南部宮内少輔にご反応ありがとうございます。
以前、ご教授いただいた件は承知しておりましたが、今回提示の資料は、存知あげませんでした。
というか、安東氏関連は、ネット検索と湊奉行さんからの若干のお知らせのみで、全く踏み込んでおらない状況でした。
どうしても南部から離れられず、盛岡南部家関連にての調べでしたが、盛岡のK先生も不明とするほど、南部家資料には見当たらない人物でもありました。
ただ、K先生が何度か私からの質問の影響で自サイトで自問自答したり、盛岡タイムスに一部関連事項を寄稿したりと結構調べられた経緯はあるようで、私としても結構勉強になりました。
南部晴政説ではありませんが、晴政と信長のこと、信直と信長・・・関連資料の考察もたいへん興味を受けました。
安東説は、これら南部家関連を自身で潰して行く過程がなってから、或いは新しい何かの発見があるのでは・・・そんな中から移行できたらと考えておりました。
ただし、丸3年、思いだけで何も進展していないのは事実でもありますが・・・・。
ご提示痛み入ります。
おそらく安東氏に関りある内容が濃厚という場面だと思っております。
ただし、信長公記には「奥州津軽の南部宮内少輔」とあっても、南部季賢とは記述されておりませんから、これも遠野孫次郎が阿曾沼広郷という見解と同じようなレベルかもしれません。
ゲームでの信長の野望では南部季賢は登場するので、名だけはしってましたが・・・笑
いずれ、このことを突き詰めるには秋田氏(安東)の中世関連の調べが必然的に必要でもあり、県立図書館にでも行った際は、少しまがってみできたいと考えてます。
でも今すぐというわけではありませんよ・・・笑
興味をそそる内容、ありがとうございます。
石田氏の出、家に関しては不明としておきます。資料も何処へやったのか、探し出すこともできなくて、歴史関係も現在は遠ざかってますので、然るべき時期がきましたら再開ということにしてますので、よろしくお願いします・・・謝