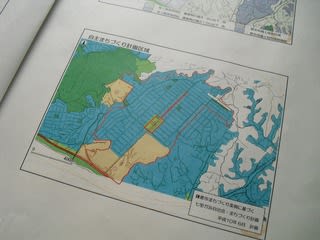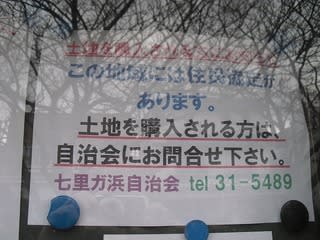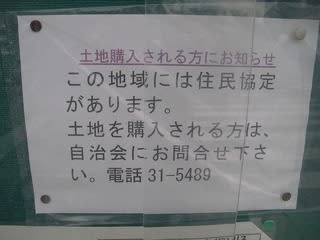我が七里ガ浜住宅地のサクラは、現在ハラハラと散っているところ。誠に残念。自宅前もたくさん花びらが溜まっている。

なぜなら斜め前のお宅にはこのような立派なサクラの木があるから。今朝の写真だ。毎年、勝手に楽しませてもらっている。借景。有難い話だ。
しかし電柱と電線が邪魔だなぁ。どう考えても、空を切り取ってしまいサクラと調和しない。そう私は思うが、最近はこうした風景も「日本独特のもの」として評価する人々も出て来ている。日本の道路交通の中心、日本橋の上の首都高などと同様に、「日本的」として評価されたりしているらしい。いろいろなモノの考え方があるものだ。

昨日東京に出た帰りに鎌倉駅で途中下車し、まずは鎌万で買い物し、それから駅前の松林堂書店に寄ったところ、店主さんに「小町通りの電線地中化工事の進捗具合をご存じ?」と尋ねられた。毎夜のようにその工事をしているのは知っているが、進捗状況までは知らなかった。すでに南の方から順調に進んでいるらしい。小町通り中ほどにまもなく消える電線と電柱もあるという。店主さんは「あるうちに見ておいたら」とおっしゃった。

で、見に行く。上画像右下の黄色い看板は、ご存じラーメン店「ひら乃」。小町通りの鎌倉駅側入口からこのあたりまではすでにもう電柱はない。180度回転して北側を見ると、電柱がまだある。○で囲ったところがまだ残っている電柱の中で最南端にあるもの。これらも順番に撤去される予定。

商店街ではないだけに、電柱電線の目立ち度では実は我が住宅街の方がひどい。撤去してもらえればうれしいのだが。

なぜなら斜め前のお宅にはこのような立派なサクラの木があるから。今朝の写真だ。毎年、勝手に楽しませてもらっている。借景。有難い話だ。
しかし電柱と電線が邪魔だなぁ。どう考えても、空を切り取ってしまいサクラと調和しない。そう私は思うが、最近はこうした風景も「日本独特のもの」として評価する人々も出て来ている。日本の道路交通の中心、日本橋の上の首都高などと同様に、「日本的」として評価されたりしているらしい。いろいろなモノの考え方があるものだ。

昨日東京に出た帰りに鎌倉駅で途中下車し、まずは鎌万で買い物し、それから駅前の松林堂書店に寄ったところ、店主さんに「小町通りの電線地中化工事の進捗具合をご存じ?」と尋ねられた。毎夜のようにその工事をしているのは知っているが、進捗状況までは知らなかった。すでに南の方から順調に進んでいるらしい。小町通り中ほどにまもなく消える電線と電柱もあるという。店主さんは「あるうちに見ておいたら」とおっしゃった。

で、見に行く。上画像右下の黄色い看板は、ご存じラーメン店「ひら乃」。小町通りの鎌倉駅側入口からこのあたりまではすでにもう電柱はない。180度回転して北側を見ると、電柱がまだある。○で囲ったところがまだ残っている電柱の中で最南端にあるもの。これらも順番に撤去される予定。

商店街ではないだけに、電柱電線の目立ち度では実は我が住宅街の方がひどい。撤去してもらえればうれしいのだが。