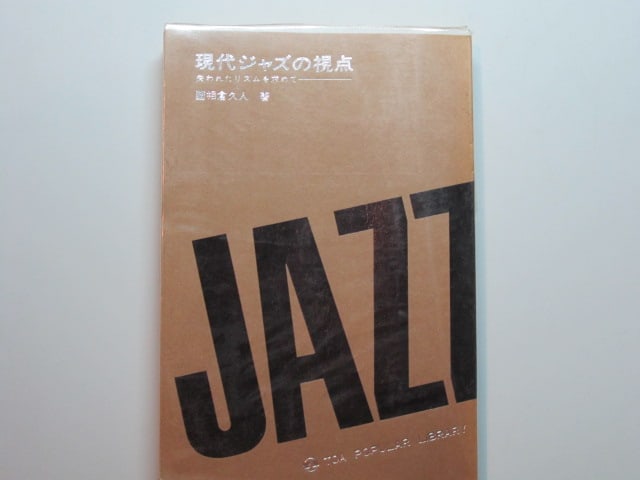このところ、夏目漱石が気になって、関係の本をあれこれと読んでいます。
理由は、よくわかりません(笑)。


そして、最新の一冊が、
森まゆみ『千駄木の漱石』(筑摩書房)だ。
夏目漱石が東京・千駄木で暮らしたのは、英国留学から戻った直後の明治36年から、日露戦争をはさんで39年の年末まで。
東京帝国大学や第一高等学校の教壇に立ちながら、徐々に作家へと移行していく時期だ。この間に書いたのが『吾輩は猫である』『坊ちゃん』『草枕』などである。
著者は漱石を自らの故郷に迎えた“隣人”の如く、その軌跡を丁寧に追っていく。
借家だった住居の歴史。生真面目に準備された講義。帝大での学生たちとの軋轢。寺田寅彦など弟子たちとの交流。そして家庭における夫や父としての漱石。
中でも興味を引くのが、小説『道草』で描かれた人間模様と、漱石とその周辺にいる実在の人々との重なり具合。作品は実在の姉、兄、妻、養父などとの確執を浮き彫りにしているのだ。
著者は『吾輩は猫である』を滑稽小説にして近隣憎悪小説、また『道草』を心理小説にして近親憎悪小説と呼んでいるが、卓見である。
さらに本書では、妻である鏡子との“せめぎ合い”も読みどころの一つだ。神経質で夢見がちな夫とヒステリーの妻がいる環境から、なぜいくつもの名作が生まれたのか。
「僕は世の中を一大修羅場と心得ている」という漱石自身の言葉が実に味わい深い。
さて、今週の「読んで、書評を書いた本」は、以下の通りです。
マブルーク・ラシュディ 中島さおり:訳『郊外少年マリク』
集英社
本城雅人 『希望の獅子』
講談社
園 子温(その・しおん)『非道に生きる』
朝日出版社
大橋博之 『SF挿絵画家の時代』
本の雑誌社
大野左紀子『アート・ヒステリー』
河出書房新社
斎藤貴男 『私がケータイを持たない理由』
祥伝社新書
・・・・私は、ケータイは持っていますが、ケータイ・メールはしていません。
ブログはこうしてやっていますが、フェイスブックも、ツイッターもやっていません。
自分なりの理由は、明確にあります。
斎藤さんの『私がケータイ・・・』に関しても、かなり共感多し、です(笑)。
* 上記の本の書評は、
発売中の『週刊新潮』(11月22日号)
ブックス欄に掲載されています。