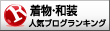NHKを見ていると大河ドラマ「べらぼう」の番宣に遭います。
江戸時代の浮世絵の版元、蔦谷重三郎がモデルなのですが、随所に吉原が登場しNHKもなかなか攻めたものだなと。
ちょうど一年程前に上野の藝大美術館で企画展「大吉原展」が開催されましたが「性的搾取が軽視されている」と悶着したことがあります。
大抵の物事のは二面性があって、見る方向によってその評価が全く変わってしまいます。
遊郭の陰の部分に蓋をして存在を消し去ってしまうというのは全く賛成しませんが、それを日向に出せるようにイメージを変えてしまうのには随分と違和感を感じます。
「大吉原展」はその辺りの提言もそこそこ難儀をしたようですが、堂々と日向を歩かせるものも数あります。
同じ新潟県の自治体でも行われているのでおそらく他の地域にもあるのだと思いますが、観光用に花魁(もしくは太夫)のように着飾らせて行列をするというもの。
「花魁(もしくは太夫)は一般の遊女と違って教養がなくてはならなくて云々、身請け(この言葉もなかなかだけど)をするにも金が全てではなくて云々」と相当に評価を上げます。と言うか、花魁と遊女の比較もすごい。
驚くのは観光花魁行列で「花魁」のなり手を募集すると、応募者があるということ。 オイオイ、オヤガナクゾ。
そこまで評価を高めてしまうとどうにも違和感を覚えざるを得ないのです。
そういえば、昨夏に金沢に行った時に気づいたのですが、昔は「東の廓」「西の廓」と言っていた場所ですが、今の記載では「東の茶屋」「西の茶屋」に変わっていました。
観光地として集客するのに「廓」では具合が悪いので「茶屋」になったのでしょう。


なかなか整った街並みなのでそこを見ながら嘗ての「性的搾取」を感じ取るべきとか、「遊里」での生活を想像しろとか面倒な事をいうつもりはないのですが、「廓」が繁華街くらいにイメージ替えしてしまうのもどうかと思います。気楽に「茶屋」とか言っていると繁華街にあるスターバックスくらいに見えてしまいそうでいけませんね。

「〇〇でありんす」とか子供が言い出したら、「子供に見せたくないテレビ番組」の上位にあがってきそうですね。あはは。
江戸時代の浮世絵の版元、蔦谷重三郎がモデルなのですが、随所に吉原が登場しNHKもなかなか攻めたものだなと。
ちょうど一年程前に上野の藝大美術館で企画展「大吉原展」が開催されましたが「性的搾取が軽視されている」と悶着したことがあります。
大抵の物事のは二面性があって、見る方向によってその評価が全く変わってしまいます。
遊郭の陰の部分に蓋をして存在を消し去ってしまうというのは全く賛成しませんが、それを日向に出せるようにイメージを変えてしまうのには随分と違和感を感じます。
「大吉原展」はその辺りの提言もそこそこ難儀をしたようですが、堂々と日向を歩かせるものも数あります。
同じ新潟県の自治体でも行われているのでおそらく他の地域にもあるのだと思いますが、観光用に花魁(もしくは太夫)のように着飾らせて行列をするというもの。
「花魁(もしくは太夫)は一般の遊女と違って教養がなくてはならなくて云々、身請け(この言葉もなかなかだけど)をするにも金が全てではなくて云々」と相当に評価を上げます。と言うか、花魁と遊女の比較もすごい。
驚くのは観光花魁行列で「花魁」のなり手を募集すると、応募者があるということ。 オイオイ、オヤガナクゾ。
そこまで評価を高めてしまうとどうにも違和感を覚えざるを得ないのです。
そういえば、昨夏に金沢に行った時に気づいたのですが、昔は「東の廓」「西の廓」と言っていた場所ですが、今の記載では「東の茶屋」「西の茶屋」に変わっていました。
観光地として集客するのに「廓」では具合が悪いので「茶屋」になったのでしょう。


なかなか整った街並みなのでそこを見ながら嘗ての「性的搾取」を感じ取るべきとか、「遊里」での生活を想像しろとか面倒な事をいうつもりはないのですが、「廓」が繁華街くらいにイメージ替えしてしまうのもどうかと思います。気楽に「茶屋」とか言っていると繁華街にあるスターバックスくらいに見えてしまいそうでいけませんね。

「〇〇でありんす」とか子供が言い出したら、「子供に見せたくないテレビ番組」の上位にあがってきそうですね。あはは。