縮緬の生地に綿を入れて➠慣れたら結構簡単です
今日は、花嫁の丸ぐけを作ってみました。
舞踊の時に使う「丸ぐけ」は、藤娘などに使いますが、花嫁の丸ぐけに比べて少し大きめです。
この丸ぐけの周囲は4cm。生地を二つ折りにして2cmで縫っていきます。
今回はミシン縫いでなく、半返しの手縫いで2.1m縫いました。
それを返して綿を入れていきます。(チョットした工夫はありますが、慣れたら結構簡単です。)
生地は縮緬。少し伸び縮みする生地でないと、綿を入れたり着付ける時に裂けてしまいます。
写真の丸ぐけの両端はこれから始末しますが、長さは約2mで仕上げます。
丸ぐけの製作は、今回で6本目だと思いますが、いつも新たな発見があって面白いものです。


 ●
● ●
●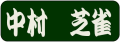 ●
●
 ●
●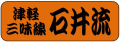 ●
● ●
●
 ●
● ●
●
補整、衿付け、襦袢、掛下、掛下帯…今日から白無垢だ!
鹿児島の「花嫁着付け講座」でお勉強している、がんばり屋の梅木さんは、習い事でも全力投球。
昼間のお仕事で疲れているのに、毎週日曜日はおけいこ場に通って来られます。
教える講師も梅木さんの熱意にこたえようと、楽しい日曜出勤です。
これまで、花嫁の補整や衿芯の作り方から始まって、襦袢の着せ付け、掛下着付けと掛下帯の結び方と、結構長い道のりでした。
「ずいぶんうまくなりました」とは学院長の弁。
花嫁の着付け講座は、お引きやメイクなど…まだまだ続きます。
この生徒さんの面白い記事がありましたのでご紹介します。
花嫁のモデルをして頂いている、「きつけ塾福元」の福元先生のブログ「小粋におごじょ」の記事です。
題して、「よく言えば度胸がある」 どうぞご覧ください。
 ●
● ●
●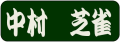 ●
●
 ●
●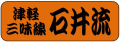 ●
● ●
●
 ●
● ●
●


























