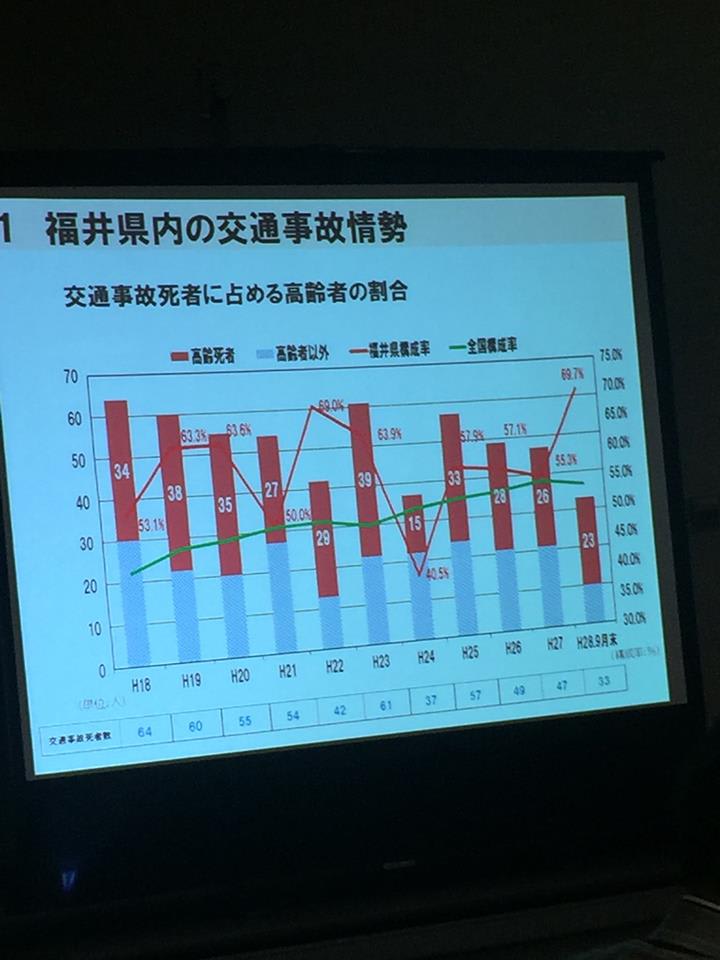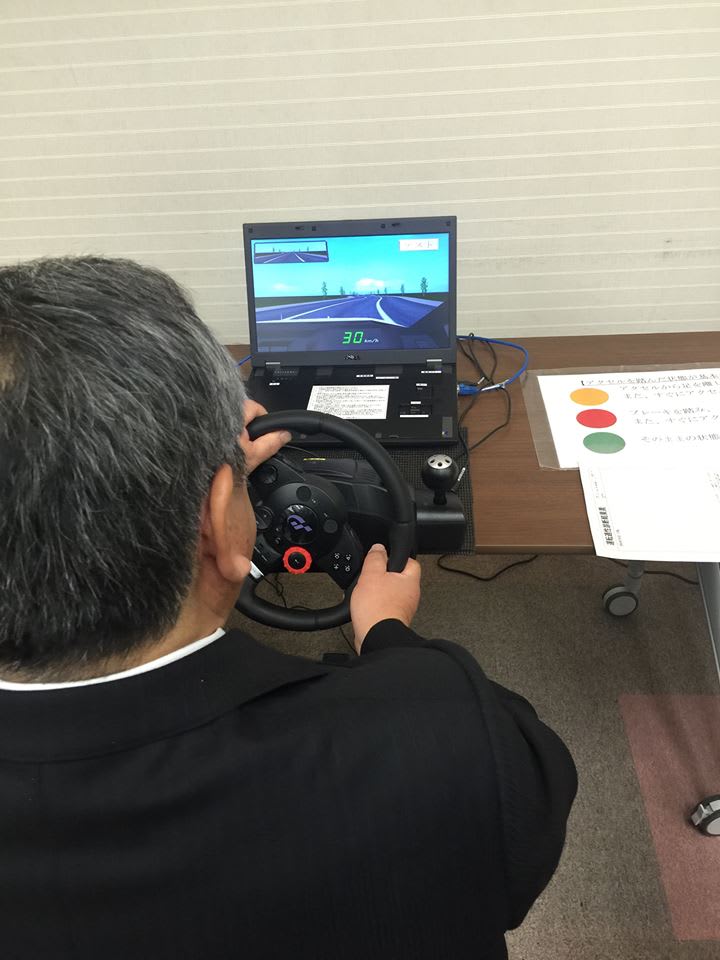20日告示の勝山市議補欠選挙に、前回選挙で52票差で議席に届かなかった久保こうじさんが挑みます。山田安信市議との2議席回復を目指します!
昨日は事務所びらきで福井市からも応援に行き、街頭宣伝やポスター張り活動などをおこないました。
地元では音楽活動で著名。耕作放棄地をヤギの活用でよみがえらせるなど行政も注目。
地に足をつけて、住民の暮らし最優先で頑張ります。
応援よろしくお願いします!
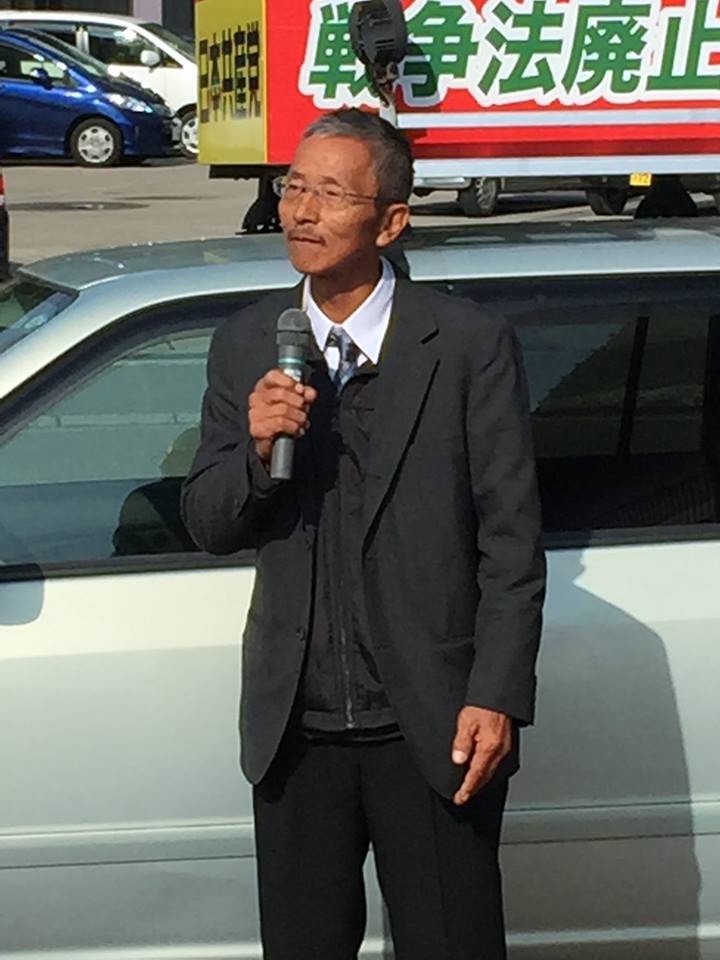


勝山支援から戻り、急いで鯖江市役所が開催した北陸新幹線に関する意見交換会に参加しました。
国土交通省の水嶋智鉄道局次長の講演をお聞きしました。
牧野市長が、新幹線と並行在来線の経営分離に合意した経緯とあまりに違う、私が市民に約束した状況と違う、フリーゲージトレインができないまま敦賀乗り換えが続くのは問題だ、と訴えられたのが胸に響きました。
水嶋次長からは、フリーゲージトレインは安全性を確認しないと前にすすめない、と述べましたが、その間の代替としての現行特急運行には明確な回答はありませんでした。
しかし、これは言うまでもなく福井県や鯖江市の責任ではなく、フリーゲージトレインふくめた新幹線を認可した国の責任なのです。そのことを曖昧にするような政府の対応は許されません。

昨日は事務所びらきで福井市からも応援に行き、街頭宣伝やポスター張り活動などをおこないました。
地元では音楽活動で著名。耕作放棄地をヤギの活用でよみがえらせるなど行政も注目。
地に足をつけて、住民の暮らし最優先で頑張ります。
応援よろしくお願いします!
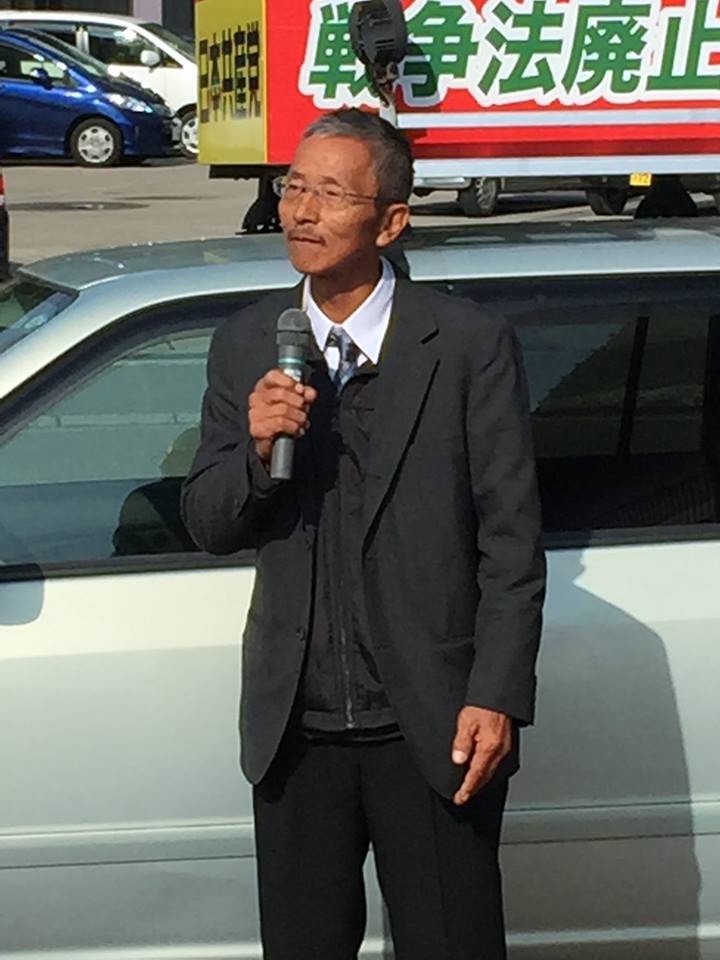


勝山支援から戻り、急いで鯖江市役所が開催した北陸新幹線に関する意見交換会に参加しました。
国土交通省の水嶋智鉄道局次長の講演をお聞きしました。
牧野市長が、新幹線と並行在来線の経営分離に合意した経緯とあまりに違う、私が市民に約束した状況と違う、フリーゲージトレインができないまま敦賀乗り換えが続くのは問題だ、と訴えられたのが胸に響きました。
水嶋次長からは、フリーゲージトレインは安全性を確認しないと前にすすめない、と述べましたが、その間の代替としての現行特急運行には明確な回答はありませんでした。
しかし、これは言うまでもなく福井県や鯖江市の責任ではなく、フリーゲージトレインふくめた新幹線を認可した国の責任なのです。そのことを曖昧にするような政府の対応は許されません。