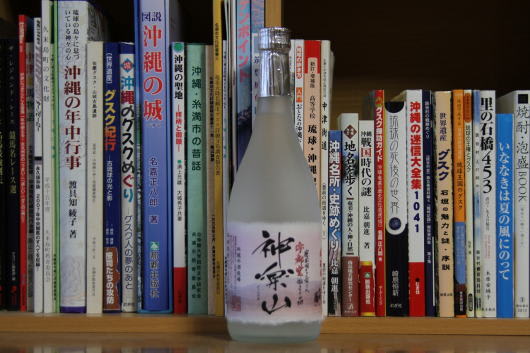鞍手町歴史民俗博物館

鞍手町で開かれている 「 炭坑 ( やま ) の仕事 」 展
24日の日曜日、みやこ町の寺田川古墳を皮切りに、
田川市ー直方市ー中間市ー鞍手町ー小竹町ー飯塚市ー嘉麻市ー川崎町をめぐった。
その行程の中で立ち寄った鞍手町の 「 鞍手歴史民俗博物館 」 で、
「 炭坑 ( やま ) の仕事 」 展が開かれていた。
鞍手。そして炭鉱といえば・・・
昭和39年 ( 1964年 ) に 「 筑豊文庫 」 を鞍手町に創設し、
坑夫の記録と資料を集成した上野英信 ( うえのえいしん ) であろう。
上野英信は昭和22年 ( 1947年 ) 、京都大学を中退して炭鉱の坑夫となり、
その後一貫して炭鉱労働者の生活と労働を負い続けたルポルタージュ作家である。
中間市で谷川 雁、森崎和江らと 「 サークル村 」 運動の中核を担い、
その後、鞍手郡鞍手町に移った。
『 追われゆく坑夫たち 』 は、昭和35年 ( 1960年)に岩波新書から刊行されたもので、
上野の代表作のひとつである。
筑豊炭田は、ほぼ一世紀近く全国の半分の石炭を産出し、日本の近代化を支えて来た。
大資本経営の炭鉱の陰で中小炭坑では非人道的労働がまかり通り、
エネルギー革命によりそれはますます苛酷になっていった。
「 苛烈きわまりない地底の 『 奴隷労働 』 は、彼らの持てる限りの財産と健康と生活を
収奪し去ったばかりではなく、彼らの人間としての微かな欲望のすべてを残酷無慙に
叩き潰してしまった 」
上野は昭和23年 ( 1948年 ) から28年 ( 1953年 ) まで、
各地の炭鉱を転々としながら、最低辺で呻吟 ( しんぎん ) する坑夫たちの叫びを記録し続けた。
「 追われゆく坑夫 」 は、自らの体験をもとに書かれたもので、
あまりに厳しいリアルな現実が各方面に衝撃を与えた。
その後も上野は、晩年まで文学運動や記録活動を続け、
昭和59年(1984年)から61年(1986年)にかけて
『 写真万葉録・筑豊 』 ( 昭和62年、日本写真協会賞受賞 ) を刊行した。
主な著書、 「 せんぶりせんじが笑った! 」 「 地の底の笑い話 」
「 どきゅめんと・筑豊 」 「 天皇陛下萬歳ー爆弾三勇士序説 」 「 出ニッポン記 」 などがある。
昭和62年(1987年)64歳で没した。