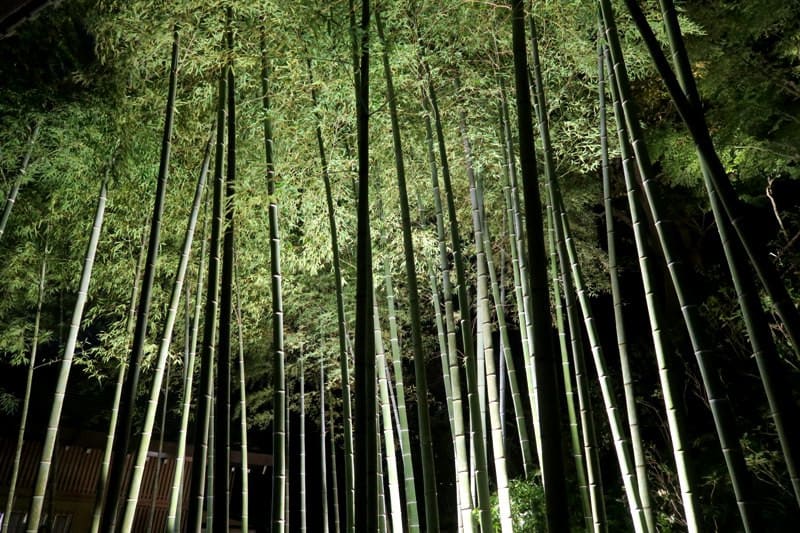のんびり回ってきた京都散策、最初に訪れた寺社は祇園さんこと八坂神社です。全国にある約2,300社の八坂神社の総本社で、京都一の繁華街、祇園四条の東に位置し、いにしえの平安遷都から京都の街を見守ってきた社です。
祇園交差点を渡って

境内最古の建造物、西楼門から

最近よく見る電子案内板
神社ナビタ

梅の花咲く頃でした

祇園造の本殿へ


参拝の列が絶えません

祇園祭の神輿が奉安される舞殿

祇園神水

女性に人気の美容水

時計塔を見上げると薙刀の先?
まずい、もう4時になる


境内最古の建造物、西楼門から

最近よく見る電子案内板
神社ナビタ

梅の花咲く頃でした

祇園造の本殿へ


参拝の列が絶えません

祇園祭の神輿が奉安される舞殿

祇園神水

女性に人気の美容水

時計塔を見上げると薙刀の先?
まずい、もう4時になる