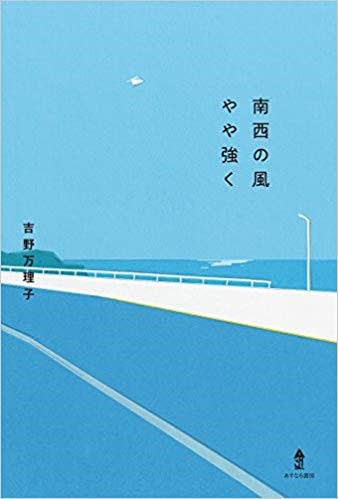
12歳、15歳、18歳の3つの時代、3つの風景が描かれる。夜の江の島。放送部の部室。予備校の帰り道。些細な風景の点描。ひとりの少年がもうひとりの少年と出会い、さらにはもうひとりの少女と出会う。家族のこと、友人のこと、好きになった女の子のこと。どこにでもあるできごとが丁寧に描かれたとき、それは唯一絶対の彼の人生の風景として心に沁みてくる。誰もが感じる孤独や焦燥、怒り、切ない想い。それを「あるある」という距離感ではなく、まるで自分のことのような傷みとして、描く。お話というより、触れたくない遠い日の記憶のような悲しみとして伝わってくる。父親がガンになったり、恋人がとんでもない病に倒れたり、まるで安っぽいメロドラマのような展開になるのに、それが気にならないのはそれが一つの暗喩になっているからだ。
ここで描かれるのはお話ではなく、あの時の気持ちだ。抑えきれない激情や、悲しみ。それが安易そうなストーリーラインに乗って描かれる。ここで大切なことは、そんなストーリーではなく、12歳、15歳、18歳という時代の気分なのであろう。誰もがそんな時代を通り抜けて大人になる。通過儀礼としてのドラマなのだ。
彼がこの傷みと向き合い、やがて大人になったとき、どんな大人になるのだろうか。反発していた父親のような男にはならないだろう。(彼には当然なれないだろうし)この後、彼女ではないどんな女性と恋をするのか。それともこのまま彼女を失わずやっていけるのか。「今」は未来が見えない。
自分がまだ何者でもなかった頃。それでも必死に生きていた頃。これはそんな10代の憂鬱とちゃんと向き合う小説だ。久しぶりに切なくてやるせない気分に浸れた。この傷みが心地よい。自分も又、彼のようにあの頃を生きてきたのだ、という当たり前のことを思い出した。今、大人になり、あの頃の思いを忘れてしまって生きていた。そんな自分が切ない。

























