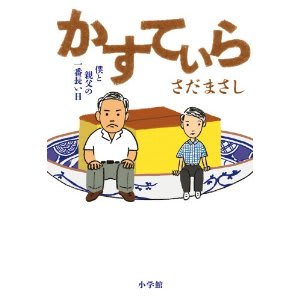
さだまさしが父との別れをつづった自伝的小説。登場人物は、すべて実名で(たぶん、そうだろう)出てくる。小説というには、あまりにストレートで、本人の日記のようだ。大切なことを、大切なまま、記憶し、記録し、それをたくさんの人たちに見てもらいたい、というのが、彼の願いなのだろう。そんな想いは確かに伝わってくる。
だが、それを読んで、どうしろ、というのか。1編の小説としては、これはちょっとなぁ、と思う。普遍性を持ちえていない。残念だが、本人の感傷の域を出ない。でも、そんなこと、誰よりも彼自身が一番よく知っていたはずだ。歌手の余芸としてではなく、本格的小説家としてもちゃんとした実績を持つ作家さだまさしが、ここまでプライベートなものを、書く。そこには、お話として再構成できない父への想いがある。では、それは自分の心の中に秘めておけばいいではないか、という考えもあるだろう。普通はそうする。でも、そうは出来ないのが今の彼なのだ。
客観性なんていらない。ありのまま、自分たち家族と父親との出来事を小さな小説としてここに綴り、上梓する。こういうわがままは彼には許される。「私家集」というスタイルはさだまさしの得意技だし。
だが、それを読んで、どうしろ、というのか。1編の小説としては、これはちょっとなぁ、と思う。普遍性を持ちえていない。残念だが、本人の感傷の域を出ない。でも、そんなこと、誰よりも彼自身が一番よく知っていたはずだ。歌手の余芸としてではなく、本格的小説家としてもちゃんとした実績を持つ作家さだまさしが、ここまでプライベートなものを、書く。そこには、お話として再構成できない父への想いがある。では、それは自分の心の中に秘めておけばいいではないか、という考えもあるだろう。普通はそうする。でも、そうは出来ないのが今の彼なのだ。
客観性なんていらない。ありのまま、自分たち家族と父親との出来事を小さな小説としてここに綴り、上梓する。こういうわがままは彼には許される。「私家集」というスタイルはさだまさしの得意技だし。

























