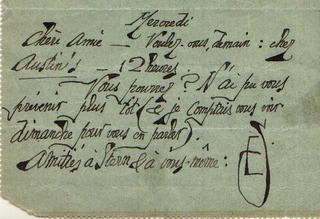◎アラン・マークス(P)(LTM)CD
全曲版なんてありえないわけで、しかしこの悪ふざけを律儀にまるまる一枚のCDに入るだけ繰り返し録音した人というのは何人かいる。ここには意味性を剥奪された無調的な単旋律の問い掛けと不協和音の堆積による宗教祭儀的な不可解な答唱からなるフレーズが40回繰り返されているが、サティの本意ではなかったにせよ計らずも極限までロマンチシズムを削ぎ落とし宗教臭さやアマチュア的な実験性も余りの単純によって際立たず、何にも似ていない、音楽ですらなくなっているこの曲は、ある意味最も先鋭でサティの生涯をかけた理念を最も純粋な形で体言した傑作と言うこともできるわけで、このようにウェットな音でありながらもまったく同じ調子を崩さない演奏家の態度が、ミニマルな側面を印象づけ、ああ、ケージがやりたがったわけだ、これは凄いと感嘆させる。初期の教会のオジーヴから生硬さを抜き去り、永遠の連続性をまるでヤコブの梯子のように続く祭壇への階段、、、これは恐ろしい作品だ。◎。