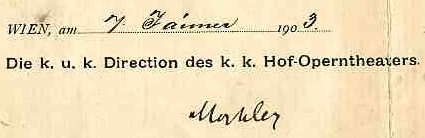○メンゲルベルク指揮ACO(pearl他)1926/5・CD
これは前に書いたシンポジウムのようなSP板起こしできくべきではない。雑音はこの曲にはそうとう邪魔。パールの綺麗に整えられた音できくと、メンゲルベルクらしさ全開(+SPらしいセカセカしたテンポ全開)のこの独特のアダージエットをたのしむことができる。有名な録音だがマーラーらしさというよりメンゲルベルク芸の一環として、非常に颯爽としたテンポですがすがしさの中に物凄い瞬間ポルタメントの渦、ルバートはわりと自然で雑味を呼び込んではいない。アダージエット単品としての解釈ともいえ、この曲だけで一つの激しい感情を表現している。○。
これは前に書いたシンポジウムのようなSP板起こしできくべきではない。雑音はこの曲にはそうとう邪魔。パールの綺麗に整えられた音できくと、メンゲルベルクらしさ全開(+SPらしいセカセカしたテンポ全開)のこの独特のアダージエットをたのしむことができる。有名な録音だがマーラーらしさというよりメンゲルベルク芸の一環として、非常に颯爽としたテンポですがすがしさの中に物凄い瞬間ポルタメントの渦、ルバートはわりと自然で雑味を呼び込んではいない。アダージエット単品としての解釈ともいえ、この曲だけで一つの激しい感情を表現している。○。