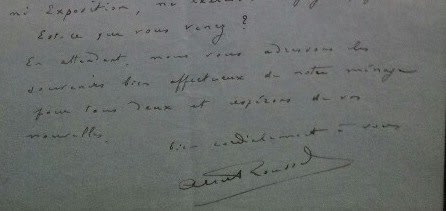<余りにも有名な2楽章アンダンテ・カンタービレはトルストイも涙した超有名曲。サロン音楽風な扱いもされるが、ウクライナのカメンカで耳にした民謡に基づくもの。3本のピツイカート伴奏の上にファーストバイオリンが奏でる鄙びた旋律がそれ。子守り歌のように優しいです。ほかの楽章も美しい。1楽章の、単音を変拍子で区切っただけの旋律や、中間部の無限音階のようなスケールの反復は非常に個性的だ。4楽章は最近テレ朝の浜ちゃんの番組(芸能人格付けチェックだったけ?)でよくBGMになっている。楽天的なチャイコフスキーが全面に出、管弦楽曲的で聞き映えがする。(2001記)>
○D.オイストラフ四重奏団(doremi)CD
いつ聞いても何度聞いても楽しめるチャイコの室内楽の最高峰だ。オイストラフは結構個性を強く出すのではなくアンサンブルとして必要とされる音を出していると言った感じでそれほど力感も解釈の個性も感じない。ウマイことはウマイのであり、雑音まじりの音の悪さを除けばこの曲を最初に聞くのに向いているとさえ言いたいが、たとえば2楽章のリアルで幻想の薄いアンサンブル、4楽章の落ち着いたテンポ、たしかに緊密ですばらしいアンサンブル能力を持っていると思うが、個性を求めたらお門違いだ。また熱さも求められない。緊密さはあるので飽きはこないから、まあ、チャイ1ファンは聴いて損はないだろう。チェロはクヌシェヴィツキー。○。
※2004年以前の記事です
○D.オイストラフ四重奏団(doremi)CD
いつ聞いても何度聞いても楽しめるチャイコの室内楽の最高峰だ。オイストラフは結構個性を強く出すのではなくアンサンブルとして必要とされる音を出していると言った感じでそれほど力感も解釈の個性も感じない。ウマイことはウマイのであり、雑音まじりの音の悪さを除けばこの曲を最初に聞くのに向いているとさえ言いたいが、たとえば2楽章のリアルで幻想の薄いアンサンブル、4楽章の落ち着いたテンポ、たしかに緊密ですばらしいアンサンブル能力を持っていると思うが、個性を求めたらお門違いだ。また熱さも求められない。緊密さはあるので飽きはこないから、まあ、チャイ1ファンは聴いて損はないだろう。チェロはクヌシェヴィツキー。○。
※2004年以前の記事です