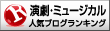小説学校時代 07
出欠点呼を覚えているでしょうか?
学校の朝は出欠点呼から始まる……わりには憶えていない。
小学校は、朝から担任がいるので担任の先生が取っていた……と思います。
たぶん、クラスの座席が頭に入っているので、一瞬で確認して出席簿に付けていたのではないかと。
クラスには50人近い児童がいたけれど、呼名確認はしていなかったように思います。先生の目に狂いはないと児童も保護者も思っていました。
中学は、朝礼が無くって一時間目の先生がチェックしていたように記憶しています。
まず自分の閻魔帳に付けて、出席簿に転記していたように思います。
クラスの出席簿は日直が職員室から学級日誌といっしょに持ち出していた……記憶が蘇って来ました。
「おはようございます、1年5組の日直です。出席簿と学級日誌とりにきました」
そう言って持って行った。持っていくについてのお作法は、上級生がやっているのを見て覚えたような気がします。
今のように、職員室のドアに「失礼します~失礼しました」までのマニュアルは貼られてはいなかった。だから、生徒によってバラつきがあり、きちんと挨拶する者も何も言わない者も居ました。わたしは「1年5組です」くらいで済ませていたように思います。
職員室の先生たちが生徒の声に応えることはほとんどありません。今の学校なら「はい」とか「ごくろうさん」ぐらいは返していると思うのですが、どうでしょう。
出席簿に付け間違いがあると、生徒は自分で申し出ました。
「すみません、この時間居てたんですけど」
「あ、そうか、すまんすまん」
これで済んでいました。相互に信頼関係があったというか、いい加減と言うか、出席簿というのはその程度のものでした。
先生たちが真剣に点呼したのは、遠足や修学旅行の時ぐらいでじゃなかったかと思います。校外学習でミスをすると置き去りとか、洒落にならない事態になるからでしょう。
高校でも朝の出席点呼はしませんでした。
建前は、一時間目の教師が点けることになっているのですが、ろくに点けていない先生も多かったように思います。一時間目の自習(つまり先生が休んでいる)も多く、遅刻に関しては、正確な把握はされていなかったのかなあ。
そうそう、程度の差はあるけれど、出席簿の管理は日直、または学級委員の書記の仕事でした。午前中に職員室前の黒板にクラスの出欠を書きに行ったことを覚えています。書き洩らしがあると『〇年〇組出欠が書かれていません、早く書きに来てください』と教務の先生が校内放送されました。それでも書きに来ないと「日直(または書記)しっかりせえ!」と担任に怒られます。
自分が教師になったときは、完全に担任がつけていました。
きちんとつけないとトラブルになります。
「〇〇、今朝は遅刻やったな」
終礼で宣告すると。
ジト目で「おった」あるいは「おったわ、ボケ!」と返されます。
ちなみに、この返事のパターンに男女の区別はありません。時には、俯いたまま「殺すぞ……」という凄みのあるのもありました。
試行錯誤の結果、以下のように定着しました。
予鈴3分前に教室の前に行き、窓から「もう鐘鳴るぞ! 急げ!」と大音声で叫びます。1分前からカウントダウンし、予鈴が鳴ると共に教室に入る。
「座れ! 自分の席に着いてないやつは欠席やぞ!」
そしてバインダーに挟んだ座席表を見ながら呼名点呼をやる。ここで大事なことは、必ず生徒の目を見ながら確認することであります。いなければ欠席記号の『/』を点けます。
目を見ておかないと「おったわ、ボケ!」をかまされます。
クラス35人余り、全員が居ると20秒ほどで終わります。たいてい20人もいないので10秒余りで終わります。
ただ、この10秒の間にも入ってくる生徒がいるので、もう一度欠席者の名前を叫んでおきます。二回目の点呼で確認できればセーフというわけです。セーフの場合は『/』にコの字を二つ加えて『出』の字に変えます。
これを続けていると「おったわ、ボケ!」をくらわなくなります。
うちの担任は出欠に関してはシビアやと刷り込んでしまうのです。
出欠点呼をきちんと取ること、掃除当番をサボらせないこと、この二つが生徒との信頼関係の基礎でありました。