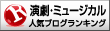小説学校時代 24
賃金職員という言葉をご存知でしょうか?
賃金職員とは、三交代を含むフルタイムで働くなど、仕事の内容、責任も正規の職員と同じなのに、「定員外」だという理由で一年未満の雇用契約の更新をくり返し、賃金や労働条件も差別されている職員のことです。 例えば夏季休暇、結婚休暇、育児休暇、介護休暇などを認められず、正規の定員職員より長時間労働となることも珍しくありません。
検索すると、上記のような説明が出てきました。
え? そんな恐ろしい仕事だったのか!?
わたしは、この賃金職員を三年間やっていました。母校である高校の賃金職員です。
最初は、図書室司書の産休補助でした。
卒業後も部活の指導と言えば聞こえはいいのですが、大学がつまらないので、週に四日ぐらいは母校に通っていました。
そんな中、在学中からお世話になっていた先生や司書の先生が「三月からの三か月だけどやってみない?」と勧められて、就職が決まっていなかったので渡りに船と引き受けました。
終わりのころになると「保健の統計員の仕事があるけど」と言われ、図書室の隣の保健室で身体測定結果の集計をやりました。
六月に終わると、他のバイトをしながら再び部活の指導に通いました。
「学校が好きやねんなあ」という評判がたちました。
あくる年に、再び司書の産休補助の仕事が回ってきて、今度は育児休暇込みでしたので、一年近くやっていました。
本性は就職浪人でしたので、仕事以外は暇です。
正規の司書は実習助手なので、勤務時間は8時30分から午後の5時15分までです。
図書室を利用する生徒は5時になると「そろそろ閉館します」と急き立てられます。
利用する生徒の半分は図書室を自習室に使っていました。家に帰っても勉強できる環境にない生徒が数十名いました。そのうちの十数人が恒常的に放課後の図書室で勉強しています。
賃金職員をやりながら部活の指導もやっていましたので、学校には6時過ぎまで居ました。それで、図書室も6時過ぎまで開放していました。
勉強の区切りがつかない生徒の為に、夏場ですと7時近くまで開けていたこともありました。
まあ、半分以上は好きで居残っているので、特に苦にもなりません。
組合的な思考をすると、正職の司書が復帰した時、同様な勤務を求められると困るので、賃金職員といえど、勤務時間はまもらなければならないのですが――生徒の役に立っていことでもあり、好きにさせておこう――ということで、自由にさせてもらえました。
二度目の臨時司書をやっていた二月ごろでしょうか、いつも最後まで残って勉強していた女生徒が頬を赤らめてカウンターに寄ってきました。
え、なにごと?
「ありがとうございました。家では勉強できないので、本当に助かりました! お陰様で無事に大学に受かりました!」
わざわざ、受験結果の報告とお礼に来てくれたのです。
いつも奥の席で勉強している姿は憶えていましたが、口を利くのも初めてですし、名前も知りません。
浅はかにも、ちょっと別の想像が頭をよぎったのですが(^_^;)
「よかったね、おめでとう!」的なことを言ってあげたと思うのですが、アタフタして定かではありません。
自分が、気まぐれ的というか気楽に居残っていたことが感謝されたり、思い違いしたりで、狼狽えたというのが正直なところでした。
「それで、どこの大学に通ったのかなあ?」
「はい、大阪大学です!」
圧倒されました。わたしが出た大学が大阪の地べたであるとしたら、大阪大学を標高で表せる山はありません。生駒山はもちろんのこと金剛山でも足りません。あっぱれ、富士の山頂でありましょう。
この間、いろいろ面白い事がありましたが、それは、また稿を改めて。