源実朝の歌を漢詩にする試みを進めています。前回同様、掛詞を駆使した歌です。新勅撰集に撰された歌で、新古今調の影響を強く受けた歌と言えます。ただ、“技術”に凝り過ぎて、訴える“想い”が軽く感じられるように思われます。
“幾夜も幾夜も”のフレーズは、漢詩では“幾世”としました。その意図は、“今生では逢瀬は遂げられないのか!”との強い“想い”を訴えたいことによります。
oooooooooooooo
詞書] 久恋
我が恋は 逢はでふる野の 小笹原
幾よまでとか 霜の置くらむ
(『金塊集』恋の部・464;『新勅撰集』恋四・904)
註] 〇ふる野:“経る”と“布留”の掛詞、“布留野”は奈良の地名; 〇幾よ:
“幾節(ヨ)”、“幾夜”、“幾世”の掛詞; 〇霜の置く:我が頭髪の白くなるこ
とを寓意。
(大意) 我が恋は、あたかも布留野のささ原に幾節も枯れ残さぬほどに霜が
置くようなものだ。すなわち、恋人に逢わずに幾夜も幾夜も過ごして頭髪
には霜がおくことであろう。
<漢詩>
陷入情網 [上平声二冬-一東韻]
我恋有如相不逢, 我が恋は 有如(アタカモ) 相逢うこともなく,
布留霜篠幾節空。 布留野(フルノ)で霜に篠(ササ)の幾節(イクヨ)もが空(キエ)る如きか。
要求幾世等下去, 幾世(イクヨ) 等(マ)ち続けることを要求(モトメ)るか,
到白髮而遊晚風。 白髮となり、而(シカ)して晚風に遊ぶに到(イタ)るまでか。
註] ○情網:恋の闇路; 〇有如:…のようだ; ○布留:“布留野”の略で、
奈良の地名; 〇篠:細いタケ、ササ。“笹”は国字; ○幾節:“幾夜”の掛
詞、“幾夜も幾夜も”の意を表すか; 〇空:消えてなくなる、尽きる。
※ 「長煙一空、皓月千里」(長煙一(ヒトタビ)空(ツ)き、皓月(コウゲツ)千里):長く
立ち込めたもやがさっと消えると、皓皓たる月が千里の彼方まで照らす(范
仲淹・岳陽楼記。)
<現代語訳>
恋焦がれる想い
我が恋は、恰も相い逢うこと叶わず、
布留野で降りた霜に篠の幾節もが枯れて消えていくようなものだ。
一体 幾世待ち続けなければならないというのか、
白髪となり、歳月を重ね、よろめくようになるまでか。
<簡体字およびピンイン>
陷入情网 Xiànrù qíng wǎng
我恋有如相不逢, Wǒ liàn yǒu rú xiāng bù féng,
布留霜筱几节空。 bùliú shuāng xiǎo jǐ jié kōng.
要求几世等下去, Xūyào jǐ shì děng xiàqù,
到白发而游晚风。 dào bái fà ér yóu wǎn fēng.
xxxxxxxxxxxx
上掲の実朝歌は、1193年、藤原良経が主催した『六百番歌合』(判詞:藤原俊成)に際して、藤原有家が提示した歌(下記)を本歌とした本歌取りの歌でないかと示唆されています(渡部泰明編『源実朝 虚実を越えて』 勉誠出版)。
我が恋は 布留野の道の 小笹原
いく秋風に 露こぼれ来ぬ (『六百番歌合』 779・旧恋)
(大意) 我が恋は、布留野の道の小笹原に置いた露のように、秋風が過ぎるご
とにこぼれ落ちていく
歌人・源実朝の誕生 (9)
源頼朝は、1190及び1195年の二度上洛を行っている。第一回目は、義経次いで奥州藤原氏の討伐を果たした翌年、1190年10月3日である。上洛軍は史上最大とされ、先陣・畠山重忠が現 茅ヶ崎辺りに至っても、後陣・千葉常胤は未だ鎌倉を出発していなかったという。両地点間は、約15km と。
11月7日に京都入りし、約一月間京都に滞在、後白河法皇と、計8回会談が行われた由。頼朝は、法皇より日本国総追捕使および日本国総地頭の地位を授けられ、名実ともに全国の軍事警察権を握ることになりました。しかし頼朝が最も切望した征夷大将軍を授かることは、法皇が反対で叶わなかった。
第2回目の上洛は、後白河法皇の没3年後、1195年2月、頼朝は政子と頼家・大姫を伴って上洛する。世の中が治まり、ある種、家族旅行の雰囲気が漂っていたのではないでしょうか。頼家は6月3日と24日に参内し、都で頼朝の後継者としての披露が行われた。後鳥羽天皇の御代である。
さて、前回提示した頼朝の歌である。本歌は、上洛の“道すがら”詠まれたとされています。さほど緊張感のなかった第2回目上洛時のようにも思える。しかし、頼朝が「日本国第一の大天狗」と喝破した後白河法皇を「得体の知れないお方だ」と、曇り空の富士に後白河法皇の姿を重ねたようにも読めますが。
道すがら 富士の煙も 分かざりき
晴るる間もなき 空の景色に
(『新古今集』巻第十 羇旅・975)
(大意) 道中、空に晴れ間を見せることはなく、富士山の噴煙も分からないほ
ど曇っていたよ。
この頼朝の上洛中、忘れてならない人物、慈円(1155~1225)が京都におられました。頼朝は、慈円とも会合を重ねていたようである。慈円は、京都にあって世の情勢を客観的に見る立場にあり、現状さらには将来見通しなど、特に、京都/鎌倉の関係等々、話題とされたのではないでしょうか。
慈円には、「一切の法(真理・存在・規範)は、ただ道理“という二文字がもっている。その他にはなにもない」とする主張があった。すなわち、 歴史のすべての事実や事件は、”道理“が現れたものとして正当視し、「あるものをある」と認める現実主義の考え方でもある。
我々はよく、歴史的事象を「時代の大きな流れだよ」、とか「時代の流れには逆らえない」と表現しますが、此処でいう“流れの方向”が、慈円の言う“道理”が現れた“事象”であるよう愚考されるが、如何であろうか。
当時の京都vs.鎌倉の関係の状況の中で評するなら「公武合体派」、「現実主義者」と言うことである。慈円自身、自らの一生を顧みて、「名利の二道をあゆむ」と率直に告白しています。



















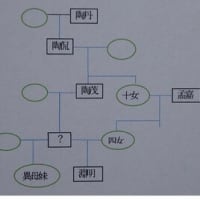






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます