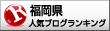(つづき)
福岡市東区の「ゴルフ場入口」バス停。
「23番」の高美台一丁目&大蔵系統、「29-1番」、及び「新宮・和白循環線」の生き残りである「無番 高美台一丁目~新宮緑ケ浜線」が停車する。
「ゴルフ場」とは、ここから南側にある「福岡カンツリー倶楽部」のことだが、西鉄バスを利用してゴルフ場を訪れる人はあまりいないと思われる(私がゴルフをやらないので、実際のところはよくわかりませんが…)。
なお、同じく東部地区には古賀市に「ゴルフ場前」というバス停もあるが、こちらのゴルフ場は「古賀ゴルフクラブ」のことである。
“仮に、福岡市東区が市の中のひとつの区ではなく、独立した「市」だったとしたら”とか、“もし仮に、戦後の福岡市の道路政策が「三次元的」な施策に積極的だったとしたら”など、「もし」とか「仮に」を考えるのは結構好きなのだが、もし仮に、ここにゴルフ場がなかったとしたら、都市計画や土地利用の形態、道路の配置やバス路線網なども、現在とは全く違う姿になっていたことだろう。
福岡市東区の人口が今よりも多くなって、「分区」が行われていた可能性もあるかもしれない。
この「ゴルフ場入口」を走る路線のうち「高美台一丁目~新宮緑ケ浜線」は、走っている区間のすべてに「23番」が走っており、エリアというか「行先」的に見ると「23番」以外の何物でもないのだが、「23番」という番号は付いておらず「無番」である。
同様に、「西鉄三苫駅~新宮緑ケ浜線」にも番号が付いていない。
「23番が23番たる所以」というか、どの路線がその番号に属するのか、という明文化された「定義」みたいなものはないので、「イメージの世界」にはなってしまうのだが、この例をみると、「23番」はあくまで、「都心部~香椎地区~末端部」を走る路線であって末端部同士を行き来するものは「23番」には含まれない(というか、含めてしまうとわかりにくくなる)というぼんやりとした「定義」を見出すことができる。
「四箇田団地~福大病院」が「12番」ではなく「無番」であったのも同様といえよう。
ただ、「原田橋~宇美営業所」が「34番」として運行していたケースなどもあり、この「定義」が末端部を多く持つ全ての路線に当てはまるものではない。
末端部同士を行き来する路線であっても、「早良営業所~椎原」「早良営業所~曲渕」などは、「都心部~西新地区~末端部」というベクトルからは逸脱していないため、福岡都心部まで足をのばさなくなった後でも依然「3番」という番号が付いている。
一方で、志賀島線をみてみると、「和白営業所~志賀島~勝馬」という区間便が登場した際、都心部へのベクトルからの逸脱はないにもかかわらず、「21番」から独立して新たに「1番」という番号が付けられている。
このあたり、「番号の付け方」に関して何らかの法則を見出して定義付けるというのはかなり難しい(というか不可能)と思われるが、あれこれと考えるのは面白い。
以前“西鉄バスの行先番号は、単なる「番号」ではなく、その数字が持つ意味を直接・間接に伝えている「名前」的な側面が多分にあって、それが面白いなぁと思う”と書いたことがあるが、別の見方をすると、「行先」という側面に加えて「方向」の要素もかなり入っていると言えそうだ。
もし(←また仮定の話である)、早良区の末端部、椎原・曲渕地区のバスに福岡市の補助金が入り、「曲渕~陽光台(複乗)~西神の原~脇山小(複乗)~椎原」のような路線ができたとしたら、それは「3番」となるだろうか、それとも「無番」となるだろうか。
(つづく)
福岡市東区の「ゴルフ場入口」バス停。
「23番」の高美台一丁目&大蔵系統、「29-1番」、及び「新宮・和白循環線」の生き残りである「無番 高美台一丁目~新宮緑ケ浜線」が停車する。
「ゴルフ場」とは、ここから南側にある「福岡カンツリー倶楽部」のことだが、西鉄バスを利用してゴルフ場を訪れる人はあまりいないと思われる(私がゴルフをやらないので、実際のところはよくわかりませんが…)。
なお、同じく東部地区には古賀市に「ゴルフ場前」というバス停もあるが、こちらのゴルフ場は「古賀ゴルフクラブ」のことである。
“仮に、福岡市東区が市の中のひとつの区ではなく、独立した「市」だったとしたら”とか、“もし仮に、戦後の福岡市の道路政策が「三次元的」な施策に積極的だったとしたら”など、「もし」とか「仮に」を考えるのは結構好きなのだが、もし仮に、ここにゴルフ場がなかったとしたら、都市計画や土地利用の形態、道路の配置やバス路線網なども、現在とは全く違う姿になっていたことだろう。
福岡市東区の人口が今よりも多くなって、「分区」が行われていた可能性もあるかもしれない。
この「ゴルフ場入口」を走る路線のうち「高美台一丁目~新宮緑ケ浜線」は、走っている区間のすべてに「23番」が走っており、エリアというか「行先」的に見ると「23番」以外の何物でもないのだが、「23番」という番号は付いておらず「無番」である。
同様に、「西鉄三苫駅~新宮緑ケ浜線」にも番号が付いていない。
「23番が23番たる所以」というか、どの路線がその番号に属するのか、という明文化された「定義」みたいなものはないので、「イメージの世界」にはなってしまうのだが、この例をみると、「23番」はあくまで、「都心部~香椎地区~末端部」を走る路線であって末端部同士を行き来するものは「23番」には含まれない(というか、含めてしまうとわかりにくくなる)というぼんやりとした「定義」を見出すことができる。
「四箇田団地~福大病院」が「12番」ではなく「無番」であったのも同様といえよう。
ただ、「原田橋~宇美営業所」が「34番」として運行していたケースなどもあり、この「定義」が末端部を多く持つ全ての路線に当てはまるものではない。
末端部同士を行き来する路線であっても、「早良営業所~椎原」「早良営業所~曲渕」などは、「都心部~西新地区~末端部」というベクトルからは逸脱していないため、福岡都心部まで足をのばさなくなった後でも依然「3番」という番号が付いている。
一方で、志賀島線をみてみると、「和白営業所~志賀島~勝馬」という区間便が登場した際、都心部へのベクトルからの逸脱はないにもかかわらず、「21番」から独立して新たに「1番」という番号が付けられている。
このあたり、「番号の付け方」に関して何らかの法則を見出して定義付けるというのはかなり難しい(というか不可能)と思われるが、あれこれと考えるのは面白い。
以前“西鉄バスの行先番号は、単なる「番号」ではなく、その数字が持つ意味を直接・間接に伝えている「名前」的な側面が多分にあって、それが面白いなぁと思う”と書いたことがあるが、別の見方をすると、「行先」という側面に加えて「方向」の要素もかなり入っていると言えそうだ。
もし(←また仮定の話である)、早良区の末端部、椎原・曲渕地区のバスに福岡市の補助金が入り、「曲渕~陽光台(複乗)~西神の原~脇山小(複乗)~椎原」のような路線ができたとしたら、それは「3番」となるだろうか、それとも「無番」となるだろうか。
(つづく)