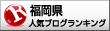(つづき)
福岡市早良区の「早寿園前」バス停。
「早寿園」とは、福岡市立の老人福祉センターである。
「早良」の「早」と、「長寿」の「寿」、…だろうか。
「93 藤崎」「3 西新」「2 早良高校」と、バス停の行先案内だけ見るとたくさんのバスが来るように錯覚してしまう。
でも実際には、「2番」は通学用に平日朝3本だけ(反対方向は夕方2本)である。
また、「93番」と「3番」も実質同一で、早良区役所が開いている平日は「93番 藤崎行き」、閉まっている土日祝日は「3番 西新行き」と、曜日によって番号と終点が変わるだけであり(いずれも現在は一時間に一本の運行)、同じ日にここに「3番」と「93番」が来ることはない。
このバス停のひとつ西の「四箇田公民館前」バス停のあたりから、東の国道263号までの間の道路が開通してからまだ20年は経っていないと思うが、「バス路線のネットワーク」という観点からは、田隈小学校前~野芥間の廃止以降、国道263号と県道内野次郎丸弥生線をつなぐ、より貴重なラインとなっている(ただ、そのような利用のされ方はされていないと思うけど)。
ちなみに開通前は、「209番」などに、四箇田団地からひとつ東まで足をのばす「四箇田団地東口行き」という系統が一日数本だけあったが、あまり定着することなく廃止されてしまった(「東口」の廃止から道路開通までの間にはタイムラグがあったかもしれません)。
(つづく)
福岡市早良区の「早寿園前」バス停。
「早寿園」とは、福岡市立の老人福祉センターである。
「早良」の「早」と、「長寿」の「寿」、…だろうか。
「93 藤崎」「3 西新」「2 早良高校」と、バス停の行先案内だけ見るとたくさんのバスが来るように錯覚してしまう。
でも実際には、「2番」は通学用に平日朝3本だけ(反対方向は夕方2本)である。
また、「93番」と「3番」も実質同一で、早良区役所が開いている平日は「93番 藤崎行き」、閉まっている土日祝日は「3番 西新行き」と、曜日によって番号と終点が変わるだけであり(いずれも現在は一時間に一本の運行)、同じ日にここに「3番」と「93番」が来ることはない。
このバス停のひとつ西の「四箇田公民館前」バス停のあたりから、東の国道263号までの間の道路が開通してからまだ20年は経っていないと思うが、「バス路線のネットワーク」という観点からは、田隈小学校前~野芥間の廃止以降、国道263号と県道内野次郎丸弥生線をつなぐ、より貴重なラインとなっている(ただ、そのような利用のされ方はされていないと思うけど)。
ちなみに開通前は、「209番」などに、四箇田団地からひとつ東まで足をのばす「四箇田団地東口行き」という系統が一日数本だけあったが、あまり定着することなく廃止されてしまった(「東口」の廃止から道路開通までの間にはタイムラグがあったかもしれません)。
(つづく)