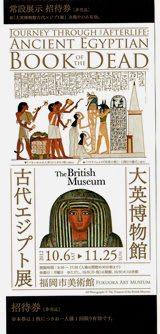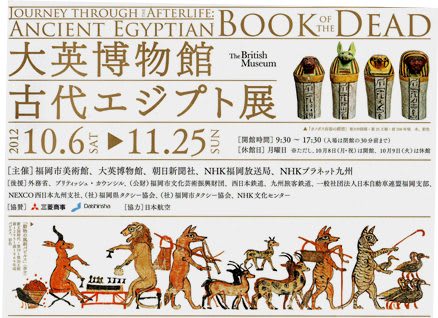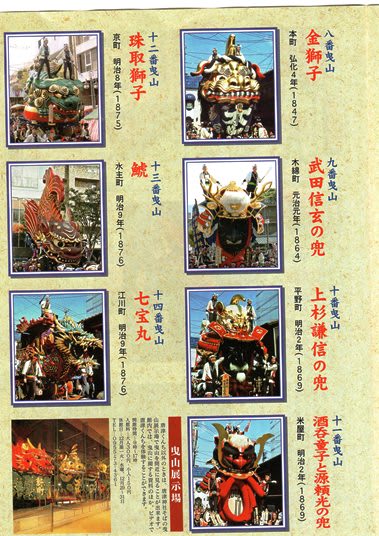遠州七窯の一つで、やきものの里として知られる上野(あがの)に在る興国寺に参詣しました。
久しぶりに訪問した弟のところで、話が弾んで、南北朝の歴史や、足利尊氏と九州との関わりに興味のある夫が、確か上野には、尊氏ゆかりの寺があったはずと言い出して、それではと、弟が運転する車で出かけました。直方までバイパスができているので,30分足らずです。寺号も何もわからないままでしたが、上野で聞けばわかるだろうと出かけました。
英彦山や田川美術館、仲愛トンネル越えで大分方面に向かう時にはいつも通過しているのですが、もう数十年上野には立ち寄っていないのに気づきました。
数多い窯元から煙の上っている処もなく、平日のせいもあって、ひっそりと人通りも殆どありません。
「ふれあい市」と書かれた道の駅らしき看板を見て、展示の花に水やりをしていた女性に、尊氏ゆかりの寺と尋ねると、「ああ、興国寺ですね。ここから3分くらいですが、分りにくい所ですから案内します。私に着いてきてください。」と先導してくださいました。
福地山麓の、山深くにひっそりと、だが堂々とした佇まいでその伽藍は建っていました。
市教育委員会の案内板で概要は盡されています。(興味がおありの方は拡大でどうぞ)開扉の時、案内状をくださるとのことでした。足利直義や尊氏の寄進状。大友氏や、大内氏の書状、細川幽斎の和歌など、文書関係の資料も失われたとはいえ多数現存しているようです。
本堂の前の静心池は、かつては戦に備えての内堀の役割を果たしたもののようでした。
敗走で九州に逃れた尊氏が潜んでいたという洞穴?という伝承の場所をちょっと探してみたのですが見つからず、散りつくした銀杏の落ち葉が、冷たい風に吹かれて舞うのみでした。
ご住職は他出しておられ、詳細を伺えず、仏殿(享保4年完成)の観音堂は閉じられていて、拝見できませんでした。春の桜のころにまた訪れてみるつもりです。
豊前 上野 興国寺