市町村のマークというか紋章。
市町村合併に伴って最近定められたものは、曲線を多用してカラフルな、そしてあまり個性が感じられない(=似たりよったり)ロゴマークみたいなのが多い。(今日6月5日を「ロゴマークの日」と定めたデザイン会社があるそうだ。ロゴというより語呂ですな)
名古屋市の「○に八」とか、弘前市の「卍(まんじ)」とかシンプルなほうが分かりやすい。
※弘前市の卍は、ナチスドイツの「ハーケンクロイツ」とは向きが異なる。15年ほど前、一部のマンホールのフタがハーケンクロイツになっていたことが指摘され、修正したことがあった。
秋田市の市章もシンプル。
秋田市のホームページ「秋田市の沿革・市章・市の木・市の花・市民歌(http://www.city.akita.akita.jp/benri/01annai/03_4.htm)」によれば、「的に「矢留」の形と、秋田市の「田」の字をあらわしています。「矢留」とは旧秋田藩主佐竹氏の居城「久保田城」の別名。」とある。
秋田市章の歴史は長く昭和3年6月制定。秋田市例規集第1編第1章「市の紋章」が昭和3年6月8日付で告示されているから、今週の土曜日で秋田市章制定85周年ということになるらしい。
例規では「直径2寸4分ニ対シ輪ノ太サ2分、中心円径4分、矢羽ノ幅ハ広キ処4分狭キ処3分斜線ハ水平線ニ対シ30度ノ角度」とか細かく定めていて、「当市出身小場恒吉氏ノ考案ニ係ルモノデアル」であるそうである。
※小場恒吉は紋様学者、美術史家、画家(1878-1958)。県立秋田工業高校教諭や東京芸術大学教授を歴任し、秋工の校章も作った。秋田市章は秋田市制40周年で定められたとのこと。
秋田市章の「色」は定められていないようで、例規集では黒色で図示されている。
また、これも明確に定められてはいないのかもしれないが、秋田市の色として「若草色」が定着している。
そんなわけで具体的な根拠は知らないけれど、実際には市章にも若草色が使われている。
「秋田市旗」では若草色の地に白抜きで市章が配置され、カラーで市章だけを表示する場合は若草色で描くことになっているようだ。
秋田市の公式ホームページの各ページにも、市章が配置されているが、若草色というよりはただの緑色になっている。
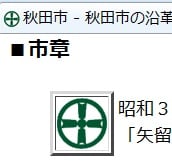 若草色とは違う
若草色とは違う
今年夏に、秋田県中央部の海沿いの市町村で開催される「第10回海フェスタ実行委員会」のホームページ(http://www.umifesta-oga.jp/)では、他の市町村章と一緒に、若草色に近い色の秋田市章が出ている。

さて、先日青森市営バスのを紹介した(リンク先末尾)けれど、各地の市営バスの車体にはその市の市章が付いていることが多い。(仙台市営バスにはない【6日訂正・仙台市バスは側面に市章があるとのこと。コメント欄参照】)
秋田市営バスでも、路線車両では正面に付いていた。(貸切車両などは側面に付いていたものもあった)
 (再掲)祝日は市旗を付けていたので、秋田市のマークが2つ
(再掲)祝日は市旗を付けていたので、秋田市のマークが2つ
少なくとも市営バス末期に在籍した車両では、ラインを銀色で、円内の背景を白みがかった緑色にした市章だった。おそらく、円形の金属製の板をビスで留めていたかと思われる。(小型バスでは2回りくらい小さい同じもの)
移管に際して中央交通に譲渡された車両は、塗り替え作業が終わるまでは、市章が剥がされた(その跡に白いシールを貼った?)状態でしばらく運行され、魂が抜かれたようで寂しく思えたものだ。
末期の市営バスの市章の中でちょっと変わっていたのが、1995年度導入の三菱製中型車(130~133の4台。現在も中央交通で活躍中)。
 130号車。バンパーがグレーなのも特徴的
130号車。バンパーがグレーなのも特徴的
この車両の市章は、平面的で車体にぴったり張り付いているように見える。市章の線は光沢のある銀色ではなくグレーっぽい。それに他の車両では見えることがあるビスやネジのようなものが見えない。
おそらく、印刷したシート状のものを貼っているのではないだろうか。
同年導入の小型車や翌年の日産ディーゼル製では通常の市章だったようだから、この年の三菱だけの仕様だったのだろうか。(三菱の路線車は1995年度導入が最後。その前の1993年度車は通常の市章)
さらに、その4台の中で、ひときわ変わった市章の車があった。
 131号車。分かりますか?(2001年9月撮影)
131号車。分かりますか?(2001年9月撮影)
市章の背景の色が違うのです。
他より黄色がかった緑色というか、蛍光色っぽいというか。これは「若草色」と言えそう。
 水滴が付いている(2002年2月撮影)
水滴が付いている(2002年2月撮影)
市章以外にも特徴があるのにお気づきでしょうか。
それは、旗を立てる棒がないこと!
上の拡大した写真では、旗を立てるべき位置に穴は開いている。必要な時だけ立てていたのだろうか?
 (再掲・2005年9月撮影)
(再掲・2005年9月撮影)
2001年9月の時点では、既にこの市章で旗の棒がない。その後、2002年3月では棒がなく、2003年2月(祝日でない日)では棒が立っていた。
最末期は、他の車両と同様に棒が常にあったことになる。
 131号車と268号車(1991年度導入)。車体の色も肌色とピンクっぽくて違う。2002年2月撮影
131号車と268号車(1991年度導入)。車体の色も肌色とピンクっぽくて違う。2002年2月撮影
 291号車(1993年度導入)と棒がある131号車。2003年11月撮影
291号車(1993年度導入)と棒がある131号車。2003年11月撮影
どうして131号車だけ、市章や旗の棒が違うのか。
おそらく、事故などで前を破損し、その復旧時に違うものに替わってしまったと考えられる。
同じようなものに271号車の側面窓や249号車のバンパーもあるのですが、いずれまた。
131号車は、2006年3月31日の秋田市交通局の最終日までこの市章(ただし「ありがとう」の幕で隠れていた)で運行し続け、最終便を担当した5台のうち1台となった(当日の運用からすれば、他の4台は増車扱いで、この131号車こそが真の最終運行の車両だったはず)後、中央交通へ譲渡・塗装変更された。(この年は車両数に余裕があったらしく、市営バスの塗装のまま中央交通で運行されることはなかった)
※塗り替えられた後の状況はこの記事後半
市営バスの市章で変わったものとして他には、
 (再掲)230号車
(再掲)230号車
 留めているビスが見える
留めているビスが見える
230号車の市章も、背景の緑色が若草色に近いように見える。
230号車は1989年導入の三菱車で、計3台(230~231号車)が導入されているものの、他の2台の画像がないため、230号車だけだったのか検証はできない。
【6日追記】
秋田市営バスと市章といえば、乗務員の制服のボタンや制帽の帽章にも、秋田市章(そのものではなく)をベースにしたものがデザインされていたはず。
なお、秋田市の市長部局などの職員(交通局の事務職員も対象か)に支給される「事務服」のボタンには市章などは使われていないらしい。
それから、交通局発行分の回数券の地紋も、薄い黄色で小さい市章がびっしりと並んでいた。
市町村合併に伴って最近定められたものは、曲線を多用してカラフルな、そしてあまり個性が感じられない(=似たりよったり)ロゴマークみたいなのが多い。(今日6月5日を「ロゴマークの日」と定めたデザイン会社があるそうだ。ロゴというより語呂ですな)
名古屋市の「○に八」とか、弘前市の「卍(まんじ)」とかシンプルなほうが分かりやすい。
※弘前市の卍は、ナチスドイツの「ハーケンクロイツ」とは向きが異なる。15年ほど前、一部のマンホールのフタがハーケンクロイツになっていたことが指摘され、修正したことがあった。
秋田市の市章もシンプル。
秋田市のホームページ「秋田市の沿革・市章・市の木・市の花・市民歌(http://www.city.akita.akita.jp/benri/01annai/03_4.htm)」によれば、「的に「矢留」の形と、秋田市の「田」の字をあらわしています。「矢留」とは旧秋田藩主佐竹氏の居城「久保田城」の別名。」とある。
秋田市章の歴史は長く昭和3年6月制定。秋田市例規集第1編第1章「市の紋章」が昭和3年6月8日付で告示されているから、今週の土曜日で秋田市章制定85周年ということになるらしい。
例規では「直径2寸4分ニ対シ輪ノ太サ2分、中心円径4分、矢羽ノ幅ハ広キ処4分狭キ処3分斜線ハ水平線ニ対シ30度ノ角度」とか細かく定めていて、「当市出身小場恒吉氏ノ考案ニ係ルモノデアル」であるそうである。
※小場恒吉は紋様学者、美術史家、画家(1878-1958)。県立秋田工業高校教諭や東京芸術大学教授を歴任し、秋工の校章も作った。秋田市章は秋田市制40周年で定められたとのこと。
秋田市章の「色」は定められていないようで、例規集では黒色で図示されている。
また、これも明確に定められてはいないのかもしれないが、秋田市の色として「若草色」が定着している。
そんなわけで具体的な根拠は知らないけれど、実際には市章にも若草色が使われている。
「秋田市旗」では若草色の地に白抜きで市章が配置され、カラーで市章だけを表示する場合は若草色で描くことになっているようだ。
秋田市の公式ホームページの各ページにも、市章が配置されているが、若草色というよりはただの緑色になっている。
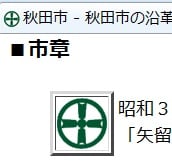 若草色とは違う
若草色とは違う今年夏に、秋田県中央部の海沿いの市町村で開催される「第10回海フェスタ実行委員会」のホームページ(http://www.umifesta-oga.jp/)では、他の市町村章と一緒に、若草色に近い色の秋田市章が出ている。

さて、先日青森市営バスのを紹介した(リンク先末尾)けれど、各地の市営バスの車体にはその市の市章が付いていることが多い。(
秋田市営バスでも、路線車両では正面に付いていた。(貸切車両などは側面に付いていたものもあった)
 (再掲)祝日は市旗を付けていたので、秋田市のマークが2つ
(再掲)祝日は市旗を付けていたので、秋田市のマークが2つ少なくとも市営バス末期に在籍した車両では、ラインを銀色で、円内の背景を白みがかった緑色にした市章だった。おそらく、円形の金属製の板をビスで留めていたかと思われる。(小型バスでは2回りくらい小さい同じもの)
移管に際して中央交通に譲渡された車両は、塗り替え作業が終わるまでは、市章が剥がされた(その跡に白いシールを貼った?)状態でしばらく運行され、魂が抜かれたようで寂しく思えたものだ。
末期の市営バスの市章の中でちょっと変わっていたのが、1995年度導入の三菱製中型車(130~133の4台。現在も中央交通で活躍中)。
 130号車。バンパーがグレーなのも特徴的
130号車。バンパーがグレーなのも特徴的この車両の市章は、平面的で車体にぴったり張り付いているように見える。市章の線は光沢のある銀色ではなくグレーっぽい。それに他の車両では見えることがあるビスやネジのようなものが見えない。
おそらく、印刷したシート状のものを貼っているのではないだろうか。
同年導入の小型車や翌年の日産ディーゼル製では通常の市章だったようだから、この年の三菱だけの仕様だったのだろうか。(三菱の路線車は1995年度導入が最後。その前の1993年度車は通常の市章)
さらに、その4台の中で、ひときわ変わった市章の車があった。
 131号車。分かりますか?(2001年9月撮影)
131号車。分かりますか?(2001年9月撮影)市章の背景の色が違うのです。
他より黄色がかった緑色というか、蛍光色っぽいというか。これは「若草色」と言えそう。
 水滴が付いている(2002年2月撮影)
水滴が付いている(2002年2月撮影)市章以外にも特徴があるのにお気づきでしょうか。
それは、旗を立てる棒がないこと!
上の拡大した写真では、旗を立てるべき位置に穴は開いている。必要な時だけ立てていたのだろうか?
 (再掲・2005年9月撮影)
(再掲・2005年9月撮影)2001年9月の時点では、既にこの市章で旗の棒がない。その後、2002年3月では棒がなく、2003年2月(祝日でない日)では棒が立っていた。
最末期は、他の車両と同様に棒が常にあったことになる。
 131号車と268号車(1991年度導入)。車体の色も肌色とピンクっぽくて違う。2002年2月撮影
131号車と268号車(1991年度導入)。車体の色も肌色とピンクっぽくて違う。2002年2月撮影 291号車(1993年度導入)と棒がある131号車。2003年11月撮影
291号車(1993年度導入)と棒がある131号車。2003年11月撮影どうして131号車だけ、市章や旗の棒が違うのか。
おそらく、事故などで前を破損し、その復旧時に違うものに替わってしまったと考えられる。
同じようなものに271号車の側面窓や249号車のバンパーもあるのですが、いずれまた。
131号車は、2006年3月31日の秋田市交通局の最終日までこの市章(ただし「ありがとう」の幕で隠れていた)で運行し続け、最終便を担当した5台のうち1台となった(当日の運用からすれば、他の4台は増車扱いで、この131号車こそが真の最終運行の車両だったはず)後、中央交通へ譲渡・塗装変更された。(この年は車両数に余裕があったらしく、市営バスの塗装のまま中央交通で運行されることはなかった)
※塗り替えられた後の状況はこの記事後半
市営バスの市章で変わったものとして他には、
 (再掲)230号車
(再掲)230号車 留めているビスが見える
留めているビスが見える230号車の市章も、背景の緑色が若草色に近いように見える。
230号車は1989年導入の三菱車で、計3台(230~231号車)が導入されているものの、他の2台の画像がないため、230号車だけだったのか検証はできない。
【6日追記】
秋田市営バスと市章といえば、乗務員の制服のボタンや制帽の帽章にも、秋田市章(そのものではなく)をベースにしたものがデザインされていたはず。
なお、秋田市の市長部局などの職員(交通局の事務職員も対象か)に支給される「事務服」のボタンには市章などは使われていないらしい。
それから、交通局発行分の回数券の地紋も、薄い黄色で小さい市章がびっしりと並んでいた。















