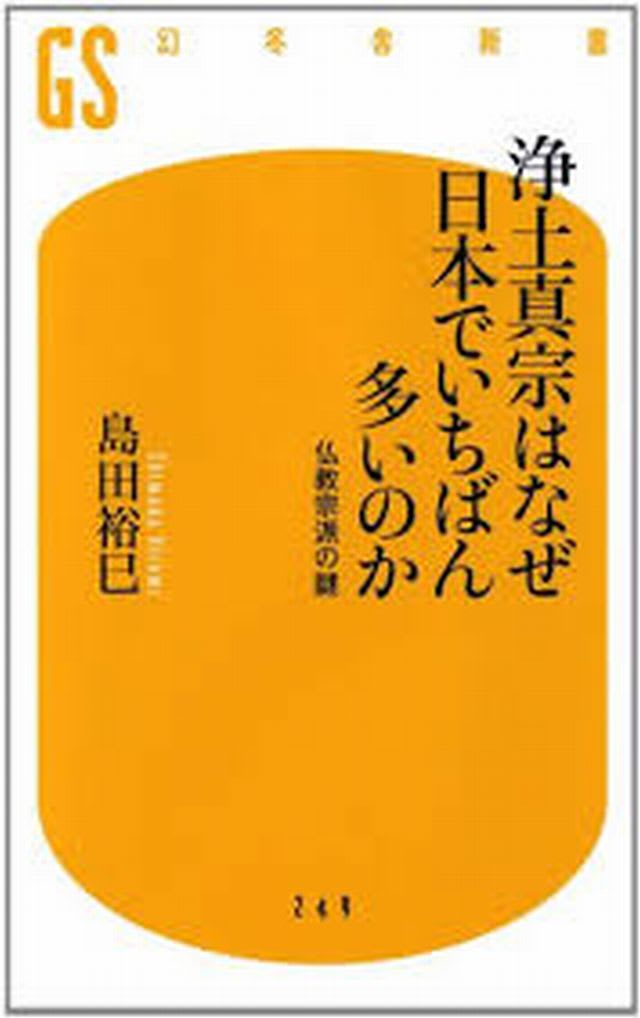🌸ロングテールの仕事とベルカーブの仕事を学ぶ
☆橘玲さんの内容と文章、難しく難解の場合多いですが
☆切り口の違う、示唆に富んだ内容が多いので
☆読んでいくうちに理解出来て、興味惹かれてきました
⛳「ユーチューバー」は小学生の「なりたい職業」で上位
☆人気のあるスペシャリストの仕事です
☆子どもから「ユーチューバーになりたい」といわれた場合の回答
☆ベルカーブとロングテールの話をしなければなりません
☆ベルカーブとロングテールの話をしなければなりません
*ベルカーブは統計学でいう正規分布
*ロングテールはべき分布のこと
⛳大谷翔平はロングテール
☆スペシャリスト(専門家)の職業
☆スペシャリスト(専門家)の職業
*「ロングテールの仕事」と「ベルカーブの仕事」がある
☆ロングテールというのは、ブロントサウルスのような恐竜に見立てる
☆ロングテールというのは、ブロントサウルスのような恐竜に見立てる
*そのテール(尾)がどこまでも長く延びていくことをいう
*そして、このしっぽの先で「とんでもないこと」が起きます
*誰でもすぐに思いつくような有名人は
*誰でもすぐに思いつくような有名人は
*みんなロングテール(長いしっぽ)の先にいます
☆「需要と供給の法則」は市場経済の大原則で
☆「需要と供給の法則」は市場経済の大原則で
*たくさんあるものは価値が低く、少ししかないものは価値が高い
*ロングテールの住人は、ほんの少ししかいないからこそ
*ロングテールの住人は、ほんの少ししかいないからこそ
*ものすごく価値が高い
☆世界中の野球選手を、縦軸を人数、横軸を人気度にして分類する
*ロングテールの端にいるのは、大谷翔平のような「特別なスター」
☆世界中の野球選手を、縦軸を人数、横軸を人気度にして分類する
*ロングテールの端にいるのは、大谷翔平のような「特別なスター」
*そのすこし左には、プロ野球や大リーグの選手たちがいます
*彼らもまた、野球の世界では「選ばれし者たち」です
*もっとも人数の多い左端のショートヘッド(短い頭)には
*もっとも人数の多い左端のショートヘッド(短い頭)には
*草野球、会社の同好会で野球を楽しんでいるアマチュアもいます
*その中間にいるのが
*社会人野球の選手や、プロを目指して頑張っている高校球児です
☆スポーツ選手や起業家だけでなく
☆スポーツ選手や起業家だけでなく
*歌手や俳優、マンガ家や小説家、「ユーチューバー」も
*「ロングテールの仕事」です
⛳「ロングテールの仕事」と「ベルカーブの仕事」の特徴
☆「ロングテールの仕事」2つの特徴がある
①いったん成功してテールの端にいくとものすごく有名になる
①いったん成功してテールの端にいくとものすごく有名になる
*そして大金持ちになる
②ほとんどの挑戦者が成功できずに競争から脱落していく
②ほとんどの挑戦者が成功できずに競争から脱落していく
☆ベルカープの仕事の2つの特徴
*医者や弁護士、 エンジニァやプログラマー、研究者など、「専門家」
①専門家になると平均以上の収入を得られる(大富豪にはなれない)
②大学や大学院などの学歴があると、専門家になりやすい
☆ロングテールの仕事はジヤンボ宝くじのようなもの
①専門家になると平均以上の収入を得られる(大富豪にはなれない)
②大学や大学院などの学歴があると、専門家になりやすい
☆ロングテールの仕事はジヤンボ宝くじのようなもの
*当たると大きな名声と大きなお金が手に入りますが
*ほとんどはハズレです
☆ベルカーブの仕事は、当たりがたくさんあるものの
*当せん金額の少ない宝くじのようなもの
⛳仕事を成功確率で考える
☆「努力の限界効用」で説明すると
☆「努力の限界効用」で説明すると
☆ロングテールの仕事は達成度99.9%以上ないと成功できない
*甲子園に出るような選手は野球の達成度で上位1%に入るでしょうが
*甲子園に出るような選手は野球の達成度で上位1%に入るでしょうが
*それでもほとんどはプロになれずに、別の仕事につく
☆ベルカーブの仕事は、達成度85%くらいでも
☆ベルカーブの仕事は、達成度85%くらいでも
*それなりの成功を手に入れることができる
*世界的な名医にならなくても、医師という専門職になれば
*平均よりもゆたかな生活が送れるでしょう
☆ロングテールの仕事は、成果を出せるか、出せないかがすべて
☆ロングテールの仕事は、成果を出せるか、出せないかがすべて
*どんなに努力しても、成果が出ないと誰も評価してくれません
☆ベルカーブの仕事は時給の高い専門職で
☆ベルカーブの仕事は時給の高い専門職で
*働いた時間によって安定した収入が得られる
☆親としては子どもの夢を応援する一方で
☆親としては子どもの夢を応援する一方で
*失敗者がたくさんいるからこそ
*ロングテールの成功者が輝くのだという現実も
*どこかで教えなくてはなりません
☆ベルカーブの仕事で成功できるのは、だいたい20%くらいでしよう
☆ベルカーブの仕事で成功できるのは、だいたい20%くらいでしよう
*学校の成績がよければ必ずうまくいくわけではありませんが
*その多くが大学・大学院卒の学歴をもっていることも事実です
☆ロングテールの仕事の成功確率が1%とすれば
☆ロングテールの仕事の成功確率が1%とすれば
*ベルカープの仕事の成功確率はその20倍です
☆ユーチューバーの成功確率は0.1%以下でしよう
☆ユーチューバーの成功確率は0.1%以下でしよう
*ベルカーブの仕事の成功確率はその200倍以上になります
⛳「夢を追う」ということ
☆もうひとつ重要なのは、「はたらける期間」
*スポーツ選手はロングテールの仕事ですが
⛳「夢を追う」ということ
☆もうひとつ重要なのは、「はたらける期間」
*スポーツ選手はロングテールの仕事ですが
*肉体的な制約から、せいぜい20年です
☆医師や弁護士などのベルカーブの仕事
*健康ならいつまでも続けることができます
*はたらける期間が長ければ、生涯の収入は多くなる
☆「お金持ちになる」とは
*はたらける期間が長ければ、生涯の収入は多くなる
☆「お金持ちになる」とは
*生涯の収入が最大になるように人生を設計することです
☆ユーチューバになりたい(ロングテールの仕事に憧れる)
☆ユーチューバになりたい(ロングテールの仕事に憧れる)
*子どもも勉強したほうがいい理由です
☆しかし、子どもがこころの底から「やりたい」と思っていることを
☆しかし、子どもがこころの底から「やりたい」と思っていることを
*親が否定すると、あまりよい結果にはならない
*それにいまは、「なにをしたらいいかわからない」という
*若者がたくさんいます
*「やりたいこと」が決まっているほうがいいかもしれません
☆数少ない成功者は
*「やりたいこと」が決まっているほうがいいかもしれません
☆数少ない成功者は
*膨大な数の失敗者のなかからしか生まれない
*それに、成功する確率だってゼロではないのです
*それに、成功する確率だってゼロではないのです
(敬称略)
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で
⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で
⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください
⛳出典、『どうしたらお金持ちになれるの?』
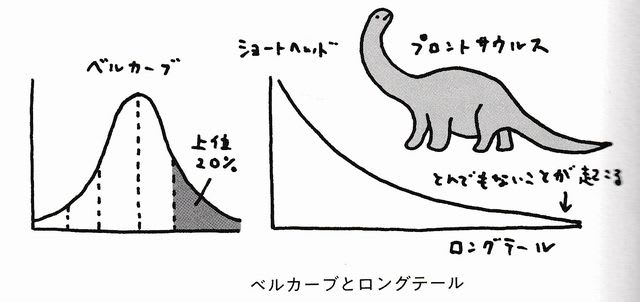


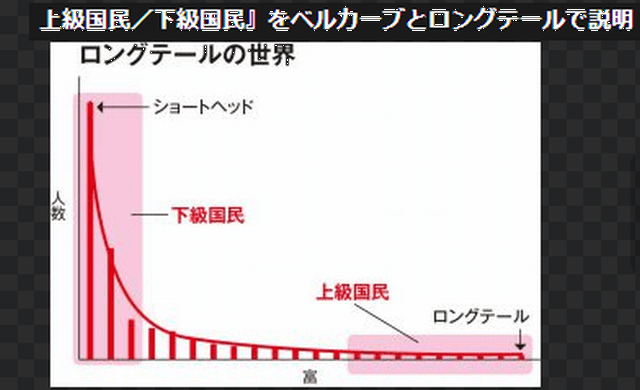
『ロングテールの仕事』『ベルカーブの仕事』
(『どうしたらお金持ちになれるの?』記事他より画像引用)