つながれた想い、うれしくて

不夜、想話 act.1―another,side story「陽はまた昇る」
射撃の特練が終わって周太は新宿駅まで戻ってきた。
今日は日勤だからこのまま東口交番へと出勤する。
改札を出ようとしたとき目に入った時計は11時過ぎ、正午に出勤予定だから時間は余裕がある。
このまま昼休憩に入るとちょうど良いのかもしれない、周太は東口交番へと連絡を入れてみた。
「ああ、そうしてくれると助かるよ。うまいもん食ってこいな」
応対してくれた柏木はそんなふうに言って笑ってくれた。
柏木とは同じシフトで、いつも一緒に勤務している。
安本の事もよく知っていて機動隊時代に一緒だったらしい。
そして柏木は茶飲み話が上手だ。
ときおり新宿では、ビルの谷間ぼんやりと、自暴自棄に座りこむ人間がいる。
都会の底で虚ろな目をして、その後、ビルや駅のホームから転落してしまう。
そういう人間をみつけては、柏木は交番で茶を出している。
茶を啜っただけで、人は少し和やかになって、すこし話してくれる。
そんなふうに心を少し解いて、柏木は話を聴いてやる。そうして帰っていく人は、転落する事は無い。
「こういう都会はね、人が多すぎて逆に孤独っていうかな。人波に自分が埋められてしまう、そんな気がするんだろうな」
柏木はそう言って、周太に教えてくれる。
周太自身が新宿での勤務中、寂しいと時折に感じてしまう。
けれど勤務の合間に柏木と話す時は、すこしだけ寛げた。
そんなふうに頼もしく和やかな柏木の雰囲気と、昨日会った御岳駐在所長の岩崎は、どこか似ていた。
「俺達の仕事はな、人間と、その生きる場所を学ぶ事なんだろうな」
岩崎は、昨日そう教えてくれた。
宮田の勤務するう御岳駐在所は、新宿駅東口交番とは、業務が全く違っていた。
山岳地域の警察と、副都心の警察。同じ警察官でも全く違う世界だった、
御岳駐在所は山岳地域であり、山での遭難救助と自殺遺体収容が主な業務だった。
山で起きる生死を見つめる現場。人は温かく、自然は美しく厳しかった。
青梅署で出会った警察医の吉村は、それら全てを見つめる人なのだと感じた。
山に廻る生死と向き合い、そうする事で山に亡くした息子を見つめている。
警察官として生きる事で、殉職した父を見つめる自分と、どこか吉村は似ていた。
そんな吉村は、周太の茶を啜って微笑んだ。
―湯原くんは、端正に生きてきた人ですね。そういう方は私は好きです
周太の事を真直ぐに見つめてくれた。
そして、あの隣との繋がりも、全てを肯定して微笑んでくれた。
―宮田くんと湯原くんが寄り添う姿は、とてもきれいでした
だから私には解ります、君たちの心の繋がりは、とても美しいです
そんなふうに、周太の心に寄り添って、13年前の事も穏やかに話させてくれた。
数時間を一緒に過ごしただけで、あんなふうに心を開いた事は、周太には初めてだった。
とても不思議で温かい、自分の悲しみも他人の想いも、全て真直ぐに見つめる人。
また吉村に会ってみたい。雲取山に行く時も、少し会いに行けたらいい。
そして、そう思う自分も周太には不思議だった。
自分は簡単には、心を開けない。
どうしてなのか自分でよく解らない。けれど、誰かといて心から寛げることは、ずっと無かった。
元からそういう所はあった。そして父が亡くなってからは、ただ、孤独になっていた。
けれど気がついたら、きれいに笑って宮田が、そっと隣に座っていた。
宮田の気配は周太を邪魔しない、ただそっと温もりを伝えてくれる。
静かに穏やかに佇んで、けれど強い腕で掴んで離さない。たまに強引だけれど、それもほんとうは、いつも嬉しい。
だからいつも思ってしまう、あの隣だけが自分の居場所。
宮田だけ。あの、きれいな笑顔の隣だけ。あの場所にだけは、心から座っていたい。
宮田は吉村医師を、とても信頼していた。
そして吉村医師も宮田を、心から信頼して息子のように想っている。
そういう吉村だからこそ、周太も好きになれるのかもしれない。
「…あ、」
周太は目を上げて驚いた。
気がついたら、あの店の前に立っている。
昼休憩はどこに行くか、まだ決めていない。
けれどたぶん、あの隣の事を考えていたから、ここに来てしまった。
「…どうしよう、」
暖簾を見あげて、周太は小さく呟いた。
昨日の夜、奥多摩から送ってくれる宮田と、この暖簾を潜った。
土曜夜の20時頃、ちょうど帰る客と入れ違いになった。
あたたかな湯気の、寛ぎが温かな店には、あの主人だけが立っていた。
「また、来てくれたんですね」
主人は嬉しそうに笑って、小さめの中華丼をサービスしてくれた。
打ち明け話をして、主人も少し、心配だったのだろう。
嬉しそうな温かい主人の笑顔が、周太も嬉しかった。
中華丼は美味しかった。うまいと宮田も主人に微笑んだ。
「本当うまいです、もっと食いたくなります」
そんなふうに、きれいに笑って、お代りを貰っていた。
宮田は正直だ。思った通りにだけ言い、行動する。
そんな率直さがいつも、相手の心の引き出しを開いてしまう。
だから昨夜もきっと宮田の笑顔に主人はつい、サービス過多になったのだろう。
「お客さん、ほんとうに良い笑顔するね。こっちが嬉しくなっちまう」
そんなふうに笑った主人の顔は、本当に嬉しそうだった。
でも、サービスだったのに、ちょっと図々しかったかもしれない。
すこし周太は心配になった。お礼とお詫びを伝えた方が、良いかもしれない。
このままこの店で、食事していこうか。
けれど、と周太は気がついた。
自分は今、活動服姿で立っている。
気がついて、ひやりと心を冷たい何かが撫でた。
一昨日の自分は、同じ姿でこの店に向かった。
今と同じように特練の帰り道、活動服姿で拳銃を携行して、ここへ来ようとした。
殺害された父の報復。父の遺体と同じ姿で、父が殺されたのと同じように、犯人を殺す。
そんな冷たい目的に、心ごと縛られ引き摺られ、孤独の中を歩いていた。
「…ごめん、なさい」
ぽつんと呟きが唇から零れた。
今更ながらに、自分の犯そうとした事の冷たさ。
その重み冷たさ全てが、自分自身に跳ね返って刺さって痛い。
周太は店から離れ、すこし離れた街路樹の陰に佇んだ。
その周太の視界に、自販機が映りこんだ。
「…あ、」
HOTのスペースに、ココアの表示が見える。
周太はそっと自販機へと歩み寄った。
昨日の夕方、吉村医師は、一杯のココアを周太に差し出してくれた。
父が好きだったココア、自分も好きだった。そして父が殉職してからは、飲まなかった。
父の生前の幸福だった時間、その全てが、喪失という名の悲しい傷になっている。
だからココアも飲めなくなった。一緒に飲んで過ごした幸せな時間が、冷たく痛い傷になって蹲っていた。
―ゆっくり、飲んでごらん。きっと温まる
そう言って差し出されて、13年ぶりに啜った。
涙が零れて、甘くて、おいしくて、温かかった。
―そうか、良かったな。温かいのは、うれしいな
そんなふうに言って、吉村は肯定してくれた。
そうして13年ぶりに周太は、父親との幸せな記憶と素直に向き合えた。
その隣では、きれいな笑顔が佇んで、穏やかに優しく見つめてくれていた。
「俺にも、ひとくち飲ませて」
きれいに笑って宮田は、周太の手から紙コップを受け取ってくれた。
そうしてまた微笑んで、周太が唇をつけた所へと、きれいな口許を寄せて、ひとくち啜った。
「うまいな。温かくて、すごく甘い」
そんなふうに微笑まれて、嬉しかった。けれどちょっと困った。
だってあんなのってほら、きいたことのあるあれじゃないだろうか。
真っ赤な首筋は、たぶん2人に見られていただろう。
でも本当は解っている。
父の記憶と周太の心の傷が、溶けこんでいた、あのココア。
それを宮田は解っていて、きれいに笑って、一緒に啜ってくれた。
その事が嬉しくて幸せで。13年間の冷たかった細かい傷は、あの時から溶け始めた。
あの隣が、すきだ
周太は小銭を出して、自販機に入れた。
がたんと出てきた焦茶色の缶を、そっと掌に持ってみる。
熱い温もりが、少しだけ冷えていた掌に沁みるようだった。
プルリングをひく、すこしほろ苦い甘い香りが起ちあがる。そっと唇をつけて啜ると、温かかった。
ほっと息をついて空を見あげる。
ビルの谷間にも青空が眩しい。街路樹の銀杏は秋にうつり、あわい黄色がきれいだった。
また少し冷え込むと天気予報は言っていた。
きっと木曜日の奥多摩は、深まる秋が美しいだろう。
この同じ空の下、奥多摩の山あいで今、宮田も吉村も笑っている。
秀介も岩崎も元気でいるだろう。国村はまた誰かを転がして、笑っているかもしれない。
あの場所へと自分も、木曜日には立っている。
「ん、」
幸せに微笑んで、周太はココアを飲みほした。
今すぐに、あの隣の気配を感じたい、寛ぎたい。
それを叶えてくれる、温かい場所は今、目の前に佇んで待っている。
空けたココアの缶を、自販機のダストボックスへ入れた。
その手を胸ポケットへ入れて、オレンジ色のパッケージを出す。
昨日の朝、あの隣が河辺駅のカフェでくれた飴。
気恥ずかしさと幸せが、首筋を昇ってしまう。それでも周太は一粒とりだした。
「…ん。おいし、」
含んだ甘さと、オレンジの香りが嬉しい。この飴をくれた、きれいな笑顔が温かい。
ほら今もう、自分はこんなふうに幸せで温かい。
いつもこんなふうに、あの隣は必ず自分のことを、温かさから離さない。
だからきっと大丈夫、もう冷たい孤独は、自分を掴めない。
周太は制帽を脱いだ。
それから振返って、いつもの店の暖簾を活動服姿のままで潜った。
「へい、いらっしゃいませ、」
あたたかな湯気と、笑顔の主人の声が迎えてくれる。日曜11時過ぎ、店には客はまだいなかった。
微笑んで、周太は主人へと挨拶をした。
「こんにちは、」
声を聴いて、主人の瞳が大きくなった。
「お客さんも、警視庁の人だったんだ」
「はい。昨日はすみません、ご馳走様でした」
カウンターに座る周太に、意外ですと主人は笑った。
「こんなに驚いて、すみません。てっきりね、学生さんか学者の卵さんだと思っていました」
「はい。前髪おろしていると、言われます」
学生時代まで、周太の前髪は長めだった。
そうしていると、穏やかで繊細な雰囲気が、学者風だとよく言われた。
けれど警察学校に入る時、ばっさり髪を切った。
入寮前に偶然会った宮田に「かわいい」と言われた事がきっかけだった。
片意地を張っていた、今ならそう素直に認められる。
だから今はもう、前髪は長めに戻した。
仕事の時は今みたいに、あげてあるけれど。
「そうですか。でも今も、お話しすると学者さんみたいです」
「どんなふうに?」
そうですねと水を渡してくれながら、主人は微笑んだ。
「真面目で一途で、きれいな純粋な目をされています。そういうお客さんは、学者さんが多いんですよ」
母は周太のことを学者になると信じていた。
東大でもどこでも進学できた、けれど母を独りにしたくなくて近所の公立大学に進んだ。
その時も母は「大学院で行ってもいいね」と笑ってくれた。
進学後も本当は、アメリカの大学への留学の話もあった。
そこは世界最高峰の工学研究学府だった、本当は少しだけ心がゆれた。
それでも母に内緒で断ってしまった、そのことは今でも母に秘密にする唯一の事でいる。
この主人も「学者」と言ってくれる。
そして父も、自分にそう望んでいたと、母の言葉の欠片から解る。
「周太」と言う名前の意味は「周=あまねくめぐらし 太=度量が大きい」
全てあまねく学び大きな器の人間になるように。学者になるには相応しい、そういう名前だった。
この主人の心には父の心の欠片が生きているのかもしれない。
そう思うと温かくて周太は嬉しかった。
カウンター越しに主人を見上げて、周太は微笑んだ。
「ありがとうございます、」
主人も微笑んでくれた。
「そんなこちらこそ。いつも来てくれて、ありがとうございます」
それから注文をして、水を飲みながら、周太は携帯を開いた。
メモリーを呼びだすと、きれいな川の写真が現われる。
昨日、白妙橋の岩場から撮った、日原川の画像だった。
碧い水と砕ける透明な飛沫。こんな水が東京にあることが嬉しい。
今飲んでいる水も、もとはあの場所を流れていた。そう思うとなんだか温かい。
昨日は周太はザイル登攀を1度しただけで、救助者役を手伝った。
背負われた宮田の背中で、本当は少し、周太は泣いた。
警察学校時代の山岳訓練を、思い出したから。
崖を滑落した周太を救助した宮田は、あの時が初めての山岳経験だった。
不慣れなザイルが肩に食い込んで、きっと宮田は痛かった。
もう降ろしてと言いたかった、けれど背中の温もりが嬉しくて、言葉は出なかった。
怪我の当日は風呂は止められた。けれど翌日は、宮田が介助してくれて風呂を済ませた。
その時も周太を支えてくれた肩には、やっぱりザイルの痕と擦過傷が出来ていた。
ごめんと呟いた周太に、きれいに笑って宮田は言ってくれた。
「大丈夫、遠慮するな。むしろ俺はさ、頼ってもらえるのが嬉しいから」
それに怪我の世話も約束しただろ?そう言って微笑んで、その後も毎日世話してくれた。
言ってもらって嬉しかった。世話をしてくれて、ほんとうは幸せで嬉しかった。
あの時は自覚していないけれど、あの時から本当は、あの隣を頼り始めていたかもしれない。
そしてたぶん、好きだった。
「山の警察官っているのかな」
山岳訓練で怪我した周太を、背負ってくれる下山の道で。宮田は、そんなふうに訊いてきた。
訊かれて、幼い日に登った奥多摩の山を想った。
奥多摩の山中で会った「警視庁」と書かれたウィンドブレーカー。
警視庁の山の警察官は、山岳救助隊だと思いだして答えた。
「山岳地域の警察官なら警視庁は奥多摩方面」
そうかと言って、宮田はあのとき微笑んだ。
そして今、宮田はあのウィンドブレーカーを着、山ヤの警察官として奥多摩の山岳救助隊員になっている。
そうして一昨日この場所で、周太のことも、主人のことも、13年前の後悔から救ってくれた。
今、座るこの席の、隣に座って微笑んで、きれいに笑って救ってくれた。
自分はどうしたら、あの想いに答えられるのだろう?
だって本当は気付いている、あの時に宮田が来てくれた理由。
自分がもしも犯人を撃つと願ったら、宮田は代りに撃つ覚悟でいた。
「周太、」
名前を呼んで抱きとめてくれた瞬間から、新宿署の保管へ戻すその瞬間まで。
きれいな切長い目は、本当はずっと周太のホルスターを見つめていた。
あの時は何故だろうと思っていた。
けれど昨日、奥多摩で、吉村医師と国村に会って、気がついてしまった。
―あの日の彼の目は覚悟していた…ただ見送って後悔するのは、あの一度だけで終わらせたかった
吉村医師はそう言った。
吉村医師が後悔した「あの一度」それは愛する息子を死なせた時のこと。
吉村医師はきっと、宮田の覚悟が何なのか、気づいていた。
―宮田くんのさ、大切な人の緊急時だった。問題無いだろ?…山ヤはね、仲間同士で助け合うんだ
国村はそう言った。
宮田はいつも笑顔でいる、だから「緊急時だった」と言われるのは、余程の表情をしていたこと。
そして国村は言った「山ヤは仲間同士で助け合う」
父に聴いたことがある。登山中に遭難事故が起きたら、山ヤは自分の計画を中断して、遭難した山ヤを助ける。
国村は、宮田自身の遭難だと言っている。それ位にきっと、宮田の表情は緊迫していたということ。
あの隣は、自分の身代わりになっても、守ろうとしてくれた。
そのことに、気がついた今朝から、ほんとうはずっと、涙が止まらない。
ほんとうはずっと、どこかで解っていた。
あの隣はきっと、身代わりになってでも、自分を守ろうとしてくれること。
だから自分はあのとき、独りでこの店へ向かってしまった。
あの隣の、きれいな笑顔を、自分だって守りたい。だからもう、巻き込めなかった。
それなのに、追いついて掴まえて抱きしめてくれた。身代わりになろうと、微笑んで佇んでくれた。
そして怒ってくれた。離れる事が、いちばん残酷な事だと悲しんでくれた。
だからもう解ってしまった。きっと、逃げても離れても無駄なこと。
きっともう自分達は、どんな時でも離れることは出来ない。
そのことに、今朝、ベッドの上で気がついた。
早めに目が覚めた寮の自室、昨日一緒に選んでくれたiPodに、いれてくれたあの曲を聴いていた。
そして昨夜送ってくれる電車の中、言ってくれた言葉を想いだした。
「出会った時から、もうずっと俺はね、I'll love you more with every breath Truly, madly, deeply, do そんなふうに周太もなってよ」
―息をするたびごとにずっと、君への愛は深まっていく ほんとうに心から、激しく深く愛している
出会って7ヶ月半、こうなってから1ヶ月半。
それなのにもう、こんなに想いが深い。
それなのにこれから、息をするたびごとに深まったら、どうなってしまうのだろう。
宮田はいつも、思ったことだけを言葉にして、行動する。
だからきっと本当に、宮田はこれからずっと、そんなふうに思い続けてしまう。
だから思う、あの隣から、逃げても離れても無駄なこと。きっともう自分達は、どんな時でも離れることは出来ない。
「はい、おまちどうさま」
温かな声と一緒に、丼が差し出されて周太は我に返った。
ありがとうございますと受取って、箸を割る。
ひとくち啜ると、温かかった。
この温かさも、宮田が連れてきて教えてくれた。
それなのに宮田は、自分はそんな温もりを捨ててでも、周太を守ろうとしてくれた。
こうやっていつも、全てを掛けて、尽くして支えて、想いを届け続けてくれる。
どうして自分の為に?そう思ってしまう。
どうしてなのと、嬉しくて、温かくて、どうしていいのか解らない。
どうしたら自分は、あの想いに答えて、自分の想いを届けられるのだろう。
「さ、どうぞ、」
温かな声に、周太は顔をあげた。
一枚のティッシュペーパーを、大きな掌が差し出してくれていた。
いま気がついた、自分の頬が濡れている。
ほんとうはずっと、朝から泣きたかった。
けれど任務があったから、警察官の一日が始まったから、泣かずに今日を過ごしていた。
でも今、温かくて涙が止まらない。
主人が温かく微笑んで周太を見てくれる。
温かな声がそっと笑って言ってくれた。
「温かいうちにね、召し上がって下さい。肚が温まるとね、元気が出て笑顔になれますよ」
そんなふうに微笑んで、温かな丼に、煮玉子と野菜炒めをよそってくれた。
キャベツがひとつ、カウンターにこぼれる。思わず周太は笑った。
「すごい大盛りですね、宮田なら食べきれるかもしれないけど」
「いつも一緒に来るお客さんだね、よく食べて、よく笑う。彼はいつも本当に、良い笑顔ですね」
「はい、」
笑って頷いた周太に、おやと微笑んで主人は言ってくれた。
「ああ、お客さんもね、良い笑顔です」
そんなふうに言ってもらえて嬉しい。
父の心の欠片をもった、目の前の人。
この人の温もりは、きっと、父の温もりの欠片が種になっている。
きれいに笑って、周太は言った。
「おやじさんも…温かな、良い笑顔ですね」
一日の勤務が終わって、寮に戻って夕飯を食べた。
週休だった深堀が、一緒に席についてくれる。
「今日も詩吟の稽古を祖母がつけてくれたんだ」
気さくに笑いながら、お弟子さんが上達した話をしてくれた。
深堀は、祖母の師範代を務めている。日曜日の今日は稽古が多いらしい。
周太の顔を見て深堀は、微笑んで訊いてくれた。
「一昨日と、昨日もだよね。宮田と楽しかった?」
一昨日の夕方に深堀とは、寮を出る前に廊下で会っている。
あのときは恥ずかしくて困った、そう思いながら周太は頷いた。
「ん、楽しかったよ。昨日は岩場で、ルートクライミングをしたんだ」
「へえ、すごいな。俺、警察学校の訓練だけだ」
「最近はね、ボルダリングが流行っているらしい」
そんな他愛ない話が楽しい。
でもやっぱり、あの隣といる時がいちばん楽しい。
そんなことを思っていたら、ふと深堀が訊いた。
「一昨日のオールはさ、どこで飲んだの?」
「…っ」
危うく茶碗を落としそうになった。
でもちょうど深堀は、秋刀魚の骨を器用に外す最中で、気づかなかった。
動揺を気づかれなくて良かった、けれど、この質問どうしよう。
ほんとうのことなんてとてもいえないはずかしすぎるから。
けれど困っていたら、深堀が言ってくれた。
「新宿で飲んだの?それとも青梅まで行ってから?」
「あ、新宿…」
ほんとうに場所の事だけだった。
深堀はもう、秋刀魚の季節だと鰯雲とかさと、秋の季語の話に入っている。
なんだか秋刀魚に助けられた。思いながら周太も、秋刀魚に箸をつけた。
食事が済んで風呂も済ませて、ほっと周太はデスクの前に座った。
鑑識の勉強ファイルを出して、ペンを持つ。
ペンを持った右腕の、シャツの袖を捲ると、すこし赤い痣がのぞいた。
昨夜あの店を出てから、南口のテラスのベンチに座った。
あのカフェでテイクアウトして、前にも座ったベンチで並んだ。
オレンジラテ?は温かくて、おいしかった。
「周太はさ、オレンジの味が好きだな」
「ん、すきだな」
11月の夜風は冷たかったけれど、きれいな笑顔の隣は温かかった。
寒いからと、いつもより肩が近くて。気恥ずかしくて、嬉しかった。
そしてまた、この痣に唇がふれてくれた。
「今日は周太、腕を引込めようとしなかったね」
そう言って宮田は微笑んで、長い指でそっと痣にふれた。
「きれいだね、周太」
あわいデスクライトに照らされた、右腕の赤い色。
卒業式のあの夜からずっと、同じところに咲き続けている。
きっともう、消えることは無い。
だって、もうそれくらい、ほらこんなにもう、想いが深いから。
鑑識のファイルに、借りてきた本からメモをとる。
木曜日に返せば良いからと、宮田が貸してくれた。
書籍自体の厚みは薄めなのに、内容は思った以上に厚く専門的で、周太は驚かされた。
宮田と吉村医師の会話にも驚いた。
宮田は救急法の成績が良かった、検定も好成績で合格している。
青梅署に配属されてからは、警察医の先生に教わっていると聴いていた。
けれどあんなに、専門的な話をしているとは思わなかった。
「救命救急士の資格はさ、学校通わないと難しいんだけどね」
それでも俺の現場には必要な知識なんだ。
そんなことを言って、あの隣は微笑んでいた。
救命救急士の資格は普通、消防庁勤務者が取得することが多い。
けれどあれだけ努力できるなら、警察官でも宮田は、いつか取得するかもしれない。
デスクに置いた父の時計が、21時前を指している。
その隣に置いた携帯が、気になってしまう。
もう鳴るかな。そう思った視線の真中で、ふっと着信ランプが灯った。
「はい、」
「今日、楽しかったんだ?」
言わなくても解ってしまう。
そんなふうにいつも、やさしい繊細な、この隣。
「ん、楽しかった。俺ね、あの店へひとりで行ったんだよ」
「そうか、おやじさん元気そうだった?」
こんなふうに訊いて、話を聴いてくれる。
きれいな低い声、やさしい穏やかな気配。
こうして電話で繋がれて、今も話で離してくれない。
こんなふうに、ほんとうに、この隣はいつも、必ず隣にきてくれる。
'Cause it's standing right before you All that you need will surely come
―君に必要なもの全てになった僕は、必ず君の元へたどりつく
そうだと言って、宮田が訊いてきた。
「白妙橋でさ、国村さんに背負われて、ザイル下降しただろ」
「ん、したね」
宮田以外の背中は嫌だな。ほんとうは、そんなふうに思ってしまった。
けれど、あんなふうに言われてしまって、宮田に背負われるのが恥ずかしくなった。
でもやっぱり、宮田の背中にすれば良かったと、すぐに後悔させられた。
だってあんなこと言われたなんて、この隣が知ったらなんて言うのだろう。
そんなふうに考えていたら、きれいな低い声が訊いた。
「あの時さ、周太、国村さんとどんな話したんだ?」
「…っあの、っ」
どうしよう、やっぱり訊かれた。
でも約束している「隠し事はしない」って。
二度も、もう破ってしまった約束。だから今もう、隠すわけにはいかない。
そっと息を吸って、周太は呟いた。
「…みやたの背中ほどは居心地良くないだろうけど、夜じゃないから我慢して」
電話の向こう、きれいな笑い声が聞こえた。
きっと笑うだろうなと、そして首筋が熱くなるだろうと、どっちももう、予想通り。
「他もさ、なんか言われただろ」
「…ん、…みやたとあうまでずっと初めては何もしていなかったでしょ…って…」
この2つだけ。
たった2つの文章なのに、もう、キャパオーバーになってしまう。
そしてこんな時はつい、自分の記憶力がちょっと憎らしい。
それになにより困るのは、どちらの指摘も本当だと言うことだ。
この2つで済んで本当に良かった。国村のザイル下降技術に、ちょっと感謝したい。
もっと時間がかかったら、きっともっと、恥ずかしかった。
言い終って、ほっとしていたら、きれいな低い声が言った。
「さっきさ、藤岡に会ったって周太、教えてくれたよな」
「ん、なんかね、最初は俺だって解らなかったって」
ふうんと呟いて、笑って訊いてくれた。
「なんで周太だって、解らなかったんだ?」
お願い今、ちょっとそれは言えない。
藤岡が周太を解らなかった理由「なんかきれいになった」
「きれいになった」そのことが、国村に言われた「初めて」のことに絡まっている。
そう思ってしまって恥ずかしくて、とても今は言えそうにない。
それでも、なんとか周太は口を開いた。
「…なんだかもう、気恥ずかしくて…今夜は無理」
なぜだか電話の向こうは、大喜びして笑っている。
もう恥ずかしい、首筋も顔もきっと真っ赤になっている。
けれどこんなふうに、電話ででも想いを繋いで、時を共有できる。
そんな今この一瞬が、嬉しくて、幸せで、温かくて。
こうしていつまでも、やさしく繋いで、ずっと掴まえていてほしい。
だから考えしまう、どうしたら自分は、この想いに応えていけるのだろう?
こんなふうに誰かを、想うことすら初めてで。
こんなふうに誰かの為にと、応えたいことも初めてで。
想いの真ん中の、あの隣のために。きれいな笑顔のために、自分は何が出来るだろう?
(to be continued)
【歌詞引用:savage garden「truly madly deeply」】
blogramランキング参加中!
ネット小説ランキング
http://www.webstation.jp/syousetu/rank.cgi?mode=r_link&id=5955

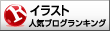
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村

不夜、想話 act.1―another,side story「陽はまた昇る」
射撃の特練が終わって周太は新宿駅まで戻ってきた。
今日は日勤だからこのまま東口交番へと出勤する。
改札を出ようとしたとき目に入った時計は11時過ぎ、正午に出勤予定だから時間は余裕がある。
このまま昼休憩に入るとちょうど良いのかもしれない、周太は東口交番へと連絡を入れてみた。
「ああ、そうしてくれると助かるよ。うまいもん食ってこいな」
応対してくれた柏木はそんなふうに言って笑ってくれた。
柏木とは同じシフトで、いつも一緒に勤務している。
安本の事もよく知っていて機動隊時代に一緒だったらしい。
そして柏木は茶飲み話が上手だ。
ときおり新宿では、ビルの谷間ぼんやりと、自暴自棄に座りこむ人間がいる。
都会の底で虚ろな目をして、その後、ビルや駅のホームから転落してしまう。
そういう人間をみつけては、柏木は交番で茶を出している。
茶を啜っただけで、人は少し和やかになって、すこし話してくれる。
そんなふうに心を少し解いて、柏木は話を聴いてやる。そうして帰っていく人は、転落する事は無い。
「こういう都会はね、人が多すぎて逆に孤独っていうかな。人波に自分が埋められてしまう、そんな気がするんだろうな」
柏木はそう言って、周太に教えてくれる。
周太自身が新宿での勤務中、寂しいと時折に感じてしまう。
けれど勤務の合間に柏木と話す時は、すこしだけ寛げた。
そんなふうに頼もしく和やかな柏木の雰囲気と、昨日会った御岳駐在所長の岩崎は、どこか似ていた。
「俺達の仕事はな、人間と、その生きる場所を学ぶ事なんだろうな」
岩崎は、昨日そう教えてくれた。
宮田の勤務するう御岳駐在所は、新宿駅東口交番とは、業務が全く違っていた。
山岳地域の警察と、副都心の警察。同じ警察官でも全く違う世界だった、
御岳駐在所は山岳地域であり、山での遭難救助と自殺遺体収容が主な業務だった。
山で起きる生死を見つめる現場。人は温かく、自然は美しく厳しかった。
青梅署で出会った警察医の吉村は、それら全てを見つめる人なのだと感じた。
山に廻る生死と向き合い、そうする事で山に亡くした息子を見つめている。
警察官として生きる事で、殉職した父を見つめる自分と、どこか吉村は似ていた。
そんな吉村は、周太の茶を啜って微笑んだ。
―湯原くんは、端正に生きてきた人ですね。そういう方は私は好きです
周太の事を真直ぐに見つめてくれた。
そして、あの隣との繋がりも、全てを肯定して微笑んでくれた。
―宮田くんと湯原くんが寄り添う姿は、とてもきれいでした
だから私には解ります、君たちの心の繋がりは、とても美しいです
そんなふうに、周太の心に寄り添って、13年前の事も穏やかに話させてくれた。
数時間を一緒に過ごしただけで、あんなふうに心を開いた事は、周太には初めてだった。
とても不思議で温かい、自分の悲しみも他人の想いも、全て真直ぐに見つめる人。
また吉村に会ってみたい。雲取山に行く時も、少し会いに行けたらいい。
そして、そう思う自分も周太には不思議だった。
自分は簡単には、心を開けない。
どうしてなのか自分でよく解らない。けれど、誰かといて心から寛げることは、ずっと無かった。
元からそういう所はあった。そして父が亡くなってからは、ただ、孤独になっていた。
けれど気がついたら、きれいに笑って宮田が、そっと隣に座っていた。
宮田の気配は周太を邪魔しない、ただそっと温もりを伝えてくれる。
静かに穏やかに佇んで、けれど強い腕で掴んで離さない。たまに強引だけれど、それもほんとうは、いつも嬉しい。
だからいつも思ってしまう、あの隣だけが自分の居場所。
宮田だけ。あの、きれいな笑顔の隣だけ。あの場所にだけは、心から座っていたい。
宮田は吉村医師を、とても信頼していた。
そして吉村医師も宮田を、心から信頼して息子のように想っている。
そういう吉村だからこそ、周太も好きになれるのかもしれない。
「…あ、」
周太は目を上げて驚いた。
気がついたら、あの店の前に立っている。
昼休憩はどこに行くか、まだ決めていない。
けれどたぶん、あの隣の事を考えていたから、ここに来てしまった。
「…どうしよう、」
暖簾を見あげて、周太は小さく呟いた。
昨日の夜、奥多摩から送ってくれる宮田と、この暖簾を潜った。
土曜夜の20時頃、ちょうど帰る客と入れ違いになった。
あたたかな湯気の、寛ぎが温かな店には、あの主人だけが立っていた。
「また、来てくれたんですね」
主人は嬉しそうに笑って、小さめの中華丼をサービスしてくれた。
打ち明け話をして、主人も少し、心配だったのだろう。
嬉しそうな温かい主人の笑顔が、周太も嬉しかった。
中華丼は美味しかった。うまいと宮田も主人に微笑んだ。
「本当うまいです、もっと食いたくなります」
そんなふうに、きれいに笑って、お代りを貰っていた。
宮田は正直だ。思った通りにだけ言い、行動する。
そんな率直さがいつも、相手の心の引き出しを開いてしまう。
だから昨夜もきっと宮田の笑顔に主人はつい、サービス過多になったのだろう。
「お客さん、ほんとうに良い笑顔するね。こっちが嬉しくなっちまう」
そんなふうに笑った主人の顔は、本当に嬉しそうだった。
でも、サービスだったのに、ちょっと図々しかったかもしれない。
すこし周太は心配になった。お礼とお詫びを伝えた方が、良いかもしれない。
このままこの店で、食事していこうか。
けれど、と周太は気がついた。
自分は今、活動服姿で立っている。
気がついて、ひやりと心を冷たい何かが撫でた。
一昨日の自分は、同じ姿でこの店に向かった。
今と同じように特練の帰り道、活動服姿で拳銃を携行して、ここへ来ようとした。
殺害された父の報復。父の遺体と同じ姿で、父が殺されたのと同じように、犯人を殺す。
そんな冷たい目的に、心ごと縛られ引き摺られ、孤独の中を歩いていた。
「…ごめん、なさい」
ぽつんと呟きが唇から零れた。
今更ながらに、自分の犯そうとした事の冷たさ。
その重み冷たさ全てが、自分自身に跳ね返って刺さって痛い。
周太は店から離れ、すこし離れた街路樹の陰に佇んだ。
その周太の視界に、自販機が映りこんだ。
「…あ、」
HOTのスペースに、ココアの表示が見える。
周太はそっと自販機へと歩み寄った。
昨日の夕方、吉村医師は、一杯のココアを周太に差し出してくれた。
父が好きだったココア、自分も好きだった。そして父が殉職してからは、飲まなかった。
父の生前の幸福だった時間、その全てが、喪失という名の悲しい傷になっている。
だからココアも飲めなくなった。一緒に飲んで過ごした幸せな時間が、冷たく痛い傷になって蹲っていた。
―ゆっくり、飲んでごらん。きっと温まる
そう言って差し出されて、13年ぶりに啜った。
涙が零れて、甘くて、おいしくて、温かかった。
―そうか、良かったな。温かいのは、うれしいな
そんなふうに言って、吉村は肯定してくれた。
そうして13年ぶりに周太は、父親との幸せな記憶と素直に向き合えた。
その隣では、きれいな笑顔が佇んで、穏やかに優しく見つめてくれていた。
「俺にも、ひとくち飲ませて」
きれいに笑って宮田は、周太の手から紙コップを受け取ってくれた。
そうしてまた微笑んで、周太が唇をつけた所へと、きれいな口許を寄せて、ひとくち啜った。
「うまいな。温かくて、すごく甘い」
そんなふうに微笑まれて、嬉しかった。けれどちょっと困った。
だってあんなのってほら、きいたことのあるあれじゃないだろうか。
真っ赤な首筋は、たぶん2人に見られていただろう。
でも本当は解っている。
父の記憶と周太の心の傷が、溶けこんでいた、あのココア。
それを宮田は解っていて、きれいに笑って、一緒に啜ってくれた。
その事が嬉しくて幸せで。13年間の冷たかった細かい傷は、あの時から溶け始めた。
あの隣が、すきだ
周太は小銭を出して、自販機に入れた。
がたんと出てきた焦茶色の缶を、そっと掌に持ってみる。
熱い温もりが、少しだけ冷えていた掌に沁みるようだった。
プルリングをひく、すこしほろ苦い甘い香りが起ちあがる。そっと唇をつけて啜ると、温かかった。
ほっと息をついて空を見あげる。
ビルの谷間にも青空が眩しい。街路樹の銀杏は秋にうつり、あわい黄色がきれいだった。
また少し冷え込むと天気予報は言っていた。
きっと木曜日の奥多摩は、深まる秋が美しいだろう。
この同じ空の下、奥多摩の山あいで今、宮田も吉村も笑っている。
秀介も岩崎も元気でいるだろう。国村はまた誰かを転がして、笑っているかもしれない。
あの場所へと自分も、木曜日には立っている。
「ん、」
幸せに微笑んで、周太はココアを飲みほした。
今すぐに、あの隣の気配を感じたい、寛ぎたい。
それを叶えてくれる、温かい場所は今、目の前に佇んで待っている。
空けたココアの缶を、自販機のダストボックスへ入れた。
その手を胸ポケットへ入れて、オレンジ色のパッケージを出す。
昨日の朝、あの隣が河辺駅のカフェでくれた飴。
気恥ずかしさと幸せが、首筋を昇ってしまう。それでも周太は一粒とりだした。
「…ん。おいし、」
含んだ甘さと、オレンジの香りが嬉しい。この飴をくれた、きれいな笑顔が温かい。
ほら今もう、自分はこんなふうに幸せで温かい。
いつもこんなふうに、あの隣は必ず自分のことを、温かさから離さない。
だからきっと大丈夫、もう冷たい孤独は、自分を掴めない。
周太は制帽を脱いだ。
それから振返って、いつもの店の暖簾を活動服姿のままで潜った。
「へい、いらっしゃいませ、」
あたたかな湯気と、笑顔の主人の声が迎えてくれる。日曜11時過ぎ、店には客はまだいなかった。
微笑んで、周太は主人へと挨拶をした。
「こんにちは、」
声を聴いて、主人の瞳が大きくなった。
「お客さんも、警視庁の人だったんだ」
「はい。昨日はすみません、ご馳走様でした」
カウンターに座る周太に、意外ですと主人は笑った。
「こんなに驚いて、すみません。てっきりね、学生さんか学者の卵さんだと思っていました」
「はい。前髪おろしていると、言われます」
学生時代まで、周太の前髪は長めだった。
そうしていると、穏やかで繊細な雰囲気が、学者風だとよく言われた。
けれど警察学校に入る時、ばっさり髪を切った。
入寮前に偶然会った宮田に「かわいい」と言われた事がきっかけだった。
片意地を張っていた、今ならそう素直に認められる。
だから今はもう、前髪は長めに戻した。
仕事の時は今みたいに、あげてあるけれど。
「そうですか。でも今も、お話しすると学者さんみたいです」
「どんなふうに?」
そうですねと水を渡してくれながら、主人は微笑んだ。
「真面目で一途で、きれいな純粋な目をされています。そういうお客さんは、学者さんが多いんですよ」
母は周太のことを学者になると信じていた。
東大でもどこでも進学できた、けれど母を独りにしたくなくて近所の公立大学に進んだ。
その時も母は「大学院で行ってもいいね」と笑ってくれた。
進学後も本当は、アメリカの大学への留学の話もあった。
そこは世界最高峰の工学研究学府だった、本当は少しだけ心がゆれた。
それでも母に内緒で断ってしまった、そのことは今でも母に秘密にする唯一の事でいる。
この主人も「学者」と言ってくれる。
そして父も、自分にそう望んでいたと、母の言葉の欠片から解る。
「周太」と言う名前の意味は「周=あまねくめぐらし 太=度量が大きい」
全てあまねく学び大きな器の人間になるように。学者になるには相応しい、そういう名前だった。
この主人の心には父の心の欠片が生きているのかもしれない。
そう思うと温かくて周太は嬉しかった。
カウンター越しに主人を見上げて、周太は微笑んだ。
「ありがとうございます、」
主人も微笑んでくれた。
「そんなこちらこそ。いつも来てくれて、ありがとうございます」
それから注文をして、水を飲みながら、周太は携帯を開いた。
メモリーを呼びだすと、きれいな川の写真が現われる。
昨日、白妙橋の岩場から撮った、日原川の画像だった。
碧い水と砕ける透明な飛沫。こんな水が東京にあることが嬉しい。
今飲んでいる水も、もとはあの場所を流れていた。そう思うとなんだか温かい。
昨日は周太はザイル登攀を1度しただけで、救助者役を手伝った。
背負われた宮田の背中で、本当は少し、周太は泣いた。
警察学校時代の山岳訓練を、思い出したから。
崖を滑落した周太を救助した宮田は、あの時が初めての山岳経験だった。
不慣れなザイルが肩に食い込んで、きっと宮田は痛かった。
もう降ろしてと言いたかった、けれど背中の温もりが嬉しくて、言葉は出なかった。
怪我の当日は風呂は止められた。けれど翌日は、宮田が介助してくれて風呂を済ませた。
その時も周太を支えてくれた肩には、やっぱりザイルの痕と擦過傷が出来ていた。
ごめんと呟いた周太に、きれいに笑って宮田は言ってくれた。
「大丈夫、遠慮するな。むしろ俺はさ、頼ってもらえるのが嬉しいから」
それに怪我の世話も約束しただろ?そう言って微笑んで、その後も毎日世話してくれた。
言ってもらって嬉しかった。世話をしてくれて、ほんとうは幸せで嬉しかった。
あの時は自覚していないけれど、あの時から本当は、あの隣を頼り始めていたかもしれない。
そしてたぶん、好きだった。
「山の警察官っているのかな」
山岳訓練で怪我した周太を、背負ってくれる下山の道で。宮田は、そんなふうに訊いてきた。
訊かれて、幼い日に登った奥多摩の山を想った。
奥多摩の山中で会った「警視庁」と書かれたウィンドブレーカー。
警視庁の山の警察官は、山岳救助隊だと思いだして答えた。
「山岳地域の警察官なら警視庁は奥多摩方面」
そうかと言って、宮田はあのとき微笑んだ。
そして今、宮田はあのウィンドブレーカーを着、山ヤの警察官として奥多摩の山岳救助隊員になっている。
そうして一昨日この場所で、周太のことも、主人のことも、13年前の後悔から救ってくれた。
今、座るこの席の、隣に座って微笑んで、きれいに笑って救ってくれた。
自分はどうしたら、あの想いに答えられるのだろう?
だって本当は気付いている、あの時に宮田が来てくれた理由。
自分がもしも犯人を撃つと願ったら、宮田は代りに撃つ覚悟でいた。
「周太、」
名前を呼んで抱きとめてくれた瞬間から、新宿署の保管へ戻すその瞬間まで。
きれいな切長い目は、本当はずっと周太のホルスターを見つめていた。
あの時は何故だろうと思っていた。
けれど昨日、奥多摩で、吉村医師と国村に会って、気がついてしまった。
―あの日の彼の目は覚悟していた…ただ見送って後悔するのは、あの一度だけで終わらせたかった
吉村医師はそう言った。
吉村医師が後悔した「あの一度」それは愛する息子を死なせた時のこと。
吉村医師はきっと、宮田の覚悟が何なのか、気づいていた。
―宮田くんのさ、大切な人の緊急時だった。問題無いだろ?…山ヤはね、仲間同士で助け合うんだ
国村はそう言った。
宮田はいつも笑顔でいる、だから「緊急時だった」と言われるのは、余程の表情をしていたこと。
そして国村は言った「山ヤは仲間同士で助け合う」
父に聴いたことがある。登山中に遭難事故が起きたら、山ヤは自分の計画を中断して、遭難した山ヤを助ける。
国村は、宮田自身の遭難だと言っている。それ位にきっと、宮田の表情は緊迫していたということ。
あの隣は、自分の身代わりになっても、守ろうとしてくれた。
そのことに、気がついた今朝から、ほんとうはずっと、涙が止まらない。
ほんとうはずっと、どこかで解っていた。
あの隣はきっと、身代わりになってでも、自分を守ろうとしてくれること。
だから自分はあのとき、独りでこの店へ向かってしまった。
あの隣の、きれいな笑顔を、自分だって守りたい。だからもう、巻き込めなかった。
それなのに、追いついて掴まえて抱きしめてくれた。身代わりになろうと、微笑んで佇んでくれた。
そして怒ってくれた。離れる事が、いちばん残酷な事だと悲しんでくれた。
だからもう解ってしまった。きっと、逃げても離れても無駄なこと。
きっともう自分達は、どんな時でも離れることは出来ない。
そのことに、今朝、ベッドの上で気がついた。
早めに目が覚めた寮の自室、昨日一緒に選んでくれたiPodに、いれてくれたあの曲を聴いていた。
そして昨夜送ってくれる電車の中、言ってくれた言葉を想いだした。
「出会った時から、もうずっと俺はね、I'll love you more with every breath Truly, madly, deeply, do そんなふうに周太もなってよ」
―息をするたびごとにずっと、君への愛は深まっていく ほんとうに心から、激しく深く愛している
出会って7ヶ月半、こうなってから1ヶ月半。
それなのにもう、こんなに想いが深い。
それなのにこれから、息をするたびごとに深まったら、どうなってしまうのだろう。
宮田はいつも、思ったことだけを言葉にして、行動する。
だからきっと本当に、宮田はこれからずっと、そんなふうに思い続けてしまう。
だから思う、あの隣から、逃げても離れても無駄なこと。きっともう自分達は、どんな時でも離れることは出来ない。
「はい、おまちどうさま」
温かな声と一緒に、丼が差し出されて周太は我に返った。
ありがとうございますと受取って、箸を割る。
ひとくち啜ると、温かかった。
この温かさも、宮田が連れてきて教えてくれた。
それなのに宮田は、自分はそんな温もりを捨ててでも、周太を守ろうとしてくれた。
こうやっていつも、全てを掛けて、尽くして支えて、想いを届け続けてくれる。
どうして自分の為に?そう思ってしまう。
どうしてなのと、嬉しくて、温かくて、どうしていいのか解らない。
どうしたら自分は、あの想いに答えて、自分の想いを届けられるのだろう。
「さ、どうぞ、」
温かな声に、周太は顔をあげた。
一枚のティッシュペーパーを、大きな掌が差し出してくれていた。
いま気がついた、自分の頬が濡れている。
ほんとうはずっと、朝から泣きたかった。
けれど任務があったから、警察官の一日が始まったから、泣かずに今日を過ごしていた。
でも今、温かくて涙が止まらない。
主人が温かく微笑んで周太を見てくれる。
温かな声がそっと笑って言ってくれた。
「温かいうちにね、召し上がって下さい。肚が温まるとね、元気が出て笑顔になれますよ」
そんなふうに微笑んで、温かな丼に、煮玉子と野菜炒めをよそってくれた。
キャベツがひとつ、カウンターにこぼれる。思わず周太は笑った。
「すごい大盛りですね、宮田なら食べきれるかもしれないけど」
「いつも一緒に来るお客さんだね、よく食べて、よく笑う。彼はいつも本当に、良い笑顔ですね」
「はい、」
笑って頷いた周太に、おやと微笑んで主人は言ってくれた。
「ああ、お客さんもね、良い笑顔です」
そんなふうに言ってもらえて嬉しい。
父の心の欠片をもった、目の前の人。
この人の温もりは、きっと、父の温もりの欠片が種になっている。
きれいに笑って、周太は言った。
「おやじさんも…温かな、良い笑顔ですね」
一日の勤務が終わって、寮に戻って夕飯を食べた。
週休だった深堀が、一緒に席についてくれる。
「今日も詩吟の稽古を祖母がつけてくれたんだ」
気さくに笑いながら、お弟子さんが上達した話をしてくれた。
深堀は、祖母の師範代を務めている。日曜日の今日は稽古が多いらしい。
周太の顔を見て深堀は、微笑んで訊いてくれた。
「一昨日と、昨日もだよね。宮田と楽しかった?」
一昨日の夕方に深堀とは、寮を出る前に廊下で会っている。
あのときは恥ずかしくて困った、そう思いながら周太は頷いた。
「ん、楽しかったよ。昨日は岩場で、ルートクライミングをしたんだ」
「へえ、すごいな。俺、警察学校の訓練だけだ」
「最近はね、ボルダリングが流行っているらしい」
そんな他愛ない話が楽しい。
でもやっぱり、あの隣といる時がいちばん楽しい。
そんなことを思っていたら、ふと深堀が訊いた。
「一昨日のオールはさ、どこで飲んだの?」
「…っ」
危うく茶碗を落としそうになった。
でもちょうど深堀は、秋刀魚の骨を器用に外す最中で、気づかなかった。
動揺を気づかれなくて良かった、けれど、この質問どうしよう。
ほんとうのことなんてとてもいえないはずかしすぎるから。
けれど困っていたら、深堀が言ってくれた。
「新宿で飲んだの?それとも青梅まで行ってから?」
「あ、新宿…」
ほんとうに場所の事だけだった。
深堀はもう、秋刀魚の季節だと鰯雲とかさと、秋の季語の話に入っている。
なんだか秋刀魚に助けられた。思いながら周太も、秋刀魚に箸をつけた。
食事が済んで風呂も済ませて、ほっと周太はデスクの前に座った。
鑑識の勉強ファイルを出して、ペンを持つ。
ペンを持った右腕の、シャツの袖を捲ると、すこし赤い痣がのぞいた。
昨夜あの店を出てから、南口のテラスのベンチに座った。
あのカフェでテイクアウトして、前にも座ったベンチで並んだ。
オレンジラテ?は温かくて、おいしかった。
「周太はさ、オレンジの味が好きだな」
「ん、すきだな」
11月の夜風は冷たかったけれど、きれいな笑顔の隣は温かかった。
寒いからと、いつもより肩が近くて。気恥ずかしくて、嬉しかった。
そしてまた、この痣に唇がふれてくれた。
「今日は周太、腕を引込めようとしなかったね」
そう言って宮田は微笑んで、長い指でそっと痣にふれた。
「きれいだね、周太」
あわいデスクライトに照らされた、右腕の赤い色。
卒業式のあの夜からずっと、同じところに咲き続けている。
きっともう、消えることは無い。
だって、もうそれくらい、ほらこんなにもう、想いが深いから。
鑑識のファイルに、借りてきた本からメモをとる。
木曜日に返せば良いからと、宮田が貸してくれた。
書籍自体の厚みは薄めなのに、内容は思った以上に厚く専門的で、周太は驚かされた。
宮田と吉村医師の会話にも驚いた。
宮田は救急法の成績が良かった、検定も好成績で合格している。
青梅署に配属されてからは、警察医の先生に教わっていると聴いていた。
けれどあんなに、専門的な話をしているとは思わなかった。
「救命救急士の資格はさ、学校通わないと難しいんだけどね」
それでも俺の現場には必要な知識なんだ。
そんなことを言って、あの隣は微笑んでいた。
救命救急士の資格は普通、消防庁勤務者が取得することが多い。
けれどあれだけ努力できるなら、警察官でも宮田は、いつか取得するかもしれない。
デスクに置いた父の時計が、21時前を指している。
その隣に置いた携帯が、気になってしまう。
もう鳴るかな。そう思った視線の真中で、ふっと着信ランプが灯った。
「はい、」
「今日、楽しかったんだ?」
言わなくても解ってしまう。
そんなふうにいつも、やさしい繊細な、この隣。
「ん、楽しかった。俺ね、あの店へひとりで行ったんだよ」
「そうか、おやじさん元気そうだった?」
こんなふうに訊いて、話を聴いてくれる。
きれいな低い声、やさしい穏やかな気配。
こうして電話で繋がれて、今も話で離してくれない。
こんなふうに、ほんとうに、この隣はいつも、必ず隣にきてくれる。
'Cause it's standing right before you All that you need will surely come
―君に必要なもの全てになった僕は、必ず君の元へたどりつく
そうだと言って、宮田が訊いてきた。
「白妙橋でさ、国村さんに背負われて、ザイル下降しただろ」
「ん、したね」
宮田以外の背中は嫌だな。ほんとうは、そんなふうに思ってしまった。
けれど、あんなふうに言われてしまって、宮田に背負われるのが恥ずかしくなった。
でもやっぱり、宮田の背中にすれば良かったと、すぐに後悔させられた。
だってあんなこと言われたなんて、この隣が知ったらなんて言うのだろう。
そんなふうに考えていたら、きれいな低い声が訊いた。
「あの時さ、周太、国村さんとどんな話したんだ?」
「…っあの、っ」
どうしよう、やっぱり訊かれた。
でも約束している「隠し事はしない」って。
二度も、もう破ってしまった約束。だから今もう、隠すわけにはいかない。
そっと息を吸って、周太は呟いた。
「…みやたの背中ほどは居心地良くないだろうけど、夜じゃないから我慢して」
電話の向こう、きれいな笑い声が聞こえた。
きっと笑うだろうなと、そして首筋が熱くなるだろうと、どっちももう、予想通り。
「他もさ、なんか言われただろ」
「…ん、…みやたとあうまでずっと初めては何もしていなかったでしょ…って…」
この2つだけ。
たった2つの文章なのに、もう、キャパオーバーになってしまう。
そしてこんな時はつい、自分の記憶力がちょっと憎らしい。
それになにより困るのは、どちらの指摘も本当だと言うことだ。
この2つで済んで本当に良かった。国村のザイル下降技術に、ちょっと感謝したい。
もっと時間がかかったら、きっともっと、恥ずかしかった。
言い終って、ほっとしていたら、きれいな低い声が言った。
「さっきさ、藤岡に会ったって周太、教えてくれたよな」
「ん、なんかね、最初は俺だって解らなかったって」
ふうんと呟いて、笑って訊いてくれた。
「なんで周太だって、解らなかったんだ?」
お願い今、ちょっとそれは言えない。
藤岡が周太を解らなかった理由「なんかきれいになった」
「きれいになった」そのことが、国村に言われた「初めて」のことに絡まっている。
そう思ってしまって恥ずかしくて、とても今は言えそうにない。
それでも、なんとか周太は口を開いた。
「…なんだかもう、気恥ずかしくて…今夜は無理」
なぜだか電話の向こうは、大喜びして笑っている。
もう恥ずかしい、首筋も顔もきっと真っ赤になっている。
けれどこんなふうに、電話ででも想いを繋いで、時を共有できる。
そんな今この一瞬が、嬉しくて、幸せで、温かくて。
こうしていつまでも、やさしく繋いで、ずっと掴まえていてほしい。
だから考えしまう、どうしたら自分は、この想いに応えていけるのだろう?
こんなふうに誰かを、想うことすら初めてで。
こんなふうに誰かの為にと、応えたいことも初めてで。
想いの真ん中の、あの隣のために。きれいな笑顔のために、自分は何が出来るだろう?
(to be continued)
【歌詞引用:savage garden「truly madly deeply」】
blogramランキング参加中!
ネット小説ランキング
http://www.webstation.jp/syousetu/rank.cgi?mode=r_link&id=5955


















