あざやかな夜明け、あたらしい陽

萬紅、第三夜act.1―side story「陽はまた昇る」
時計は5時半。黎明のときだった。
闇は夜明けの前が最も濃い。濃密な浄闇に鎮まる山上で、空を見上げていた。
「星がふってくる、そんな感じがするな」
濃い暗闇にも黒目がちの瞳が輝いてみえる。
座っている木のベンチも闇の底に沈み、すぐ隣の顔だけが、ほの白く見えていた。
冷気が最も凍るのも、夜明け直前の黎明どき。山上の大気は冷たくて、氷水が融けたようだった。
「…こほっ」
軽い咳の音に、英二は隣を見た。
平気と微笑んでくれるけれど頬が少し赤い。山上の冷気で紅潮しているのだと、英二には見れば解る。
冷たい空気がダイレクトに肺に入って、咳が出たのだろう。
きっと寒いのだろう、英二は長い腕を伸ばした。
「ほら周太、来いよ」
「…え、でも」
自分の前に座らせた周太を、ホリゾンブルーの登山ジャケットごと背中から抱きしめた。
ジャケット越しに、お互いの熱が寄り添って温かい。温もりが幸せで、英二は微笑んだ。
「隣に誰かいるって、温かいだろ?」
「…となりっていうかなんていうか…」
恥ずかしそうな声が、ちいさく呟くように答えてくれる。
けれど本当は、うれしくて幸せに微笑んで、きっと瞳は笑っている。
そう思って英二は、抱きしめた肩越しに覗きこんだ。
「今、うれしい?」
「…ん、…うれしい、な。でも、すごく、…はずかしいぞきっとおれたち」
言われて英二は顔を廻らすと、闇に馴れた目に周囲が映る。
いつのまにか、中年夫婦のハイカーと山仲間3人組も外へ出ていた。
自分達と同じように、朝日を迎えるのだろう。きれいに英二は笑いかけた。
「おはようございます、冷え込みますね」
「おはようございます。まあ、仲良しですね」
ハイカーの妻が可笑しそうに笑ってくれる。
ええと頷いて、英二はきれいに笑った。
「はい、仲良いです。こうすると温かいですよ」
「あら、いいわね。ちょっとあなた、私達もしましょう?」
妻が夫の手をひいて、向こうのベンチへ歩きだす。
ロマンスグレーの夫が、気恥ずかしげに微笑んでいる。
「若い頃にしたね、でも今は少し恥ずかしいよ」
「そうね、でも今もう寒くって私、」
「じゃあ仕方ないな、」
そんなふうに笑って、夫婦も真似て座りこんだ。
気恥ずかしげでも楽しそうに、夫婦で笑っている。
それを見て、3人組の男達が英二に笑いかけた。
「こういうのも、山ならではだな」
周太を抱きしめたまま、英二は微笑んで答えた。
「ええ。山の寒気には人も、温かく寄り添えて良いですね」
「そうだな。うん、山は良いな」
きれいに笑って、英二は答えた。
「はい。温かくて、山は良いですね」
へえと男達は英二を見、笑いかけてくれた。
「きれいな笑顔だな、山ヤって感じだ」
「うれしいですね、ありがとうございます」
そう笑いあって3人は、じゃあとカメラを担いで山頂へと歩いていった。
見送って英二は、肩越しに微笑んだ。
「ほらな、恥ずかしくないよ?周太、」
肩越しに、黒目がちの瞳が見つめてくれる。
すこし潤んだ瞳が、きれいだと英二は見つめた。
黒目がちの瞳を微笑ませて、そっと周太は言った。
「…ありがとう、英二」
「うん。こっちこそいつも、嬉しいから」
なんにも恥ずかしいことなんか、自分達はしていない。
英二はいつも、そう思っている。
なぜなら自分はこんなにも、自分の全てをかけて想っている。
いつだってそう。心の底から真直ぐに、見つめて偽らず寄り添っている。
きっとそれは得難いこと、きれいな想い、穏やかな温もり。真摯は涯なく続いてしまう、そう心から信じている。
だから自分はいつも誇らしい、この隣に座ること。
こわれないように、静かに腕に力をいれて、英二は周太を抱きしめた。
頬に頬よせるように、きれいに英二は微笑んだ。
「ほら、周太。夜が明ける」
東の方角に、稜線が赤く輝き始めた。
あわいブルーの輝きが、遠く空の境界を顕して透明になる。
紺青が透ける闇は中天へ払われて、星は眠りについていく。
彩る雲は、薄紅に朱金に艶めいて、白さが空にまばゆく浮かんだ。
「…きれいだ」
頬寄せた唇が、やわらかく吐息をついた。
心響かす気配がうれしくて、英二は微笑んだ。
「ああ。きれいだな、」
こんなふうに寄り添って、一緒に山の朝を見られた。
そしてこんなふうに、隣は嬉しそうに笑ってくれる。
そうして今、幸せがこんなに温かい。
仕度して山荘を出ると、周太が遠慮がちに口を開いた。
「あのさ、コースって決めてあるよな」
「おう、計画書出してるし」
そうかと呟いて、物言いたげな唇を噤んでしまう。
ああきっとこの事だ、気がついて英二は笑った。
「あのブナの木には、今日も寄るから」
黒目がちの瞳が大きくなる。どうして解るんだと瞳が驚いている。
ほら、やっぱりそうだと英二は嬉しかった。
「言ったろ、あの場所は好きだって。だから俺、いつも往復で寄っているんだ」
「…俺も、好きだ」
同じように好きなことは、嬉しい。そうして想いも重ねられたらいい。
気恥ずかしげな様子が可愛い、つい英二は意地悪したくなった。
笑いかけて英二は言った。
「好きな場所にさ、好きな人を佇ませて眺めたいし、俺は」
「…そういうことをさこういうところではちょっと、」
また首筋が赤くなる。かわいくて嬉しくて、英二は笑った。
こんな初々しい隣が、ほんとうに好きだ。
雲取山頂を通って、帰路は唐松谷林道へと向かう。
奥多摩小屋の前にさしかかると、小屋番に声をかけられた。
「ヘリが来ますから、小屋に避難して下さい」
しばらくするとヘリコプターが来た。
ホバリングの風が強い。荷物を降ろすと、すぐまた飛び去っていく。
物珍しげに周太は見上げ、プロペラが巻く風を頬に受けていた。
「こんなに近くでヘリを見たの、俺、初めてだ」
「あ、また“初めて”なんだ?」
“初めて”で首筋が赤くなる。
たぶん昨夜のことを、想いだしているのだろう。
昨夜の山荘は静かだった。
おかげで、山荘前の夜景もゆっくり眺められた。よく晴れた大気に、新宿の夜景も遠くあざやかだった。
ココアを啜りながら、遠く新宿の夜を見て、周太は言った。
「ほんとうに、ここの空と繋がっているんだな」
大都会の底で、ときおり寂しさを周太は感じている。
そのことは英二も気付いていた。だから周太を、ここへ連れて来たかった。
英二は微笑んだ。
「そうだよ周太。空で繋がって俺は、いつも周太の隣にいる」
黒目がちの瞳が、見上げて見つめて、微笑んだ。
「…ん、うれしいな。繋がっているんだな、いつも」
「そうだよ、」
そう微笑み返した英二に、黒目がちの瞳が静かに近づいた。
そうだといいなと思いながら、英二は軽く睫を伏せた。
そっと周太はキスをしてくれた。
長い指の掌で、なめらかな頬を抱きとめる。
ココアの香が甘くて、温かかった。
ふれるだけ。けれどおかしくなりそうで、ただ英二は受けとめていた。
ゆっくり離れられてから、きれいに英二は微笑んだ。
「甘いね、周太のキスは」
そんなふうに英二は笑った、でも、本当は泣きたかった。
幸せで、泣きたかった。
「ねだらないでさ、周太からしてくれたの“初めて”だな、」
「…ん。…あまりいわないで恥ずかしくなる…」
首筋から頬まで赤らめているのが、夜闇に透けて、きれいだった。
昨夜は、空いていたおかげで、個室でのんびりできた。
置かれた豆炭の炬燵が物珍しくて、周太は興味深げに構造をチェックしていた。
21時の消灯、山荘では早めに眠りに入る。翌朝の朝日を楽しみに、登山客は早寝も多かった。
着替えて布団を敷いて、壁に凭れて並んで、窓から空を見あげた。
星と月の明かりで、あわく青い夜が部屋に充ちていた。
iPodのイヤホンを片方ずつ繋ぐ。
穏やかな曲が流れ始めて、静かに周太が言った。
「英二、…聴いて?」
黒目がちの瞳は、真直ぐに見つめてくれる。
物言いたげな唇が、そっと開いて言葉が零れた。
「…I'll love you more with every breath Truly, madly, deeply, do」
“息をするたびごとにずっと、君への愛は深まっていく ほんとうに心から、激しく深く愛している“
この歌詞は本当に、自分の本音だと、いつも英二は想う。
そして、この隣にも想ってほしいと、もうずっと求め続けている。
どうしてこの歌詞を口にしてくれるのかな。
思いながら見つめる隣で、赤らめた頬のまま周太は告げてくれた。
「この歌詞はね…俺の、本音だから」
この隣にも想ってほしいと、もうずっと求め続けていた。
息をするたびごとに。それは生きている限りと言う意味。
この隣も、自分に捕まってくれたのかな。
そんな想いが心から溢れて、切長い目から一滴、白い頬を伝っておちた。
うれしい。
昼間告げてくれた言葉、「愛している」
あまりに幸せで、幻だったのかとすら、今も想っていた。
英二は告げた。
「周太、聴いて?」
黒目がちの瞳を覗きこんで、そっと告げる。
「 ‘cause I am counting on A new beginning A reason for living A deeper meaning」
“君への想いはきっと、新しい始まり、生きる理由、より深い意味 そう充たす引き金となる”
黒目がちの瞳が大きくなる。この顔が好きだなと、嬉しくなる。
隣を見つめながら、静かに英二は言った。
「ほんとうに俺、もうずっと、そう想っている。だからもう、離れてしまったら、俺はね、生きていられない」
夜の底に包まれた空間で、黒目がちの瞳が見上げてくれる。
きれいな頬に、きれいな涙が零れて、そっと答えてくれた。
「…俺も、そう…」
告げてくれた唇がいとしくて、そっと唇で英二はふれた。
やわらかな熱が幸せで、愛しくて嬉しかった。
英二は微笑んだ。
「約束して、もう離れていかないで。どんな時も、どんな所でも、俺を離さずにいてよ」
長い指で、目の前の涙を拭う。
拭われた瞳で真直ぐに見上げて、周太は言ってくれた。
「約束する…だからもう、ひとりにしないで」
「うん、」
拭った目許にくちづけて、黒目がちの瞳を覗きこんだ。
そっと笑って英二は、周太へと願った。
「約束する、だから笑って周太。俺の名前を呼んで、キスしてよ」
きれいに周太は笑ってくれた。
「英二、」
かすかなオレンジの香と、ほろ苦く甘い吐息。やわらかな唇の温もりが、愛しかった。
そっと離れた唇に、英二から口づけて抱きしめた。
英二は大好きな、黒目がちの瞳に笑いかけた。
「周太への想いがね、俺の生きる理由と意味。生きている限りずっと周太を想うよ。
どんな時でも俺は、必ず周太の隣に帰る。
ひとりになんかしない、一緒に生きていてよ。いつも、離れていても守り続けて、必ず笑顔にさせるから」
見上げてくれる、黒目がちの瞳が純粋だった。
周太は静かに唇を開いた。
「…ん、俺だって英二を守りたい、一緒に生きたい。…俺もう、いつも、ずっと、英二の帰りを待っているんだ」
純粋な瞳から、涙がこぼれて落ちた。
「ほんとうは、いつも俺は不安だ…山はなにが起きるか解らない、だから不安…いつも天気予報を見てしまう…」
山では天候が生死を支配する。
そのことを、不安に想って心配して、周太は泣いてくれている。
いつのまに、そんなふうに想ってくれたのだろう。そんなふうに想ってくれていた、その事が英二は嬉しかった。
嬉しくて見つめる視線の真中で、きれいな純粋な瞳が、微笑んでくれた。
「でも信じている、約束を信じて待ってる…愛している、英二」
しあわせだ、ほんとうに。
うれしくて幸せに、きれいに英二は笑った。
「信じて待っていて。愛しているだけ、必ず周太の隣へ、俺は帰られるから。だから信じて?」
抱きしめて頬寄せて、温もりが嬉しかった。
微笑んでくれる、黒目がちの瞳を見つめて笑って、穏やかな温もりに寄り添った。
そんなふうに寄り添って、ただ抱きしめて昨夜は、山の夜に眠った。
そうして目覚めた今朝は、ただ幸せで温かかった。
ヘリコプターの風が止んだ。
小屋に避難していた登山客が、山道へと動き出す。英二も隣に微笑んだ。
「行こう、周太、」
さわやかな秋晴れが、清澄な空気に心地好かった。
隣を歩くホリゾンブルーの登山ジャケット姿に、英二は笑いかけた。
「昨夜みたいに眠ったの、なんか警察学校の寮みたいだったな」
「…ん、そうだな。懐かしくて、…なんか嬉しかった」
気恥ずかしそうに、でも微笑んで周太は答えてくれる。
なんだか幸せで嬉しくて、つい英二は意地悪したくなった。
「卒業してからはさ、しないで寝たのは、“初めて”だよな」
「…っ」
ほら、やっぱり真っ赤になった。
見慣れたこんな反応も、幸せで。うれしくて笑いながら、英二は言った。
「ほら、こっちの道に行くぞ。ちゃんと着いて来いよ、周太」
笑って唐松谷への道を示すと、困った顔のまま少し俯いている。
けれど、すこし唇をかんで、ひとつ息を周太は吐いた。
そうして、どうしたのかなと見つめる英二を、黒目がちの瞳が見上げて微笑んだ。
「ん、着いていく…だからずっと連れて行って、英二」
いつのまにこんなふうに、言えるようになったんだろう。
思っていなかった予想外の、隣からの反応。
うれしくて英二は、きれいに笑った。
「ああ、ずっと連れていく。だからちゃんと着いてきてよ、周太」
唐松谷林道へ入ると、陽光が落葉松の森へと射しこんだ。
陽に透けた黄金の梢が華やいで、隣の頬をあかるく照らし大気を染める。
隣はそっと息を呑んだ。
「黄色の黄葉は、眩いな」
「うん、きれいだろ、」
微笑んだ英二の視界で、ホリゾンブルーの登山ジャケットがあざやかだった。
誕生日に贈った登山服を、きちんと周太は着てくれている。
あわいブルーが黄金に映える、この色を選んで正解だった。
そっと英二は話しかけた。
「周太の服の色、ホリゾンブルーって言うんだ」
「ほりぞんぶるー? …ん、きれいな色で、俺、気に入ってる」
よかったと笑って、英二は続けた。
「地平線や水平線近くの空の色をな、ホリゾンブルーっていうんだ」
「きれいで、広々とした名前だな」
「だろ、」
黄金の木洩日のなか、ホリゾンブルーの隣と歩く。
奥多摩をながれる渓流の色とも、すこし似た色で英二は好きだった。
きれいだなと隣を見遣りながら、英二は登山地図をクリップボードにセットする。
ここからまた、台風などの崩落で通行止めになっていた。
チェックポイントで立ち止まり、メモをとる。
この隣は、時折は、興味深そうに手元を眺めていた。
けれど黄葉とその足許の植物が、周太の心を惹きつけている。
メモを終わって周太の視線を追うと、きれいな赤い実をつけた木がたっていた。
「ナナカマドだ、」
楽しそうに植物の名前を教えてくれる。
周太の実家には、緑豊かな庭がある。周太の祖父が建てたという、木造の古い家だった。
古くても端正な家は植物に囲まれて、木肌の焦茶と白壁が緑に映えて美しい。
この隣の穏やかな静けさが育ったことが、頷ける家だなと英二も思う。
そんなふうに植物に囲まれて育った周太は、自然が好きらしく、花や木の名前を知っていた。
「ヨウシュウヤマゴボウ。これで布が染められる」
黒紫の実を眺めて、微笑んでいる。
懐かしそうに、けれど微笑んだまま、英二を振り向いて教えてくれた。
「父がね、山で教えてくれたんだ」
周太の父は、妻と息子を山に連れて、休日を過ごしたらしい。
アルバムにも山頂で撮られた、かわいい笑顔の写真があった。
13年前までの幸福な記憶を、こんなふうに笑顔で、話してくれている。
少し前まで、13年前までの幸福な記憶は、周太の心の傷にもなっていた。
それでも、警察学校の山岳訓練の時で少しだけ、周太は父の幸せな記憶を話している。
怪我をして背負われた英二の背中に、幼い日に父に背負われた記憶を重ねて、口を開いてくれた。
あのときと、今と。
話してくれる声もトーンも、同じようで全く違っている。
そして表情は、ずっと明るくて幸せで、きれいになった。
すこしは自分も、周太のために、生きられているのだろうか。
そんな想いの中心で、きれいに笑って草木を眺める笑顔が、愛しかった。
唐松谷林道を分岐まで降りて、野陣尾根へと入った。
登山道からすこし逸れる、隠された道を辿って、あの場所へと戻る。
ブナの巨樹を見あげて、黒目がちの瞳が微笑んだ。
「今日も、きれいだな」
「ああ、今日が一番きれいで、この秋の最後かもな、」
ブナの木を眺めて倒木に座る。木洩日の光が昨日よりもやわらかい。
また少し、秋が梢をおだやかに変えていた。
オレンジ色のパッケージから一粒、周太は口に含んだ。さわやかな甘い香が、森の香と馴染んでとけていく。
「俺もほしいな、」
笑いかけると、周太は困ったような顔になった。
掌の空になったパッケージを見せて、英二を見上げる。
「ごめん、最後の1個だった…下山したら買うな?」
謝られて、わざと英二は少し拗ねた顔をしてみせた。
「今、ほしいんだけど?」
「…ごめん、」
どうしようと黒目がちの瞳が困っている。
ふっと笑って英二は、周太の頬にそっと掌をよせた。
「謝らなくていいよ、もらうから」
「…え、?」
見上げる唇に唇をよせると、英二は深く重ねた。
「…っまって、」
驚いたままの唇はやわらかくて、そのままほどけて受け入れてしまう。
温かな感覚の底で、かわいいなと英二は微笑んだ。
かすかに視界を開くと、目の前の瞳は瞠いたままでいる。
その瞳には今、自分しか映っていない。それが英二には嬉しい。
甘さとガラスの様な感触をみつけて、英二はそっと唇を離した。
「ありがと、」
口の中で甘さを転がしながら、英二は笑った。オレンジの甘い香りが、英二の口許からこぼれる。
呆然としたままの隣は、赤くなるのも忘れて英二を見つめている。
その顔をのぞきこんで英二は微笑んだ。
「この飴、なんだか随分と甘いな、周太?」
たちまち目の前の顔が真っ赤になっていく。
かわいいなと英二は微笑んだ。
「返してほしい?」
ほら、もう真っ赤だ。そんな隣の反応が、かわいくて、楽しくて仕方ない。
こんなふうに、いつものように、予想した通りに初々しい。
うれしくて、英二は笑っていた。
けれど意外なことが起きた。
「…ん、かえして」
ぼそっと呟いて周太は、そっと唇をよせた。
端正な唇に、やわらかな唇が重なる。
ぎこちなく含まされる熱、困ったように探る温もり。
蕩かされていく
そんな熱にうかされて、英二はされるがままになっていた。
「…ない、」
離れて、困ったような真っ赤な顔が、ぼそりと言った。
可笑しくて、幸せで、英二は笑った。
「ああ、俺、すぐ飲みこんだから」
「…え、」
周太の意外な行動が、英二はうれしかった。
うれしくて、幸せで、止めてほしくなくて。
それで英二は、飴を飲みこんでしまった。
生真面目ですこし頑固な周太、「返して」と言ったらその通りにしようとする。
返してもらうまで、頑張って探そうとするだろう。
探す時間を引き延ばすには、探し物を消してしまえばいい。
悪戯っぽい目で、英二は教えた。
「だって見つけたら周太、すぐ止めただろ?」
「…ん、」
「気持ちいいから、止めてほしくなかったからさ。見つけられたくないから、飲んじゃった」
ほら、今度こそもう真っ赤になる。
今頃になって、自分のしたことに途惑っている。
こんなに赤くなって大丈夫なのかな。そう思いながらも、つい英二は言ってしまった。
「こういうキスも周太からは、“初めて”だね」
言われて、困っている。
けれど、黒目がちの瞳があげられて、真直ぐに見つめてくれた。
その瞳が、英二が見たことのない表情で、こっちを見ている。
どうしたと目だけで訊くと、物言いたげな唇が開いた。
「…初めては全部うれしいから…」
きれいに英二は、笑った。
「うん。俺こそ、うれしいよ」
おいで、と長い腕を伸ばして、そっと抱きしめた。
昨日も今日も、このブナの下で。いったい、どれだけ幸せだったろう。
あの日。報復の孤独へと周太が引き摺られかけた日。
もし15分を遅れていたら、こんな幸せを自分は知らないままだった。
そしてこの隣を、孤独のままに冷たく終わらせていた。
そして今日は、あの日からちょうど、1週間の日。
あの日に刻まれた周太と自分の傷は、もうこんなふうに癒えている。
もしも自分が、男ではなく、警察官ではなく、山ヤで山岳救助隊員ではなくて、ここに居なかったら。
どれが欠けてもきっと、あの15分で間に合った瞬間に、周太を掴まえられなかった。
自分が自分で、良かった。
こんな今の自分を与えられている、そういう自分で良かった。そんなふうに思える。
そして想ってしまう、願ってしまう。
こうして全てをかけるなら、きっと自分は、この隣を抱きしめ守って、生き続けていけるだろう。
卒配期間が終わって、初任科総合が終わって、本配属になる。
そのときにきっと、辛い運命と冷たい真実が、周太の前に現れる。そのことを、自分も周太の母も、もう知っている。
周太が、父親の軌跡を辿ることを望む以上、その未来を避ける事は、もう出来ない。
そして自分は、周太が望む場所の隣で、離さずに、ずっと守り続けていく。
きっとその時は「警察官」という立場が、自分達を引き離す。
それでも自分は、どんな手をつかっても、この隣を守るだろう。
自分達を引き離そうとする「警察官」の立場すら、追いつめ利用して自分は離れない。
直情的で思ったことしか言えない、出来ない。
けれど自分の能力は要領が良い。そして正直であるほどに、周りは自分に手を差し伸べる。
だからきっと大丈夫。
昨日から結んだ、いくつかの約束。その全てを自分は、果たすことが出来るだろう。
この隣への想いが、自分の生きる理由と意味。生きている限りずっと想い続ける。
どんな時でも自分は、必ずこの隣に帰る。ひとりになんかしない、一緒に生きていく。
もう自分は、名前を呼ばれて、求めてられている。
だからずっと自分は、この隣に帰って、守って微笑まられる。
抱きしめた隣に、英二は微笑んだ。
「愛してるよ、周太」
純粋な瞳が、そっと見上げて微笑んでくれる。
ほらもう、この隣はこんなにも、きれいに眩しくなっている。
だからきっと大丈夫。どんな場所に立たされても、この純粋さは誰にも冒せない。
目の前の瞳を見つめて、英二は微笑んだ。
「周太は、きれいだ」
ふわり、白いはなびらが舞いおりた。
黒目がちの瞳を、そっとかすめるように、やわらかな白がふってくる。
黄金の梢にかかる空から、あわい雪がしずかに降ってきた。
そっと英二は笑った。
「初雪だな、」
頬にふれる冷たさが、周太を微笑ませる。
微笑んだ唇がそっと開かれた。
「これも…初めてだな、」
「そうだな、」
純粋なこの隣を、自分はもう愛している。
そんな想いが温かい、英二は笑って、空を見あげた。
見上げる上空の、雲の流れは早い。すぐに雪は止んで、きっと晴れが戻るだろう。
念のために軽アイゼンは持っている、けれど使わずに済みそうだった。
よかったと思いながら、英二は周太に微笑んだ。
「ココア、作ってやるよ」
草地を少し整地する。
昨日より、馴れた手つきで英二は作れた。
あわい雪を眺めながら、大切そうに周太はカップを抱えてくれる。
「温かいね、」
「だろ、」
笑った周太の顔が、心から愛しかった。
甘く湯気の燻らせるココアが、温かい。
ときおり降りてくる雪が、そっと隣の黒髪に舞う。
穏やかな静けさが、居心地が良い。好きなこの空気に、英二は微笑んだ。
昨日カフェで買ったブレッドの袋を、英二は取り出した。
トラベルナイフでブレッドに切れ込みを入れ、チーズを挟む。
クッカーで軽くあぶってから、周太に渡した。
「こんなことも出来るのか」
「うん、国村に教わったんだ」
頂きますと、ひとくち齧ると微笑んでくれた。
「ん、おいしい。すごいな、英二」
「よかった、」
こういう時間は好きだ、英二は心から微笑んだ。
すぐにやんだ雪と一緒に、また歩き出す。
もどった陽射に、豊かな梢は明るい秋の空気に佇んでいる。
すこしだけ水気を帯びた道の、落葉の香が清々しかった。
「あ、」
隣の声に英二は、周太の視線の先を追った。
陽のあたる枯葉の合間から、凛と青い花が咲いている。
そっと周太は傍に跪くと、英二を見あげて教えてくれた。
「りんどうだよ、英二」
田中の最後の一葉は、りんどうだった。
農家で写真家の田中は、生まれ育った御岳を愛し、国村を山ヤに育て上げた。
そんな山ヤの田中は、氷雨にうたれる青い花を、写真に納めて生涯を終えた。
あわい初雪のなか、青く輝いた、りんどうの花。
あの氷雨の夜に背負った、美しい山ヤの生涯と、自分の想いが温かい。
そうして、凍える雪にも凛とした花姿に、この隣を重ねてしまう。
きれいに英二は、笑った。
「きれいだ、」
初雪がふれば、奥多摩は眠りの準備に入る。
そうして山ヤの警察官は、雪山での活動に入る。
英二にとって初めての、雪山での山岳救助と山ヤの生活が始まる。
奥多摩交番に戻ったのは14時だった。
日原林道から野陣尾根、唐松谷林道と報告をしていく。
全て終わると、後藤が楽しげに休憩室へと誘ってくれた。
「俺も今日は、ちょうど上がりだから」
そう言いながら、ミズナラの樽で醸造されたウィスキーを出してくれた。
周太には水割りで渡してくれる。
その水は、日原集落の水場で汲んできた、湧水だった。
「おいしいです、」
「そうだろう?」
微笑んだ周太に、嬉しそうに後藤は笑いかけた。
英二にはロックで渡してくれる。
「日原の秋は、どうだったかい?」
「はい、目の底が染まりそうでした」
「そうか、そんなにか、」
そんなふうに話していると、後藤の携帯が鳴った。
ちょっとごめんよと出て、少し話すとすぐに切る。
そのまま後藤はもう、ミズナラの酒のロックを作り始めた。
「今すぐな、俺の酒仲間が来るよ」
5分ほどして現われたのは、吉村医師だった。
ミズナラの酒を受取りながら、吉村は微笑んだ。
「往診の帰りに寄れと、きのう連絡をくれたんですよ」
笑いながら後藤が吉村を見た。
「だってなあ、吉村も一緒に飲みたかっただろう?」
「はい、そうですね。ご一緒出来て嬉しいです」
後藤は北国の出身だった。
高校時代から山ヤだった後藤は、高卒で警視庁警察学校に進んでいる。
そして、山ヤの警察官として奥多摩交番に配属された。
第七機動隊山岳救助レンジャーとして離れた時期もあるが、警察官の生涯の大半は奥多摩だった。
「吉村とは、俺が最初にここへ赴任した時からだな」
「そうですね、私の実家が、こちらですから」
吉村は奥多摩出身で、若い頃から地元の山に親しんでいる。
10年前に地元に戻って開業医となり、青梅警察署の警察医になった。
その前は医科大付属病院の教授として勤務している。
「では30年来の飲み仲間ですか?」
「そうだな、もうそんなになるか」
そんな話をしながら、ゆっくりとミズナラの香を楽しんだ。
吉村と周太が話す様子に微笑みながら、後藤は英二に訊いた。
「あの木な、元気にしていたかい?」
「はい、黄葉がとても綺麗でした」
そうかと微笑んだ後藤の顔が、懐かしそうで、英二は切なくなった。
―あのブナはな、かみさんを最初に山へ連れていった時、見つけたんだ
けれどもう俺は行かない。だから誰かに座って欲しかった
大切な人がいる。そういう奴に、あのブナを譲りたかったんだ
3年前に妻を亡くした後藤は、そんなふうに英二に話してくれた。
そんな後藤の気持ちが、英二は心から嬉しい。
けれどこの事について英二は、後藤に訊いてみたいことがあった。
でも訊いていいのか解らずにいた、今が良い機会なのかもしれない。
「副隊長に俺は、ずっと訊きたい事があります」
「おう、なんだい?」
気さくに笑って、後藤は促してくれる。
口を開いてしまったら、英二は基本止められない。
そんな俺でも受けとめてくれたらいいな、思いながら英二は微笑んだ。
「俺は率直にしか話せません、失礼を先にお詫びします」
「ああ、構わんよ。宮田のそういうところは、俺も好きだぞ」
微笑んで後藤は、英二の目を見てくれる。
真直ぐ見つめ返して、英二は訊いた。
「あの場所の事です。なぜ、国村に譲らなかったのですか」
国村は、才能あるクライマーとして、ファイナリストの素質を嘱望されている。
英二と同年の国村だが、高卒で警察官となり4年の長がある。そして山は18年のキャリアを持つ。
トップクライマーだった両親と田中の薫陶で、5歳から山ヤの経験を積んでいた。
そうして生粋の山ヤに育った国村は、純粋無垢な山への想いに生きている。
そんな国村は、山を甘くみる遭難者への怒りを隠さない。
冷静沈着だけれど大胆不敵、自由人で厳しい。そして山ヤらしい快活さが底抜けに明るい。
そんな国村は山ヤとして美しい。だからこそ、山岳救助隊員の全員が、国村のことを大切にしている。
そして後藤は国村のことを、本当に可愛がっている。
先日の不用意な道迷い遭難の夜間捜索でも、遭難者よりむしろ国村の心配をしていた。
そういう国村になら、あの場所を譲っても不思議は無かった。
笑って、後藤は答えてくれた。
「うん、あいつはな、もう昔から、自分の場所を持っているんだよ」
だから俺から譲る必要が無いんだ。
そう言って後藤は、グラスに口をつけた。
そうして深い目を微笑ませ、英二を見つめながら話してくれた。
「国村のことは、生まれた時から知っているよ。あいつの両親とはな、山ヤ仲間だったんだ。
その両親にな、まだ5歳のあいつを、雲取山へ登らせると言われた時は、俺も驚いた。
5歳児の脚では、とても無理だと思った。だからな、両親がおんぶしてだろうと思っていたよ」
雲取山は標高2,017.1m。東京の最高峰になる。
低山であっても、急峻な道も多く遭難者も出る。決して甘いコースとは言えない。
「でもなあ、あいつ、自分の脚で登ってさ、ちゃんと自分で降りて来たんだよ」
「5歳で、ですか」
そうだと頷いて、後藤は続けた。
「まだ5歳なのにと、俺も本当に驚いた。それでその時にな、俺は国村に訊いたんだよ。辛くなかったかとね」
あいつなんて言ったと思うかい?
そう首を傾げてから、後藤は破顔した。
「自分ちの山で仕事手伝うより、ずっと楽だ。ただ歩くだけなのに、楽しかったよ。そう言ってな、飄々と笑ったんだ」
国村らしい答えだった。
痩身だけれど国村は、持久力とパワーが並外れている。
体力をつけるコツを訊いた英二に「休日は農業やるからじゃない」と国村は答えた。
あいつ5歳の頃から変わっていないんだ。そう思うと英二は可笑しかった。
「国村らしいです、」
「だろう?」
後藤も楽しそうに笑った。
「俺もなあ、5歳で山仕事を手伝わせて、体力をつけたとは予想外だったよ。
国村の家の山は、急斜面で険しいんだ。それを4歳頃には自力で登っていたらしい。
そうやってな、あいつはずっと山で生きている。それでどうも、特別な場所を子供の時から、持っているらしいんだ」
「ああ、国村ならきっと、そうです」
「だろう?」
頷いて、温かな目を英二に向けてくれる。
グラスを啜って後藤は、真直ぐに英二を見て微笑んだ。
「あの場所、彼は気に入ったのかい?」
はいと頷いて英二は答えた。
「ずいぶん長い時間、ブナの水音を聴いていました。
それから見上げて『こんなふうに静かに穏やかに生きられたらいい』そう言っていました」
後藤の目が、嬉しそうに笑っている。
静かに頷いて、ほっと息をつくと後藤は言った。
「きれいな瞳の通りに、純粋なのだな」
「はい、」
きれいに笑った英二に、ゆっくりと後藤は頷いて、温かく微笑んだ。
「大切にするといい、あの場所も、彼も」
やっぱり後藤は解っている。
そしてあの場所へ、連れていくに相応しいと認めてくれた。
自分達の繋がりが理解され難いことを、英二はよく知っている。
最上級の山ヤである後藤に、受けとめてもらえた。うれしいと心から英二は笑った。
「はい、ありがとうございます」
きれいに笑って、英二はミズナラの酒を飲みほした。
(to be continued)
【歌詞引用:savage garden「truly madly deeply」】
blogramランキング参加中!
ネット小説ランキング
http://www.webstation.jp/syousetu/rank.cgi?mode=r_link&id=5955

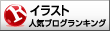
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村

萬紅、第三夜act.1―side story「陽はまた昇る」
時計は5時半。黎明のときだった。
闇は夜明けの前が最も濃い。濃密な浄闇に鎮まる山上で、空を見上げていた。
「星がふってくる、そんな感じがするな」
濃い暗闇にも黒目がちの瞳が輝いてみえる。
座っている木のベンチも闇の底に沈み、すぐ隣の顔だけが、ほの白く見えていた。
冷気が最も凍るのも、夜明け直前の黎明どき。山上の大気は冷たくて、氷水が融けたようだった。
「…こほっ」
軽い咳の音に、英二は隣を見た。
平気と微笑んでくれるけれど頬が少し赤い。山上の冷気で紅潮しているのだと、英二には見れば解る。
冷たい空気がダイレクトに肺に入って、咳が出たのだろう。
きっと寒いのだろう、英二は長い腕を伸ばした。
「ほら周太、来いよ」
「…え、でも」
自分の前に座らせた周太を、ホリゾンブルーの登山ジャケットごと背中から抱きしめた。
ジャケット越しに、お互いの熱が寄り添って温かい。温もりが幸せで、英二は微笑んだ。
「隣に誰かいるって、温かいだろ?」
「…となりっていうかなんていうか…」
恥ずかしそうな声が、ちいさく呟くように答えてくれる。
けれど本当は、うれしくて幸せに微笑んで、きっと瞳は笑っている。
そう思って英二は、抱きしめた肩越しに覗きこんだ。
「今、うれしい?」
「…ん、…うれしい、な。でも、すごく、…はずかしいぞきっとおれたち」
言われて英二は顔を廻らすと、闇に馴れた目に周囲が映る。
いつのまにか、中年夫婦のハイカーと山仲間3人組も外へ出ていた。
自分達と同じように、朝日を迎えるのだろう。きれいに英二は笑いかけた。
「おはようございます、冷え込みますね」
「おはようございます。まあ、仲良しですね」
ハイカーの妻が可笑しそうに笑ってくれる。
ええと頷いて、英二はきれいに笑った。
「はい、仲良いです。こうすると温かいですよ」
「あら、いいわね。ちょっとあなた、私達もしましょう?」
妻が夫の手をひいて、向こうのベンチへ歩きだす。
ロマンスグレーの夫が、気恥ずかしげに微笑んでいる。
「若い頃にしたね、でも今は少し恥ずかしいよ」
「そうね、でも今もう寒くって私、」
「じゃあ仕方ないな、」
そんなふうに笑って、夫婦も真似て座りこんだ。
気恥ずかしげでも楽しそうに、夫婦で笑っている。
それを見て、3人組の男達が英二に笑いかけた。
「こういうのも、山ならではだな」
周太を抱きしめたまま、英二は微笑んで答えた。
「ええ。山の寒気には人も、温かく寄り添えて良いですね」
「そうだな。うん、山は良いな」
きれいに笑って、英二は答えた。
「はい。温かくて、山は良いですね」
へえと男達は英二を見、笑いかけてくれた。
「きれいな笑顔だな、山ヤって感じだ」
「うれしいですね、ありがとうございます」
そう笑いあって3人は、じゃあとカメラを担いで山頂へと歩いていった。
見送って英二は、肩越しに微笑んだ。
「ほらな、恥ずかしくないよ?周太、」
肩越しに、黒目がちの瞳が見つめてくれる。
すこし潤んだ瞳が、きれいだと英二は見つめた。
黒目がちの瞳を微笑ませて、そっと周太は言った。
「…ありがとう、英二」
「うん。こっちこそいつも、嬉しいから」
なんにも恥ずかしいことなんか、自分達はしていない。
英二はいつも、そう思っている。
なぜなら自分はこんなにも、自分の全てをかけて想っている。
いつだってそう。心の底から真直ぐに、見つめて偽らず寄り添っている。
きっとそれは得難いこと、きれいな想い、穏やかな温もり。真摯は涯なく続いてしまう、そう心から信じている。
だから自分はいつも誇らしい、この隣に座ること。
こわれないように、静かに腕に力をいれて、英二は周太を抱きしめた。
頬に頬よせるように、きれいに英二は微笑んだ。
「ほら、周太。夜が明ける」
東の方角に、稜線が赤く輝き始めた。
あわいブルーの輝きが、遠く空の境界を顕して透明になる。
紺青が透ける闇は中天へ払われて、星は眠りについていく。
彩る雲は、薄紅に朱金に艶めいて、白さが空にまばゆく浮かんだ。
「…きれいだ」
頬寄せた唇が、やわらかく吐息をついた。
心響かす気配がうれしくて、英二は微笑んだ。
「ああ。きれいだな、」
こんなふうに寄り添って、一緒に山の朝を見られた。
そしてこんなふうに、隣は嬉しそうに笑ってくれる。
そうして今、幸せがこんなに温かい。
仕度して山荘を出ると、周太が遠慮がちに口を開いた。
「あのさ、コースって決めてあるよな」
「おう、計画書出してるし」
そうかと呟いて、物言いたげな唇を噤んでしまう。
ああきっとこの事だ、気がついて英二は笑った。
「あのブナの木には、今日も寄るから」
黒目がちの瞳が大きくなる。どうして解るんだと瞳が驚いている。
ほら、やっぱりそうだと英二は嬉しかった。
「言ったろ、あの場所は好きだって。だから俺、いつも往復で寄っているんだ」
「…俺も、好きだ」
同じように好きなことは、嬉しい。そうして想いも重ねられたらいい。
気恥ずかしげな様子が可愛い、つい英二は意地悪したくなった。
笑いかけて英二は言った。
「好きな場所にさ、好きな人を佇ませて眺めたいし、俺は」
「…そういうことをさこういうところではちょっと、」
また首筋が赤くなる。かわいくて嬉しくて、英二は笑った。
こんな初々しい隣が、ほんとうに好きだ。
雲取山頂を通って、帰路は唐松谷林道へと向かう。
奥多摩小屋の前にさしかかると、小屋番に声をかけられた。
「ヘリが来ますから、小屋に避難して下さい」
しばらくするとヘリコプターが来た。
ホバリングの風が強い。荷物を降ろすと、すぐまた飛び去っていく。
物珍しげに周太は見上げ、プロペラが巻く風を頬に受けていた。
「こんなに近くでヘリを見たの、俺、初めてだ」
「あ、また“初めて”なんだ?」
“初めて”で首筋が赤くなる。
たぶん昨夜のことを、想いだしているのだろう。
昨夜の山荘は静かだった。
おかげで、山荘前の夜景もゆっくり眺められた。よく晴れた大気に、新宿の夜景も遠くあざやかだった。
ココアを啜りながら、遠く新宿の夜を見て、周太は言った。
「ほんとうに、ここの空と繋がっているんだな」
大都会の底で、ときおり寂しさを周太は感じている。
そのことは英二も気付いていた。だから周太を、ここへ連れて来たかった。
英二は微笑んだ。
「そうだよ周太。空で繋がって俺は、いつも周太の隣にいる」
黒目がちの瞳が、見上げて見つめて、微笑んだ。
「…ん、うれしいな。繋がっているんだな、いつも」
「そうだよ、」
そう微笑み返した英二に、黒目がちの瞳が静かに近づいた。
そうだといいなと思いながら、英二は軽く睫を伏せた。
そっと周太はキスをしてくれた。
長い指の掌で、なめらかな頬を抱きとめる。
ココアの香が甘くて、温かかった。
ふれるだけ。けれどおかしくなりそうで、ただ英二は受けとめていた。
ゆっくり離れられてから、きれいに英二は微笑んだ。
「甘いね、周太のキスは」
そんなふうに英二は笑った、でも、本当は泣きたかった。
幸せで、泣きたかった。
「ねだらないでさ、周太からしてくれたの“初めて”だな、」
「…ん。…あまりいわないで恥ずかしくなる…」
首筋から頬まで赤らめているのが、夜闇に透けて、きれいだった。
昨夜は、空いていたおかげで、個室でのんびりできた。
置かれた豆炭の炬燵が物珍しくて、周太は興味深げに構造をチェックしていた。
21時の消灯、山荘では早めに眠りに入る。翌朝の朝日を楽しみに、登山客は早寝も多かった。
着替えて布団を敷いて、壁に凭れて並んで、窓から空を見あげた。
星と月の明かりで、あわく青い夜が部屋に充ちていた。
iPodのイヤホンを片方ずつ繋ぐ。
穏やかな曲が流れ始めて、静かに周太が言った。
「英二、…聴いて?」
黒目がちの瞳は、真直ぐに見つめてくれる。
物言いたげな唇が、そっと開いて言葉が零れた。
「…I'll love you more with every breath Truly, madly, deeply, do」
“息をするたびごとにずっと、君への愛は深まっていく ほんとうに心から、激しく深く愛している“
この歌詞は本当に、自分の本音だと、いつも英二は想う。
そして、この隣にも想ってほしいと、もうずっと求め続けている。
どうしてこの歌詞を口にしてくれるのかな。
思いながら見つめる隣で、赤らめた頬のまま周太は告げてくれた。
「この歌詞はね…俺の、本音だから」
この隣にも想ってほしいと、もうずっと求め続けていた。
息をするたびごとに。それは生きている限りと言う意味。
この隣も、自分に捕まってくれたのかな。
そんな想いが心から溢れて、切長い目から一滴、白い頬を伝っておちた。
うれしい。
昼間告げてくれた言葉、「愛している」
あまりに幸せで、幻だったのかとすら、今も想っていた。
英二は告げた。
「周太、聴いて?」
黒目がちの瞳を覗きこんで、そっと告げる。
「 ‘cause I am counting on A new beginning A reason for living A deeper meaning」
“君への想いはきっと、新しい始まり、生きる理由、より深い意味 そう充たす引き金となる”
黒目がちの瞳が大きくなる。この顔が好きだなと、嬉しくなる。
隣を見つめながら、静かに英二は言った。
「ほんとうに俺、もうずっと、そう想っている。だからもう、離れてしまったら、俺はね、生きていられない」
夜の底に包まれた空間で、黒目がちの瞳が見上げてくれる。
きれいな頬に、きれいな涙が零れて、そっと答えてくれた。
「…俺も、そう…」
告げてくれた唇がいとしくて、そっと唇で英二はふれた。
やわらかな熱が幸せで、愛しくて嬉しかった。
英二は微笑んだ。
「約束して、もう離れていかないで。どんな時も、どんな所でも、俺を離さずにいてよ」
長い指で、目の前の涙を拭う。
拭われた瞳で真直ぐに見上げて、周太は言ってくれた。
「約束する…だからもう、ひとりにしないで」
「うん、」
拭った目許にくちづけて、黒目がちの瞳を覗きこんだ。
そっと笑って英二は、周太へと願った。
「約束する、だから笑って周太。俺の名前を呼んで、キスしてよ」
きれいに周太は笑ってくれた。
「英二、」
かすかなオレンジの香と、ほろ苦く甘い吐息。やわらかな唇の温もりが、愛しかった。
そっと離れた唇に、英二から口づけて抱きしめた。
英二は大好きな、黒目がちの瞳に笑いかけた。
「周太への想いがね、俺の生きる理由と意味。生きている限りずっと周太を想うよ。
どんな時でも俺は、必ず周太の隣に帰る。
ひとりになんかしない、一緒に生きていてよ。いつも、離れていても守り続けて、必ず笑顔にさせるから」
見上げてくれる、黒目がちの瞳が純粋だった。
周太は静かに唇を開いた。
「…ん、俺だって英二を守りたい、一緒に生きたい。…俺もう、いつも、ずっと、英二の帰りを待っているんだ」
純粋な瞳から、涙がこぼれて落ちた。
「ほんとうは、いつも俺は不安だ…山はなにが起きるか解らない、だから不安…いつも天気予報を見てしまう…」
山では天候が生死を支配する。
そのことを、不安に想って心配して、周太は泣いてくれている。
いつのまに、そんなふうに想ってくれたのだろう。そんなふうに想ってくれていた、その事が英二は嬉しかった。
嬉しくて見つめる視線の真中で、きれいな純粋な瞳が、微笑んでくれた。
「でも信じている、約束を信じて待ってる…愛している、英二」
しあわせだ、ほんとうに。
うれしくて幸せに、きれいに英二は笑った。
「信じて待っていて。愛しているだけ、必ず周太の隣へ、俺は帰られるから。だから信じて?」
抱きしめて頬寄せて、温もりが嬉しかった。
微笑んでくれる、黒目がちの瞳を見つめて笑って、穏やかな温もりに寄り添った。
そんなふうに寄り添って、ただ抱きしめて昨夜は、山の夜に眠った。
そうして目覚めた今朝は、ただ幸せで温かかった。
ヘリコプターの風が止んだ。
小屋に避難していた登山客が、山道へと動き出す。英二も隣に微笑んだ。
「行こう、周太、」
さわやかな秋晴れが、清澄な空気に心地好かった。
隣を歩くホリゾンブルーの登山ジャケット姿に、英二は笑いかけた。
「昨夜みたいに眠ったの、なんか警察学校の寮みたいだったな」
「…ん、そうだな。懐かしくて、…なんか嬉しかった」
気恥ずかしそうに、でも微笑んで周太は答えてくれる。
なんだか幸せで嬉しくて、つい英二は意地悪したくなった。
「卒業してからはさ、しないで寝たのは、“初めて”だよな」
「…っ」
ほら、やっぱり真っ赤になった。
見慣れたこんな反応も、幸せで。うれしくて笑いながら、英二は言った。
「ほら、こっちの道に行くぞ。ちゃんと着いて来いよ、周太」
笑って唐松谷への道を示すと、困った顔のまま少し俯いている。
けれど、すこし唇をかんで、ひとつ息を周太は吐いた。
そうして、どうしたのかなと見つめる英二を、黒目がちの瞳が見上げて微笑んだ。
「ん、着いていく…だからずっと連れて行って、英二」
いつのまにこんなふうに、言えるようになったんだろう。
思っていなかった予想外の、隣からの反応。
うれしくて英二は、きれいに笑った。
「ああ、ずっと連れていく。だからちゃんと着いてきてよ、周太」
唐松谷林道へ入ると、陽光が落葉松の森へと射しこんだ。
陽に透けた黄金の梢が華やいで、隣の頬をあかるく照らし大気を染める。
隣はそっと息を呑んだ。
「黄色の黄葉は、眩いな」
「うん、きれいだろ、」
微笑んだ英二の視界で、ホリゾンブルーの登山ジャケットがあざやかだった。
誕生日に贈った登山服を、きちんと周太は着てくれている。
あわいブルーが黄金に映える、この色を選んで正解だった。
そっと英二は話しかけた。
「周太の服の色、ホリゾンブルーって言うんだ」
「ほりぞんぶるー? …ん、きれいな色で、俺、気に入ってる」
よかったと笑って、英二は続けた。
「地平線や水平線近くの空の色をな、ホリゾンブルーっていうんだ」
「きれいで、広々とした名前だな」
「だろ、」
黄金の木洩日のなか、ホリゾンブルーの隣と歩く。
奥多摩をながれる渓流の色とも、すこし似た色で英二は好きだった。
きれいだなと隣を見遣りながら、英二は登山地図をクリップボードにセットする。
ここからまた、台風などの崩落で通行止めになっていた。
チェックポイントで立ち止まり、メモをとる。
この隣は、時折は、興味深そうに手元を眺めていた。
けれど黄葉とその足許の植物が、周太の心を惹きつけている。
メモを終わって周太の視線を追うと、きれいな赤い実をつけた木がたっていた。
「ナナカマドだ、」
楽しそうに植物の名前を教えてくれる。
周太の実家には、緑豊かな庭がある。周太の祖父が建てたという、木造の古い家だった。
古くても端正な家は植物に囲まれて、木肌の焦茶と白壁が緑に映えて美しい。
この隣の穏やかな静けさが育ったことが、頷ける家だなと英二も思う。
そんなふうに植物に囲まれて育った周太は、自然が好きらしく、花や木の名前を知っていた。
「ヨウシュウヤマゴボウ。これで布が染められる」
黒紫の実を眺めて、微笑んでいる。
懐かしそうに、けれど微笑んだまま、英二を振り向いて教えてくれた。
「父がね、山で教えてくれたんだ」
周太の父は、妻と息子を山に連れて、休日を過ごしたらしい。
アルバムにも山頂で撮られた、かわいい笑顔の写真があった。
13年前までの幸福な記憶を、こんなふうに笑顔で、話してくれている。
少し前まで、13年前までの幸福な記憶は、周太の心の傷にもなっていた。
それでも、警察学校の山岳訓練の時で少しだけ、周太は父の幸せな記憶を話している。
怪我をして背負われた英二の背中に、幼い日に父に背負われた記憶を重ねて、口を開いてくれた。
あのときと、今と。
話してくれる声もトーンも、同じようで全く違っている。
そして表情は、ずっと明るくて幸せで、きれいになった。
すこしは自分も、周太のために、生きられているのだろうか。
そんな想いの中心で、きれいに笑って草木を眺める笑顔が、愛しかった。
唐松谷林道を分岐まで降りて、野陣尾根へと入った。
登山道からすこし逸れる、隠された道を辿って、あの場所へと戻る。
ブナの巨樹を見あげて、黒目がちの瞳が微笑んだ。
「今日も、きれいだな」
「ああ、今日が一番きれいで、この秋の最後かもな、」
ブナの木を眺めて倒木に座る。木洩日の光が昨日よりもやわらかい。
また少し、秋が梢をおだやかに変えていた。
オレンジ色のパッケージから一粒、周太は口に含んだ。さわやかな甘い香が、森の香と馴染んでとけていく。
「俺もほしいな、」
笑いかけると、周太は困ったような顔になった。
掌の空になったパッケージを見せて、英二を見上げる。
「ごめん、最後の1個だった…下山したら買うな?」
謝られて、わざと英二は少し拗ねた顔をしてみせた。
「今、ほしいんだけど?」
「…ごめん、」
どうしようと黒目がちの瞳が困っている。
ふっと笑って英二は、周太の頬にそっと掌をよせた。
「謝らなくていいよ、もらうから」
「…え、?」
見上げる唇に唇をよせると、英二は深く重ねた。
「…っまって、」
驚いたままの唇はやわらかくて、そのままほどけて受け入れてしまう。
温かな感覚の底で、かわいいなと英二は微笑んだ。
かすかに視界を開くと、目の前の瞳は瞠いたままでいる。
その瞳には今、自分しか映っていない。それが英二には嬉しい。
甘さとガラスの様な感触をみつけて、英二はそっと唇を離した。
「ありがと、」
口の中で甘さを転がしながら、英二は笑った。オレンジの甘い香りが、英二の口許からこぼれる。
呆然としたままの隣は、赤くなるのも忘れて英二を見つめている。
その顔をのぞきこんで英二は微笑んだ。
「この飴、なんだか随分と甘いな、周太?」
たちまち目の前の顔が真っ赤になっていく。
かわいいなと英二は微笑んだ。
「返してほしい?」
ほら、もう真っ赤だ。そんな隣の反応が、かわいくて、楽しくて仕方ない。
こんなふうに、いつものように、予想した通りに初々しい。
うれしくて、英二は笑っていた。
けれど意外なことが起きた。
「…ん、かえして」
ぼそっと呟いて周太は、そっと唇をよせた。
端正な唇に、やわらかな唇が重なる。
ぎこちなく含まされる熱、困ったように探る温もり。
蕩かされていく
そんな熱にうかされて、英二はされるがままになっていた。
「…ない、」
離れて、困ったような真っ赤な顔が、ぼそりと言った。
可笑しくて、幸せで、英二は笑った。
「ああ、俺、すぐ飲みこんだから」
「…え、」
周太の意外な行動が、英二はうれしかった。
うれしくて、幸せで、止めてほしくなくて。
それで英二は、飴を飲みこんでしまった。
生真面目ですこし頑固な周太、「返して」と言ったらその通りにしようとする。
返してもらうまで、頑張って探そうとするだろう。
探す時間を引き延ばすには、探し物を消してしまえばいい。
悪戯っぽい目で、英二は教えた。
「だって見つけたら周太、すぐ止めただろ?」
「…ん、」
「気持ちいいから、止めてほしくなかったからさ。見つけられたくないから、飲んじゃった」
ほら、今度こそもう真っ赤になる。
今頃になって、自分のしたことに途惑っている。
こんなに赤くなって大丈夫なのかな。そう思いながらも、つい英二は言ってしまった。
「こういうキスも周太からは、“初めて”だね」
言われて、困っている。
けれど、黒目がちの瞳があげられて、真直ぐに見つめてくれた。
その瞳が、英二が見たことのない表情で、こっちを見ている。
どうしたと目だけで訊くと、物言いたげな唇が開いた。
「…初めては全部うれしいから…」
きれいに英二は、笑った。
「うん。俺こそ、うれしいよ」
おいで、と長い腕を伸ばして、そっと抱きしめた。
昨日も今日も、このブナの下で。いったい、どれだけ幸せだったろう。
あの日。報復の孤独へと周太が引き摺られかけた日。
もし15分を遅れていたら、こんな幸せを自分は知らないままだった。
そしてこの隣を、孤独のままに冷たく終わらせていた。
そして今日は、あの日からちょうど、1週間の日。
あの日に刻まれた周太と自分の傷は、もうこんなふうに癒えている。
もしも自分が、男ではなく、警察官ではなく、山ヤで山岳救助隊員ではなくて、ここに居なかったら。
どれが欠けてもきっと、あの15分で間に合った瞬間に、周太を掴まえられなかった。
自分が自分で、良かった。
こんな今の自分を与えられている、そういう自分で良かった。そんなふうに思える。
そして想ってしまう、願ってしまう。
こうして全てをかけるなら、きっと自分は、この隣を抱きしめ守って、生き続けていけるだろう。
卒配期間が終わって、初任科総合が終わって、本配属になる。
そのときにきっと、辛い運命と冷たい真実が、周太の前に現れる。そのことを、自分も周太の母も、もう知っている。
周太が、父親の軌跡を辿ることを望む以上、その未来を避ける事は、もう出来ない。
そして自分は、周太が望む場所の隣で、離さずに、ずっと守り続けていく。
きっとその時は「警察官」という立場が、自分達を引き離す。
それでも自分は、どんな手をつかっても、この隣を守るだろう。
自分達を引き離そうとする「警察官」の立場すら、追いつめ利用して自分は離れない。
直情的で思ったことしか言えない、出来ない。
けれど自分の能力は要領が良い。そして正直であるほどに、周りは自分に手を差し伸べる。
だからきっと大丈夫。
昨日から結んだ、いくつかの約束。その全てを自分は、果たすことが出来るだろう。
この隣への想いが、自分の生きる理由と意味。生きている限りずっと想い続ける。
どんな時でも自分は、必ずこの隣に帰る。ひとりになんかしない、一緒に生きていく。
もう自分は、名前を呼ばれて、求めてられている。
だからずっと自分は、この隣に帰って、守って微笑まられる。
抱きしめた隣に、英二は微笑んだ。
「愛してるよ、周太」
純粋な瞳が、そっと見上げて微笑んでくれる。
ほらもう、この隣はこんなにも、きれいに眩しくなっている。
だからきっと大丈夫。どんな場所に立たされても、この純粋さは誰にも冒せない。
目の前の瞳を見つめて、英二は微笑んだ。
「周太は、きれいだ」
ふわり、白いはなびらが舞いおりた。
黒目がちの瞳を、そっとかすめるように、やわらかな白がふってくる。
黄金の梢にかかる空から、あわい雪がしずかに降ってきた。
そっと英二は笑った。
「初雪だな、」
頬にふれる冷たさが、周太を微笑ませる。
微笑んだ唇がそっと開かれた。
「これも…初めてだな、」
「そうだな、」
純粋なこの隣を、自分はもう愛している。
そんな想いが温かい、英二は笑って、空を見あげた。
見上げる上空の、雲の流れは早い。すぐに雪は止んで、きっと晴れが戻るだろう。
念のために軽アイゼンは持っている、けれど使わずに済みそうだった。
よかったと思いながら、英二は周太に微笑んだ。
「ココア、作ってやるよ」
草地を少し整地する。
昨日より、馴れた手つきで英二は作れた。
あわい雪を眺めながら、大切そうに周太はカップを抱えてくれる。
「温かいね、」
「だろ、」
笑った周太の顔が、心から愛しかった。
甘く湯気の燻らせるココアが、温かい。
ときおり降りてくる雪が、そっと隣の黒髪に舞う。
穏やかな静けさが、居心地が良い。好きなこの空気に、英二は微笑んだ。
昨日カフェで買ったブレッドの袋を、英二は取り出した。
トラベルナイフでブレッドに切れ込みを入れ、チーズを挟む。
クッカーで軽くあぶってから、周太に渡した。
「こんなことも出来るのか」
「うん、国村に教わったんだ」
頂きますと、ひとくち齧ると微笑んでくれた。
「ん、おいしい。すごいな、英二」
「よかった、」
こういう時間は好きだ、英二は心から微笑んだ。
すぐにやんだ雪と一緒に、また歩き出す。
もどった陽射に、豊かな梢は明るい秋の空気に佇んでいる。
すこしだけ水気を帯びた道の、落葉の香が清々しかった。
「あ、」
隣の声に英二は、周太の視線の先を追った。
陽のあたる枯葉の合間から、凛と青い花が咲いている。
そっと周太は傍に跪くと、英二を見あげて教えてくれた。
「りんどうだよ、英二」
田中の最後の一葉は、りんどうだった。
農家で写真家の田中は、生まれ育った御岳を愛し、国村を山ヤに育て上げた。
そんな山ヤの田中は、氷雨にうたれる青い花を、写真に納めて生涯を終えた。
あわい初雪のなか、青く輝いた、りんどうの花。
あの氷雨の夜に背負った、美しい山ヤの生涯と、自分の想いが温かい。
そうして、凍える雪にも凛とした花姿に、この隣を重ねてしまう。
きれいに英二は、笑った。
「きれいだ、」
初雪がふれば、奥多摩は眠りの準備に入る。
そうして山ヤの警察官は、雪山での活動に入る。
英二にとって初めての、雪山での山岳救助と山ヤの生活が始まる。
奥多摩交番に戻ったのは14時だった。
日原林道から野陣尾根、唐松谷林道と報告をしていく。
全て終わると、後藤が楽しげに休憩室へと誘ってくれた。
「俺も今日は、ちょうど上がりだから」
そう言いながら、ミズナラの樽で醸造されたウィスキーを出してくれた。
周太には水割りで渡してくれる。
その水は、日原集落の水場で汲んできた、湧水だった。
「おいしいです、」
「そうだろう?」
微笑んだ周太に、嬉しそうに後藤は笑いかけた。
英二にはロックで渡してくれる。
「日原の秋は、どうだったかい?」
「はい、目の底が染まりそうでした」
「そうか、そんなにか、」
そんなふうに話していると、後藤の携帯が鳴った。
ちょっとごめんよと出て、少し話すとすぐに切る。
そのまま後藤はもう、ミズナラの酒のロックを作り始めた。
「今すぐな、俺の酒仲間が来るよ」
5分ほどして現われたのは、吉村医師だった。
ミズナラの酒を受取りながら、吉村は微笑んだ。
「往診の帰りに寄れと、きのう連絡をくれたんですよ」
笑いながら後藤が吉村を見た。
「だってなあ、吉村も一緒に飲みたかっただろう?」
「はい、そうですね。ご一緒出来て嬉しいです」
後藤は北国の出身だった。
高校時代から山ヤだった後藤は、高卒で警視庁警察学校に進んでいる。
そして、山ヤの警察官として奥多摩交番に配属された。
第七機動隊山岳救助レンジャーとして離れた時期もあるが、警察官の生涯の大半は奥多摩だった。
「吉村とは、俺が最初にここへ赴任した時からだな」
「そうですね、私の実家が、こちらですから」
吉村は奥多摩出身で、若い頃から地元の山に親しんでいる。
10年前に地元に戻って開業医となり、青梅警察署の警察医になった。
その前は医科大付属病院の教授として勤務している。
「では30年来の飲み仲間ですか?」
「そうだな、もうそんなになるか」
そんな話をしながら、ゆっくりとミズナラの香を楽しんだ。
吉村と周太が話す様子に微笑みながら、後藤は英二に訊いた。
「あの木な、元気にしていたかい?」
「はい、黄葉がとても綺麗でした」
そうかと微笑んだ後藤の顔が、懐かしそうで、英二は切なくなった。
―あのブナはな、かみさんを最初に山へ連れていった時、見つけたんだ
けれどもう俺は行かない。だから誰かに座って欲しかった
大切な人がいる。そういう奴に、あのブナを譲りたかったんだ
3年前に妻を亡くした後藤は、そんなふうに英二に話してくれた。
そんな後藤の気持ちが、英二は心から嬉しい。
けれどこの事について英二は、後藤に訊いてみたいことがあった。
でも訊いていいのか解らずにいた、今が良い機会なのかもしれない。
「副隊長に俺は、ずっと訊きたい事があります」
「おう、なんだい?」
気さくに笑って、後藤は促してくれる。
口を開いてしまったら、英二は基本止められない。
そんな俺でも受けとめてくれたらいいな、思いながら英二は微笑んだ。
「俺は率直にしか話せません、失礼を先にお詫びします」
「ああ、構わんよ。宮田のそういうところは、俺も好きだぞ」
微笑んで後藤は、英二の目を見てくれる。
真直ぐ見つめ返して、英二は訊いた。
「あの場所の事です。なぜ、国村に譲らなかったのですか」
国村は、才能あるクライマーとして、ファイナリストの素質を嘱望されている。
英二と同年の国村だが、高卒で警察官となり4年の長がある。そして山は18年のキャリアを持つ。
トップクライマーだった両親と田中の薫陶で、5歳から山ヤの経験を積んでいた。
そうして生粋の山ヤに育った国村は、純粋無垢な山への想いに生きている。
そんな国村は、山を甘くみる遭難者への怒りを隠さない。
冷静沈着だけれど大胆不敵、自由人で厳しい。そして山ヤらしい快活さが底抜けに明るい。
そんな国村は山ヤとして美しい。だからこそ、山岳救助隊員の全員が、国村のことを大切にしている。
そして後藤は国村のことを、本当に可愛がっている。
先日の不用意な道迷い遭難の夜間捜索でも、遭難者よりむしろ国村の心配をしていた。
そういう国村になら、あの場所を譲っても不思議は無かった。
笑って、後藤は答えてくれた。
「うん、あいつはな、もう昔から、自分の場所を持っているんだよ」
だから俺から譲る必要が無いんだ。
そう言って後藤は、グラスに口をつけた。
そうして深い目を微笑ませ、英二を見つめながら話してくれた。
「国村のことは、生まれた時から知っているよ。あいつの両親とはな、山ヤ仲間だったんだ。
その両親にな、まだ5歳のあいつを、雲取山へ登らせると言われた時は、俺も驚いた。
5歳児の脚では、とても無理だと思った。だからな、両親がおんぶしてだろうと思っていたよ」
雲取山は標高2,017.1m。東京の最高峰になる。
低山であっても、急峻な道も多く遭難者も出る。決して甘いコースとは言えない。
「でもなあ、あいつ、自分の脚で登ってさ、ちゃんと自分で降りて来たんだよ」
「5歳で、ですか」
そうだと頷いて、後藤は続けた。
「まだ5歳なのにと、俺も本当に驚いた。それでその時にな、俺は国村に訊いたんだよ。辛くなかったかとね」
あいつなんて言ったと思うかい?
そう首を傾げてから、後藤は破顔した。
「自分ちの山で仕事手伝うより、ずっと楽だ。ただ歩くだけなのに、楽しかったよ。そう言ってな、飄々と笑ったんだ」
国村らしい答えだった。
痩身だけれど国村は、持久力とパワーが並外れている。
体力をつけるコツを訊いた英二に「休日は農業やるからじゃない」と国村は答えた。
あいつ5歳の頃から変わっていないんだ。そう思うと英二は可笑しかった。
「国村らしいです、」
「だろう?」
後藤も楽しそうに笑った。
「俺もなあ、5歳で山仕事を手伝わせて、体力をつけたとは予想外だったよ。
国村の家の山は、急斜面で険しいんだ。それを4歳頃には自力で登っていたらしい。
そうやってな、あいつはずっと山で生きている。それでどうも、特別な場所を子供の時から、持っているらしいんだ」
「ああ、国村ならきっと、そうです」
「だろう?」
頷いて、温かな目を英二に向けてくれる。
グラスを啜って後藤は、真直ぐに英二を見て微笑んだ。
「あの場所、彼は気に入ったのかい?」
はいと頷いて英二は答えた。
「ずいぶん長い時間、ブナの水音を聴いていました。
それから見上げて『こんなふうに静かに穏やかに生きられたらいい』そう言っていました」
後藤の目が、嬉しそうに笑っている。
静かに頷いて、ほっと息をつくと後藤は言った。
「きれいな瞳の通りに、純粋なのだな」
「はい、」
きれいに笑った英二に、ゆっくりと後藤は頷いて、温かく微笑んだ。
「大切にするといい、あの場所も、彼も」
やっぱり後藤は解っている。
そしてあの場所へ、連れていくに相応しいと認めてくれた。
自分達の繋がりが理解され難いことを、英二はよく知っている。
最上級の山ヤである後藤に、受けとめてもらえた。うれしいと心から英二は笑った。
「はい、ありがとうございます」
きれいに笑って、英二はミズナラの酒を飲みほした。
(to be continued)
【歌詞引用:savage garden「truly madly deeply」】
blogramランキング参加中!
ネット小説ランキング
http://www.webstation.jp/syousetu/rank.cgi?mode=r_link&id=5955


















