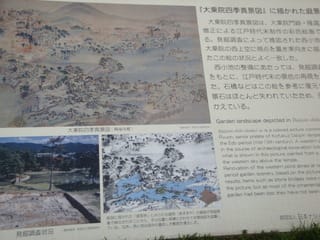奈良町を歩いた後、午後3時頃に奈良ホテルに着きました。
奈良町の東側、奈良公園の高台にあり、周辺のあちこちから独特のクラシックな建物が見上げられます。
1909(明治42)年に「関西の迎賓館」として創業しました。
京都の都ホテルを創業した西村仁兵衛が明治39年、眺望に恵まれた高畑町飛鳥山を坪1円で買収し、山を削って、辰野金吾設計で桃山御殿風檜造りの和洋折衷の建物ができあがりました。ホテルの経営は、大日本ホテル株式会社から大正2年5月には鉄道院に移りました。大正2年から昭和20年までは鉄道院の、言わば国営で、利潤に追われることなく、多くの外国からの賓客や、皇族や首相達が来館しました。
戦後は昭和27年まで米軍の接収を受け、財団法人日本交通公社が営業を委ねられました。昭和31年から58年までは株式会社都ホテルが経営、昭和58年からは国鉄と都ホテルの50%ずつの出資による株式会社奈良ホテルが設立、以来、営業を続けています。
堂々とした玄関。
宿泊棟です。鬼瓦は東大寺大仏殿などでも見られる鴟尾(しび)です。
玄関車寄せの中は和風の格天井になっています。
玄関を入ったところのフロントロビー。
フロントロビーの天井も吹き抜け格天井、二階の欄干が取り囲んでいます。
フロントロビーに鳥居形のマントルピース(暖炉)と、その横に上村松園の「花嫁」が掛けられています。
マントルピースはほとんどの本館客室に備え付けられていて、大正初期まで使われていました。
「花嫁」の絵は、鉄道省観光局が、観光日本宣伝のために昭和10年頃ポスターに使用した作品です。この他、館内には数多くの絵画や芸術作品が掛けられていて、超一流の美術館になっています。
奈良ホテルのジオラマがありました。
一階奥の部屋はバー、その前には奈良ホテルと牛乳石鹸の創業が同じ年だったという縁で、鹿デザインの牛乳石鹸箱が積まれていました。
二階に上がる大階段の親柱の擬宝珠は、元は真鍮製でしたが、戦時中に供出したため、代用品として奈良の伝統工芸、赤膚焼で製作されました。
売店でも売られている石鹸をお土産にもらいました。
ティーラウンジ。
ロビー「桜の間」。
この部屋に1922(大正11)年にアインシュタインがひいたというピアノがありました。ピアノの脚部に鉄道省の動輪マークがあります。
廊下の展示コーナーに、これまでにホテルで使われていた食器やカトラリー、宿泊した客の写真、ホテルの歴史が展示されていました。
二階に上がる階段。改修により、エレベーターもあります。
階段から廊下には全て赤い絨毯が敷き詰められています。
窓からは若草山の丘と満開の桜が見えました。
廊下の各所にあるスチーム暖房のラジエーター。
1914(大正3)年から全館セントラルヒーティングになり、今も使われています。細かく美しい模様が刻まれています。
非常時にドアを壊して脱出するためのものか、つるはしが備え付けられていました。
宿泊室の内部。天井が高い和風の造りになっています。
ここにも暖炉があります。
夕食は、メインダイニングルームの「三笠の間」は改修工事中で使えず、新館の「金剛の間」でいただきました。新型コロナウィルスの感染防止のため、ビュッフェ形式ではなくフレンチ・コースとなりました。
オードブル。
ポタージュスープ。
海の幸のパイ包み焼き、シャンパンソース。
国産牛フィレ肉の一皿、温野菜添え、チャコールソース。
デザート、コーヒー。
翌朝の朝食は洋食と和食と茶粥朝食の中から選べたので、茶粥朝食をいただきました。
奈良ホテルが3月末まで改修工事をしていたため、通常よりも格安のプランがあり、一生に一度の贅沢な一夜を過ごすことができました。