「近代化遺産全国一斉公開2006」の一環として「近江八幡の近代化遺産見学会~ホフマン窯とヴォーリズ建築」の募集があり、参加させていただきました。
中川煉瓦製造所は八幡堀の続き、琵琶湖への水運が利用しやすい場所に窯を築き、1883(明治16)年から1967(昭和42)年まで煉瓦を製造していました。
ホフマン窯の大きな煙突。高さ30メートルもあります。
ホフマン窯というのはドイツ人フリードリッヒ・ホフマンが改良したもので、複数の窯を順繰りに使って煉瓦を焼けるようになっていて、輪窯、輪環窯、丸窯ともいいます。煙突の周りを窯が取り囲んでいるものが多いようですが、ここのは直線の窯の横に煙突がついているものでした。横幅14メートル、長さは55メートルです。
長い窯の内部をいくつかの区画に区切って一つの区画毎に煉瓦を積んで焼いて行きます。出来上がった区画の煉瓦を取り出して、すぐ次の区画で焼くことができ、隣の熱が伝わって次の区画も温度が上がりやすく、効率的にできています。
元は覆いの屋根があったのですが、今は野ざらしになっているので、雨水が窯の内部まで入ってきています。
煉瓦がもともとは土からできているもの、植物がなじみやすく窯の上部には草木が生い茂り根を張ってきています。屋根をつけるなどしなければ、保存が危ぶまれます。
煉瓦が崩れやすくなっているので、見学者はヘルメットをかぶって窯に入ります。
入り口。
窯の内部の高さは3.2メートルです。
仕切りの壁。
煉瓦を焼く時にはこのように間をすかして組み上げ、熱が行き渡りやすいようにしました。
天井に所々穴が開いていて、そこから粉炭を投げ入れて燃やしたのだそうです。
機械場跡。
事務所跡。今年6月に壁の煉瓦が一部崩れ落ちたそうです。
保存の手立てを早くとらないといけません。
縄縫工場跡。煉瓦を運ぶための縄を製造していました。
昔の中川煉瓦製造所の様子。
煉瓦を乾燥するための木造の乾燥場もたくさん並んでいます。
ホフマン窯、機械場、事務所、縄縫工場とも1916(大正5)年頃の築で、国登録有形文化財に指定されています。
今は敷地内で老人ホームを経営しておられる中川氏が小さい頃に煉瓦を焼いている窯の上で遊んだ思い出とか話してくださり、近代化遺産活用連絡協議会の方達が休業してから一度だけ煉瓦を焼いたことがあるけれど、また火を入れてみたいという願いとか、機械場等も何かに活用して保存していきたいというお話をされていました。






















 でしたが、雨が降るまでに行けるだけ行こうと思って自転車で駆けつけると、
でしたが、雨が降るまでに行けるだけ行こうと思って自転車で駆けつけると、




































 が本降りになってきたので、スタンプ3個集めたここでリタイア
が本降りになってきたので、スタンプ3個集めたここでリタイア (お手上げ)、最後の三条通りにある車石碑は見ることができませんでした。
(お手上げ)、最後の三条通りにある車石碑は見ることができませんでした。










 。
。












 になっていました。ぽっちりとはかわいいもののことで、舞妓さんの帯留めのことを指すそうです。
になっていました。ぽっちりとはかわいいもののことで、舞妓さんの帯留めのことを指すそうです。

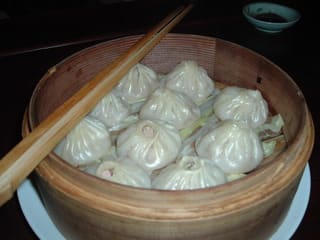








 、左側が教育会館
、左側が教育会館 。共に1931(昭和6)年の建築で、国の登録有形文化財です。
。共に1931(昭和6)年の建築で、国の登録有形文化財です。






































 らしきのもありました。
らしきのもありました。










