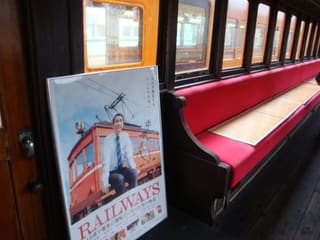平成の大改修中の姫路城天守閣を真横から見学できる見学施設
『天空の白鷺』は2014年1月15日までで終了します。改修工事は2009年10月の着工から2014年まで丸5年かけて行われ、これから素屋根や足場を撤去していく予定なので、見学ができなくなるのです。
開催中に何とか間に合って見に行くことができました。

修理期間中、天守閣はすっぽりと鉄骨と屋根の覆いの中に入っています。

かっこいい「菱の門」を通って、

高い石垣の曲線を眺めて、

「天空の白鷺」の建物の中に入ります。
1階から8階までエレベーターで上がるのですが、その待ち時間がいきなり行くと1~2時間になることもあるというので、予め予約して行きました。
ところが、この日は雨だったせいか、エレベーターの前はこの状態で、全然待ち時間なしで見られました。
この後15日が近づいて来たらまた混雑するかもしれません。

8階に上がると、天守閣の最上層、5層の大屋根がガラス越しに目の前に現われます。
大迫力です。

もう修理の仕事はほぼ終わっているので、工事の人の姿はありませんが、もっと前なら瓦職人さんや左官さんが働いているのが見えたことでしょう。

階段で7階に下りると、一つ下の層が見えます。
白鷺城と言われるのは、屋根瓦の一つ一つの端が漆喰で塗り固められているので、白い部分がたくさん見えるからでしょう。

漆喰壁の塗り見本。
左から右へ、木に縄を絡めた下地の上に土壁、漆喰壁と何層にも塗り重ねていくのがわかります。

天守閣の高さから姫路市街を眺めたところ。
雨天の上に、ガラス越しで室内の景色が写りこんでしまって、お見苦しくてすみません。

西の丸を眺めたところ。

西の丸には、本多忠政が息子忠刻と千姫の居館として建てた御殿がありましたが、今は百廊下と化粧櫓だけが残っています。百間廊下は奥女中や家来達が居住した長屋廊下、化粧櫓は千姫が毎日百間廊下から男山天満宮を参拝する時に休憩した部屋です。

化粧櫓の中に千姫の人形がありました。

乾曲輪に今話題の黒田官兵衛ゆかりの瓦がありました。
中央の円い鬼瓦に十字模様が描かれていて、キリシタンだったという官兵衛に関係するものと言われています。
「ひめじの官兵衛 大河ドラマ館」なるイベントが1月12日から2015年まで開催されるらしく、今年の姫路は「官兵衛」で盛り上がることでしょう。