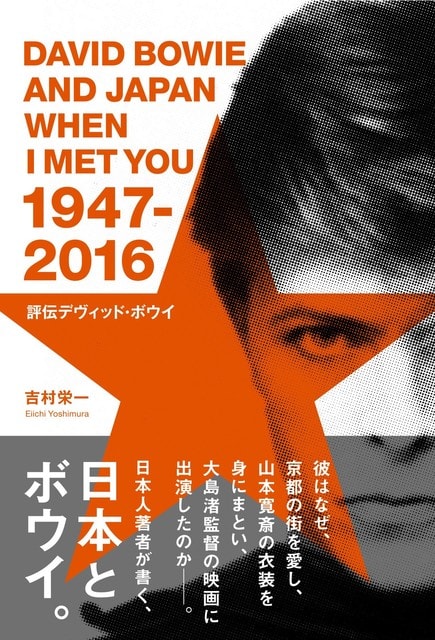
デヴィッド・ボウイの人生と作品を回顧する展覧会「DAVID BOWIE is」の売店で購入した。デヴィッド・ボウイの伝記的な本はたくさん出ているが、とくに日本とのかかわりについて書いてあるこの本が気になって選んだ。読んでみると、新聞記事調で出生から死亡までの出来事や活動が過不足なく淡々と記述されている。日本とのかかわりについては様々な局面が確かに書かれてはいるのだが、私としては京都とのかかわりについてもっとたくさんページを費やして記述してほしかった。また、筆者の個人的なボウイへの熱い思い入れが感じられず、淡白すぎる文章には物足りなさも感じるが、きっちりと事実関係が書かれた記録としての価値はあるのだろう。
本書の中で、とくに興味を感じたところ、おもしろかったところを下記にまとめた。
・ボウイはバイ・セクシャルとしてのイメージがあるが、それはプロモーションのための作られたイメージのようで、「ハンキー・ドリー」時代に行ったゲイ宣言は妻のアンジーのアイデアだという。だからこの本の中にも、男性の恋人はいっさい出てこない。
・もともと飛行機嫌いで、1973年4月5日の初来日の時は客船オロンセイ号でロスアンジェルスから横浜港大さん橋にやってきた。その後、飛行機嫌いは克服している。
・「ロウ」を出した後の1977年にプロモーションで来日したとき京都にも行き、このころからボウイの京都愛は始まった。京都の定宿は俵屋旅館、好きなそば店は晦庵河道屋(みそかあんかわみちや)、散策したのは東山の古川町商店街、鰻の蒲焼を野田屋で買った。このあたりに行けば、ボウイの足跡をたどれるのだろう。また、よく行ったライブハウスは「礫礫」や「クラブ・モダーン」であった。東山の九条山に住んでいたという都市伝説があったが、そこに住んでいたのは友人で名前の似たデヴィッド・キッドという中国文化を研究する米国人で、ボウイはそこに泊まることはよくあった。だからボウイは京都に家まで持っていたわけではない。
・ボウイの音楽はニューウェイヴの出現に大きな影響を与えた。私は「スケアリー・モンスターズ」あたりがニューウェイヴの音楽的原型になったと思っていたが、このアルバムの発売は1980年なので、1970年代後半に出現したニューウェイヴよりタイミング的にすこし後になる。筆者の吉村によれば、ニューウェイヴ・バンドの多くはジギー・スターダストを観て音楽に目覚め、その後の「ヤング・アメリカンズ」「ロウ」といった変身するボウイを目の当たりにして、音楽に常識は必要がないということを信じた世代で、自由な発想で斬新な音楽を次々と生み出した、と述べている。一方のボウイも、ニューウェイヴ・バンドが好きだったようで、ボウイが会場で目撃されたライブや会っていたアーティストとして、ヒューマン・リーグ、ブロンディ、トーキング・ヘッズ、スージー・アンド・ザ・バンシーズ、クラッシュ、ジョー・ジャクソン、ゲイリー・ニューマン、ブームタウン・ラッツのボブ・ゲルドフが挙げられている。ヴィサージのスティーブ・ストレンジは「アッシェズ・トゥ・アッシェズ」のPVに出演している。ボウイとニューウェイヴ・アーチストたちは双方向に影響し合っていたようだ。
・ローリング・ストーンズのビル・ワイマンは、ニュー・オーリンズの音楽に東洋や沖縄音楽の要素をミックスした「泰安洋行」など細野晴臣の音楽に夢中になっており、ボウイに紹介したところボウイも愛聴していたという。ロックへの民族音楽の導入の先駆けであったようだ。
・日本のアーティストとしては他に、サンディー・アンド・ザ・サンセッツが好きだった。ロンドンでサンディー・アンド・ザ・サンセッツが客演するジャパンのコンサートがあり、楽しみに会場に行ったところ、ジャパンのツアー・マネージャーから招待リストにボウイの名前がないと言って追い返されてしまった。それ以来、互いにへんなしこりができてしまったのだろうか。ジャパンは私が好きなバンドの一つだが、音楽やファッションは、グラム、ヨーロピアン、民族音楽趣味のところがデビッド・ボウイの影響を受けており、とくにボーカリストのデヴィッド・シルビアンは髪型、スタイル、ステージ上での動きなど明らかにボウイの真似をしていることがうかがえる。そんなデヴィッド・シルビアンは、ボウイへの追悼コメントの中で「僕はマニアじゃない。ボウイのアルバムはもう何十年も聴いていない。非難もお勧めもお断りします」と書いている。大好きだったと言えばいいのに、相変わらずひねくれた人だ。
・1996年6月に日本ツアーが行われ、4、5日の日本武道館コンサートの前座は布袋寅泰だった。私はこの5日のコンサートを見に行ったが、訳あってコンサートの最初のほうしか見れていない。コンサートの途中で帰ることなど後にも先にもこの時くらいしかないだろう。










