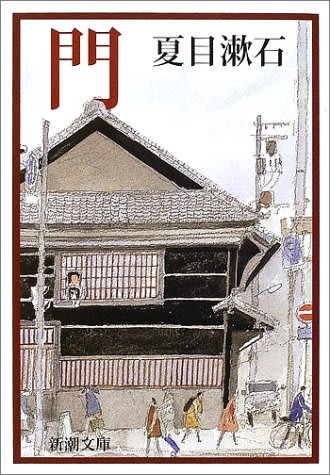
夏目漱石が鎌倉の円覚寺に参禅した経験を元に書かれたと言われているのが「門」である。
しかし、参禅についてのことが出てくるのはほとんど終わり近くになってからであって、それまでは日々の暮らしや出来事がずっと述べられていく。そのストーリーはざっと下記のようなものである。
家計は楽ではないが、主人公の宗助と妻の御米とはお互いに気遣いあう仲のよい夫婦である。宗助は役所に務めている。休みの日曜日には街中を散歩したりして息抜きをするが、どこか落ち着いた満ち足りた気分にはなれない。叔父の所に預かってもらっていた弟の小六の面倒を見てやらなければならなくなったのも気が重い。宗助はふと、歯医者の待合室にある雑誌「成効」の中にある「風碧落を吹いて浮雲尽き、月東山に上って玉一団(風が大空の浮雲を吹きはらうように迷いが晴れ、山の端を照らすわやかな月のように心が澄みわたるの意で、悟りの境地を表現した語)」と書いてあるのを読み、こんな心持とは最近無縁であるが、そうなれたら人間もさぞ嬉しかろうと思った(第五章)。いつも気持ちがどんよりと重いが、すっきりとしたらいいだろうなという希求があるのである。後半で禅に救いを求めることになる伏線である。
御米は自分に子供ができないことを苦にしていて、その原因は過去のある出来事にあると思っている(第十三章)。その過去の出来事とは、宗助が親友の安井を裏切って御米を奪って結婚したという事実である。そして二人でひっそりと暮らしてきたのだが、安井が近くにやってくることを宗助は聞く(第十六章)。そのことで宗助は大いに心を乱し、居ても立っても居られなくなる。それで心を楽にすることを求めて、鎌倉の禅寺に行く(第十八章)。しかし悟ることなどとてもできそうにないし、心がちっとも楽にならない。老師から言い渡された公案「父母未生以前本来の面目は何か」の答えを考えているとさらに心が苦しくなる。そして10日ほどで家へ帰ることを決める(第二十一章)。「自分は門を開けて貰いに来た。けれでも門番は扉の向側にいて、敲いても遂に顔さえ出してくれなかった。ただ、「敲いても駄目だ。独りで開けて入れ」という声が聞こえただけであった。(中略)けれどもそれを実地に開ける力は、少しも養成する事が出来なかった。」と宗助は思う。こうしてタイトルの「門」の意味するところが示される。家に帰ったら、安井はもういなくなったという。禅寺で心を楽にすることもできなかったが、心を苦しめていた原因もなくなった。しかし、このような心を乱すことはこれからもまた起きるかもしれないと宗助は思って、「門」は終わる。
最後の解説で柄谷行人は、「門」を三角関係を中心に分析していて、奪い取った相手を今度は憎むようになるという心理学的な解釈を述べているが、そういうフロイト的な要素もこの本にはあるのかもしれないが、それは本質ではないと思う。漱石はおそらく三角関係にこだわりがあったので、それを取り上げて書いているのだが、三角関係のみならず様々な事柄によって、過去に罪悪感を感じたり後悔の念を持ったり、将来に不安を抱いたりするものである。そうした心の中の苦しみを解消するために禅に行きついたのだが、やってみたら到底歯が立たなかったという話である。しかし、漱石は「門」の中で禅について相当深く理解しているような記述をしていると思った。「門」を突破できなかったにしても、ずいぶんその近くまで来ていたように思う。病弱で50歳で亡くなった漱石にとって、門を突破するためには、健康ともう少し長い寿命が必要だったのかもしれない。ちなみに、宗助は禅寺で「剽軽な羅漢の様な顔をしている気楽そうな」居士(在家修行者)に会うが、これは鈴木大拙のことだという。









