
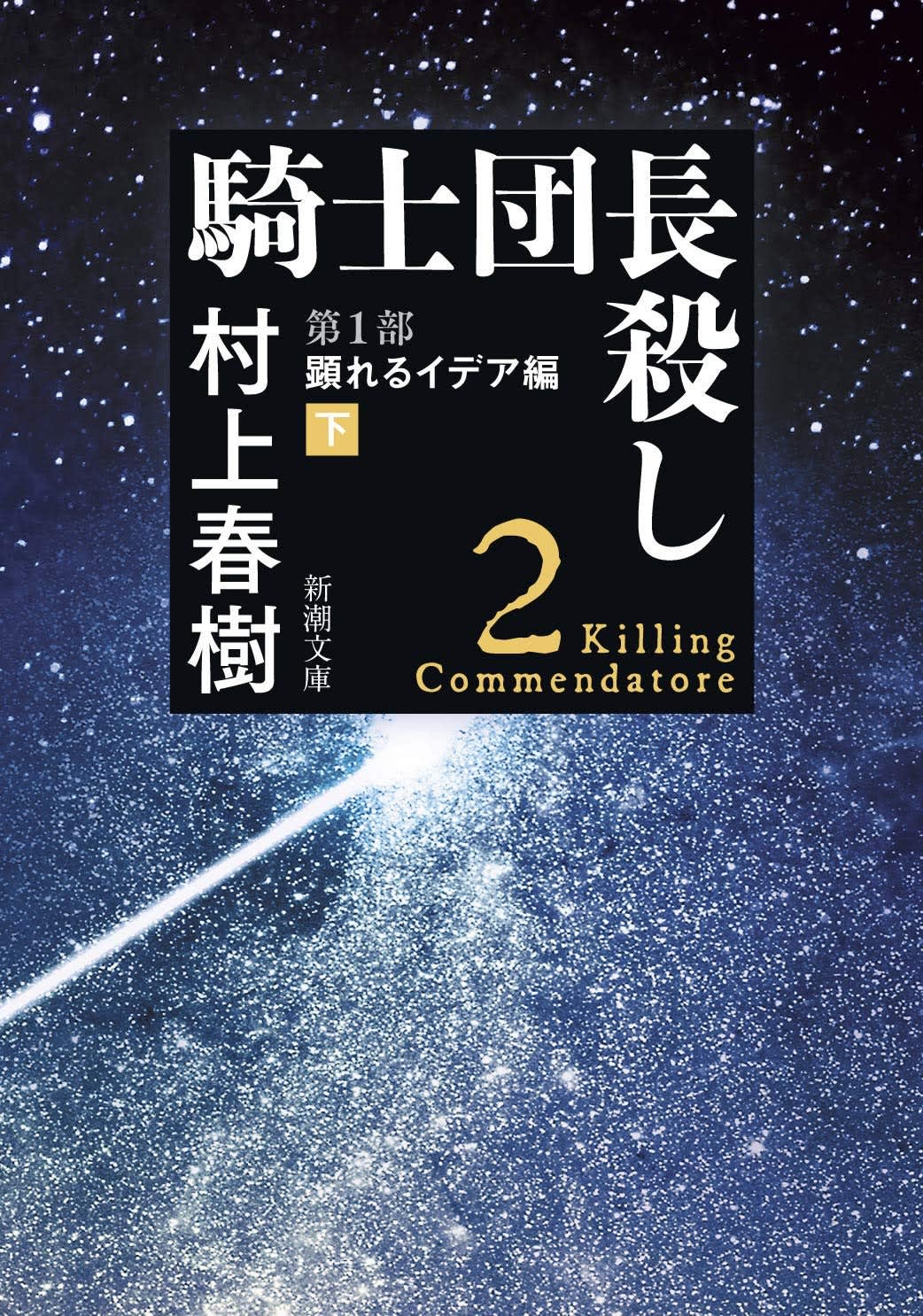

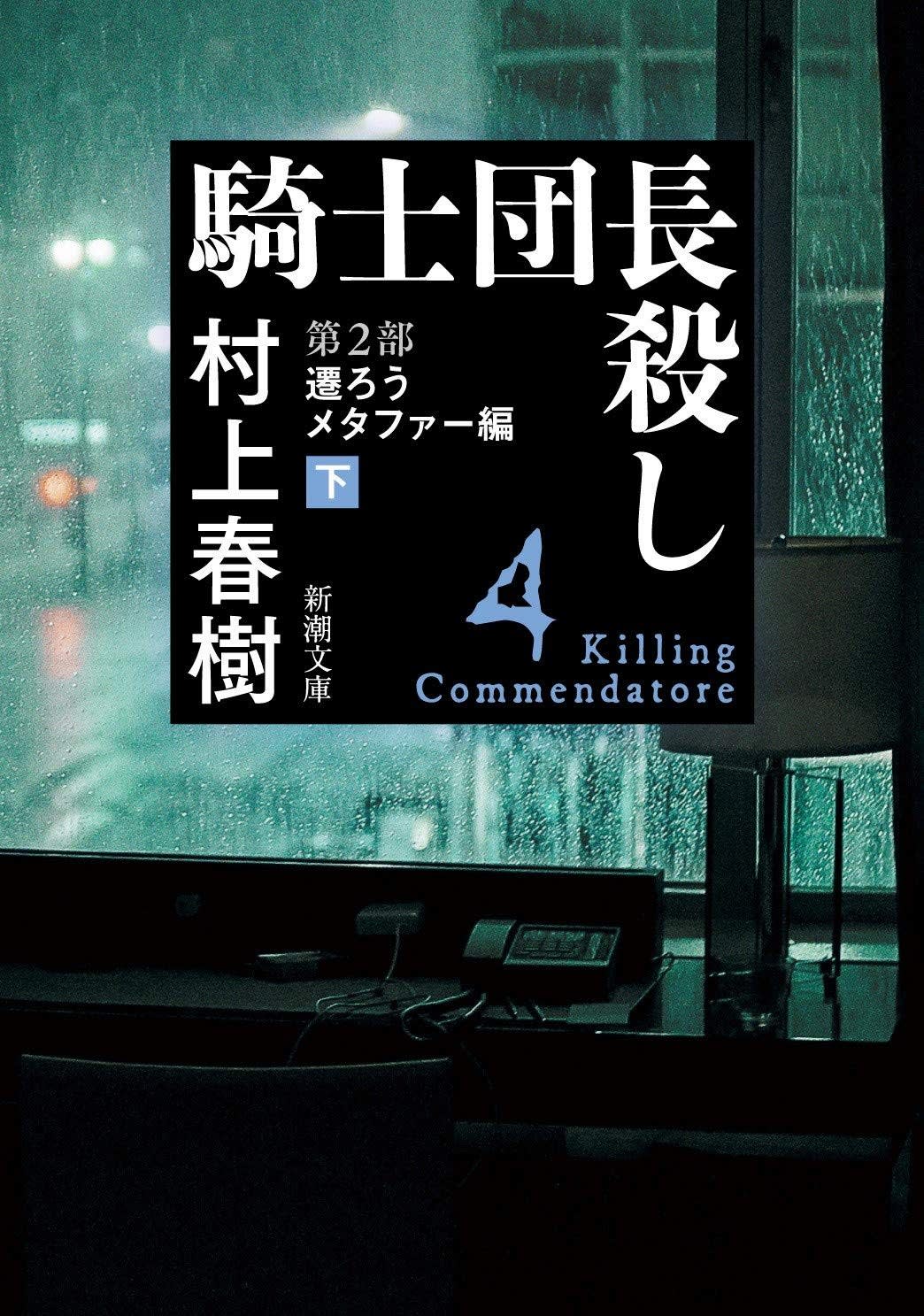
30代の肖像画家の男が、妻と離婚し再びよりを戻すまでの9カ月間に起きた物語である。その期間のことを思い返す形で文章が書かれている。主人公は「私」であり、名前は示されない。旅、身近な人の死、セックス、人生あるいは世界の謎が出てくるところは、これまでの村上長編小説のスタイルに則っている。離婚の原因である妻の不義に心を痛め、長旅を経て、新しい家でなんとか新しい生活を始めようとする。ところが、その家で予想もつかない様々な不思議な出来事が起きていき、非現実が現実を侵食していく。そして現実的な平穏が戻ってきたところで、妻とよりを戻して物語は終わる。
重要なモチーフは重層的であり、絵画であったり、第二次世界大戦がもたらした人間の不幸であったり、自らの心の奥にあるどす黒いものであったりするのだが、複雑な舞台装置の陰から浮かび上がってくるテーマは、親が子を残すということではないだろうか。それは、子供への無上の愛についてでもあるし、自らの遺伝子を残すということについてでもある。これまでの村上春樹の小説ではあまりなかったテーマではないだろうか。さらに言えば、プライベートで実子を持たない彼がなぜこのことを書いたのか不思議な感じがした。あるいは、子供を持たないからこそ挑んだ、精神的な実験だったのかもしれない。「私」は「免色」という男に、親近感や連帯感を感じる。そして「私」はこう考える―「我々はある意味では似たもの同士なのかもしれない―そう思った。私たちは自分たちが手にしているものではなく、またこれから手にしようとしているものでもなく、むしろ失ってきたもの、今は手にしていないものによって前に動かされているのだ。(第1部下、p.235)」
結婚にも家族を持つことにもまったく関心のない人生を送ってきたはずの冷静で完璧な男「免色」は、自分の実の娘かもしれないが確証はない少女の存在を知り、その少女の様子を見ることだけに全ての精力を注ぎ込む生き方をしている。それは愛情なのか、本能なのかもわからない。「免色」は「私」にこう言う―「この世界で何を達成したところで、どれだけ事業に成功し資産を築いたところで、私は結局のところワンセットの遺伝子を誰かから引き継いで、それを次の誰かに引き渡すためだけの便宜的な、過渡的な存在に過ぎないのだと。その実用的な機能を別にすれば、残りの私はただの土塊のようなものに過ぎないのだと(第2部上、p.167)」
ここでは、自らの成功にはもはや価値を感じず、極端に生物学的な存在としてのみ自分の存在意義を見出すような精神に至っている。
一方で、「私」に部屋を貸してくれた「雨田」は高名な画家である父について述べる―「おまえにはDNAを半分やったんだから、そのほかにやるものはない。あとのことは自分でなんとかしろ、みたいな感じなんだ。でもな、人間と人間との関係というのは、そんなDNAだけのことじゃないんだ。そうだろ?何もおれの人生の導き手になってくれとまでは言わない。そこまでは求めないよ。しかし父親と息子の会話みたいなものが少しはあってもよかったはずだ。自分がかつてどんなことを経験してきたか、どんな思いを抱いて生きてきたか、たとえ僅かな木れっ端でもいい、教えてくれてもよかったはずだ(第2部下、p.36)」
自らの実の子を持っても、まったく興味を持たない親もいる。
「私」の元妻「ユズ」は妊娠して子供を産むことを決意する。その子の父親が誰なのかははっきりしないが、「私」は夢の中で明確に「ユズ」を身籠らせる行為をした。そして「ユズ」に対してこう言う―「ひょっとしたらこのぼくが、君の産もうとしている子供の潜在的な父親であるかもしれない。そういう気がするんだ。ぼくの思いが遠く離れたところから君を妊娠させたのかもしれない。ひとつの観念として、とくべつの通路をつたって(第2部下、p.356)」
そして、「私」は「ユズ」と夫婦に戻り、「ユズ」が生んだ子供「むろ」を育てる。
「彼女が誰を父親とする子供なのか、事実が判明する日が来るかもしれない。しかしそんな「事実」にいったいどれほどの意味があるのだろう?むろは法的には正式に私の子供だったし、私はその小さな娘をとても深く愛していた。そして彼女と一緒にいる時間を慈しんでいた。彼女の生物学的な父親がたとえ誰であっても、誰でなくても、私にはどうでもいいことだった。それはまったく些細なことなのだ。それによって何かが変更をうけたりするわけではない(第2部下、p.371)」
イデアやメタファーといったいかに観念的なものであろうと信じているのであれば、その子は自分への贈りものなのだと言って結んでいる。
現実には様々な親子のありようがあるが、子は親にとってかけがえのない宝物のはずだいうことを、メッセージとして伝えたかったのではないだろうか。
もし自分に子供がいたらきっとそう思うはずだと、村上春樹は言っているようにも思える。
重要なモチーフは重層的であり、絵画であったり、第二次世界大戦がもたらした人間の不幸であったり、自らの心の奥にあるどす黒いものであったりするのだが、複雑な舞台装置の陰から浮かび上がってくるテーマは、親が子を残すということではないだろうか。それは、子供への無上の愛についてでもあるし、自らの遺伝子を残すということについてでもある。これまでの村上春樹の小説ではあまりなかったテーマではないだろうか。さらに言えば、プライベートで実子を持たない彼がなぜこのことを書いたのか不思議な感じがした。あるいは、子供を持たないからこそ挑んだ、精神的な実験だったのかもしれない。「私」は「免色」という男に、親近感や連帯感を感じる。そして「私」はこう考える―「我々はある意味では似たもの同士なのかもしれない―そう思った。私たちは自分たちが手にしているものではなく、またこれから手にしようとしているものでもなく、むしろ失ってきたもの、今は手にしていないものによって前に動かされているのだ。(第1部下、p.235)」
結婚にも家族を持つことにもまったく関心のない人生を送ってきたはずの冷静で完璧な男「免色」は、自分の実の娘かもしれないが確証はない少女の存在を知り、その少女の様子を見ることだけに全ての精力を注ぎ込む生き方をしている。それは愛情なのか、本能なのかもわからない。「免色」は「私」にこう言う―「この世界で何を達成したところで、どれだけ事業に成功し資産を築いたところで、私は結局のところワンセットの遺伝子を誰かから引き継いで、それを次の誰かに引き渡すためだけの便宜的な、過渡的な存在に過ぎないのだと。その実用的な機能を別にすれば、残りの私はただの土塊のようなものに過ぎないのだと(第2部上、p.167)」
ここでは、自らの成功にはもはや価値を感じず、極端に生物学的な存在としてのみ自分の存在意義を見出すような精神に至っている。
一方で、「私」に部屋を貸してくれた「雨田」は高名な画家である父について述べる―「おまえにはDNAを半分やったんだから、そのほかにやるものはない。あとのことは自分でなんとかしろ、みたいな感じなんだ。でもな、人間と人間との関係というのは、そんなDNAだけのことじゃないんだ。そうだろ?何もおれの人生の導き手になってくれとまでは言わない。そこまでは求めないよ。しかし父親と息子の会話みたいなものが少しはあってもよかったはずだ。自分がかつてどんなことを経験してきたか、どんな思いを抱いて生きてきたか、たとえ僅かな木れっ端でもいい、教えてくれてもよかったはずだ(第2部下、p.36)」
自らの実の子を持っても、まったく興味を持たない親もいる。
「私」の元妻「ユズ」は妊娠して子供を産むことを決意する。その子の父親が誰なのかははっきりしないが、「私」は夢の中で明確に「ユズ」を身籠らせる行為をした。そして「ユズ」に対してこう言う―「ひょっとしたらこのぼくが、君の産もうとしている子供の潜在的な父親であるかもしれない。そういう気がするんだ。ぼくの思いが遠く離れたところから君を妊娠させたのかもしれない。ひとつの観念として、とくべつの通路をつたって(第2部下、p.356)」
そして、「私」は「ユズ」と夫婦に戻り、「ユズ」が生んだ子供「むろ」を育てる。
「彼女が誰を父親とする子供なのか、事実が判明する日が来るかもしれない。しかしそんな「事実」にいったいどれほどの意味があるのだろう?むろは法的には正式に私の子供だったし、私はその小さな娘をとても深く愛していた。そして彼女と一緒にいる時間を慈しんでいた。彼女の生物学的な父親がたとえ誰であっても、誰でなくても、私にはどうでもいいことだった。それはまったく些細なことなのだ。それによって何かが変更をうけたりするわけではない(第2部下、p.371)」
イデアやメタファーといったいかに観念的なものであろうと信じているのであれば、その子は自分への贈りものなのだと言って結んでいる。
現実には様々な親子のありようがあるが、子は親にとってかけがえのない宝物のはずだいうことを、メッセージとして伝えたかったのではないだろうか。
もし自分に子供がいたらきっとそう思うはずだと、村上春樹は言っているようにも思える。









