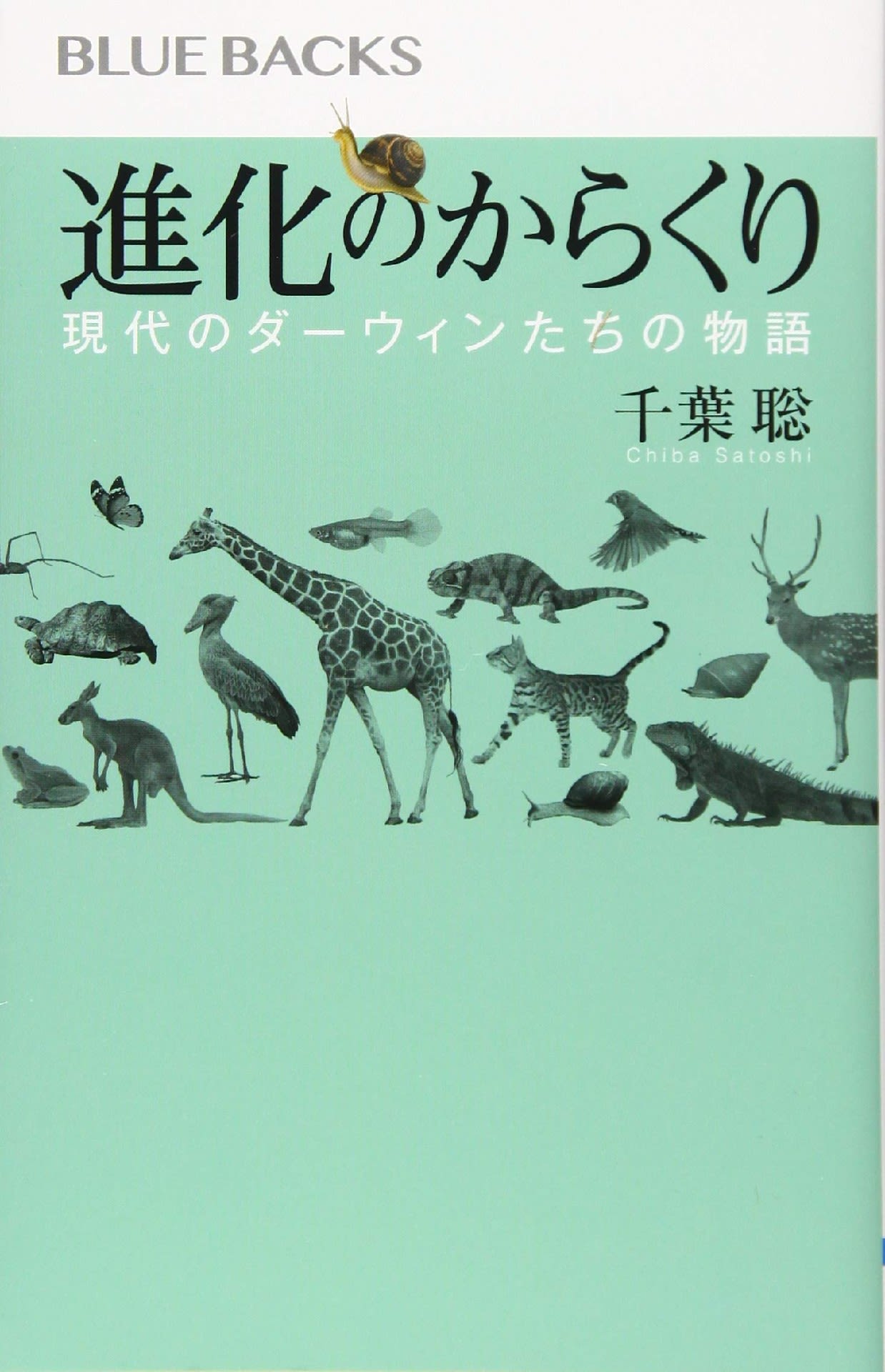
巻貝の進化を研究する東北大学教授の千葉聡博士と研究仲間をめぐる物語である。著者の千葉氏は、前著の「歌うカタツムリ」で毎日出版文化賞・自然科学部門を受賞しているだけあって、生物系の名文筆家である。巻貝というあまり目立たない生物を対象にした研究は、注目されることも少ないが、それでも進化生物学の謎の解明に斬りこんでいくためのよい材料になりうるということを示してくれている。巻貝の進化の研究者への取材レポートやエピソードなどがいくつか紹介されるが、彼らはみな著者の弟子であったことが、後のほうの章で次第にほのめかされていく。だから、千葉ファミリーという研究者グループの生態学という読み方もできる。また、著者は、古生物学(地学)からスタートして、のちに生態学者(生物学)となった変わり種であることも明かしている。
進化学はアカデミアの研究者だけで成り立っているわけではないという。「元々本書では、魅力的な研究成果を挙げながらも、偶然あるいは本人が望まなかったため、プロとしての活躍の場をアカデミア以外の世界に移した人々のストーリーも等しく取り上げるはずであった。だがいくつかの困難な問題があり、それは果たせなかった。強調しておきたいのは、科学への貢献こそが重要なのであって、その世界に籍があるか否かは些末な話ということだ。・・・プロとして科学や産業や社会に直接貢献することも素晴らしいが、プロにならずとも、良きファンとして科学を支えることはそれ以上に素晴らしいことだと思う」われわれのような、在野の進化学ファンにとってはうれしい言葉だ。
進化を考える上で、「種」とは何かは難しい問いであり、たくさんんの定義がある。しかし、有性生殖をする多細胞生物で、最も多くの場面で種の定義として採用されているのは、生物学的種と呼ばれる定義ー互いに交配できる個体からなる集団で、かつ他の集団に属する個体とは交配できない集団ーである。染色体の数や形、構造などが違っている個体間では、交尾しても正常な受精が行われにくいうえ、胚発生が上手くいかないのが普通であるので、別種と考える。ところが、巻貝のカワニナ類の染色体は7対から20対と様々で、種で異なるだけでなく、同種の同じ集団の中で、染色体の形が個体ごとに違っている場合があるし、染色体数が異なる集団が交雑して、雑種ができたりしているという。生物学の常識に反する奇妙な現象であるが、その理由は解明されていないようだ。
日本の進化学の歴史についてふれられている。「1980年代は、進化ー突然変異、自然選択、遺伝的浮動を中心原理とする総合説を扱う講義は、大学ですら稀だった。当時、私の知る生物学の教授は、進化なんてホラ話、まともな研究者は相手にしない、と断言していた。なぜ日本の進化学は、こんな扱いを受けるほど崩壊していたのか。原因は主に三つ。科学への政治介入、海外動向への無関心、そして権威主義だ。」として、旧ソ連のルイセンコ説という共産主義と結びついた疑似科学が日本でも席巻していたこと、今西進化論という世界では通用しない日本独自の進化論が一世を風靡していたこと、ポストモダン思想と生物学の合体から生まれた特異な進化説が総合説を否定する論陣を張っていたことを挙げている。一方で、木村資生博士の中立説や、伊藤嘉昭博士や若手たちの研究など世界標準とつながる研究も生まれており、魑魅魍魎が跋扈する無法地帯の様相を呈していた。このあたりの記述は、80年代に生物学科の大学生だった私自身、当時体験していたことが含まれていて共感をおぼえた。
進化の新たな知見が見出されつつあるー①同じ環境の下では、同じ系統の種は、同じ性質と同じ群集を進化させる。②遺伝的、形態的にいったん分化した集団が出会って交配したり、異なる種が環境変化の後に雑種を作ったりした。つまり、系統の分化と融合の繰り返しによって適応拡散をおこしていた。(2022年のノーベル生理学・医学賞を受賞したペーボ博士が発見した、ホモ・サピエンスとネアンデルタール人の交配がまさにこれに相当するのだろう)③種分化しつつある集団に見えるものが、寄生虫の感染の有無を示すものである場合もある。









