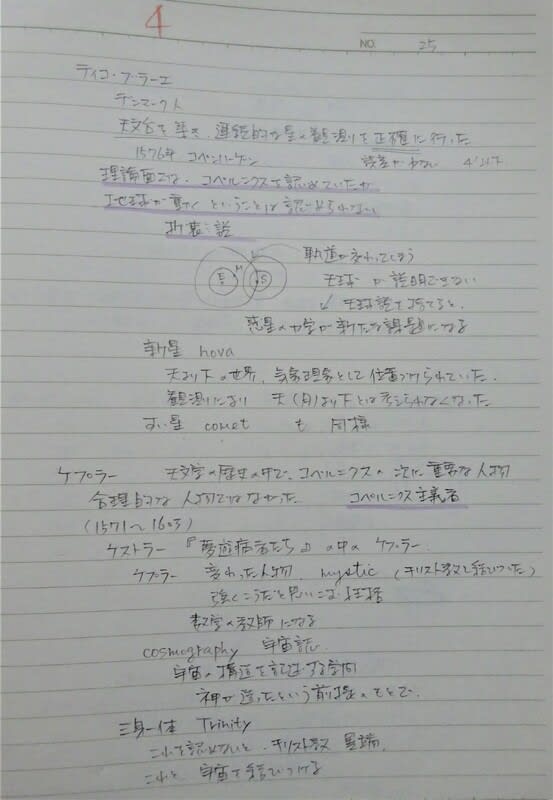冒頭から、朝日新聞2021.09.07付夕刊“取材考記” 東京科学医療部 桜井林太郎氏による、「論文引用数 中国躍進の一方で日本10位 科学技術力の岐路 おごり捨てて」を、以下に要約引用しよう。
科学技術政策について考えさせられるレポートが先月、公表された。 注目度が高い科学論文の数で、中国が米国を抜き、初めて首位に立ったという。
文科省の調査結果によりそれが判明したが。中国は、年間の論文総数でも2年連続で1位となり、「質・量ともに世界一になった」と焙じたメディアもあった。
「10年前、中国の研究者は独創性が高い日本の論文を追いかけていたが、今では中国の論文を日本の研究者が追試していることも多い」と嘆く。
ただ、中国が質でも世界一になったと言い切るのは時期尚早という意見もある。 理工系のある大学教授によると「中国は自国の科学雑誌への投稿を促し、核が高い雑誌に育てた上で、論文を引用し合う場合も多い」からだ。
文科省の研究所の分析でも、英ネイチャーや米サイエンスといった世界屈指の科学史のシェアでは今尚、米国が圧倒的に強かった。 中国は、米国に次ぐ英独の2位争いに加わろうと猛追している段階だ。
一方、日本の凋落ぶりは目を覆うばかりだ。 日本は、研究者数と研究開発費は世界3位で、論文総数は4位。 なのに、「トップ10%論文数」の順位は2000年代半ばから下がり続けている。 今回はインドにも抜かれ、G7最下位の世界10位に転落した。
研究時間の減少や博士課程進学者の減少など、さまざまな要因が原因として挙げられている。 しかし、最大の原因は「慢心」にあったのではないか。
この10年余り、皮肉にも日本はノーベル賞の受賞ラッシュに沸いた。
「中国のノーベル賞はごくわずか。科学技術力は日本が上だ」 そんな話を何度も耳にした。
現状の認識がこの有様では、中国だけでなく、世界から取り残されてしまうだろう。 日本政府も危機感を強めテコ入れを始めた。
日本の科学技術力は今まさに分岐点にある。 「失われた10年」を「失われた20年にしてはいけない。
(以上、朝日新聞夕刊記事より要約引用したもの。)
私事及び私見に入ろう。
自慢話になるかもしれないが。
我が亭主が現役時代は物理学研究者であった事実を、当エッセイ集に於いて幾度か公開しているが。
我が亭主も、ネイチャー論文提出歴がある。
大学及び大学院修士・博士課程において「理学博士」を取得した後、自身の専門であるバイオホロニクスを指導いただける他大学の研究室教授の元に研究の場を移し、そこでネイチャー論文等々複数の論文を提出後。
国内某大手技術開発研究所へ、ヘッドハンティングにて物理学研究者として入社したようだ。 (“ようだ”と表現するのは、我々夫婦は見合晩婚につきその時代の亭主の活躍ぶりは話に聞けども、私は直接知らない身故だ。)
加えて、私自身も理化学研究所勤務時にネイチャー論文・サイエンス論文等々を提出している基礎医学研究者の下で、その論文作成に必要な諸実験を担当させていただいている。
理研の場合、研究内容の外部漏洩防止措置が厳しく(いや、何処の企業も同様だろう)、私の現役中はその論文内容を読むことが叶わなかった。
我が理研退職時に研究者の粋なサプライズプレゼントで、それら論文のコピーを何本か頂いた時には感激だった。 (今尚、それら私自身が実験でかかわった論文コピーは自宅のどこかに保存してあるが、全部英文論文につき今となっては私側にそれら論文を読む能力があるのやら、どうなのやら…)😫
上記朝日新聞記事内にある「博士課程進学者の減少」問題はまさに今の時代、科学技術発展に於いて切実な課題であろう。
我が亭主がその道のりを歩んだ時代とは、博士課程進学者がまだしも何とかなった時代背景であったことと振り返る。
亭主の場合、研究活動のため某大手民間企業にやっとこさ就業できたのが35歳時だったのだが、亭主実家の経済力に支えられてそれが叶ったと聞いている。
今の混沌とした時代背景に於いて、博士課程を修了後名だたる論文を世に発表するのに要する年月を考察すると。
確かに、博士課程に進学する人材確保が困難な時代であることを察してあまりある。
上記記事は「ノーベル賞」に関しても触れているが。
私は上記某国立開発法人研究所へ通っていた時代に「ノーベル賞」に関して見聞した事実がある。
それを暴露すると。 「あれは順番待ちだ。ノーベル財団側は早めに受賞者を決定している。」
これに関しては、後に私も他の分野の受賞で十分に納得した。 平和賞のマララ氏等…
それは、あくまでも余談として。
最後に表題に戻るが。
原左都子の結論としては、表題に掲げたとおりだ。
科学技術力の国家間競争・比較は「論文引用数」ではなく、あくまでも研究内容でものを言うべきではなかろうか。