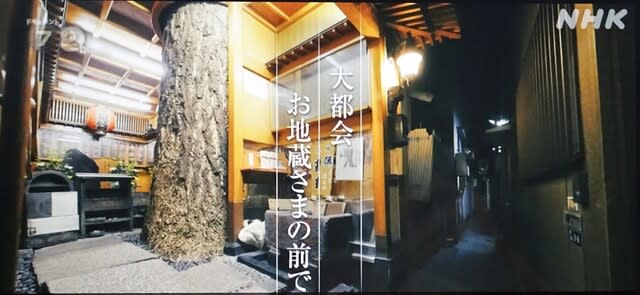(BS朝日 昭和偉人伝から)
6月30日は
実業家 小倉昌男が亡くなった日
小倉昌男は ヤマト運輸の
「クロネコヤマトの宅急便」
の生みの親
ヤマト福祉財団理事長
小倉は
1924(T13)年
大和運輸(T8年創業)の
社長小倉康臣の次男として
東京・代々木に生まれる。
1942(S17)年
東京高等学校高等科卒業
1947(S22)年
東京大学経済学部(旧制)卒業
1948(S23)年
大和運輸に入社
1971(S46)年
康臣の後を継いで
代表取締役社長
1975(S50)年
「宅急便開発要項」を社内発表する。
基本的な考え方として
①需要者の立場になってものを考える
②永続的・発展的システムとして捉える
③他より優れ、かつ均一的なサービスを保つ
④不特定多数の荷主または貨物を対象とする
⑤徹底した合理化を図る
この宅急便の原点「5箇条」を
もとに新商品開発を進めた。
1976(S51)年
オイルショック後に低迷していた
大和運輸の業績回復のため
・電話1本で集荷
・1個でも 家庭へ集荷
・翌日配達
・運賃は安くて明瞭
・荷造りが簡単
のコンセプトの“宅急便”の名称で
民間初の個人向け
小口貨物配送サービスを始める。

(BS朝日 昭和偉人伝から)
サービス開始当時は
関東地方のみだったが
その後 配送網を全国に拡大し
ヤマト運輸(1982年に商号変更)が
中小の会社から 売上高一兆円の
大手運輸会社に発展する基礎を築く。
1987(S62)年
代表取締役会長
1991(H3)年
代表取締役相談役
1993(H5)年
名誉会長
1995(H7)年
退任後
ヤマト福祉財団理事長として
障害者が自立して
働く場所作りに取り組んだ。
2005(H17)年
アメリカ・ロサンゼルスの
長女宅で死去 享年80
ちなみに 現在
創業・小倉家は
現・ヤマト運輸とは
無関係になっている。

当方コレクション