昔と違って、今の英語教育はすっかり多読・多聴流行り。私はあまりこの風潮が好きではないのだが(^^;; まず敵(?)を知らないことには話にならないので、
 ←私は英語だけより対訳が好きだけどね
←私は英語だけより対訳が好きだけどね
「多聴多読マガジン別冊 英語の多読最前線」というのを買ってみた。
読んでみたら、予想よりずっとおもしろくて、いろんな学校や塾で、ひとことで「多読」といってもほんとうに様々な実践をされていることがわかった。
塾でいうとSEGが多読で有名らしいのだが(マジで!? SEGって数学オタク(よしぞう含む)みたいな子が行くところだとばかり思ってたけど)、そういうところだとかなり個別に生徒の様子(読後の反応など)を見て、レベルが合うことはもちろん、個々の興味関心に合うものをお奨めしたりす、「多読のコンシェルジュ」的なことをするらしい。
学校だと、なかなかそこまで個別に対応できないよね。
ともかく、そうやってきめ細かく指導することで何を求めているかというと、「すべり読み」の防止。「すべり読み」というのは、目が滑ってスムーズに読めてるみたいに進んでいるけど実際には英文が読めていない。知っている単語や絵からの推測で楽しめちゃうけど実は大誤解してるかもという状態。
これをどう防止するかが教育現場的には大きな課題なのですね。借りた絵本を読んだふりして開かずに返しちゃってる、とかは論外としても(笑)
この本の中には「「すべり読み」と「新・多読三原則」」という特別座談会もありました。
なんでも、これまで言われてきた「多読三原則」というのは、「辞書は引かない」「わからないところは飛ばす」「つまらなければあとまわし」だったそうなんだけど、わからないばっかりの本を「わからないところは飛ばす」しまくってるとほんとにわけわからなくなってしまいます。
そこで、原則を改めまして「英語は英語のまま理解する」「7~9割の理解度で読む」(*)「つまらなければあとまわし」というふうに変えたんですね。「わからないところは飛ばす」じゃ限度がなくなっちゃうんで、理解度の数字を出して歯止めをかけたところはちょっと前進した感じ。
でもそれをどうやって確認するかってことになるとね。本人がよくわかって調整していればいいけれど、やる気のない子も含めて外から確認するとなるとけっこう難題。
一言ふた言感想を書かせるなんてのは、一文字も読まなくたって無難なこと書けちゃうし、かといって詳細な感想や要約を書かせようとしたら多読どころではないし(^^;; いくつか設問に答えてもらうというあたりがよさそうな気がするけど(実際そういう試みはある)、すべての本に設問をつけ、それに基づき実施チェックをするなんてほんとうにたいへん。
それに、ちゃんと設問をつけてあっても(公文英語とかそんな感じ)、素直な設問であれば「すべり読み」でも6割7割すぐクリアできちゃうから歯止めになっていないんですよね。またろうとこじろうは、この手で公文英語の効果をわりとドブに捨てました(笑)
その中で、豊田高専の事例は目を引きました。読書量(記録)を成績評価に使うと「すべり読み」どころか「読んだふり」が横行するので、読書量については全体の10%、それもある程度の量ですぐサチるようにしてあります。その代わり、定期テスト4割、小テスト2割、外部テスト(TOEIC)3割と、要するに学習成果のほうを測る方式。
定期テストの内容は、初見の長めの文章を、短めな時間で読み、内容についての設問に答える方式。まさに、ふだんきちんと(すべらず、すばやく)多読しているかどうかが表れますね。
相手があんまり子どもだと、評価の率を求めていることに合わせる(そのことによって正しい態度に誘導する)というのはできないけれど、高専だからね。それで大きな成果を挙げているようで、ほんとうに先生方の努力に頭が下がります。学年ごとのTOEIC平均グラフをみると、元々が英語好きとはとてもいえない高専生によくぞここまで、と感激です。あぁまたろうの高専でやってくれればよかったのに。
(*)10割もよくないんだって。それって読むのが遅すぎるってことで(←ぎくっ)
にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも
にほんブログ村 中高一貫教育

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社 ←またろうがイラストを描いた本(^^)
←またろうがイラストを描いた本(^^)

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社
(今回もイラストはまたろう)
「多聴多読マガジン別冊 英語の多読最前線」というのを買ってみた。
読んでみたら、予想よりずっとおもしろくて、いろんな学校や塾で、ひとことで「多読」といってもほんとうに様々な実践をされていることがわかった。
塾でいうとSEGが多読で有名らしいのだが(マジで!? SEGって数学オタク(よしぞう含む)みたいな子が行くところだとばかり思ってたけど)、そういうところだとかなり個別に生徒の様子(読後の反応など)を見て、レベルが合うことはもちろん、個々の興味関心に合うものをお奨めしたりす、「多読のコンシェルジュ」的なことをするらしい。
学校だと、なかなかそこまで個別に対応できないよね。
ともかく、そうやってきめ細かく指導することで何を求めているかというと、「すべり読み」の防止。「すべり読み」というのは、目が滑ってスムーズに読めてるみたいに進んでいるけど実際には英文が読めていない。知っている単語や絵からの推測で楽しめちゃうけど実は大誤解してるかもという状態。
これをどう防止するかが教育現場的には大きな課題なのですね。借りた絵本を読んだふりして開かずに返しちゃってる、とかは論外としても(笑)
この本の中には「「すべり読み」と「新・多読三原則」」という特別座談会もありました。
なんでも、これまで言われてきた「多読三原則」というのは、「辞書は引かない」「わからないところは飛ばす」「つまらなければあとまわし」だったそうなんだけど、わからないばっかりの本を「わからないところは飛ばす」しまくってるとほんとにわけわからなくなってしまいます。
そこで、原則を改めまして「英語は英語のまま理解する」「7~9割の理解度で読む」(*)「つまらなければあとまわし」というふうに変えたんですね。「わからないところは飛ばす」じゃ限度がなくなっちゃうんで、理解度の数字を出して歯止めをかけたところはちょっと前進した感じ。
でもそれをどうやって確認するかってことになるとね。本人がよくわかって調整していればいいけれど、やる気のない子も含めて外から確認するとなるとけっこう難題。
一言ふた言感想を書かせるなんてのは、一文字も読まなくたって無難なこと書けちゃうし、かといって詳細な感想や要約を書かせようとしたら多読どころではないし(^^;; いくつか設問に答えてもらうというあたりがよさそうな気がするけど(実際そういう試みはある)、すべての本に設問をつけ、それに基づき実施チェックをするなんてほんとうにたいへん。
それに、ちゃんと設問をつけてあっても(公文英語とかそんな感じ)、素直な設問であれば「すべり読み」でも6割7割すぐクリアできちゃうから歯止めになっていないんですよね。またろうとこじろうは、この手で公文英語の効果をわりとドブに捨てました(笑)
その中で、豊田高専の事例は目を引きました。読書量(記録)を成績評価に使うと「すべり読み」どころか「読んだふり」が横行するので、読書量については全体の10%、それもある程度の量ですぐサチるようにしてあります。その代わり、定期テスト4割、小テスト2割、外部テスト(TOEIC)3割と、要するに学習成果のほうを測る方式。
定期テストの内容は、初見の長めの文章を、短めな時間で読み、内容についての設問に答える方式。まさに、ふだんきちんと(すべらず、すばやく)多読しているかどうかが表れますね。
相手があんまり子どもだと、評価の率を求めていることに合わせる(そのことによって正しい態度に誘導する)というのはできないけれど、高専だからね。それで大きな成果を挙げているようで、ほんとうに先生方の努力に頭が下がります。学年ごとのTOEIC平均グラフをみると、元々が英語好きとはとてもいえない高専生によくぞここまで、と感激です。あぁまたろうの高専でやってくれればよかったのに。
(*)10割もよくないんだって。それって読むのが遅すぎるってことで(←ぎくっ)
にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも
にほんブログ村 中高一貫教育

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社
(今回もイラストはまたろう)










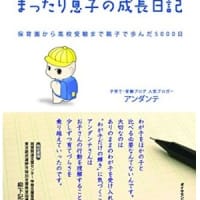












それはそれで意味はあるのかもしれないけど、一文一文構文解析して、わからないところは辞書引いて、なおかつすばやくってのがいいと思うんだけどなあ。無茶言ってますかねぇ?
文法や構文を習って、辞書引いてしっかり訳読して、そしたらわりとさっさと正確に読めるようになるじゃないですか、それでいいんじゃないかと私は思ってましたが(オプションで、しゃべりたい人はそれ用の練習すりゃね)、いまどきはすらすら読めて大意がとれるみたいなのを「生きた英語」というらしいですよ。すらすら読めてしゃべれるくせに翻訳者としては使い物にならなかったりしますが。
うちの子どもたちは昔風の英語も今風の英語もできないから論外です(-_-#
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11341956.html
昔と指導要領が変わってきているから、英語の学習法も変えなきゃということみたいです。
精読と多読のバランスは大事だと思います。英語を英語のまま理解することも大事というか、子どもを見てると、何が何でも日本語に訳そうとするから、何とかならんかなと思うこともないですが。でもまあ初学者は和訳を徹底して、ある程度レベルが上がれば英語を英語のままで理解することもできるかな、と。
国際的な職場であれば英語が公用語になるのは仕方ないですが、そうでない職場まで英語が出来なければというプレッシャーが掛かるのは如何なものかと思います。何で読んだが忘れたけど、フィリピンって国民のかなりの割合が英語しゃべれるけど年収は日本よりずっと低いんです。英語しゃべれるとグローバルってのも眉唾だし、英語なしで生きていけない国に日本がなって今より幸せかっていうと、相当疑わしいわけです。
わからん。昔英語ができなかった人の言い訳にしか見えない(暴言)...
まだ全部読んでないんですが、今はこういうのが流行なんですね。私は、中高生には詰めこみでも何でもいいから、とりあえず単語5000覚えなさい!派なんですが。
洋書をどんどん読めるのでなければ、日本人向けの週刊新聞がいいと思います。興味がある所だけ読めばいいですから。
これでずいぶん単語力が上がりました。
歌を習っているのでイタリア語もやっていますが、こちらは地道にNHKのテキストをやるつもりです。
ところで、アンダンテさんは暗記が苦手とおっしゃるのになぜ英語が得意なのですか?
使える英語ばやりで使えない翻訳者ばっかり増えてるという噂(翻訳会社さんの)が気になるところでございます。
「なんとなく訳」じゃ困るんで…
ちゃんと訳せるようにしてから流暢さ、というのが難しいというのが昔風英語の結論だった、んでしょうかね??
それで、今のアプローチがほんとにうまくいって、一般の人の「使える英語」プラス、プロの人の緻密な英語というふうになるなら指導要領を変えた甲斐があるというものですけど。
> 英語なしで生きていけない国に日本がなって今より幸せか
イヤだそれは(-_-;;
はっは(^^;; そうかも。
流行りというか、amachan-papaさんがおっしゃるように、公式に方向転換したんですね。
辞書を引かない「多読」は、新しいことを知る・理解するのは不向きなので、多読をするにしても、ほかにどういう学習を組み合わせるかが重要な気がします。
イタリア語!! 確かに、歌をやるなら歌詞がわからないと…!? 私は伴奏しかやりませんがほんとは伴奏やるんだってわかってたほうがいいには違いない(^^;; イタリア語とドイツ語。とてもそこまで手が回りません。
> 暗記が苦手とおっしゃるのになぜ英語が得意なのですか?
えー
英語では暗記で勉強したことないから。暗記いらないよ。私は単語集で単語を覚えたこともないです。